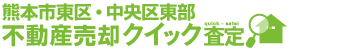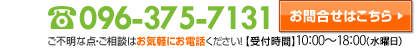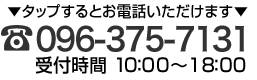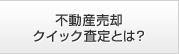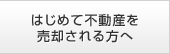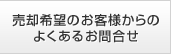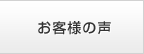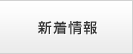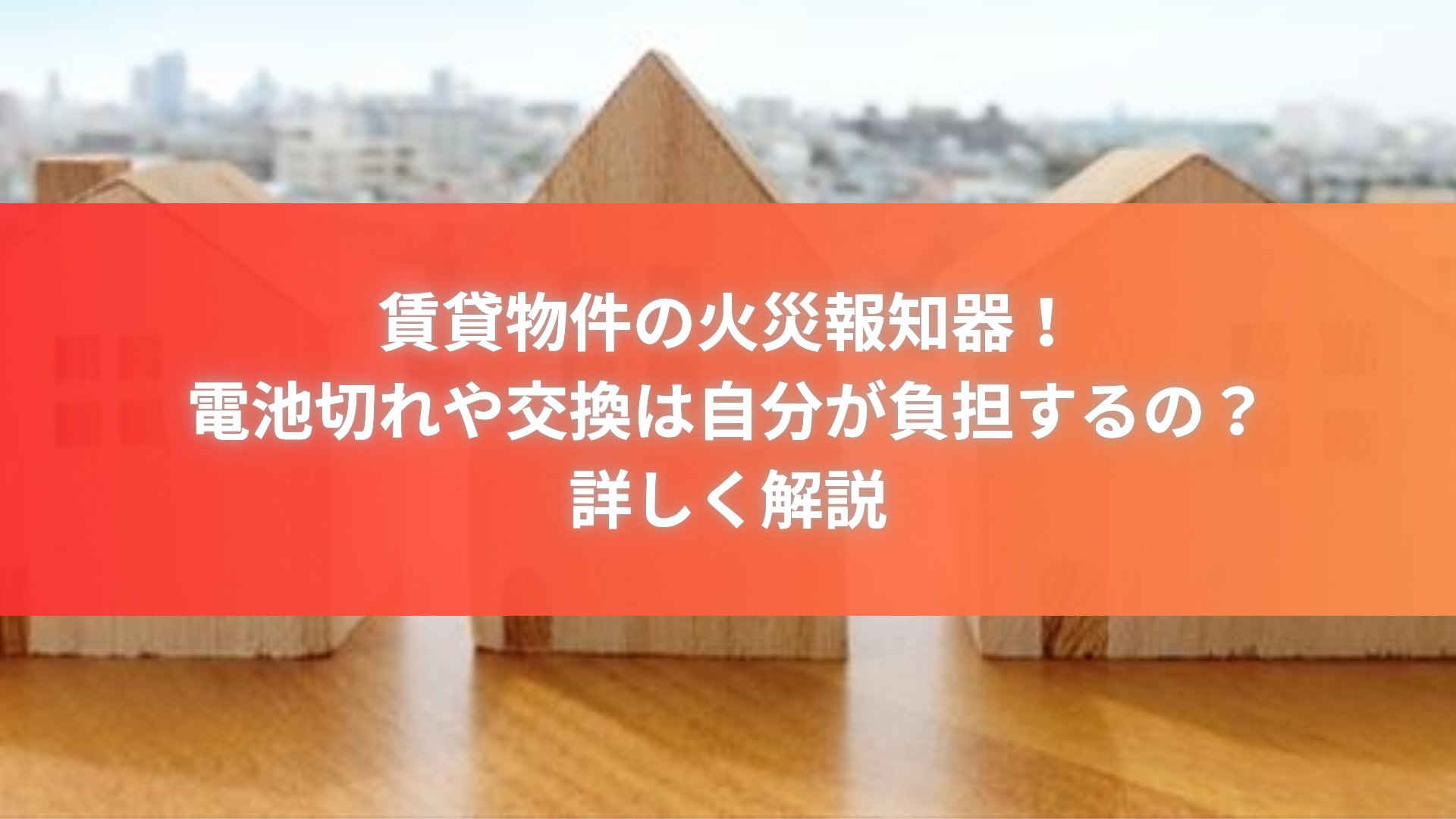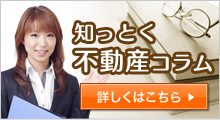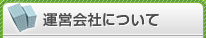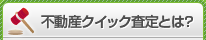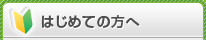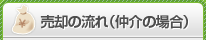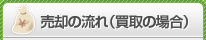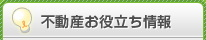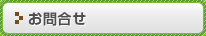火災から命を守るために重要な「火災報知器」。消防法の改正に伴い、2006年に新築住宅、2011年には既存住宅を含むすべての住宅で設置が義務付けられました。賃貸物件の場合は部屋ごとに設置されているため「電池切れで警報音が鳴ったらどうやって止めればいいの?」「電池交換は自分でやるの?」など、火災報知器について疑問をお持ちの方も少なくありません。
もし、自分の部屋の火災報知器が電池切れになったら、どうのように対応すればよいのでしょうか。また、その場合にかかった費用はどうなるのでしょうか。今回は、火災報知器が電池切れした場合の対処方法や、交換するタイミング、賃貸物件の火災報知器の重要性などについて解説します。賃貸物件に住む人なら、いつ誰に起きてもおかしくありません。今後の予備知識として身につけておきましょう。
目次
火災報知器が電池切れした場合の対処法

火災報知器の電気切れは突然やってきます。寝ているときに突然大きな警報音が鳴れば、驚いて慌ててしまう方も多いでしょう。どんなときでも落ち着いて対応できるように、ここでは火災報知器が電池切れした場合の対処法を確認しておきましょう。
警報音が鳴った場合は停止ボタンを押す
火災報知器は電池切れする前に、大きな警報音が鳴ったり、「電池切れです」などのアナウンスが鳴ったりします。夜中に突然鳴り出すこともあり、「もしかして火災が発生したのでは?」と感じてしまう方もいるかもしれません。
警報音は家中に鳴り響くため、まずは警報音を止める必要があります。音を止めるときは、火災報知器の本体についている停止ボタンやひもを引っ張ると止めることができます。また、一度止めてもしばらくすると鳴り出す仕様になっているため、早めに対応することが重要です。
電池交換方法の手順
火災報知器の警報音が鳴ったら、必ず電池交換を行いましょう。火災報知器の種類にもよりますが、電池交換の大まかな手順は次のとおりです。
- 火災報知器の本体を天井や壁から取り外す
- リチウム電池を抜く
- 新しいリチウム電池を入れてコネクタをつなぐ
- 再度天井や壁に取り付けて、ボタンを押し動作確認をする
以上が大まかな流れですが、火災報知器のメーカーや型番で検索すると、電池交換の方法を調べることができます。あらかじめ調べておくと、いざというときに役立つでしょう。また、火災報知器に使われている電池は、一般的な電池ではなく、多くの場合はリチウム電池が採用されています。リチウム電池はホームセンターや家電量販店、インターネット通販等で購入できるので、突然の電池切れに備えて家に常備しておくことをおすすめします。
警報音が鳴り止まらないときの対処法
警報音が鳴り止まないときは、以下の方法を試してみましょう。
- 警報音停止のスイッチを再度押す
- 故障しているか確認する
火災報知器のボタンやひもを引っ張っても警報音が止まらない場合は、再度停止スイッチを押してみてください。中には、長押しが必要な火災報知器もあるため、一度押して止まらない場合は長押しで対応しましょう。また、電池交換をしても警報音が鳴り続ける場合は故障している可能性があります。表示灯が点滅していたり、「ピピピ」と聞き慣れない音がしたりしている場合は、取扱説明書で故障に当てはまるか確認してみましょう。電池切れで警報音が鳴り続けていると、周囲の人が火災と勘違いしてしまう可能性があります。周囲の方へ迷惑をかけないためにも、事前に警報音を止める方法やリセット方法を確認しておくことをおすすめします。
火災報知器の電池交換するタイミングについて

警報音が鳴ったらすぐに電池交換を行うべきですが、それ以外でも日頃からボタンやひもを操作して正常に動作するか確認しておきましょう。消防庁では、作動点検のポイントを以下のように解説しています。
- 住警器にある「ボタンを押す」あるいは「引きひもを引く」ことで警報音がきちんと鳴るかどうか確認しておきましょう。
- 点検は、「お手入れを行った後」など、定期的に確認する時期を決めておくと便利です。最低限1年に1回は点検を行ってください。
- 点検の際は、実際の警報音がどんなものであるか家族で確認しましょう。
火災報知器を点検して反応がない場合は、すでに電池切れか本体が故障している、もしくは寿命を迎えている可能性が高いです。すぐに電池交換か本体の交換を行いましょう。
火災報知器の本体を交換するタイミングについて

火災報知器本体の交換時期はおおむね10年です。設置した時期から10年を経過している場合は、本体を交換するタイミングと言えるでしょう。なお、本体の設置年数は設置時に記入しているか、もしくは製造年を確認することでおおよその設置年数がわかります。ただし、賃貸物件の場合、火災報知器の設置と正常な動作を保つことは貸主の責任です。したがって、入居者が勝手に交換することは避け、管理会社や大家さんへ連絡をして対応してもらいましょう。
賃貸物件の火災報知器!取り付けは重要

2011年6月以降、すべての住宅に火災報知器を設置が義務付けられていますが、火災報知器を設置していなかった場合、どのような罰則が課せられるのでしょうか。ここでは、賃貸物件オーナーのリスクや、火災報知器の設置場所や注意点について見ていきます。
賃貸物件オーナーのリスク
火災報知器の設置は義務化されていますが、実は、設置していなくても法律上の罰則はありません。そのため、現在の賃貸物件における火災報知器の設置率は100%ではないのが実情です。しかし、賃貸物件に火災報知器を設置しなかった場合、オーナーには以下のようなリスクがあります。
- 火災が発生して死者が出た場合、オーナーが責任追及される可能性がある
- 火災が起きても火災保険が適用されず保険金を受け取れない可能性がある
オーナーが火災報知器を設置していなかったために、火災の被害が拡大した場合には、瑕疵または過失と判断され、オーナーは責任を追求されることになるでしょう。また、火災報知器未設置の場合は、火災保険がおりない可能性もあります。保険が適用されなければ、建物で発生した損害や修繕費用はすべてオーナーの自己負担となるため、火災報知器を設置せずに放置するリスクは非常に高いと考えられます。
火災報知器の設置場所
火災報知器の「設置場所」は、基本的に寝室と寝室がある階の階段上部(1階の階段は除く)と決められています。しかし、設置が義務付けられている場所は自治体によっても異なります。例えば、東京都の場合は、リビング、子ども部屋、寝室、居室、階段、キッチンなどに設置が必要です。このように、自治体によってルールが異なるため、いちど自治体で定められた設置場所を確認してみましょう。
取り付け位置については「天井」または「壁面」に取り付けることが一般的で、天井の場合は壁や梁から60cm以上離れた天井の中央付近に取り付けます。照明機器は感知の妨げになる可能性があるためできるだけ離す、エアコンの吹き出し口からも1.5m以上離れた場所に取り付けるなど、細かなルールが設けられています。
火災報知器のよくある質問

「火災報知器の設置や交換はオーナーと入居者どちらがやるべき?」と思う方も多いでしょう。そこで、ここでは火災報知器にまつわる以下の質問について解説します。
- 火災報知器の設置は賃貸オーナーがするの?
- 火災報知器が電池切れ!電池交換は賃貸オーナーがするの?
さっそく回答を見ていきましょう。
火災報知器の設置は賃貸オーナーがするの?
東京都の火災予防条例では、「住宅の『関係者』が住宅用火災警報器を設置し、維持しなければならない」と定めています。この住宅の「関係者」が非常に重要で、具体的に以下の三者を指します。
- 賃貸物件の所有者である「オーナー」
- 賃貸物件の管理者である「管理会社・不動産会社」
- 占有者である「入居者」
このように、法的には三者すべてに住宅用火災警報器の設置・管理義務があることになります。しかし、実際のところは、入居者が退去したタイミングで管理会社やオーナーが点検を行い、設置や交換をすることが多いです。
火災報知器が電池切れ!電池交換は賃貸オーナーがするの?
火災報知器「本体の交換」は、基本的に管理会社やオーナーが行います。それでは、「電池交換」についてはどうでしょうか。火災報知器の電池が切れてしまったとき、一番初めに気がつくのは入居者です。そのため、入居者が電池交換をする機会のほうが圧倒的に多いでしょう。例えば、エアコンのリモコンの電池が切れたから交換するようなイメージです。
その場合、リモコンの電池代はオーナーに請求するでしょうか?火災報知器の電池切れもこの感覚に近く、基本的には入居者が負担することのほうが多いのが実情です。入居者が火災報知器の電池切れを放置すれば、実際に火災が起きたときのリスクが高くなります。したがって、警報音が鳴ったら放置せず、すぐに対応することが重要です。なお、賃貸契約書に火災報知器についての定めがある場合は、管理会社へ連絡して指示を仰ぎましょう。
火災報知器はどこで購入する?リースもある?

火災報知器を入居者が買う機会は少ないかもしれませんが、どこでどのように購入できるのか把握しておくと安心です。ここでは、火災報知器にはどのような種類があるのか、どこで購入できるのか、リースする(借りる)ことはできるのかについて解説します。
火災報知器の種類
火災報知器は、煙や炎を感知する「煙式(光電式)」と周囲の熱が上昇するのを感知する「熱式(定温式)」の2種類があります。東京消防庁のホームページでは、居室や階段などは煙式、台所など火災以外の煙で警報器が誤作動する可能性がある場所は熱式の設置を推奨しています。また、条例によって設置場所が指定されているため、消防庁が推奨する煙式でなく、熱式を採用する場合は設置場所の選定に注意が必要です。
発報方式は、火災を感知した警報器のみが鳴る「単独式」と、1ヶ所で火災保管地するとすべての警報器が連動して鳴る「連動式」の2種類です。また、耳が不自由な方のために光と音の両方で知らせるタイプもあるため、ご自身やご家族のライフスタイルに合わせて選びましょう。
火災報知器の販売店
火災報知器を自分で購入する場合は、インターネット通販やホームセンター、家電量販店で購入することができます。本体は2,000円~3,000円前後で購入できますが、電池式のものが多いため、火災報知器の種類に合った電池も購入しておきましょう。なお、取り付けは自分で行うことも可能です。ただし、壁や天井に穴を空ける必要があるため、賃貸物件の場合は事前に管理会社へ確認しておきましょう。
火災報知器のリースについて
電力会社や電気会社では、火災報知器のリースを行っています。ガスや電気の料金と一緒に支払うことができて、月々数百円から借りることができます。さらに、契約期間中は機器の交換や管理などもおまかせできるため、管理の手間を省くことができます。ただし、ガス会社との契約が前提になるケースが多いため、解約や転居の際には注意が必要です。
まとめ
今回は、「火災報知器の電池切れや交換は入居者負担するのか?」について解説しました。普段あまり意識にすることのない火災報知器ですが、火災が起きた際、住人の命を守る重要な役割を担っています。そのため、火災報知器の電池が切れたときは、なるべく後回しにせず早急に対応しましょう。
火災報知器の電池が切れたときは、大きな警報音や「電池切れです」といったアナウンスが鳴り響くことがあります。寝ているときや夜中に大きな音がして驚いてしまう方も多いと思いますが、落ち着いて本体についているボタンやひもを引いて警報音を止めましょう。一度警報音止めても、しばらくすると再度警報音が鳴り出すことがあります。いつ鳴っても困らないよう、火災報知器の交換用電池を常備しておくことをおすすめします。
なお、火災報知器の電池交換は基本的には入居者負担ですが、本体の故障や交換は管理会社やオーナーが行うことが一般的です。ただし、賃貸契約書に定めがある場合は、その内容に合わせて対応しましょう。火災報知器の対応で困ったときは、自己判断せず管理会社に相談するのが得策です。