



cat
1,294
2026年2月1日 現在
-
運営会社について
クイック査定とは?
はじめての方へ
売却の流れ(仲介の場合)
売却の流れ(買取の場合)
不動産お役立ち情報

賃貸住宅にお住まいの方は、自宅の水道メーターがどこにあるかご存じですか?設置場所を事前に知っておくことは、緊急時の止水や漏水の早期発見など、いざというときに役に立ちます。
本記事では、マンションやアパートなど賃貸住宅における水道メーターの設置場所や、普段はあまり意識することのない水道メーターに関する疑問をわかりやすく解説します。

自宅の水道メーターを普段から目にする機会は少ないですよね。
実は同じ賃貸住宅でも、建物の規模や構造、管理方法によって設置場所は異なります。ここからはアパート、マンション、戸建ての3タイプに分けて、それぞれの設置場所を解説します。
ご自身のお住まいに当てはめながら、実際に探す際の参考にしてみてください。
設置場所として考えられるのは以下のとおりです。
まず、小規模物件では、各部屋の玄関脇に設置されているケースが多く、入居者自身で簡単に確認できます。
少し規模の大きな物件では、共用廊下の端や階段下などのスペースに、他の部屋とまとめて設置されていることも。その際は部屋番号などをしっかり確認し、自宅のものを特定します。水漏れなどの緊急時は焦ってしまいがちですが、誤って他の部屋のバルブを閉めてしまわないよう注意が必要です。
また、築年数が古い物件や寒冷地にある物件は、地面に埋め込まれている場合もあります。これはスペースの有効活用や、寒冷地での凍結防止を目的としたものです。特に古い物件では、蓋が硬くなっている場合もあるので、日頃から位置を認識しておくと安心です。
マンションは規模が大きくなるため、設置場所が異なる場合があります。設置されている可能性が高いのは、以下の場所です。
多くのマンションでは、各部屋の玄関横にパイプシャフト内にメーターボックスが設置されています。そこには、ガスや電気のメーターも一緒に収められているのが一般的です。
一方で大規模マンションや高層マンションでは、全住戸分のメーターを管理人室や共用部に集中して設置されていることも。戸数が多いマンションでは、検針員が効率的に検針できるよう設計されているのです。
なお、マンションのメーターボックスには、鍵がかかっている場合があります。その場合は、入居者自身で自由に確認することはできません。まずは施錠されているのかどうかを確認し、必要に応じて管理会社や管理人に問い合わせるようにしましょう。
戸建て住宅では、敷地内の道路側や玄関横の地面に埋め込まれていることが多いです。検針員が敷地に入らずに確認できるよう道路に近い場所に設置されています。
多くの場合、地面に四角い蓋があり、その中に水道メーターと止水栓が収められています。戸建てでは自分で確認する機会が多く、漏水チェックや水道料金の確認にも役立ちます。
例えば、蛇口をすべて閉めているのに針が回っている場合は、どこかで漏水している可能性が高いです。緊急時には止水栓を閉めることで被害を最小限に抑えられます。特に冬場は凍結による破損が起こることもあるため、定期的に確認しておくと安心です。

配置されていそうな場所を探したのに見つからない場合は、以下の対処法があります。
管理会社や大家さんはもちろん、水道局も水道料金の請求をおこなう立場なので、設置位置に関する情報を持っている可能性が高いです。それぞれの対処法について、詳しく見ていきましょう。
まず頼りになるのが管理会社や大家さんです。特にマンションは構造が複雑なので、入居者が自力で探しても見つけにくいケースがあります。
管理会社や大家さんは建物の設計図がわかっているため、正確な位置を教えてもらえる可能性が高いです。電話やメールで問い合わせれば、すぐに案内してもらえることも多く、緊急時には迅速な対応が期待できます。
また、設置場所が施錠されている場合は、入居者が勝手に開けることはできません。そのような場合も管理会社や大家さんに連絡することで、鍵の開閉や立ち会いを依頼できます。
さらに、漏水や水道料金の異常が疑われるときも、まずは管理会社や大家さんに相談することで、必要に応じて専門業者や水道局へ連絡してもらえるため安心です。日常的に顔を合わせる大家さんであれば直接聞きやすく、管理会社の場合も入居者サポート窓口が整っていることが多いため、困ったときはまず連絡してみるのが最も確実な方法といえます。
水道局は各住宅にあるメーターの設置場所について、情報を持っています。
水道局に問い合わせれば、住所や契約者情報をもとに、設置場所を調べてもらえることも。自分で探しても見つからず、管理会社や大家さんにも頼れない場合は、水道局の情報が大きな助けになるでしょう。
まずは水道局の問い合わせ窓口に連絡してみると良いです。ただし、私設メーターの場合は水道局側も詳細な位置情報を持っていないケースが多いため、その点に留意する必要があります。

水道メーターは、数字の読み取り方によって、直読式と円読式の2種類に分類されます。それぞれのタイプについて詳しく見ていきましょう。
数字がそのまま表示されるタイプで、読み取りが簡単です。表示部分にはデジタル式またはアナログ式の数字が並んでいて、一目で水道使用量を確認できます。
最近の住宅では直読式が主流です。誤読の心配が少なく、検針作業の効率化などのメリットがあります。
直読式は利用者自身が水漏れの有無を確認する際にも便利です。たとえば、蛇口を全て閉めているのに数字が増え続けている場合、どこかで漏水している可能性があるとすぐに判断できます。
最近ではスマートメーター化が進み、直読式をベースに通信機能を持たせて、各住戸を訪問せずに遠隔で使用量を把握できる仕組みも導入され始めています。
円読式水道メーターは、針のついた複数の文字盤が並んでおり、それぞれの針の位置で使用量を読み取るタイプです。古い住宅や昔からあるアパートなどでよく見られる形式で、直読式に比べると直感的には読み取りづらく、ある程度は慣れが必要です。
複数の針が異なる単位を示しているため、正確に使用量を把握するには針の位置を丁寧に確認しなければなりません。黒い針と赤い針で単位が異なり、黒い針は立方メートル、赤い針はリットルの単位です。
このように前提となる知識が必要なため、利用者が自分で確認する際には誤読しやすく、慣れていないと正しい使用量を把握しづらいのがデメリットです。
しかし、円読式は構造がシンプルで製造コストが低く、長期間にわたり安定して使用できるというメリットがあります。耐久性が高いため、古い住宅でもまだ現役で使われていることが多いのです。

水道メーターが故障してしまった場合、以下のような原因が考えられます。
それぞれの故障原因について詳しく見ていきましょう。
激しい水圧の変化が繰り返されると、メーターの内部の部品に負担がかかり、故障しやすくなります。たとえば水圧が急上昇することで、歯車や計測機構が損傷することも。
水圧の変化は、地震や台風などが原因で発生することもあります。こうした自然災害による影響は利用者自身では制御できません。異常を感じたら、早めに管理会社や水道局に相談しましょう。
寒冷地や冬場の厳しい寒さのもとでは、凍結によって故障することがあります。屋外に設置されているメーターは外気温の影響を受けやすく、内部の水が凍ると膨張してメーターが破損してしまうからです。
そうなれば針が動かなくなったり、計測が停止したりするほか、最悪の場合には破損によって水漏れが発生することもあります。こうしたトラブルを防ぐためには、保温材でメーターを覆う、寒波が予想される際に水抜きを行うなどの対策が有効です。
凍結による故障は日常生活に直結する問題であり、冬場は特に注意が必要です。
水道メーターは長期間使用することで内部部品が摩耗し、計測の精度が低下していきます。
経年劣化によって針の動きが鈍くなったり、数字の表示が不正確になったりすることがあり、結果として水道料金に影響を及ぼすこともあります。
水道メーターの有効期間は8年と定められており、定期的な交換が義務づけられています。メーターの蓋の裏などに有効期限ラベルが貼られているので、設置場所を確認する際にあわせて有効期限も確認しておくのがおすすめです。

「水道メーターが故障したかもしれない」と異常を感じたら、自己判断せずに大家さんや管理会社、水道局に連絡をすることが第一です。
故障したときの対処の流れをまとめました。
水道メーターが故障したまま水道を使い続けると、水漏れや誤針の原因になります。水漏れや異音などの違和感を感じたら、水道の使用は控えましょう。
まずは大家さん・管理会社に連絡します。大家さんが設置した私設メーターの場合は、大家さんが修理を手配してくれます。
公設メーターの場合は、水道局に直接問い合わせる必要があります。水道局のほうで修理を手配します。
修理業者が来て、点検・交換をしてくれます。費用負担は公設メーターなら水道局、私設メーターなら大家さんです。

水道メーターは、誰が設置したかによって、公設メーターと私設メーターの2種類に分けられます。
公設メーター:水道局が設置
私設メーター:賃貸住宅の大家さんが設置
アパートやマンションの場合、各住戸に公設メーターを直接設置している場合もあれば、建物全体の公設メーターから枝分かれして各住戸に私設メーターを設置している場合もあります。
賃貸住宅の場合、自宅のメーターがどちらのタイプかによって、交換費用の負担者が異なります。それぞれの費用負担者は、以下のとおりです。
公設メーター:水道局が交換費用を負担
私設メーター:大家さんが交換費用を負担
いずれにせよ、賃貸住宅の入居者が費用負担することは基本的にありません。ただし、以下のような特別な事情がある場合は、費用負担を求められる可能性があります。
この他にも、大家さんが負担した私設メーターの交換費用を、共益費に含めるかたちで、入居者が間接的に負担するケースもあります。
水道メーターの場所を把握しておくことは、水漏れなど緊急時の対応に役立ちます。アパートやマンションでは玄関横や共用スペース、戸建てでは敷地内の道路側にあることが多いです。直読式と円読式といった読み取り方式の違いも、事前に頭に入れておくとスムーズに対応できます。
故障時は自己判断せず、必ず管理会社や水道局へ連絡しましょう。メーターの交換費用は、公設メーターなら水道局、私設メーターなら大家さんが負担するのが原則です。ただし、故意や過失による破損や、賃貸契約に明記されている場合は、入居者が費用を負担する場合もあります。
賃貸住宅に住む場合は、事前に契約内容を確認しておくと、費用負担に関するトラブルを未然に防ぐことができます。
部屋探しをしていて「定期借家」という言葉を目にした経験はありませんか?日常生活ではなかなか使用しない言葉であるため、「読み方がわからない」「意味がわからない」という方も少なくありません。建物の賃貸契約には、「普通借家契約」と「定期借家契約」があります。それぞれの意味を理解しておけば、物件選びの選択肢が広がるため知っておいて損はないでしょう。
そこで今回は、定期借家の読み方や意味、定期借家が導入された理由、定期借家のメリット・デメリット、普通借家との違いなどについて詳しく解説します。

ここでは、定期借家の読み方と意味について解説します。
定期借家は、「ていきしゃっか」と読みます。初めて読む方は「ていきしゃくや」と読み間違えやすいですが、正しくは「ていきしゃっか」であるため注意しましょう。
定期借家契約は、期間に定めのある賃貸借契約のことで、契約期間の満了に伴って契約が終了します。つまり、普通借家契約のような更新はありません。たとえば、契約期間1年の定期借家契約をしたら、借主は1年後に退去しなければいけません。では仮に、借主が「もう一年借りたい」となった場合は、どうなるのでしょうか。この場合、貸主と協議して合意が得られれば再契約することが可能です。
しかし、貸主の合意が得られなければ再契約できないため、1年後に退去しなくてはなりません。このように、定期借家契約は貸主に決定権があるというのが大きな特徴です。なお、定期借家の契約期間には制限が設けられていないため、1年未満や2年以上という契約も有効です。

定期借家制度は、2003年3月1日に施工された比較的新しい仕組みです。ではなぜ、定期借家制度が導入されたのか、その背景には以下のような理由があります。
普通借家制度は、借主の契約更新の要望を貸主が拒否することはできません。これは、貸主側にとって、とても心理的負担が大きいものです。さらに、マナーを守らない入居者に居座られたり、多額の立ち退き料を支払って退去してもらったり、貸主には多くのリスクがありました。こうした問題を解消し、貸主が安心して物件を貸し出しできるよう定期借家制度は導入されました。貸主の負担が減ることで、より多くの良質な物件が市場に供給されます。また、柔軟な賃貸借契約の整備により、短期利用など多様なニーズに対応しやすくなったと言えるでしょう。

定期借家契約にはメリット・デメリットがあります。人によってはメリットに魅力を感じて契約する方もいるでしょう。まずは、定期借家契約のメリットから紹介します。
項目ごとに解説します。
最初に紹介するメリットは、「短期契約ができる」ことです。普通借家契約の場合は2年契約が一般的ですが、定期借家契約は貸主が自由に契約期間を設定できます。そのため、1年未満の短期契約も可能です。短期間の契約はデメリットのように感じる方もいるかもしれませんが、何らか理由で少しの期間だけ借りたいという方には最適です。
2つ目のメリットは、「物件の選択肢が広がる」ことです。定期借家の物件を「なんとなく」という理由で避けている方もいるでしょう。しかし、あらかじめ定期借家の特徴を理解していれば借りやすくなり、状況に合わせた選択ができるようになります。
定期借家の物件は、築年数が浅い物件や戸建ての賃貸なども多く、比較的家賃が安く設定されています。また、更新料が発生しないため、長期で住む場合と比較して総支払額を抑えることができます。物件によっては敷金・礼金が必要ない物件のあるため、初期費用を抑えつつ短期で入居したいという方にはぴったりでしょう。

次に、定期借家契約をするデメリットを紹介します。契約前にあらかじめデメリットを理解しておくことで、「こんなはずじゃなかった」という思いがけないトラブルを防ぐことができます。デメリットは以下の3つです。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
定期借家契約は、貸主側の都合で契約期間が決まっています。そのため、借主側が「もっと長く住みたい」と思っていても再契約できない可能性があります。長期的に居住するつもりで借りてしまうと、想定外の退去や引っ越し費用が必要になるため注意が必要です。ただし、貸主と合意が取れた場合は、契約期間を更新したり、再契約したりできるケースもあります。
定期借家契約では、契約期間中の解約が原則認められていません。仮に、入居後に状況が変わっても契約終了まで住み続ける必要があります。ただし、床面積200㎡未満の物件では、転勤、介護、療養など、やむを得ない事情がある場合には解約が認められるケースもあります。法律上のやむを得ない事情に該当する場合、借主は1ヶ月前に貸主への通知が必要であり、通知すれば貸主の「承諾」は必須ではありません。
定期借家契約では、従前の契約と再契約は別物となるため、契約内容が大幅に変わる可能性があります。たとえば、これまでは家賃10万円で借りられていた部屋が、再契約後は家賃15万円に値上げされたというケースもあります。貸主が家賃を大幅に変更することは自由であり、借主が再契約後の家賃に応じることができなければ賃貸契約は終了となります。
また、再契約後は定期借家契約の期間を短くすることも可能です。このように、貸主都合で借主が不利な状況になる点はデメリットと感じる方もいるでしょう。

定期借家と普通借家には、以下のような違いがあります。
項目ごとに解説します。
定期借家契約は、公正証書などの書面で行うことが必須条件です。これは、制度の濫用を防ぎ、借主を保護することを目的としています。また、契約内容の明確化と証拠力・執行力を高め、トラブルを未然に防ぐ効果があります。契約期間は貸主が自由に決めることができますが、書面には「契約の更新はなく期間の満了とともに契約終了」の旨を記載し、説明をしなければいけません。一方、普通借家契約は口頭契約も可能です。ただし、契約期間は1年以上で設定する必要があります。
先にお伝えしたように、定期借家契約は期間満了によって契約が終了するため、契約更新はありません。また、貸主からの中途解約も不可となっています。ただし、貸主と借主、双方の合意があれば再契約可能です。一方、普通借家契約は借主が希望すれば、契約を更新して住み続けることができます。貸主側からの中途解約は、正当事由がない限り認められず、万が一正当事由があっても立ち退き費用が発生するケースが多いです。
賃料の増額請求権とは、現在支払っている賃料が相場と比較して不相当になった場合、貸主に対して家賃の減額・増額を請求できる権利です。そもそも賃貸物件は、景気動向や需要供給のバランスによって賃料が変動します。そのため、同じ物件に長く住んでいると、入居時の家賃が相場と合わなくなってくることがあるのです。定期借家契約も普通借家契約も、原則として賃料の増減額請求が認められています。
ただし、定期借家契約は賃料の増減額請求権を排除する特約を定めることが可能です。一方、普通借家契約は賃料の増減額請求権を排除する特約は無効ですが、家賃を増額しないことについての特約のみ認められます。
定期借家契約は、契約期間が1年以上の場合のみ、期間満了の6ヶ月前までに貸主側から契約終了の旨を通知する義務があります。これを怠ると、契約終了を借主に主張できず、事実上更新されてしまう可能性があります。なお、1年未満の契約では通知義務はありません。また、普通借家契約にも通知義務はありません。

定期借家物件を借りる際は、契約書に以下のポイントが記載されているかチェックしましょう。
契約書に「更新がなく期間の満了により終了する」ことの記載があるか、書面で説明を受けたかを確認しておきましょう。これらの記載がなく説明も不十分な場合は、特約が無効となり、通常の普通借家契約として扱われる可能性があります。合わせて、契約期間や借主側からの中途解約に関する事項、再契約の可否についても確認しておくと安心です。再契約が可能な場合は、再契約時の金額や流れなどについて相談しておくと再契約への不安が軽減するでしょう。
今回は、定期借家契約の読み方や普通借家契約との違いなどについて解説しました。定期借家契約は貸主保護を目的とした制度で、読み方は、「ていきしゃっかけいやく」です。「ていきしゃくや」と読み間違えやすいため注意しましょう。また、定期借家契約は原則更新ができません。更新できないことはデメリットに感じるかもしれませんが、状況によってはメリットになることもあります。
そのため、更新できないというイメージだけで敬遠するのではなく、自身の状況と照らし合わせながら考えることで択肢を広げることができるでしょう。
定期借家契約と普通借家契約との違いは、契約方法や更新期間、中途解約の可否、賃料の増減額請求権、通知義務などがあります。あらかじめ理解しておくことで想定外の事態を防ぐことができるでしょう。さらに、契約時には「更新がなく期間の満了により終了する」旨の記載や「借主側からの中途解約の可否」を確認しておくとより安心安全に契約することができます。
「賃貸やアパートに住んでいる場合でも車庫証明は必要なの?」引越しや車の購入をきっかけに、このような疑問を持つ方は少なくありません。
結論から言えば、賃貸・アパートであっても車庫証明は必須です。そして、そのためには大家さんや管理会社の協力が欠かせません。
本記事では、賃貸物件にお住まいの方が車庫証明を取得する際の手続きについて詳しく解説します。大家さんや管理会社とのやり取り次第で、手続きのスムーズさが大きく変わることもあります。
初めて申請する方にとって役立つ内容をまとめていますので、ぜひ参考にしてください。

車庫証明は、所有している自動車が、どこに保管されているか証明してくれる公的な書類です。
日本では自動車の保管場所の確保等に関する法律、通称「車庫法」が定められています。その法律の中で、「自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所を確保しなければならない」という条文があるのです。
車庫証明はこの法律に基づいた書類なので、車庫証明がない状態では法律違反になります。車を購入する場合は、そもそも車の登録ができず運転できません。引越しなどで保管場所の変更の届け出をおこなわなかった場合は、罰金が科せられるので注意しましょう。

賃貸マンションやアパートの敷地内には、入居者専用の駐車場がついていることもありますよね。でも、たとえ敷地内の駐車場を使う場合でも、車を持っているなら車庫証明が必要になります。
さらに賃貸物件ならではの注意点もあります。それは、申請に必要な書類の一部を大家さんに記入してもらわなければならないこと。自分だけで書類を揃えることはできないので、大家さんの予定も考えながら、手続きを進める必要があります。

車庫証明の申請に必要な書類は、主に以下の3つです。
特に注意したいのは、3.保管場所の使用権原を疎明する書類です。保管場所が、自分の所有地か、貸駐車場かによって、必要な書類が異なります。
賃貸物件の場合は「保管場所使用承諾証明書」が必要です。この書類には駐車場の所有者または管理委託者の署名欄があり、大家さんか管理会社に記入をお願いしなければなりません。
また自治体によっては、駐車場賃貸借契約のコピーを提出するよう求められることもあります。詳しくは、お住まいの地域の警察署ホームページなどで確認しておくと安心です。
大家さんの記入が必要な「保管場所使用承諾証明書」ですが、場合によっては駐車場の賃貸借契約を代用することもできます。
ただし代用するためには、いくつかの条件を満たさなければなりません。契約書に次の内容がきちんと記載されていることがポイントです。
この他にも細かな条件があり、書類に不備があると代用できないケースもあります。賃貸借契約書での代用を考えている場合は、事前に警察署に電話して、確認しておきましょう。
もちろん、もっとも一般的で確実な方法は「保管場所使用承諾証明書」を提出すること。ですが、どうしても承諾証明書を準備できない事情があるときは、このような代替手段があることも覚えておくと役立ちます。

申請手続きの流れは、以下のとおりです。
車庫のある地域を管轄する警察署に行くと、車庫証明の申請書類をもらえます。直接行かなくても、ホームページからファイルをダウンロードし、自宅で印刷できる場合も多いので、ぜひチェックしてみてください。
入手したら、記載例を参考にして、必要事項を記入します。
必要な書類がすべて揃ったら、警察署へ提出しましょう。申請書類のほかに認印を持参しておくと、万が一不備があった場合でもその場で書き直せるので安心です。
また申請手数料がかかります。手数料は地域により異なりますが、だいたい2,000~3,000円程度。申請時に領収証紙や収入印紙で支払うケースもあるため、現金を準備しておきましょう。
なお、警察署の窓口は土日祝日や年末年始は休みで、平日も受付時間が限られています。事前に受付時間を確認して、予定を調整してから行くようにしましょう。
車庫証明の申請から交付までの期間は、3〜7日間程度かかるのが一般的です。
交付を受ける際は、申請受付時に渡された控えの用紙や、領収書などが必要になります。なくさないように、大切に保管しておきましょう。

同じマンション内に引っ越して、車庫が変わらない場合はどうでしょうか?答えは車庫証明の再取得が必要です。
なぜなら、たとえ車庫は同じでも、家の住所が変わっているからです。法律上、車の所有者の自宅の住所が変わったら、住所変更手続きをおこなうことが義務付けられています。
近隣に引っ越した後も、忘れずに手続きを進めましょう。

車庫証明を申請する際は、以下のポイントに注意しましょう。
繰り返しになりますが、車庫証明の申請に必要な書類のひとつ「保管場所使用承諾証明書」には、大家さんの記入が欠かせません。そのため、お願いするときはできるだけ早めに動くことが大切です。
余裕を持って書類を渡しておけば、大家さんの負担も軽くなります。引越しや車の購入が決まったら、早い段階で相談しておきましょう。
その際には車庫証明の手続きについて分かりやすく説明し、記入していただいたら感謝の気持ちをきちんと伝えるなど、丁寧な対応を心がけることがスムーズな手続きにつながります。
手続きには手数料がかかり、その金額は地域によって異なります。申請当日に慌てないためにも、いくらかかるのか事前に確認しておきましょう。
賃貸物件によっては、大家さんや管理会社が申請に必要な書類を既に持っている場合もあります。ただし大家さんが記入できるのは、あくまで「保管場所使用承諾証明書」のみです。
また、管理会社や車のディーラーに車庫証明代行を依頼することもできます。ただし手数料は1万円~3万円かかることもあり、自分で申請するより高くつく点に注意が必要です。
車庫証明は、所有している車の保管場所を証明する公的な書類です。法律で義務づけられているため、車を購入したり引っ越したりしたら、必ず申請して交付を受けなければなりません。
賃貸物件に住んでいる場合は、大家さんに記入してもらう書類もあります。駐車場の賃貸借契約で代用できる方法や、管理会社などに手続きを代行依頼する方法もあります。事前に情報をしっかりと調べた上で、コストと手間を天秤にかけて自分に合った方法を選びましょう。
事故物件は「心理的瑕疵物件」とも呼ばれ、人の死に関わる過去がある物件のことを指します。人の死に関わる過去は心理的に好ましいことではなく、新居を探している人にとっては避けたい物件とも言えるでしょう。そのため、事故物件が気軽に検索できる大島てる事故物件マップは多くの人の関心を集めています。しかし、近年「大島てるが見られなくなった」という情報が拡散しているのをご存知ですか?「大島てるが見られなくなったら困る」という方も多いため、今回の記事では大島てる事故物件マップは終了したのか?について解説します。また、サイトの使い方や調べ方、削除依頼の流れなどについても解説しますので、最後までご覧いただき今後の参考にお役立てください。

SNSやインターネット上には「大島てるが終了した!」「見られない」など、様々な意見がありますが、事実と異なる情報も多いため注意が必要です。ここでは、実際に大島てる事故物件マップサイトが終了したのかについてお伝えします。
結論からお伝えすると、大島てる事故物件マップサイトは終了していません。2025年現在もサイト運営は継続され、イベント情報や最新情報も日々更新されています。(2025年11月時点)
ただし、一部のユーザーには「物件情報を取得できませんでした」と表示されるなど、一時的な問題が起きていたと報告されています。そのことが原因で「終了した」と噂されるようになった可能性も考えられます。次の項目では、噂されるようになった具体的な原因について解説します。

前項でお伝えしたように、大島てる事故物件マップは現在も運営されており、事故物件の情報提供という役割を担っています。ではなぜ「終了した」と噂されるようになったのでしょうか。ここでは、考えられる4つの原因について解説します。
項目ごとに見ていきましょう。
短時間のサーバーメンテナンスやアクセスが集中した際の一時的な表示エラーなどがネット回線トラブルと呼ばれます。特に、テレビで紹介された後などはアクセスが集中しやすく、サイトが表示されないことがあります。しかし、これらは一時的なものであるため、再度アクセスすることで解消されます。また、ルーターなどの不具合、Wi-Fiの電波トラブル、回線事業者の通信障害なども考えられます。このように、何らかの原因で起きたネット回線トラブルが原因で終了したと噂されるようになった可能性があります。
スマホやPCでの表示トラブルも一つの原因と考えられます。たとえば、「炎マークが表示されない」「マップが表示されない」「地図が真っ白のまま」等は、実際のユーザーに起こったトラブル事例です。このような場合は、以下の方法を試してみてください。
また、ブラウザにインストールしている拡張機能がサイトの表示を妨げている可能性もあります。その場合は、広告を非表示にしたり、サイトメニューを最小化したりする方法も効果的です。それでも表示しない場合は、別のデバイスやブラウザから試してみましょう。
サイトがリニューアルしたり、仕様変更したりすると、見慣れない画面に戸惑いを感じる方もいるでしょう。それが原因で「大島てるが使えなくなった」と噂されるようになった可能性も否定できません。仕様変更に伴って使い方が多少変わることはありますが、基本的には今まで通り利用できます。
大島てる事故物件マップに掲載されている情報が誤っている場合は、サイト運営側の判断により情報が削除されます。また、名誉毀損やプライバシー保護の観点から、一部の事故物件は削除・非表示になるケースもあります。一部ユーザーは、「調べていた物件が見られなくなった」という体験から「大島てるが終了した」と感じる方もいるでしょう。しかし、これは一部の情報を変更しただけであり、サイトが終了したわけではありません。大島てる事故物件マップは、事実情報に基づいて日々変更されるため、気になる場所があれば最新情報を確認することが大切です。

大島てる事故物件マップの主な機能は「地図検索」で、事故物件の情報を視覚的に調べられるとして広く利用されています。しかし、サイトの存在は知っていても使ったことがないという方も多いでしょう。また、スマートフォンとパソコンでの使い方が異なるため、初めて利用する方は戸惑うかもしれません。そこでここでは、大島てる事故物件マップに関する以下の基本情報を解説します。
項目ごとに見ていきましょう。
大島てるは2005年から続く民間運営の事故物件サイトで、正式名称は「大島てる・事故物件公示サイト」です。投稿件数は10万件を超えており、全国の事故物件を掲載しています。一般の方が事故物件を気軽に検索できる手軽さや、ユニークなコンセプトから不動産業界だけでなく多方面から注目を集めています。その一方で、一般の方が自由に事故物件に関する情報を投稿できることから、掲載される情報の信憑性については保証されていません。このような誤情報は、物件を売却しようとする人にとっては物件価値の低下原因となり、購入希望者にとっては、お気に入りの物件を諦める原因になる可能性があります。
スマートフォンは、表示画面が小さいものの、場所を問わず気軽に事故物件を検索できることがメリットです。スマートフォンで大島てる物件公示サイトを見る際は、ブラウザアプリの検索バーに「大島てる」と入力します。すると、一番上に「大島てる物件公示サイト」が表示されるためアクセスします。サイトが表示されたら「新着情報」の事故物件リストをタップすると、事故物件の地図画面に切り替わります。指でスワイプして地図を動かしたり、ピンチイン・ピンチアウトで拡大縮小したりすることが可能です。また、画面上部にある検索ボックスに気になる物件の住所を入力すると、該当エリアの事故物件と詳細を確認することができます。炎マークは事故があったことを意味しており、タップすることで事故の詳しい内容について閲覧可能です。
パソコンは表示画面が大きいため、複数のエリアを並行して調べることや、広範囲の調査ができることがメリットです。パソコンから見る場合も同様に、ブラウザの検索バーに「大島てる」と入力します。検索すると一番上に「大島てる物件公示サイト」が表示されるため、クリックしてサイトを開きます。パソコンの場合は、画面が大きいためサイト全体が一度に表示されます。画面上部の検索ボックスに地名や駅名、住所を入力すれば気になる目的地の地図が確認できます。マウスでスクロールしたり、拡大縮小したりしながらご自身が見やすいように調整しましょう。

大島てる事故物件マップには、炎マークの意味や掲載ルールがあります。では、具体的な内容やルールについて確認していきましょう。
炎マークは、事故物件であることを示しており、ユーザーから寄せられた情報を基に運営側が内容確認をしてから掲載しています。掲載の対象は、火災、事故、自殺、事件などで、告知義務に該当する重大な事案です。なお、炎マークでは主に以下の内容を確認することができます。
ただし、地図上に炎マークがないからといって事故物件ではないとは言い切れません。あくまでも参考情報の一つとして捉え、客観的に活用することが望ましいでしょう。
大島てる事故物件マップに投稿された内容は、運営側は事実確認を行っています。しかし中には、虚偽の報告や誤情報も掲載されてしまうことがあります。もし誤情報や訂正、削除希望があれば、サイト上の専用フォームから申請することが可能です。これはサイトの信憑性を高めるだけでなく、所有者のプライバシー保護や名誉毀損などの法律に抵触しないためにも重要とされています。

事故物件の不動産取引では「告知義務」が課せられています。そのため、事故物件の所有者側は、事故の内容を買主や借主に告知しなければなりません。しかし、センシティブな内容も含まれるため、取引は十分に配慮して慎重に行う必要があります。ここでは、事故物件掲載に関する以下の内容について解説します。
安心して取引を行うために、事故物件に関するルールや告知義務の内容についてしっかり理解しておきましょう。
不動産取引では、重大な事故や事件があった場合に買主や売主に対してその事実を告知する義務があります。これを「告知義務」と言い、国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」では以下のように定めています。
不動産取引においては、とりわけ住宅として用いられる不動産において、過去に人の死が発生した場合、その事案の内容に応じて、一部の買主・借主にとって不動産取引において契約を締結するか否かの判断に重要な影響を及ぼす可能性があることから、売主・貸主は、把握している事実について、取引の相手方等である買主・借主に対して告知する必要があり、過去の裁判例に照らせば、取引目的、事案の内容、事案発生からの時間の経過、近隣住民への周知の程度等を考慮して、信義則上、これを取引の相手方等に告知すべき義務の有無が判断されている。
引用:「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」
要約すると、知っていたら「買わない」「借りない」可能性がある物件情報は、買主・借主に対してきちんと伝えなければならないということです。なお、告知義務の期間は、賃貸契約では概ね3年間、売買契約では無期限とされています。ただし、賃貸契約でも事件性や社会的な影響が大きい場合は、3年を超えても告知義務が生じるケースもあります。
結論からお伝えすると、事故物件の公示は違法ではありません。所有者の立場からすると、物件が大島てる事故物件マップに掲載されることは避けたいと考えるでしょう。しかし、先述したように事故物件には告知義務があります。物件に何らかの瑕疵があれば、その事実を買主・借主に告知しなくてはなりません。もし、事故物件であることを隠して販売した場合は、宅建業法違反となります。契約解除だけでなく、損害賠償請求される可能性もあるため注意が必要です。
売主の中には、「勝手に事故物件を掲載したら名誉毀損ではないのか?」と考える方もいます。これは難しい問題ですが、名誉毀損にあたるかどうかは掲載内容が「事実であるかどうか」が重要な判断基準となります。ここでは、大島てる事故物件サイトに掲載された所有者が裁判を起こした事例を紹介します。
Aさんは、所有しているマンションが大島てるに掲載されたとして、慰謝料の支払いや掲載の削除、謝罪広告を求め裁判をしました。なお、このマンションでは、実際に死体遺棄事件が発生しています。しかし、Aさんは「名誉毀損」「営業妨害」であると主張しました。しかし、裁判所はAさんの訴えを棄却し、死体遺棄事件の事実を掲載することは名誉毀損にあたらないとして慰謝料の支払い、情報の削除、謝罪広告をすべて認めませんでした。判決後、Aさんから50万円の支払いをもって情報の削除依頼がありましたが、大島てる物件公示サイト運営側が応じることはありませんでした。
上記ケースのように、事実に基づく情報であれば原則として名誉毀損にはあたりません。ただし、事実と異なる情報やプライバシーの侵害と認められるような情報については削除されたり、裁判になったりする可能性もあるでしょう。

大島てる事故物件マップは、誤情報であれば削除依頼を行うことができます。ただし、すべての情報が削除されるわけではありません。運営側が事実確認に基づいて判断するため、削除までに時間を要する場合があります。物件情報が削除されるまでの流れは以下の通りです。
削除依頼は難しい作業ではありませんが、依頼者の名前やメールアドレス、コメント投稿時にパスワードを設定する必要があります。なお、オンラインでの削除依頼が難しい場合は、郵送で削除依頼することも可能です。その際は、以下の住所宛に削除依頼を郵送してください。
〒162-0815
東京都新宿区筑土八幡町6-7
株式会社大島てる
(2025年11月時点)

大島てる事故物件マップは、気軽に事故物件が見つけられる便利なサイトです。ただし、その情報を100%鵜呑みにしてしまうのは危険です。ここでは、大島てる事故物件マップを賢く使うための3つのポイントを紹介します。
それぞれのポイントを詳しく見ていきましょう。
先述したように、大島てる事故物件マップはユーザー投稿が主体のサイトです。そのため、すべての情報が正確であるとは限りません。嫌がらせ目的の投稿が含まれている可能性もあるため、掲載されている情報を鵜呑みにするのは避けましょう。
大島てる事故物件マップの情報は日々更新されていますが、新しい情報がリアルタイムで更新されているわけではありません。したがって、炎マークがないからといって、その物件が事故物件ではないとは言い切れません。
物件の詳しい情報については不動産会社でも確認することができます。また、インターネットでも過去のニュースを検索することができるため、自分で調べてみるのも有効です。大島てる事故物件マップはとても便利なサイトですが、掲載されている情報はあくまでも参考程度に留めておきましょう。

事故物件には告知義務がありますが、「何かあれば不動産会社が教えてくれる」と安心するのではなく、ご自身で事故物件を見分けるための知識を持っておくことが大切です。ここでは、事故物件を見分ける3つの方法を紹介します。
さっそく見ていきましょう。
事故物件がどうか見分ける最も簡単な方法は、図面や物件詳細情報の備考欄を確認することです。備考欄に「告知事項あり」「心理的瑕疵あり」と記載されている場合は要注意。特に心理的瑕疵は、ほぼ間違いなく事故物件と言えるでしょう。ただし、告知事項は心理的瑕疵に限定されたものではなく、以下の場合でも告知義務と記載する場合があります。
不動産取引では、上記のような瑕疵がある場合でも買主・借主に告知する義務があります。
最近は、内見せずネットに掲載された情報だけで物件を決める方も増えています。しかし、事故物件かどうか判断するためには内見することをおすすめします。事故物件には、シミや血液、体液などの汚れが染み付いています。この汚れはハウスクリーニングできれいな状態にしますが、臭いは通常のハウスクリーニングだけでは落としきれません。そのため、内見時に生ゴミのような臭いがしたり、異変を感じたりする場合は、不動産業者に確認したほうが良いでしょう。
事故物件は必ずしも値下げされているわけではありません。しかし、事故物件に対して嫌悪感を抱く方は一定数存在します。そのため、類似物件と比較して1割~5割程度価格を下げて貸し出したり、売却したりしているケースが多いです。特に、人気エリアにも関わらず家賃が安い物件は事故物件である可能性が高いでしょう。また、割引率は事故の種類にも関係しています。
ただし、上記はあくまでも一例であり、割引率は築年数やエリアによっても変動するため、詳しい情報は不動産業者に確認しましょう。
今回は、大島てる事故物件マップは終了したのかについて解説しました。大島てる事故物件マップは調べたい場所の住所を入力すれば、日本各地の事故物件を調べることができます。家探しをしている方にとって、事故物件かどうかは大きな問題です。今後の生活にも大きな影響を与えるため、事前に調べておくことで不安を減らすことができるでしょう。しかし、大島てる事故物件マップの情報だけで周辺地域の安全性を判断することは危険です。住む場所を決めるときは、実際に自分の目で見たり、警視庁の犯罪統計やニュースを参考にしたりしながら地域の安全性を判断しましょう。
なお、事故物件の不動産取引は、一定の条件下での告知義務が設けられています。そのため、正しい情報であれば、所有者や管理会社などの希望があっても掲載情報を削除してもらうことはできません。一方、不適切な情報や誤情報に対しては、訂正や削除される可能性が高いため、コメントで削除依頼をするか郵送で削除依頼を送りましょう。
気に入った不動産を見つけたとき、買主は売主に対する意思表示として、購入申し込みをすることが可能です。しかし、購入申し込みには法的拘束力がなく、キャンセルされてしまう可能性もあります。
本記事では、不動産購入の申し込みキャンセル率について解説します。キャンセルされる理由や対処法についても紹介しているため、これから不動産を売却しようとしている方は必見です。

購入申し込みとは、買主が「この物件を購入したい」という意志を売主に伝える重要なステップです。購入申し込みの際は、購入申込書や買付証明書といった書面を提出するのが一般的です。これらの書面には、買主の情報や買付価格が記載されているため、売主が買主を決めるための判断材料にもなります。
購入申し込みのタイミングは、多くの場合、物件の内見後です。気に入った物件を押さえる意味合いはあるものの、法的拘束力はないため、同じ物件に複数の購入申し込みが入ることもあります。
買主は購入申込書を出した後に、住宅ローンの事前審査を受けます。そして、事前審査に通過し、売主と条件合意できれば、晴れて不動産売買契約の締結に進むことができます。このように、購入申し込みは、不動産売買の出発点として非常に重要な役割を担っているのです。

購入申し込みは、不動産売買に向けた大きな第一歩。不動産売却を進めている売主にとって、購入申し込みが入ることは嬉しいものです。しかし、一度購入申し込みが入ったからといって、必ず契約に至るとは限りません。実際には、途中でキャンセルされるケースもあるのです。
キャンセルする背景には、買主のさまざまな事情や気持ちの揺らぎがあります。主な理由は、以下のとおりです。
購入申し込みは法的拘束力がないため、気軽に提出できるものです。その分、買主の少しの迷いがキャンセルにつながることも。
ここからは、それぞれのキャンセル理由について詳しく解説します。
不動産の購入は、人生の中でも指折りの大きな買い物です。そのため、購入申し込みをした後で「本当に支払えるのか」と不安になり、キャンセルに至るケースは少なくありません。
具体的には、以下のような理由が挙げられます。
「自分の収入に対して、物件価格が高すぎる」
「ローンの返済額を試算したら、購入後の生活が苦しくなりそう」
「子どもの教育費など、将来の支出を見落としていた」
資金面の悩みは、購入申し込み後に現実的な試算を始めたことで浮かび上がることが多く、結果としてキャンセルにつながってしまうのです。
物件に対して不安を感じ、キャンセルとなることもあります。多くの買主は購入した物件での長期的な生活を想定しており、快適に住み続けられるかどうかは重要なポイントです。また、将来的に売却する可能性も見据え、資産価値や売却のしやすさを重視する方も多いです。
たとえば、築年数が古く老朽化が進んでいる物件や、周辺の騒音・治安に懸念がある物件は、購入後の生活に不安を感じやすくなります。さらに、再建築不可や接道義務を満たしていないなど、法令上の制限がある物件は、「将来的に売却しにくいだろう」と敬遠される傾向があります。
こうした不安は、購入申し込みを出してから、物件の詳細を調べるうちに顕在化することが多いです。買主としては後悔のない選択をしたいため、購入申し込み後であっても、キャンセルを選ぶことがあります。キャンセルを減らすためには、内見時に物件の懸念点も含めて丁寧に説明することが重要です。
購入申し込みをした後で、他に魅力的な物件に乗り換えることは珍しくありません。たとえば、同じような条件で低価格の物件や、同価格帯でも立地や設備が優れている物件は、買主にとって魅力的な選択肢になります。
「より良い条件の物件を、少しでも安く買いたい」というのが、多くの買主に共通する心理です。購入申し込みを取り下げても、キャンセル料が発生しない場合「乗り換えたほうが得だ」と考えるのは自然の流れといえます。
こうした事態を防ぐためには、あらかじめ競合物件の情報を把握しておくことが大切です。そして、自分の物件と比較されたときに、どのような点に優位性があるか伝えられるようにしておきましょう。買主が他物件と迷ったときに、納得感を持って選んでもらえるようにすれば、キャンセルの抑止につながります。
家族に反対されて、購入申し込みをキャンセルしてしまうケースもあります。特に、一人で内見を済ませて、そのまま購入申し込みをしてしまうと、このような事態が起こりやすくなります。
たとえば、旦那さんにとっては理想的な物件でも、奥さんにとっては「騒音が気になる」「キッチンの使い勝手が悪い」など、生活面での不満が出ることも。このように、普段一緒に暮らす家族でも、物件に求める条件や価値観はそれぞれ異なるものです。
購入した後は、家族全員がその物件で暮らすことになるため、事前の同意は欠かせません。家族で住む予定がある場合は、内見の段階から全員で物件を確認し、納得したうえで購入申し込みをしてもらうほうが無難です。
もし一人で申し込みをして、後日家族が物件を見に来る場合は、意見の食い違いによるキャンセルのリスクが高まるため、慎重な対応が求められます。
ローンの審査に通らず、購入申し込みが白紙に戻ることもあります。たとえ購入の意志があっても、ローンの審査に通らなければ物件を購入することはできません。
買主は購入申し込みの後に、金融機関の事前審査を受けます。その際、収入など返済能力に問題があると判断されれば、審査を通過することはできません。買主自身の返済能力に問題がなくても、再建築不可や接道義務を満たさないなど、物件の条件が原因で審査に落ちることもあります。
審査基準は金融機関によって異なるため、一つの金融機関で審査に通らなくても、他の金融機関では通過する可能性があります。ただ、審査に落ちたという事実が、買主に資金面の不安を与え、「やはり購入は見送ろう」とキャンセルにつながることもあります。

購入申し込みのキャンセル率は公式に公表されていませんが、一般的には約1割〜1.5割程度といわれています。つまり、10件の申し込みがあれば、1件以上はキャンセルになる可能性があるということ。不動産を売却する立場からすれば、決して他人事とはいえない数字だと思います。
しかし、すべての物件が一様に1割〜1.5割のキャンセル率というわけではありません。キャンセルされやすい物件とそうでない物件があり、その差は大きく開いています。
キャンセルされやすいのは、物件情報が不十分、築年数が古い、立地に課題があるなど、買主にとって懸念材料がある物件です。逆に、築浅で立地条件が良く、内見時に物件の懸念点を丁寧に伝えている場合は、買主の納得感が高まるため、キャンセル率も低くなるでしょう。
売却を成功させるためには、物件の魅力だけでなく、誠実な対応も重要です。情報の透明性を高めることが、買主との信頼関係を築く鍵となります。

もし購入申し込み後にキャンセルが発生すると、売買の話は振り出しに戻り、売主としては精神的にも時間的にも、大きな負担となります。「買主へ何かペナルティを請求できないのか」と疑問を持つ方も少なくないでしょう。
購入申し込みには、基本的に法的拘束力がありません。そのため、買主にペナルティを請求するのは難しいのが現実です。
ただし、キャンセルが起きたタイミングによっては、ペナルティを請求できることも。ここからは以下の3つのタイミングに分けて、ペナルティの有無や適切な対処法について詳しく解説します。
売買契約を結ぶ前にキャンセルしてきた場合は、残念ながらペナルティを請求することはできません。購入申込書はあくまで「購入の意思表示」であり、法的な拘束力がないためです。
この段階で売主ができることは、まず買主からキャンセルの理由を聞くことです。解消できそうな理由であれば、条件の見直しや再交渉をおこない、売買の再開につなげることも可能です。
売買契約を締結した後に、買主がキャンセルを申し出た場合は、契約違反とみなされる可能性があります。この場合は、契約に記載された「違約金」や「手付金の放棄・返還義務」などの条項に基づき、対処します。
違約金と手付金の相場は、以下のとおりです。
違約金:売買金額の10%〜20%
手付金:売買金額の5%~10%
売買契約後にローンの本審査が不承認になった場合は、ローン特約が適用されるかどうかが重要なポイントです。それによって、ペナルティの請求可否が決まります。ローン特約とは、本審査に通らなかった場合に、契約を無条件で白紙に戻すことができる条項です。
この特約が契約書に盛り込まれている場合、買主は違約金なしで契約を解除できます。そのため、売主からペナルティを請求することはできません。
一方で、特約がない場合や、買主の書類不備や虚偽申告が原因で審査に落ちた場合は、違約金の請求が認められる可能性があります。

不動産を売却する場合、購入申し込みのキャンセルはできるだけ避けたいものですよね。売主の心がけによって、購入申し込みのキャンセル率を下げることは可能です。ここからは、キャンセルを防ぐために有効な方法について、以下のとおり解説します。
購入申し込みのキャンセルを防ぐためには、買主との信頼関係の構築が欠かせません。物件の良い面だけでなく、懸念点まで包み隠さず説明することで、買主は安心して判断できます。
たとえば築年数や周辺環境に関する質問には誠実に答え、生活のイメージを具体的に伝えることが重要です。売主の対応が誠実であれば、申し込み後の迷いや不安が減ります。
時間的な余裕を持つことも、キャンセル率低下につながります。売却を急ぎすぎると、買主も急かされてしまい、冷静な判断ができないまま申し込みをしてしまう可能性があります。
結果的に資金面や物件に対する不安、家族の反対などが浮き彫りになり、キャンセルにつながるケースも。余裕を持って内見日程を調整したり、複数回の見学を許容したりすることで、買主は納得感を持って意思決定できるようになります。
購入申し込みが入ったとしても、契約に至るまでにキャンセルが発生するリスクは常にあります。こうした事態に備えて、二番手・三番手の申し込み者を確保しておけば、売却活動を停滞させずに次の交渉に移ることができます。
人気エリアや条件の良い物件では、複数の申し込み者が現れることが多いです。購入の意志がある顧客に対しては、真摯に情報提供をおこない、安心感を与えることが重要です。そうすることで、次点の候補者として前向きな姿勢を維持してもらうことができます。
信頼のおける不動産業者に依頼することは、キャンセルを防ぐうえで何より重要です。中には、買主に購入申し込みを急かしたり、物件の良い面だけを強調したりする業者も少なくないからです。このような対応は買主の迷いや不安につながりやすく、結果的にキャンセルのリスクを高める要因となり得ます。
一方で物件のメリット・デメリットを丁寧に説明し、買主の資金状況や購入意欲を的確に見極めてくれる業者であれば、安心して売却を任せられます。買主が納得したうえで申し込みすれば、無駄なキャンセルを防ぐことができるでしょう。
購入申し込みは、買主が売主に対して「この物件を購入したい」という意志表示をするものです。しかし、法的な拘束力がないため、買主の迷いや不安が原因でキャンセルされてしまうことがあります。
こうした事態を防ぐには、物件のメリット・デメリットを包み隠さず説明することや、買主の購入意志を的確に判断することが肝心です。売主自身の誠実な対応と信頼できる不動産会社選びが、売却をスムーズに進める鍵となるでしょう。
「中古マンションを購入するなら、なるべく築浅の物件がいい」そう考える方は多いのではないでしょうか?中古マンションは新築よりも価格が安い傾向があり、なおかつ築浅であれば設備も新しくて、お得に感じますよね。
しかし、「築浅」というキーワードだけに飛びついてしまうと、思わぬ落とし穴にはまってしまうことも。本記事では築浅でも避けたほうがいい中古物件の特徴を中心にご紹介します。「中古物件選びに失敗したくない」という方は、ぜひ本記事の内容をチェックしてみてください。

築浅物件とは、できてから間もない中古物件のことです。「築年数が浅い」という言葉を略して、築浅と呼ばれています。
中古マンションの中でも、築浅物件は人気があります。設備が比較的新しい物件が多く、新築よりも価格を抑えやすいためです。
実際のところ、築浅=築〇年以内というはっきりとした定義は、存在しません。築何年を築浅とするかどうかは、不動産会社の判断によって分かれます。
一般的には、築5年以内とされることが多いです。しかし一方で、築10年でも築浅として扱われるケースもあります。
広告や物件情報に記載されている「築浅」という言葉だけに踊らされるのではなく、築年数がいつなのか、しっかりと確認することが大切です。
築浅物件は設備が新しく、見た目も綺麗です。高値が付きやすいため、売却のハードルが低い傾向があります。
築浅の中古物件が売却される背景には、さまざまな事情があります。主な売却理由を挙げると、以下のとおりです。
特に注意したいのは、3つ目の「周辺環境や間取りが合わなかった」ケースです。売主が実際に住んでみた結果、騒音や日当たり、動線の不便さなどがストレスとなり、住み心地に不満を感じて売却に至ることがあります。
このような物件を購入すると、自分自身も売主と同じような不満を抱えてしまい、長く住めなくなる恐れがあります。後悔を防ぐためにも、売主に売却理由を確認するようにしましょう。売主に直接聞きづらい場合は、仲介に入っている不動産会社を通して質問してもらうのも手です。

売主に売却理由を尋ねても、必ずしも物件のネックが明確になるとは限りません。さらに、住み心地の良し悪しは人によって感じ方が異なるため、物件選びではさまざまな視点からチェックすることが肝心です。
築浅でも避けたほうがいい物件の特徴は、以下のとおりです。
それぞれの特徴を具体的に見ていきましょう。
物件価格が相場よりも明らかに高い場合、築浅であっても損をしてしまうリスクがあります。もちろん、築年数が浅いことを理由に割高な価格設定になっている場合も多いのですが、築浅だけを売りにしすぎて立地や設備が相場に見合っていないことも。
相場より割高な価格で買ってしまうと、資産価値が下がりやすいです。仮に自分が売却するとなれば、その時点でさらに築年数が経過しているため、相場と同等の価格で売り出すと購入価格>売却価格となってしまい、売却損が出ます。
また、高額な住宅ローンを組むことで、返済負担が増し、生活のゆとりがなくなることも。「築浅だから」と安易に受け入れるのではなく、まずは周辺の取引事例や類似条件の売り出し物件と比較し、本当に妥当な価格なのかを確かめましょう。
事故物件とは、過去に他殺や自殺などの理由で、人が亡くなった物件を指します。法律上の明確な定義は存在しないのですが、不動産取引では「その事実を知っていたら契約しなかった」と判断される事案があった場合、心理的瑕疵物件として扱われます。
自分が住む場合に抵抗がなければ、生活に支障はないかもしれません。ただし、将来的に賃貸や売却を考えている場合は、心理的な抵抗感から入居者が集まりにくい傾向があります。
心理的な要因は人によって受け止め方は異なりますが、物件の資産性を重視するのであれば避けたほうが良いでしょう。売主や仲介会社に告知義務が果たされているかを確認し、過去の履歴を調べることが大切です。
中古マンションを選ぶ際に、意外と見落としがちなのが駐車場です。公共交通のアクセスが良好な都心の物件であれば大きな問題はありませんが、郊外の物件で駐車場がないのは致命的です。
結果として敷地外の駐車場を別で契約しなければならず、不便な生活を強いられることになるからです。駐車場料金の負担もかさみますし、売却する場合も資産価値の維持が難しくなります。
いくら築浅で設備が整っていても、駐車場がない物件は長期的な目線で見ると不利になることが多いため、慎重に検討したほうが良いでしょう。
線路沿いの築浅物件は、騒音や振動が大きなネックになることがあります。電車や踏切の音は窓を閉めていても、どうしても気になってしまう場合もあるでしょう。
早朝・夜間も騒音が続けば、睡眠の質も下がり、体を壊してしまいます。特に音に敏感な人には、線路沿いの物件はおすすめしません。
また振動による不快感や、建物への影響も懸念されます。売却や賃貸に出す場合も、線路沿いの物件は敬遠されやすいです。
もし気になっている物件が線路沿いに立地している場合は、時間帯を変えて内見に行き、騒音や振動を体感してみることが重要です。
墓地が近くにある物件は、静かで落ち着いた環境であることが多いですが、中には心理的な抵抗感・恐怖感を抱く方もいます。また、お墓は嫌悪施設に該当するため、不動産売却時の重要事項説明で買主へ共有することが求められます。
市場では敬遠されがちなため、売却や賃貸で不利になることがあります。お墓が持つマイナスイメージによって、市場相場よりも価格が落ちることも少なくありません。
気になる場合は仲介会社に確認してみるのはもちろん、内見時はすべての窓を開けてみて、墓地が近くにないか確認しておきましょう。
日当たりが悪い物件は、住み心地が損なわれるだけでなく、さまざまな面で悪影響があります。日照が不足することで、室内に湿気がこもりやすくなり、カビが生えやすくなります。そうなれば、建物の腐朽につながりかねません。
また、冬場は室温が下がりやすく、暖房費がかさむなど経済的な負担も増えます。心理的にも、自然光が少ない環境は気分が沈みやすく、居住者の満足度を下げる要因となります。
日当たりの悪さは、周辺の建物との関係性によって発生するものなので、単独で改善するのは難しいです。購入前に現地を複数の時間帯で確認し、周辺建物の影響や季節による日照条件を把握しておくと良いでしょう。
駅から遠い立地は利便性に欠けるため、日常生活に不便を感じやすいのが難点です。通勤・通学に時間がかかるだけでなく、買い物や外出などちょっとした移動も負担が大きくなります。
特に都市部では駅からの距離が、物件の資産性に大きな影響をおよぼします。立地条件は変えられません。「今は駅から遠くても問題ない」という方も、子どもが生まれたり、高齢になったりしたときに移動が大変になることも考えられます。
内見に行く際は、物件から駅まで自分の足で歩いてみて、距離や周辺環境を自分の感覚で確かめることが大切です。長期的な視点で見て、不便がないかどうかを確認するようにしましょう。

築浅物件を購入するメリットは、物件が比較的新しく清潔でありながら、新築よりも手頃な価格で取得できる点です。
「新築は予算的に難しいけれど、築年数が経った物件は使用感が気になる」という方にとって、築浅物件はちょうど良い選択肢といえるでしょう。
ここからは築浅物件を購入するメリットについて解説します。
築浅物件は建物がまだ新しく、築古物件よりも室内や設備の使用感が少なめです。壁や床の傷みも少なく、水回りも清潔で快適に使える状態が保たれています。
新築同様の住み心地を得られるため、入居後すぐにリフォームや修繕を行う必要がなく、そのままの状態で安心して生活を始められる点が大きな魅力です。
築浅物件は新築に比べて価格が抑えられていることが多く、予算に限りがある方でも手が届きやすいのがメリットです。
建物の状態は良好でありながら、購入価格を抑えられるため、コストパフォーマンスに優れています。築浅物件は、まさに新築と中古の良いところを兼ね備えた選択肢といえるでしょう。

築浅物件が築浅物件でいられる期間が限られているため、物件数が少なく、需要と供給の関係で価格が高くなりやすいなどのデメリットがあります。
また、新築と中古では住宅ローン控除の適用条件が異なるため、違いを理解した上で築浅を選ぶことが大切です。
築浅物件は市場に出回る数が非常に限られています。そもそも築浅と呼べる期間は、非常に短いです。その上、売却されるタイミングは所有者のライフイベントや転勤など特殊な事情によることが多いため、常に豊富に流通しているわけではありません。
物件が少ないということは、希望エリアや希望条件が固まっている方にとっては、それを満たす築浅物件を見つけるのがなおさら難しくなるということ。人気エリアでは購入希望者が集中しやすく、競争が激しくなる傾向があります。
そのため、じっくり比較検討することがないまま、妥協して購入してしまうケースも。築浅物件を狙う場合は条件の優先順位を整理して、早めに情報収集することが重要です。
築年数が浅い物件ほど、価格が割高になりやすい傾向があります。新築よりは安いものの、築10年以上の物件と比べると高めの価格設定が多く、コストパフォーマンスを考えたときに見劣りする可能性があります。
なぜ築浅物件が高いかというと、「新築から間もない」という心理的な安心感から需要が集中しやすいため。ライバルが多くなれば、さらに価格が上昇することもあります。
築浅物件の多くは「既存住宅」として扱われるため、住宅ローン控除を利用する際には新築よりも条件が厳しくなることが多い点に注意が必要です。
住宅ローン控除とは、ローン残高の一定割合を所得税から差し引ける制度ですが、新築住宅では最大13年間の控除が受けられるケースがある一方、既存住宅では原則10年に制限されます。
さらに、借入限度額も新築より低く設定されている項目が多く、同じローン残高でも減税額が小さくなる傾向があります。
ただし例外もあり、不動産会社がリフォームして再販する「買取再販住宅」は控除期間が13年に延長されます。また、省エネ基準を満たさない新築住宅はそもそも住宅ローン控除の対象外となるため、築浅物件であっても条件次第では新築より有利に減税を受けられるケースもあります。
つまり、築浅物件を選ぶ際には「既存住宅扱い」という不利な側面だけでなく、制度の適用条件を確認することで、思わぬメリットを享受できる可能性があるのです。

マンションの購入は大きな費用がかかるため、できる限り後悔のない選択をしたいものです。特に築浅物件は人気が高く、購入希望者が多いため、焦って購入してしまいがち。そうならないように、物件選びでは慎重さが求められます。
以下のポイントを意識して物件を選ぶと、失敗を避けやすくなります。
それぞれのポイントについて詳しく見ていきましょう。
築浅物件が適切な価格で売り出されているかどうかは、周辺相場を見ればすぐにわかります。逆に相場を知らずに購入すると、後々売却や賃貸に出すときに資産価値が下がりやすく、損失につながることも。
相場の調べ方は、不動産ポータルサイトや公的な取引事例データベースの活用がおすすめです。エリア・築年数・間取りが同じような物件に絞り込んで、客観的な価格帯を把握できます。
相場をしっかり理解しておけば、提示された価格が妥当かどうかを冷静に判断でき、安心して購入に踏み切ることができます。
建物と同じくらい、物件の住み心地を左右するのが、周辺環境です。地図アプリや人の話だけではわからないことも多いため、かならず自分の足で周辺を歩いてみましょう。
昼と夜、平日と休日など時間帯を変えて訪れることで、騒音や人通り、治安の雰囲気を把握できます。スーパーや病院、学校など、日常的によく利用する施設が近くにあるかどうかもチェックしておきたいポイントです。
また、線路や幹線道路が近いと、騒音に悩まされることも。墓場や工場が近いと、心理的な抵抗感や環境面の不安につながることもあります。
契約書には売買代金や引渡し条件だけでなく、物件の権利関係、管理規約、修繕積立金の額や支払い方法など、将来の生活に直結する情報が記載されています。
特に注意すべきは、物件の契約不適合責任やアフターサービスの範囲です。築浅物件であっても、売主や施工会社の保証期間がどこまで残っているかによって、万一の不具合発生時の対応が変わります。
また、管理組合の規約や修繕計画を確認することで、将来的な費用負担や住環境の維持に関する見通しを立てることができます。
不明点や不安がある場合は、必ず仲介会社や司法書士など専門家に確認し、納得したうえで契約を進めることが、後悔のない購入につながります。
築浅物件は、できてから間もない中古物件です。設備が比較的新しい物件が多く、新築よりも価格を抑えやすいため、人気があります。
市場に出回る物件数が非常に少ないため希少性が高く、需要が集中することで相場より割高に売り出されるケースも少なくありません。競合が多いとつい焦ってしまいがちですが、物件の条件や価格を冷静に見極めることが、後悔のない購入につながります。
そのためには、周辺の相場を確認すること、実際に周辺環境を歩いて確かめること、そして契約書の内容を丁寧に確認すること。こうした一つひとつのチェックを怠らない姿勢こそが、安心して暮らせる築浅物件選びのポイントです。
「住宅ローンの本審査に通れば大丈夫」と安心していませんか。実は本審査後も、油断は大敵です。さまざまな事情により、審査時の条件と変わってしまい、融資を受けられなくなる場合があるのです。
本記事では住宅ローン本審査承認後に落ちる理由や、どのくらいの確率で落ちるのか解説します。これからマイホームを購入予定の方は、本審査承認〜融資実行のプロセスを円滑に進めるために、本記事の内容を参考にしてください。

本審査の時と比べて経済状況や健康状態に変化があった場合、本審査に通過した後でも融資を受けられなくなる可能性があるため注意が必要です。経済状況や健康状態の変化とは、具体的に以下のようなケースが考えられます。
それぞれのケースについて、詳しく見ていきましょう。
金融機関は返済能力を重視しており、収入は最も重要な判断材料の一つです。
収入が変わる主なケースとして、本人の転職・退職などが挙げられます。さらに、夫婦2人の収入を合算して借りる収入合算タイプの住宅ローンでは、配偶者の収入変化も融資に影響をおよぼします。そのため、審査後の転職や退職は避けたほうが良いでしょう。
信用情報とは、借り入れや返済の履歴を記録したものです。クレジットカードの延滞や新たなローン契約は信用情報に悪影響を与える可能性があります。
絶対に避けなければならないのは、新しい借り入れをしたり、既にある借金の返済を遅らせたりすることです。クレジットカードは、キャンペーンなどで気軽に作ってしまいがちですが、金融機関からは「債務が増えた」とみなされる可能性があるため、要注意です。
さらに、金融事故といわれる自己破産や債務整理に陥った場合は、信用情報に深刻な傷がつきます。
年収に対するローン返済額の割合を、返済負担率といいます。
返済負担率=ローン返済額÷年収
返済負担率が高くなるほど、ローン返済の負担が大きくなります。そのため返済負担率が上がると、金融機関から「返済能力が低下した」とみなされ、本審査の承認を取り消される可能性があります。
返済負担率が上がる要因は、新たなローン契約や年収の減少が挙げられます。年収が変わらないのにローンの返済額が増えれば、返済負担率が上がってしまいます。一方で転職や離職の結果、年収が減って返済負担率が上がるパターンもあります。
本審査承認後は、新しいローンの借り入れや、転職・離職は控えたほうが良いです。
住宅ローンを利用する際には、団体信用生命保険(団信)への加入が求められることが一般的です。団信は、契約者が死亡または高度障害になった場合に、保険会社がローン残高を肩代わりしてくれる制度です。
住宅ローンを利用する場合は、金融機関による審査と、保険会社による団信の審査がおこなわれます。団信の審査では、持病や健康状態が重要な判断材料になります。
健康診断で異常が見つかったり入院や手術をともなう病気に罹ったりすると、場合によっては、本審査の承認取り消しとなる可能性があります。

そもそも住宅ローンを利用する場合は、本審査の前に事前審査というプロセスがあります。ここからは本審査と事前審査の違いについて解説します。
事前審査の目的は、住宅ローンを借り入れできるかどうか、「おおよその見込み」を確認することです。借り入れできる見込みがあると分かれば、物件の申し込みや売買契約に進む後押しになります。
売主にとっても、購入希望者が事前審査に通っていることは大きな安心材料です。複数の申し込みがある場合には、交渉を有利に進める要素にもなり得ます。
ただし、事前審査結果はあくまで仮の判断です。融資が確定したわけではないため、後の本審査で却下される可能性もあります。また、事前審査を受けたからといって、必ず借りなければならない義務もありません。
審査スピードは比較的速く、1〜3営業日程度で結果が出ます。提出書類もシンプルで、本人確認書類や源泉徴収票などが中心です。保険会社による団信の審査も、事前審査の段階ではおこなわれません。
住宅ローンの本審査とは、金融機関が申込者に対して「本当に融資を実行できるかどうか」を正式に判断するための審査です。事前審査があくまで仮の見込みであるのに対し、本審査は融資契約の可否を決定する重要なプロセスです。
本審査では、収入や勤務先の安定性、信用情報、返済負担率などが総合的にチェックされます。提出書類も多岐にわたり、本人確認書類や収入証明書に加え、売買契約書、住民票、印鑑証明書などが必要になります。また、団体信用生命保険(団信)への加入審査もこの段階で行われ、健康状態の申告が求められます。
本審査を受けるタイミングは、売買契約を締結した後です。審査期間は通常1〜2週間程度かかります。万が一本審査に通らず、融資を受けられなかった場合は、売買契約は解約となる可能性もあるため、慎重な準備が欠かせません。
無事に承認されれば、融資契約へと進み、物件購入の手続きが本格化します。

買主が本審査に落ちた場合、不動産売買を履行することができなくなり、原則として契約は不成立となります。そうなれば売主は予定していた売買金額を受け取れません。そのため、以下のようなペナルティが発生し得ることを覚えておきましょう。
本審査に落ちた場合、売主は融資を受けられず、売買代金を受け取れません。これは買主の都合による契約解除であり、融資を受けられず期日までに売買代金の支払わなかったことが債務不履行とみなされれば、違約金の支払いが発生する可能性があります。
違約金の相場は、売買金額の10%〜20%が目安です。売主が宅建業者であれば、宅建業法により違約金の上限金額が定められており、売買金額の20%を超えることはありません。
たとえば売買金額4,000万円の場合、違約金は400万円〜800万円程度です。かなり大きな金額であり、家計に大きな影響をおよぼすことがわかります。
しかし、後ほどご紹介する「ローン特約」を契約で定めている場合、融資が不成立となった場合も、違約金の支払いなしで契約を解除することが可能です。
契約の内容によっては、既に支払っている手付金が返還されないことがあります。手付金は不動産売買契約を締結するときに、買主から売主に対して支払うお金です。
法制度上、手付金には証約手付・解約手付・違約手付という3つの意味があり、それぞれの特徴は以下のとおりです。
| 種類 | 意味 |
|---|---|
| 証約手付 | 契約が成立したことの証明となる |
| 解約手付 | 契約当事者に解約できる権利を持たせる |
| 違約手付 | 債務不履行があった場合の違約金としての性質を持つ |
日本の不動産売買では、手付金は原則として「解約手付」として扱われることが多いですが、契約書に証約手付・違約手付と明記されている場合は、そちらの内容が優先されます。
解約手付の場合は、買主は手付金を放棄することにより、契約を解除することができます。手付解除ができるのは、契約相手が履行に着手する前までです。売主が登記準備を始めるなど、履行に着手していると、手付解除は認められない可能性があります。
手付金は売買金額の5〜10%で設定されることが多いです。4,000万円の物件価格だった場合は、200万円〜400万円となります。
ただし、住宅ローン特約があれば、本審査に通らなくても契約を解除でき、手付金についても全額返還してもらうことが可能です。

違約金や手付金は非常に高額になるため、「本審査の承認を取り消されたらどうしよう」と不安になりますよね。そのリスクヘッジとなるのが、住宅ローン特約です。ここからは、住宅ローン特約とは何か、その種類について解説します。
住宅ローン特約は、買主がローンの審査に通らなくても、違約金や手付金の没収を受けずに契約を解除できるようにするための特約です。
融資特約や融資条項とも呼ばれ、不動産売買契約または重要事項説明書に記載される、買主保護のための重要な特約です。この特約があることで、買主は融資否認という不可抗力に対して、契約解除の選択肢を持つことができます。
しかし住宅ローン特約は万能ではありません。買主が誠実に融資申込を行い、期限内に解除の意思表示をすることが前提です。買主としての履行を怠ると、特約が無効となり、違約金や手付金の没収が発生する可能性があります。
住宅ローン特約は、解除条件型と解除権保留型の2種類に分類できます。
解除条件型は、住宅ローンが不成立となれば、自動的に契約解除となるタイプです。買主が意思表示を忘れても契約解除される点は安心感がありますが、他に融資してくれそうな金融機関が見つかっても、契約は解除されてしまいます。
解除権保留型は、住宅ローンが通らなかった場合、買主が定められた期限内に意思表示をすることで、契約が解除されるタイプです。解除通知がなければ契約は継続するため、別の金融機関で改めてローン審査を受けられます。ただし期限までに意志表示をしないと、違約金などのリスクが発生する可能性があります。
解除条件型は、ローン不成立のリスクを最小限に抑えたい方におすすめです。一方で複数の金融機関でローン審査を受ける予定の方は、解除権保留型にしたほうが柔軟に対応できるでしょう。

ここまでローン不成立のペナルティや住宅ローン特約について解説してきましたが、リスクを避ける最も確実な方法は、そもそも本審査に通り、融資実行までその承認を取り消されないことです。ここからは本審査通過後、スムーズに融資を受けるために、意識しておきたいポイントを解説します。
金融機関は住宅ローンの融資をするとき「安定した返済能力」を重視します。転職や退職は収入の安定性が疑われる要因になり得ます。融資実行までは、現在の職場を変えないことが鉄則です。
収入合算で住宅ローンを申し込んでいる場合は、家族の収入変動にも注意しなければなりません。
審査後に借金の新たな借り入れや延滞があると、信用情報に問題があるとみなされ、融資が取り消されることがあります。
クレジットカードの新規発行や、ローン契約は控えましょう。クレジットカードの支払いやローンの返済も支払い遅延が起きないよう、期日管理を徹底することが大切です。
通常の審査では貯金額そのものが重視されることは少ないですが、返済負担率が高い場合や借入額が大きい場合には、金融機関から貯金額の確認を求められることがあります。
決済時には頭金や諸費用の支払いが必要になりますし、購入後の引越し費用や生活費も必要です。本審査に通ったからといって油断せず、貯金は計画的に維持することが大切です。
健康状態は団信の審査に大きな影響をおよぼします。融資実行前に健康診断等で異常が発覚すると、団信に加入できず本審査の結果が白紙になることも。
普段から体調管理を意識し、急な入院や病気にかかるリスクを減らすことが重要です。
融資実行前に、収入や健康状態に問題が発生すると、本審査に通過していても融資を取り消されることになります。そうなれば違約金や手付金没収などのリスクが生じるため、日頃の生活管理を徹底し、契約には住宅ローン特約を必ず盛り込んでおくことが重要です。
「埋蔵文化財包蔵地」という言葉を聞いたことがありますか?これから家を建てる場所がこの土地に該当する場合、工事に大きな影響が生じる可能性があるため、ぜひ押さえておきたいキーワードです。
この記事では、埋蔵文化財包蔵地とはどのような土地か整理したうえで、家を建てる場合のデメリットや売却する方法について解説します。これから家を建てようとしている方は必見です。

貝塚・古墳・住居跡などの遺跡や、石器・土器などの遺物が土の中に埋もれている土地を指します。文化財保護法によって定められており、開発によって貴重な文化財が失われるのを防ぐための仕組みです。
既に周知されているものは「周知の埋蔵文化財包蔵地」と呼ばれ、文化庁によるとその数は全国で約46万箇所にものぼります。そして発掘調査の件数は、毎年およそ9千程度。この数を見てもわかるように「自分の土地に遺跡が埋まっていた」というケースは決して珍しいことではありません。
たとえば家の基礎工事で土地を掘削していたら、土器が出てきたケース。この場合は新たに発見した包蔵地である可能性が高いため、自治体に確認して必要な手続きを踏むことになります。
もし適切な手続きを経ずに無断で発掘してしまうと、文化財保護法に違反する恐れがあるため、くれぐれも注意しましょう。無届発掘には罰則が設けられており、5万円以下の過料が科せられます。

家を建てることは可能ですが、着工前に現地の発掘調査がおこなわれるため、工事スケジュールが後ろ倒しになる恐れがあります。
最初の手続きとして、文化庁長官への事前の届け出が義務付けられています。これは周知の包蔵地はもちろん、新たに判明した包蔵地も同様です。
届け出内容を踏まえ、教育委員会がその土地での発掘調査をするかどうかの判断をします。過去に調査が実施されていない土地であれば、まず試掘調査をおこなう流れです。
試掘の結果、遺跡・遺物が見つからなければ予定通り工事を進めることが可能です。一方で何か発見された場合は、盛土などの方法で文化財を保護できないか協議することになります。
保存が不可能であれば、遺跡の記録を残すための本発掘調査が始まります。現状を変更することは許されないため、工事が2カ月〜1年もの間ストップしてしまうことも。さらに、本発掘調査にかかる費用は、開発事業者が負担するのが一般的です。
このように包蔵地に家を建てることは、所有者にとって負担が大きく、ほとんどメリットがありません。
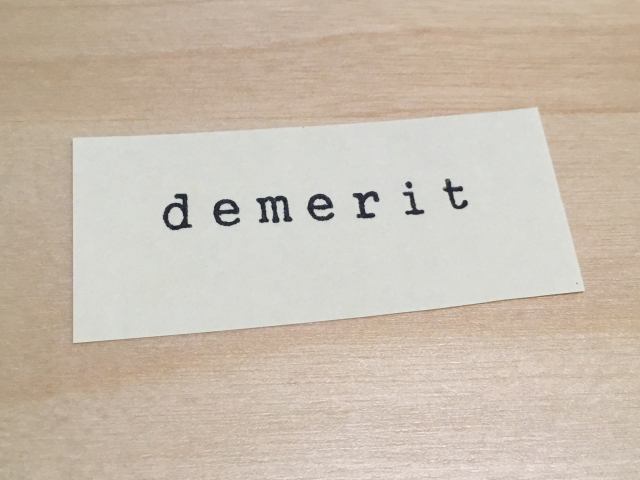
包蔵地で家を建てる場合のデメリットは、以下のとおりです。
それぞれのデメリットについて、詳しく見ていきましょう。
本発掘調査にかかる費用は、基本的に開発者で負担する必要があります。「令和6年度 埋蔵文化財関係統計資料」によると、個人住宅を建てる前におこなわれた本発掘調査費の合計は、677件で7億4,251万円。つまり1件につき110万円程度かかる計算になり、金銭的な負担が非常に大きいことがわかります。
ただし、個人が家を建てる場合は、本発掘費の負担は求めないケースがほとんどです。代わりに、国庫補助など公費を使って費用が支払われます。
文化財が埋まっている場合は、事前の届け出や発掘調査が必要になり、その影響で工事着手が遅れる可能性があります。
まず事前の届け出に関しては、工事着手の日から60日前までにおこなわなければなりません。事前に該当することが分かっているのであれば、全体のスケジュールを見据えて届け出の準備ができます。しかし、新たに遺跡が出土した場合は、その時点で届け出をしなければならず、自治体の判断を待つ時間が発生します。
また、発掘調査が必要と判断された場合は、さらに工事着手が後ろ倒しになります。試掘期間は1日から1週間、本発掘期間は数週間から1年以上かかることも。家を建てたくても、調査のスケジュールを優先しなければならず、施主にとっては大きな負担になるでしょう。
包蔵地に家を建てる場合、工期遅延によって、固定資産税の住宅用地特例を受けられず、税金の負担が増える可能性があります。
固定資産税の住宅用地特例は、住宅用地の固定資産税を減額する制度です。200㎡までの小規模住宅用地は課税標準が6分の1、200㎡を超える一般住宅用地は課税標準が3分の1に軽減されます。
ただし、本特例を受けられるのは1月1日時点で住宅が建っている土地です。そのため、更地の状態では適用を受けられません。更地の状態で土地を購入した場合や、家の建て替えのために古家を取り壊した場合は、注意が必要です。埋蔵文化財の発掘調査が長引き、翌年の1月1日時点で家が完成していなければ、通常の税率で固定資産税を支払うことになります。
いざ売ろうとしても、買い手が見つかりづらいのが現実です。先述のとおり、家を建てる場合は、工期遅延や発掘費用の負担などのリスクがあり、買い手から敬遠されるためです。
さらに、買い手が住宅ローンの融資を受けられない可能性もあります。上記のような工事遅延リスクがあるため、金融機関は自治体からのお墨付きがもらえない限り、住宅ローン審査を通さないことが多いのです。住宅ローンを利用できなければ、買い手の金銭負担は大きくなる一方です。
買い手は、できるだけリスクが少ない土地を選ぶ傾向があります。相場どおりの価格では売るのは難しく、包蔵地であることを理由に値下げを求められるケースも少なくありません。

埋蔵文化財包蔵地で家を建てるのは、多くのデメリットがあります。そのため、売却する際は、後々トラブルにならないよう慎重な対応が必要です。
埋蔵文化財包蔵地をスムーズに売却する方法は、以下の3つです。
それぞれの方法について、詳しく見ていきましょう。
埋蔵文化財包蔵地かどうか定かではない場合、まずは自分で調べてみることが大切です。多くの自治体では、土木・建築工事を予定している方向けに、埋蔵文化財の照会を受け付けています。
照会方法は、自治体の窓口に直接行くか、ファックスなどの方法で対応可能です。自治体の回答は書面で発行されるため、記録として残すこともできます。照会の結果、埋蔵文化財包蔵地に該当しない場合は、買い手にとって大きな安心材料になるでしょう。
ただし、事前に調べていても、工事中に埋蔵文化財が発見されるケースもあります。この方法で100%保証できるとは言い切れませんが、売主として必要な手続きを踏み、責任を果たしたうえで売却に臨むことができます。
売却する土地が埋蔵文化財包蔵地に該当する場合は、買主に対する丁寧な説明が必要です。口頭による説明だけでなく、重要事項説明にも記載し、認識の齟齬が起きないよう注意しましょう。
埋蔵文化財包蔵地である事実に加え、家を建てる際に必要な手続きまで説明するのが望ましいです。特に事前の届け出義務や工期遅延のリスクについては、買主も知っておきたいポイントのため、具体的に説明することが大切です。
もし埋蔵文化財包蔵地であることを隠して売却した場合は、契約不適合責任に基づき、買主から契約解除や損害賠償などを求められる可能性があります。たとえ売却に不利となる情報であっても、土地の状況を正直に伝えることが売主としての責任です。
埋蔵文化財包蔵地を売りに出してもなかなか買い手がつかない場合は、買取業者に売却するという選択肢があります。買取業者は埋蔵文化財包蔵地など敬遠されがちな土地でも、一定の条件下で積極的に買い取ってくれるため、売却のハードルを一段下げることができます。
また、買取業者はプロの不動産会社であり、契約不適合責任が免除される点も大きなメリットです。売却後にトラブルが発生するリスクを軽減できるため、安心して売却することができます。
ただし、買取価格は仲介による売却価格の7〜8割程度が相場になります。できるだけ高く売りたいという方には向きませんが、一刻も早く土地を手放したい場合や煩雑な手続きから解放されたい場合は、有力な選択肢になるでしょう。
埋蔵文化財包蔵地とは、歴史的な遺跡や遺物が土の中に埋もれている土地で、文化財保護法の保護対象になっています。
このような土地に家を建てる場合は、事前の届け出や発掘調査が必要になります。結果として工事着手が遅れるリスクがあるほか、発掘調査費の負担を求められたり、固定資産税の減額を受けられなかったりと、所有者に不利益が生じる可能性があります。
これらの背景から、埋蔵文化財包蔵地は売却時にも買い手から敬遠されがちです。スムーズに売却するためには、自治体の照会サービスにより埋蔵文化財包蔵地かどうかを明らかにし、該当する場合は重要事項説明に明記するなどして、買い手に丁寧に説明することが大切です。
早期売却を目指す場合は、買取業者への売却を検討するのも手です。ただし買取業者への売却は価格が安くなる傾向があります。それぞれの選択肢のスピードと価格のバランスを見極めて、納得いく売却方法を選ぶことが大切です。
高圧送電線は「高圧線」とも呼ばれ、各家庭に電気を届ける重要な役割を担っています。一方で、住む場所の近くに高圧送電線があると、人体への影響や健康被害を不安視する方もいるでしょう。「一生に一度」とも言われる住宅購入では、あらかじめ気になることやリスクをしっかりと把握しておくことが大切です。そこで今回は、高圧送電線とは何か、高圧送電線の電磁波による人体への影響、高圧送電線が近くにあることのメリット・デメリットなどについて詳しく解説します。住宅購入を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

まずは、高圧送電線(以下、高圧線)は、どのようなものか理解しておきましょう。電圧には、「低圧」「高圧」「特別高圧」の3種類があります。
| 低圧 | 600V以下 |
|---|---|
| 高圧 | 600V以上7000V以下 |
| 特別高圧 | 7000V以上 |
高圧線は、文字通り強い電圧の電気(6600V)を運ぶための電線です。家庭で使用される低圧線は100V~200Vであるため、高圧線には強力な電力が通っていることがわかります。高圧線は威力が強く、感電の危険性が高いため、人や植物などが触れないよう電柱や鉄塔の最上部に設置されています。

物件の近くに高圧線がある場合、「人体への影響や住宅被害は大丈夫?」と不安に感じる方も少なくありません。ここでは、人体への影響があるのか、住宅被害は大丈夫なのかについて解説します。
結論から言うと、人体へのリスクがないとは言い切れないため、個人の考えに応じて選択する必要があるというのが現状です。国際がん研究機関(IARC)では、送電線や家電製品に関係する電磁波の発がん性について「可能性があるかもしれない」と分類しています。しかし現時点では、高圧線の人体への影響や健康被害について明確な因果関係は証明されていません。
また、東京電力の調査によると、送電線や変電機器などの近くは電磁波が大きいものの、普段生活している場所では身近な家電製品と同じかそれ以下の電磁波レベルだと言われています。(ただし、距離による。)これを見ると、家庭内にある家電製品やスマートフォンからも電磁波は発生しているため、過度に心配しすぎる必要はないとも考えられます。
一方で、日本が設けている規制上限(電磁界の上限値)は、韓国・ドイツ・スイスなどが設けている値より高く設定されています。また、「長期的な影響の存在を示す科学的な証拠」が現時点では見つかっていないことから、安全だと断言するのは難しいと言えるでしょう。
高圧線や送電線は日頃から保守点検され、必要に応じて工事も行われています。そのため、基本的には電線が切れて住宅や住民に被害を与える可能性は低いでしょう。しかし、メンテナンスが行き届いていなかったり、電線の劣化が進んでいたりすると電線が切れてしまうことがあります。
また、大地震や豪雨、洪水などが発生した場合も同様に電線が切れてしまう可能性があるでしょう。このとき、切れた電線に近づいたり触れたりしてしまうと、感電する可能性があり大変危険です。実際に断線が発生すれば、住宅や住民に被害が出る可能性はゼロとは言い切れないでしょう。

高圧線や送電線が近くにあることで、大きなメリットが得られるケースもあります。ここでは以下5つのメリットを紹介します。
ご自身の希望条件と照らし合わせながら見ていきましょう。
高圧線の鉄塔が近くにあると「電磁波の影響がある」「危険」と考える方が一定数存在するため、土地や住宅は価格が安くなる傾向にあります。場合によっては、周辺相場より大幅に値下げして売り出しされることもあるため、価格重視の方にとっては大きなメリットとなるでしょう。
高圧線が敷地内の上空を通っている場合、線下補償料が支払われるケースがあります。線下補償料とは、電力会社から受け取れるお金のことで、送電線による建物の高さ制限、地価の下落など「土地の利用価値が制限されることに対する対価」として支払われます。線下補償料は地域や契約内容によって異なりますが、一般的には以下の計算式で算出されます。
補償額=単価×使用面積×使用年数
たとえば、単価2,000円、敷地が100㎡の住宅では、年間20万円支払われることになります。これはあくまでも一例ですが、意外と大きな金額になることもあるため、気になる物件があれば線下補償料がもらえるのか確認してみることをおすすめします。
敷地内に電柱が立っている場合も、電柱敷地料という使用料がもらえます。ただし、先ほど紹介した線下補償料に比べてもらえる額は少ないです。物件の状況によっても異なりますが、年間2,000円未満と考えておきましょう。少ない金額かもしれませんが、日々の電気代が少しだけ安く使えると考えるとお得に感じられます。
雷は高い場所に落ちるという性質を持っているため、近くの高い建物に落雷した場合、少なからず人や建物にも影響があります。しかし、鉄塔はしっかりとした落雷対策がされているため、落雷による周辺地域への被害は少ないでしょう。また、鉄塔は避雷針の役割も担っているため、雷が落ちたとき電気を地面に流してくれるはたらきがあります。
高圧線近くは、建物の高さ制限があったり、建物が少なかったりするため、日当たりが確保しやすいというメリットがあります。また、広い空間が確保しやすいことから風通しの良い物件が多いです。日当たりや風通しは、カビや結露の発生を防ぐ、快適な室内空間を維持するなど住宅の寿命を延ばすだけでなく、住人の心身の健康維持にも大きなメリットとなるでしょう。
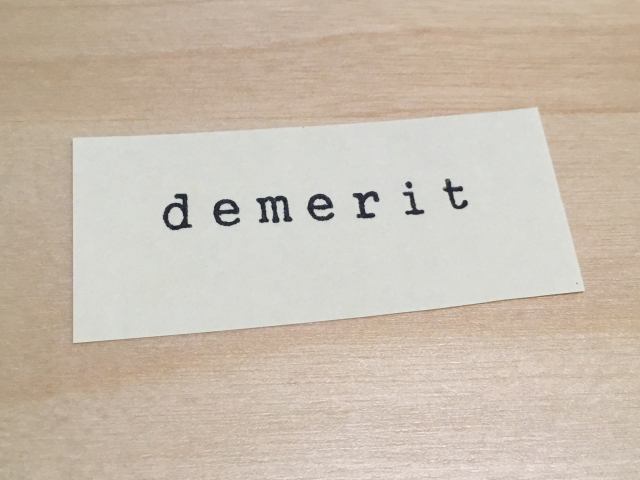
次に、高圧線や送電線が近くにあることで考えられる5つのデメリットを紹介します。
高圧線や送電線による意見は賛否両論です。ご自身の意見や考えをしっかり整理して、デメリットに影響されすぎないよう気を付けましょう。
多くの方が不安になるのは、やはり「電磁波の問題」でしょう。先述した通り、現時点では人体への影響や健康被害について明確な因果関係は証明されていません。しかし、どうしても「電磁波」を不安視する声は多いものです。また、電磁波の影響については、インターネット上にも様々な意見があります。中には根拠のない情報もあるため注意が必要です。住宅購入時は「あれも、これも」と希望条件が膨らみがちですが、あまり多くを求めると物件購入のチャンスを逃がしてしまいます。ご自身やご家族で何を優先すべきか、住宅に求める条件に優先順位をつけて考えてみましょう。
高圧線や送電線が近いと、「景観が悪くなる」というのもデメリットの一つです。特に、眺望の良さを求める人にとっては、大きなデメリットになる可能性があります。たとえば、毎朝起きて窓を開けたとき、目の前に大きな鉄塔や電柱、電線が広がっているとどうでしょうか。景観については個人差も大きいですが、人によっては、圧迫感や閉塞感を感じてしまうこともあるようです。一方で、景観をあまり気にしない人にとっては大きなデメリットとはならないでしょう。
高圧線などの鉄塔は、嫌悪施設に該当します。嫌悪施設とは、周囲の人から嫌煙されやすい建物のことで、具体的には以下のような建物や施設のことです。
上記に該当する建物が物件周辺にあると、物件が売れないという問題が起こりえます。なかなか売却できなければ、売却価格を大きく下げたり、更地として売り出したり、売却方法を工夫する必要が出てくるでしょう。将来的に売却を検討している方は、これらのデメリットを踏まえた上で慎重な判断が必要です。
電線近くの物件は、建築制限が設けられているケースがあります。たとえば、高圧線の下に位置している土地(高圧線下地)では、離隔距離の制限によって「建物の高さを送電線から3m以上低くしなければならない」というルールがあります。これらは、新築を建築するときだけでなく、建て替えや増築する際にも制限がかかってしまうため注意が必要です。特に中古住宅を購入して増築を検討している場合、希望通りの増築ができない可能性もあるため、あらかじめ不動産会社に確認しておきましょう。
天気の悪い日や、湿度の高い日は送電線から音が鳴ることがあります。これは、「コロナ放電」と呼ばれる現象です。コロナ放電は、送電線の周囲にある空気が高電圧によって部分的に分離し、電流が空気中を通る際に音が発生します。「ジジジ」「ビリビリ」「バチバチ」などの音がするため、静かな住宅街では気になる方もいるでしょう。また、夜中にこの音が鳴りだすと気になって眠れないという方もいるかもしれません。そのため、購入前に現地で音がしないか確認してみるのがおすすめです。天気の悪い日に行くことで、状況がより把握しやすくなるでしょう。
今回は、高圧線や送電線の人体への影響や健康被害について、また高圧線が近くにあることで考えられるメリット・デメリットについて解説しました。高圧線が近いと、どうしてもデメリットに目が行きがちですが、多くのメリットも存在します。
本文中でもお伝えしたように、現時点では高圧線や送電線の人体への影響について明確な因果関係は証明されていません。しかし、物件近くに鉄塔や電柱があることを不安視する方が多いのも実情です。不安を感じたまま生活するとストレスを感じて、また引っ越しをすることにもなりかねません。人体へのリスクがないとも言い切れないため、ご自身や家族の考え方に応じて慎重に判断しましょう。
賃貸マンションやアパートを経営するオーナーにとって、管理会社との関係は非常に重要です。連絡しても対応してくれないなど、管理会社の対応が悪いと、賃貸経営にも悪影響を及ぼします。
この記事では、対応が悪い管理会社の特徴やそのような管理会社を使い続けるデメリットについて解説します。対応が悪いときに、どのような対処法を取るべきかまで解説しているため、管理会社との関係にお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。

賃貸経営が成功するか否かは、管理会社の力量にかかっているといっても過言ではありません。
管理会社の仕事は、オーナーに代わって賃貸物件の運営・管理をおこなうこと。具体的には空室の募集や入居者審査、家賃の回収、クレーム・トラブル対応、退去手続きなど多岐にわたります。
これらの業務を遂行する上では、入居者と接触することも多いため、入居者満足度に直結する重要な仕事を管理会社に任せているということになります。

管理会社の対応が悪いと、入居者満足度が低下し、賃貸経営に悪影響を及ぼします。それでは対応が悪い管理会社を見極めるには、どのようなポイントに注意すれば良いのでしょうか?対応が悪い管理会社の特徴は、以下のとおりです。
それぞれの特徴について、詳しく見ていきましょう。
何か確認事項があって管理会社に連絡をしても、対応してくれなかったり、対応が遅かったりしませんか。もし思い当たる場合は、管理会社の対応力に問題があるといえます。
不動産管理の仕事は、スピードが命です。たとえば水漏れが発生した場合、入居者からすれば、一刻も早く修理してもらいたいですよね。それなのに、こちらから連絡をしても管理会社から何の反応もないようでは、入居者の不満は募る一方です。
対応が遅れる背景には、担当者の手が回っていないケースやクレーム対応を避けているなど、さまざまな理由が考えられます。いずれの理由にせよ、迅速な対応ができない管理会社は、信頼できるパートナーとは言い難いです。
管理会社の担当者が横柄だったり無愛想だったりすると、入居者からの印象が悪くなります。電話やメールのやりとりが雑、現地対応の時に挨拶もないという状態では、「このマンションは、本当に大丈夫なのかな」と不安を抱かれるのも無理はありません。
オーナーにとっても、態度が悪い管理会社は大きなストレス要因です。報告が遅い、こちら側の質問に対して面倒そうな態度を取られるなど、誠意のない対応が続けば、安心して任せることができません。
管理会社は物件の顔であり、入居者の窓口になる存在です。その対応ひとつで物件の印象や入居者満足度が大きく左右されます。そして担当者の態度の悪さは、入居者満足度の低下だけでなく、空室率の上昇にも直結します。
オーナーと入居者双方が安心できるよう、態度の悪い管理会社は早めに見直し、誠実な対応ができる管理会社への乗り換えを検討したほうが良いでしょう。
本来、入居者からのクレームの一次対応は、管理会社の役割です。騒音、設備不良、近隣トラブルなど、日常的に発生する問題は、管理会社側で処理し、オーナーには必要な報告だけが届くのが理想的な体制といえます。管理会社が入居者との窓口として機能するからこそ、オーナーは安心して本業や賃貸経営に集中できるのです。
しかし、対応力に欠ける管理会社の場合、入居者が直接オーナーに連絡してくるケースが増えてしまいます。これは、管理会社とのやり取りがうまくいかず、「管理会社と話しても解決しない」と入居者が感じてしまっている証拠です。感情的になりやすいクレームほど、管理会社が適切に対応できないと、オーナーが矢面に立たされることになります。
入居者からの直接連絡が常態化すると、オーナーの精神的負担は大きくなり、対応に追われることで本業に支障をきたす可能性も。入居者の不満がたまると、物件の評判にも悪影響を及ぼします。インターネットの口コミやレビューで「管理が行き届いていない物件」として認識されると、入居希望者の印象も悪くなり、空室リスクが高まります。
頻繁に入居者から直接連絡が来るようであれば、管理会社がクレーム対応を十分に担えていない可能性があります。オーナーの負担を軽減し、物件の価値を守るためにも、対応力のある管理会社への見直しを検討することが重要です。
設備が故障した際、迅速に修理対応が行われないと、入居者の不満は一気に高まります。特に給湯器やエアコンなど、日常生活に欠かせない設備の不具合は、1日でも早く対応しなければ生活に支障をきたします。
入居者が困って管理会社に連絡しても、対応が遅れたり放置されたりすると、信頼は失われます。修理の手配が後回しになり、連絡もないまま時間が過ぎていくような状況では、入居者の不満が募るばかりです。オーナーにとっても、修理の見積もりが遅かったり、発注までに時間がかかったりして、物件運営に支障をきたします。
一方、対応力のある管理会社は、設備の故障に対して即座に動くフットワークの軽さがあります。入居者の不安を最小限に抑えるとともに、オーナーにも迅速に報告してくれるでしょう。こうした姿勢が、入居者満足度の向上と物件の価値維持につながります。修理対応のスピードと丁寧さは、管理会社の質を見極める重要なポイントです。
空室対策も、管理会社の重要なミッションの一つです。にも関わらず、空室がなかなか埋まらない場合、管理会社の対応力不足が関係している可能性があります。
たとえば、募集活動を怠っている、内見対応が不親切、広告の写真や文章のクオリティが低いなどの理由で、入居希望者の関心を引けず、空室が長引くケースは多いです。
特に、物件情報の掲載が遅れたり、写真が暗く魅力が伝わりづらかったりすると、他の競合物件に埋もれてしまいます。オーナーに空室対策を任せられている以上、管理会社には戦略的な募集活動をおこなう責任があります。
優良な管理会社は、物件のターゲットを的確に見極め、そのニーズを満たせるような募集活動を実行していくはずです。広告では物件の魅力を最大限に引き出し、空室期間を最小限に抑える努力を惜しみません。
空室が続いている場合は、管理会社の対応を見直すことが、収益改善の第一歩となる可能性があります。
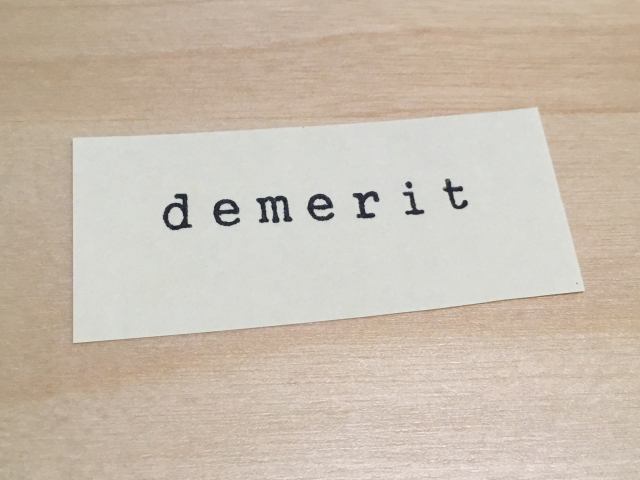
対応に問題がある管理会社を使い続けると、入居者にとっても、オーナーにとっても悪影響を及ぼします。具体的なデメリットは、以下の通りです。
それぞれのデメリットについて、詳しく見ていきましょう。
対応に問題がある管理会社は、修理や点検の対応を後回しにする可能性があります。共用部や専有部の設備が適切なタイミングで修繕されないと、物件の劣化が加速し、住環境に深刻な影響を及ぼします。
たとえば物件が劣化すると、雨漏りや排水不良などのトラブルが発生し、住まいとしての安全性や快適性を損なわれます。入居者の生活の質は悪化し、そのような状態が長く続けば、退去につながりかねません。
影響は入居者だけにとどまりません。たとえば、外壁タイルが剥がれて落下すれば、近くを通りがかった人がケガをするなど、近隣住民も危険にさらされます。
見た目もボロボロになって見栄えが悪くなり、好んで住む人はいなくなります。そうなれば、物件全体が徐々にスラム化していくリスクも否定できません。
こうした事態を防ぐためには、適切な修繕は物件を継続的におこなうことが不可欠です。安全・快適な住環境を守るために、管理会社の対応に不安がある場合は、早めに手を打ちましょう。
管理会社が自らの職務を果たせない場合、貸主であるオーナーの負担は増える一方です。
たとえば、入居者からのクレームがオーナーに直接寄せられるようになりますし、漏水などの緊急対応では、オーナーが直接修理業者を手配するような事態も起こり得ます。
さらに、修繕の不備が原因で、近隣住民に危害を加えてしまった場合、事故や訴訟リスクといった法的なリスクも高まります。
管理会社は本来、オーナーの業務を代行し、負担を軽減するための存在。にもかかわらず、かえってオーナーの負担を増やしてしまうようでは、わざわざ管理費を払ってまで管理会社に委託する意味がなくなってしまいます。
管理が行き届いていない物件に、住みたいと思う人は誰もいません。一度発生した空室を埋めるのは非常に難しく、長い時間を要するでしょう。
空室が長期間続くことは、オーナーにとって多くのデメリットがあります。一つ目はキャッシュフローの悪化です。空室の部屋は収入がゼロになるため、空室期間が長引くほど、キャッシュフローはどんどん悪化していきます。
また、「人気のない物件」というネガティブな印象を抱かれるリスクもあります。長期間にわたり広告を出し続けることで、物件の魅力が疑問視され、仲介会社や入居希望者から敬遠されてしまうのです。
こうした状況を打開しようと、安易に家賃を下げたり、入居審査の基準を緩めたりするのは避けるべきです。短期的には空室が埋まっても、長期的にはキャッシュフローや物件のブランド価値を損なう結果になりかねません。
まずは管理会社の募集活動に改善の余地がないか検討し、根本的な対策を講じることが大切です。

管理会社の対応が悪いときは、以下のような対処法があります。
まずは、管理会社の担当者に不安に思っていることを直接伝えてみましょう。伝え方は、記録が残るメールや書面での連絡をおすすめします。口頭や電話では内容が曖昧になりやすく、意思疎通が十分に図れないケースも多いからです。
文面では、管理会社にどう対応してほしいのか、要望を伝えます。たとえば「修繕対応を〇月〇日までに実施してほしい」など、内容と期限を明確に伝えることで、相手も対応しやすくなります。
そして何より大切なポイントは、感情的にならず、冷静な姿勢を保つことです。やりとりの経緯や事実を正確に記載することで、担当者も状況を社内に報告しやすくなり、会社としての対応も検討しやすくなります。
それでも改善が見られない場合は、担当者の変更を申し出ることも選択肢の一つです。その際は、担当者本人ではなく、管理会社や担当部署の責任者に直接連絡を取るようにしましょう。
管理会社と話しても、聞き入れてもらえない場合は、公的な相談窓口に相談するのも手です。たとえば、各都道府県の宅建協会では、「不動産無料相談所」という無料の相談を受け付けています。
最終的な選択肢は、管理会社の変更です。こちらから不安や要望を伝えても状況が変わらないようであれば、その管理会社を使い続けるメリットは薄れてしまいます。
新しい管理会社を選ぶ際は、担当者の人柄や信頼感を見るのはもちろんのこと、空室対策の実績や、トラブル対応の柔軟さなど、実務面での対応力もしっかりと見極めたうえで選ぶのがポイントです。
担当者の対応が遅かったり、態度が悪かったりする管理会社は、対応に問題があると言わざるを得ません。そのような管理会社を使い続けると、入居者の満足度が低下し、物件のブランド価値を損なうリスクがあります。実務面でも、入居者からクレームが来る、空室が埋まらないなど、オーナーに大きな負担がかかります。
不満を感じている場合は、早めに管理会社に連絡し、具体的な改善点を伝えましょう。それでも改善が見られない場合は、管理会社を変えるという選択肢もあります。管理会社の変更は一定の手間がかかりますが、長期的に見れば、物件の価値や入居者満足度を守るために欠かせない判断です。信頼できるパートナーを選び、安定した賃貸経営を目指しましょう。
賃貸物件から引っ越す場合、管理会社による退去立会いがおこなわれます。これは、退去時に部屋の状態を確認し、必要な修繕の範囲を判断するための重要なプロセスです。退去立会いで何を確認されるか事前に把握しておくことで、修繕費用に差が出る場合もあります。
本記事では賃貸物件の退去立会いについて解説します。日程の決め方から、引越し当日の流れ、どのようなポイントがチェックされるかまで詳しくまとめています。これから引越しを控えている方は必見です。

管理会社は、退去立会いによって物件の状態を確認し、必要な修繕の範囲や費用負担を判断します。
引越し当日に行われるのが一般的ですが、荷物の搬出入でバタバタする場合は、別日に設定することも可能です。
借主側は入居者本人、貸主側は管理会社の担当者が立ち会うケースが多いです。双方で部屋の状態を確認しながら、たとえば壁の汚れが入居前からあったものか、入居中に発生したものかなどを協議します。
この確認は、修繕の範囲や費用負担について合意を得ることが目的であり、後々のトラブルを防ぐためにも非常に重要です。
その後におこなわれる修繕工事は「原状回復」と呼ばれますが、これは単に「借りた当時の状態に戻すこと」ではありません。
国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によれば、原状回復とは「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義されています。
つまり、入居当初からの傷や汚れ、自然な経年劣化などは貸主の負担で修繕されるべきということです。賃借人が負担するのは、故意や過失による損傷、注意義務違反、または通常の使用を超えるような使い方によって生じた損耗・毀損に限られます。
立会いでは、こうした判断が現場で行われるため、事前に流れや確認ポイントを把握しておくことが、余計な費用負担を避けるためにも大切です。

引越しの日時が決まったら、できるだけ早めに管理会社へ連絡し、立会いの日程を調整しましょう。連絡が直前になると、担当者のスケジュールが合わず希望日に対応できないこともあるため、遅くとも2週間前には希望日時を打診しておくのが安心です。
立会いは、荷物をすべて運び出した後から解約日までの間で設定するのが一般的ですが、可能であれば引越し当日に立会いを依頼すると、旧居に戻る手間が省けて効率的です。
また、立会い日までに電気・ガス・水道などのライフラインの停止手続きを済ませておく必要があります。ただし立会い当日には、電気・ガス・水道の動作確認もあるため、立会い時までは使用できる状態にしておきます。

通常、20分〜40分程度で完了します。ただし、物件が広い場合や確認事項が多い場合は、1時間ほどかかることも少なくありません。
基本的には短時間で進行しますが、修繕範囲や費用負担の話し合いで意見が食い違うと、立会いが長引くこともあります。
このように短時間で終わるケースが多いものの、状況によって所要時間が大きく変動する可能性があるため、注意が必要です。
特に一人で近隣エリアに引っ越す場合、立会いを引越し当日に設定すると、新居での荷物受け取りに間に合わないリスクがあります。
万が一の場合を想定して、引越しの翌日に設定したほうが、余裕をもって行動できるでしょう。

立会いの流れは、以下のとおりです。
立会いの前には、部屋の荷物をすべて運び出し、何もない状態にしておくことが基本です。これは、管理会社が壁や床の傷・汚れなどを隅々まで確認できるようにするためです。
家具や家電を動かすと、普段は見えない汚れやホコリが現れることも。そのままにしておくと、クリーニング費用や原状回復費用が高くなる可能性があります。
そのため、引越し前から少しずつ掃除を始めておくのが理想的です。荷物の運び出しと並行して、掃除機や雑巾で掃除をおこない、できる限りきれいな状態で臨みましょう。
事前に約束した時間になると、担当者が物件に訪問し、立会いが始まります。遅れないよう、時間前には部屋で待機しておくのが安心です。
引越し当日に予定している場合は、立会い開始までに荷物の搬出を完了しておく必要があります。部屋が空の状態でないと、確認作業が進められないため、担当者を待たせてしまうことになりかねません。
立会い当日は、以下の書類やアイテムをあらかじめ手元に準備しておきましょう
このほかにも、印鑑や身分証明書などを念のため持参しておくと安心です。
立会いが始まると、担当者と一緒に部屋の中を見て回り、壁や床、設備などの状態を細かくチェックしていきます。電気・ガス・水道の動作確認もおこなわれます。
入居者は担当者の案内に沿って同行し、傷や汚れ、破損箇所について質問や指摘があれば、その場で一つずつ丁寧に回答します。
特に傷や破損については、それが入居前からあったものなのか、入居中に発生したものなのかを明確に伝えることが重要です。
入居時に撮影しておいた室内写真があれば、証拠として提示することで、説明に説得力が増します。
もし自身で傷をつけた記憶がある場合は、どのような使い方をしていたか、どのような状況で傷ができたのかを具体的に伝えると、費用負担の判断にも役立ちます。
室内確認がすべて完了したら、退去立会いに関する書類にサインをします。
この書類には、立会いで確認された傷や破損の状況と、それに対する修繕内容、そして修繕費用の負担者が記載されています。
サインする前に、書類の内容が立会い時の話し合いと一致しているかを必ず確認しましょう。
確認を怠って署名してしまうと、後日話し合いとは異なる内容で費用請求が発生し、トラブルにつながる可能性があります。
特に、費用負担の有無や修繕の範囲については、口頭でのやり取りだけではなく、書面でも明確に記されているかチェックすることが重要です。
納得できない点があれば、その場で担当者に確認し、必要に応じて修正を依頼しましょう。
立会いがすべて完了したら、部屋の鍵を返却します。これにより、正式に物件の引き渡しが完了し、賃貸借契約も終了となります。
鍵の返却は、玄関の鍵だけでなく、ポストや物置、セキュリティキーなども含めて、受け取ったすべての鍵が対象です。
万が一、鍵を紛失している場合は、事前に管理会社へ連絡し、対応方法を確認しておきましょう。場合によっては、鍵の再発行費用が発生することもあります。
鍵の返却後は、敷金の精算や修繕費の請求がおこなわれます。敷金の返還時期は、退去立会いから1カ月くらいが目安です。敷金から修繕費用が差し引かれた残額が、指定した銀行口座に振り込まれます。

退去立会いでは、管理会社が室内の状態を細かくチェックします。どのような点が確認されるかを事前に把握しておくことで、修繕費用を抑え、敷金を多く取り戻せる可能性が高まります。
主なチェックポイントは、以下のとおりです。
それぞれのチェックポイントを詳しく見ていきましょう。
タバコやペットなどのニオイは、退去時に指摘されやすい項目です。
長く住んでいると自分では気づきにくくなりますが、外出後に部屋に戻った瞬間のニオイを意識したり、第三者に確認してもらったりすると、ニオイの有無を客観的に把握できます。
ニオイが気になる場合は、日頃からこまめな換気を心がけることが基本です。加えて、カーテンや布製品の洗濯、消臭スプレーを使った掃除など、消臭対策を徹底しましょう。
ただし、ニオイが壁紙や建材に染みついてしまっている場合は、簡単な掃除では除去できず、専門的なクリーニングや居室全体の壁紙貼り替えが必要になることがあります。
壁紙は、退去時に管理会社が特に細かくチェックする箇所のひとつです。壁紙の破れや剥がれ、喫煙による変色などがあると、修繕費を請求される可能性があります。
退去前に壁紙の状態を確認し、必要に応じて証拠を準備しておくことが、トラブルを防ぐうえで大切です。普段の生活では気づきにくいですが、家具の裏や照明の周辺、コンセントまわりなども忘れずに確認しましょう。自然光の下で全体を見渡し、スマホのライトを使って暗い部分もチェックすると、見落としを防げます。
床や畳は、引越しで家具や荷物を運び出した後に、初めて見える傷や汚れが多い場所です。
飲み物をこぼしたシミやペットによる汚れなどは、借主の過失と判断され、修繕費を請求される可能性があります。
一方で、家具を置いたことによるへこみや、日焼けによる変色などの自然な経年劣化については、借主の責任にならないケースが一般的です。ただし、判断は物件ごとの契約内容にも左右されるため、契約書の特記事項を事前に確認しておきましょう。
特に和室のある物件では、契約書の特記事項に「畳の張替えは借主負担」と明記されている場合もあります。退去前に契約書を見直し、特記事項が記載されていないかをチェックしておくことが肝心です。
キッチン、浴室、洗面台、トイレなどの水回りは、使用頻度が高く汚れが蓄積しやすい場所のため、退去時に費用請求される可能性があるポイントです。
たとえばカビや水垢は、借主が適切な手入れを怠ったと判断されることがあり、原状回復費用の対象になる場合があります。また、洗面台のひび割れや破損なども、通常の使用を超える損耗とみなされ、費用負担を求められるケースがあります。
こうしたトラブルを避けるためには、日頃からの清掃と丁寧な使用が不可欠です。
網戸は普段あまり意識しない部分ですが、破れやたるみがあると修繕費が発生することもあります。特に、子どもやペットによる破損は借主の過失とみなされることが多く、原状回復義務の対象になるケースが一般的です。
また、網戸の状態だけでなく、開閉のスムーズさやサッシのレールに歪みがないかもチェックされるポイントです。
退去立会いでは、エアコン・ウォシュレット・換気扇などの備え付け設備の動作確認もおこないます。これらの設備が故障している場合、借主の使用状況に原因があると判断されれば、修繕費を請求される可能性があります。
特に、フィルターの汚れやホコリの蓄積が原因で故障したとみなされるケースでは、借主の過失が指摘され、原状回復費用を請求されることも。退去前には設備の清掃を丁寧におこなうことが重要です。
ただし耐用年数を超えて使用している設備については、経年劣化と判断され、原状回復義務が生じない可能性もあります。
照明器具は、もともと物件に備え付けられている場合と、借主が自身で設置した場合があります。借主が設置した照明器具については、退去時に撤去するのが原則です。
そのまま残していくと、残置物として扱われ、管理会社の了承がない場合は処分費用を請求される可能性があります。
照明器具を残したい場合は、事前に管理会社へ相談し、了承を得ておくことが重要です。
退去立会いでは、電気・ガス・水道が正常に動作しているかどうかも確認されます。
また、ライフラインの利用停止手続きが済んでいるかどうかもチェックされるため、退去日までに各社への連絡を済ませておくことが重要です。
手続きが未完了のまま退去すると、退去後も基本料金が発生し、思わぬ費用負担につながることがあります。
退去立会いは、管理会社と入居者が立ち会って、退去時の部屋の状態を確認し、修繕範囲と費用負担について双方ですり合わせることです。
後々のトラブルを防ぐためにも、どの箇所がチェックされるのかを事前に把握し、必要な掃除や確認を済ませておくことが大切です。また、入居時の写真や記録があるかどうか、掃除が行き届いているかどうかによって、修繕費の負担額が大きく変わる可能性があります。
退去直前に慌てることのないよう、余裕を持って準備を進めておくことが、敷金を守る第一歩です。
アパートでよく起こるトラブルのひとつに「ゴミ出しのマナー違反」があります。例えば、ゴミを捨て時間を守らない、回収されなかったゴミが荒らされている、ゴミの悪臭問題などが挙げられます。アパートのゴミ捨て場問題は、管理会社は避けて通れない課題とも言えるため、トラブルを防ぐための対策や適切な管理は必要不可欠でしょう。
さらに、トラブル時の対処法をあらかじめ理解しておくことも大切です。そこで今回は、賃貸オーナーや管理会社が知っておくべき、ゴミ捨て場を設置する場合のルールや注意点、ゴミ捨て場の種類、トラブルになった場合の対処法などについて解説します。

各自治体によって、アパートに設置するゴミ捨て場のルールが定められています。そのため、アパートを新築・増築したり、新たにゴミ捨て場を設置したりする場合は、自治体ごとの設定基準を守らなければなりません。たとえば、横浜市では集合住宅のゴミ捨て場について、以下の設置基準を設けています。
このように、自治体ごとに細かな設置ルールが設けられているため、ゴミ捨て場を新設する際は、自治体のホームページや窓口でゴミ捨て場の規定を確認しましょう。
ゴミ捨て場を設置するときは、以下のポイントに注意が必要です。
項目ごとに詳しく見ていきましょう。
先述した通り、ゴミ捨て場は各自治体によって設置ルールがあります。また、アパートやマンションなどの共同住宅は、居住者専用のゴミ捨て場の設置が条例で義務付けられています。そのため、アパートを新築、増築する際には、ゴミ捨て場の設置について自治体へ相談し、事前に届け出をしなければなりません。
アパートのゴミ捨て場は、所有者であるオーナーか管理会社が管理します。ゴミ捨て場の管理は、物件の美観や入居者の快適性・安全性を守る重要な仕事であるため、管理会社へ委託しているオーナーも多いでしょう。しかし、法律的な定めではないため、物件によって管理責任者は異なります。自主管理しているオーナーは、自身でゴミ捨て場を管理していますが、ゴミ捨て場の管理業務は手間のかかる大変な作業です。オーナーの高齢化や管理不足によって、ゴミ捨て場のトラブルが発生しているケースも少なくありません。管理会社の方は、自主管理しているオーナーへ「管理委託を推奨する」ことも、一つのトラブル対策となるでしょう。

ゴミ捨て場のトラブルを防ぐためには、ゴミ捨てのルールを入居者に周知しなければなりません。ここでは、以下を例にあげて解説します。
さっそく詳しい内容を見ていきましょう。
近年、ゴミ袋の指定や有料化、分別を細分化している地域が増えていて、ルールを守らないゴミ出しは、回収してもらえないケースもあります。ゴミが回収されずに残ったままになると多くの悪影響が考えられるため、管理会社は自治体のルールを入居者へしっかり伝えることが大切です。なお、外国人の入居者が多い地域では、イラストや英語表記を用いて、より多くの人が理解できるよう資料を工夫しましょう。
ゴミの回収日時は自治体によって決められていて、捨てる時間帯や曜日を間違えるとゴミを回収してもらえません。また、深夜にゴミ出しを行うと騒音で近所迷惑になったり、早朝に野生動物がゴミを荒らしたりする可能性があります。そのため、状況に合わせて深夜のゴミ捨てを禁止する、ゴミ捨て場に鍵をつけるなどの対策を検討しましょう。

主に利用されているゴミ捨て場は、以下の3つです。
それぞれの特徴やメリット・デメリットを知って、物件に合ったものを選びましょう。
開放型は、背面と左右の三面がブロックや塀などで囲われているタイプのゴミ捨て場です。密閉型ほどではないものの、ゴミ捨て場の周囲に塀があるため、強風でゴミが飛ばされるリスクを低減することができます。その一方で、悪臭が漂いやすい、野生動物にゴミを荒らされやすいなどのデメリットがあるため注意が必要です。
密閉型は、比較的築年数が新しいアパートに多く見られます。専用ボックスには、ゴミ捨て場が密閉できるようフタや扉が付いていて、入居者がゴミを捨てるタイミングで自由に開閉することができます。ネコやカラスが侵入するリスクも低く、第三者にゴミを荒らされる心配も少ないでしょう。また、密閉型はニオイ漏れを防ぐ効果も期待できます。ただし、大きさに限りがあるため、ゴミの容量に制限があります。さらに、通気性が悪くニオイが充満しやすい、菌が繁殖しやすい、内部の掃除が大変など、いくつかデメリットもあります。
路上型は、行政の許可を得た上で、アパート前の道路や周辺道路にゴミ捨て場を指定するタイプです。アパートの敷地内にゴミ捨て場を設置する余裕がない場合や、世帯数が少ないアパートなどで見られます。路上タイプは、多少スペースに余裕があるため、大きめなゴミが出しやすいというメリットがあります。一方、路上にゴミを出すという性質上、多くの通行人に見られる可能性が高く、個人情報の漏洩に注意が必要です。さらに、ネコやカラスなどによる被害や、第三者による荒らし行為、不法投棄などのトラブルも想定されます。

実際にゴミ捨て場でトラブルが起きた場合、オーナーや管理会社はどのような対処を行うべきなのでしょうか。ゴミ捨てに関するトラブルは頻繁に起こるため、対処法を知っておくと「いざ」という時に役立ちます。ここでは、よく起こりがちなトラブル例とその対処法について見ていきましょう。
ゴミ収集の時間は、例えば、「朝9時」など自治体によって決められています。その上で、管理会社によって「常識的な範囲内でのゴミ出しルール」が設けられていることが多いでしょう。ただし、全ての入居者がルールを守ってくれるわけではありません。入居者の中には、ルール違反とわかっていながら身勝手な理由で深夜や早朝にゴミ出しをする人もいます。そうすると、ルールを守っている住民から不満が出たり、衛生面やニオイに関するトラブルが起こりやすくなったりします。これらを防ぐためには、入居者へゴミ捨てルールを徹底的に周知することが重要です。近年は、各自治体でゴミ捨てのルールが厳しくなっています。
さらに、外国人の入居者が増加しているため、イラストや英語・中国語表記などを用いてわかりやすい資料を配布するとよいでしょう。また、曜日ごとの簡易一覧表などを作成して、エントランスや共用部分に貼りだしておくのもおすすめです。
ルールが厳しい地域では、分別されていないゴミは回収されず残ったままになることも。残ったゴミは悪臭の原因になり、菌を繁殖させたり、野生動物を引き寄せたりする可能性があります。さらに、「次の回収日まで家に置いておきたくない」「旅行で家を留守にするから」などの理由で、回収日を無視した「先出し」が行われるケースもあります。こういったケースは、他の入居者の迷惑になるだけでなく、ルールを守らない人が増える原因になるため早めの対処が必要です。
管理会社ができる対策として、ゴミ置き場を工夫するという方法があります。ゴミの分類が「燃えるゴミ」「燃えないゴミ」「資源ゴミ」である場合、分別を細分化することで地域のルールに沿った分別が自然と行えるようになります。例えば、資源ゴミを細分化して「段ボール」「古紙」「布類」と分けておくことで、入居者も「分別する」という意識が持ちやすくなるでしょう。また、長期休暇や年末年始など、ゴミの先出しが多くなりやすい時期は、あらかじめ指定した時期だけは「先出しOK」というルールを設けておくのもおすすめです。こうすることで、回収されないゴミが何日も放置される事態を避け、衛生面やニオイの問題を回避することができるでしょう。
ゴミ捨て場が汚れていると、アパートの景観や衛生環境を損なうだけでなく、入居者の満足度の低下や物件価値の低下、入居希望者の減少などの悪影響が考えられます。そのため、管理会社は迅速な対応が必要です。初動対応では、まず現場の確認を行います。状況をしっかり確認して写真やメモをとって記録を残しておきましょう。たとえば、ゴミ捨て場が汚れされた時間帯、場所、ゴミ袋の状況などをチェックします。
さらに、入居者から聞き取りを行うのも効果的です。散乱したゴミ捨て場を清掃したら、現場の状況をまとめます。この情報は必ずオーナーと共有し、原因特定や再発防止策に役立てましょう。なかなか改善されず頻繁に汚される場合は、防犯カメラの設置を検討するのも有効な手段です。
ゴミ捨て場は、ゴミが回収されたあとも壁や床部分に染みついた汚れや、堆積した小さなゴミが原因となり悪臭が発生する場合があります。悪臭をそのまま放置すると、入居者からの不満、近隣住民からの苦情、害虫問題など、多くの悪影響が考えられるため注意が必要です。
ゴミ捨て場の悪臭が酷い場合は、定期的な清掃を行い、清潔さを保つことを心がけましょう。また、脱臭装置を設置することで消臭することもできます。ただし、清潔さを保たなければ脱臭装置の効果も半減してしまうため、定期的な清掃は必要不可欠です。
アパートの敷地内にあるゴミ捨て場は基本的に「入居者専用」です。しかし、アパートの入居者以外の人が勝手にゴミを投棄することがあり、トラブルになるケースも少なくありません。そもそも、アパートの入居者以外がゴミを捨てる行為は「不法投棄」に該当します。そのため、場合によっては法律違反になる可能性があります。違反した場合は、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、または双方が課せられます。
このようなトラブルを防ぐためには、定期的な清掃、張り紙や看板の設置、ネットで覆う、防犯カメラの設置などが効果的です。不法投棄を完全に無くすことは難しいかもしれませんが、不法投棄を減らすことができるでしょう。
アパートの退去時に、粗大ゴミが投棄されるのもよくある問題のひとつ。たとえば、いらなくなった自転車を駐輪場に置いていってしまうのはよくあるケースです。粗大ゴミを処分するには費用がかかるだけでなく、粗大ゴミを置いておくためのスペースも必要になります。なるべく粗大ゴミ投棄を防ぐためには、退去間近の入居者に対して粗大ゴミ投棄の禁止を啓蒙する、リサイクルショップや自治体などの粗大ゴミ引き取りサービスを案内するなど、適切なアプローチを行うことが重要です。
以前は、ゴミ捨て場のトラブルを防ぐために、ゴミ袋に名前や部屋番号を書くことを義務付けていた自治体もありました。しかし、近年は個人情報保護の観点から記名に反対する意見も多く、記名を強制する自治体も少なくなっています。
アパートやマンションのような集合住宅では、本文中で紹介したようなトラブルはどうしても発生しがちです。ゴミ捨て場のトラブルが多発すると、近隣住民からの苦情、入居者のモラルの低下、新規入居者の減少など、さまざまなリスクが考えられます。小さな問題でも、放置すると被害が拡大する可能性も高いため、管理者は早めの対応を心がけましょう。
賃貸オーナーや管理会社の方は、今回紹介した記事の内容を参考にしながら、ゴミ置き場拡充によるトラブル回避を検討しましょう。
不動産取得税は、土地や建物を購入したときにかかる税金の一つです。新しく不動産を取得すると、他の人は税金をいくら払ったのか気になる方も多いのではないでしょうか。実はこの税金には軽減措置があるため、条件を満たせば税負担を大幅に軽減することもできるんです。
本記事では不動産取得税の基本的な知識と、計算方法や軽減措置などを解説します。

土地や建物を取得して、その不動産の所有権を得たときに一度だけ課される地方税です。地方税とは行政サービスにかかる費用を負担するもので、都道府県に納めます。
取得方法は、購入・建築・贈与などが該当します。贈与のように無償で不動産を取得した場合でも、課税される点に注意しましょう。
一方で、相続による取得は原則として不動産取得税がかかりません。相続は無償かつ法定の権利移転であるため、課税の趣旨にそぐわないとされているためです。
納税義務者は、さまざまな取得方法によって、不動産の所有権を得た人です。具体的には、購入の場合は買主、建築の場合は施主、贈与の場合は受贈者が納税義務者となります。
納税義務は、登記の有無にかかわらず発生します。登記をしていなくても実質的に不動産を取得したと認められる場合は、納税しなければなりません。
また、共有名義で不動産を取得した場合は、共有者全員が連帯して納税義務を負います。これは、それぞれの持分割合だけ納めれば良いということではなく、共有者一人ひとりに全額の納付義務が課されているという意味です。たとえば二人で一つの不動産を共有している場合、共有者の一方が税金を納めなかったとき、もう一方の共有者に全額の請求がいきます。
納税義務者には都道府県から納税通知書が送付されます。取得の事実があれば、納税通知書が届いた時点ですでに不動産を売却していたとしても、納税義務が発生する点に注意が必要です。
このように納税義務者は、登記の有無や所有の継続に関係なく、取得の事実に基づいて課税される仕組みになっています。
課税対象となるのは、土地と建物です。それぞれの種類について詳しく解説します。
土地の種類には、以下のようなものが含まれます。
建物の種類は、以下のとおりです。
このように、さまざまな種類の土地や建物について、所有権の移転が確認された場合は課税されます。

一定の条件をみたす場合は、非課税になることもあります。これは、取得方法や取得者の属性によって、税負担が免除されることがあるためです。非課税となる代表的なケースは、以下の5つです。
先述のとおり、相続による取得は非課税です。相続は、被相続人の死亡によって法的相続人に財産が移転するものであり、取得の意志があるかどうかは関係ありません。そのため、形式的な所有権の移動と位置づけられ、課税の対象外となるのです。
ただし、例外もあります。「特定遺贈」のなかでも、遺言書によって法定相続人以外が不動産を取得する場合は、税金が課される点に注意しましょう。
合併や分割など企業再編にともなう所有権の移転は、事業継続のための形式的な変更に過ぎません。そのため実質的な取得とはみなされず、非課税となります。
しかし、非課税になるためには、一定の条件を満たす必要があります。たとえば金銭等不交付要件があり、組織再編の対価として支払えるのは株式のみで、現金などによる支払いは許可されないという要件です。株式は、承継会社または承継会社の親会社の株式に限られます。
土地区画整理事業は、土地の区画を整えて、公共施設の整備や宅地の利用増進を図る事業です。土地を再整備する際に、従前の土地の代わりに新しく割り当てられる土地のことを換地といいます。
換地は従前の土地の所有者がその権利を維持したまま、新しい土地に移る仕組みです。そのため売買や贈与のような新たな取得とはみなされず、税金はかかりません。このことは地方税法でも明記されています。
学校法人や宗教法人、社会福祉法人など特定の法人が事業に使う不動産を取得した場合、非課税です。ただし本来の事業とは関係のない用途で取得した不動産は、課税対象になります。
不動産価格が以下の免税点を下回る場合は、免税対象となります。
土地:10万円
新築・増築・改築した家屋:23万円
家屋:12万円
ただし、免税された土地・家屋に隣接する土地・家屋を1年以内に取得した場合は、免税された土地・建物と合わせて1つの土地・家屋とみなされます。その際、不動産価格が免税点を超えた場合は課税対象となるため注意しましょう。

税額がいくらかかるのか知りたい方は、固定資産税評価額がわかれば、自分で計算することができます。事前にいくらかかるのか知っておくと、時間に余裕を持って納税資金を準備することができます。納税通知書が来ても焦らずに対応できますよね。
ここからは税額の計算方法と計算例をご紹介します。
固定資産税評価額に税率を掛けて算出します。基本的な計算式は、以下のとおりです。
不動産取得税=固定資産税評価額(課税標準額)×税率4%
ただし土地と住宅家屋には税率の軽減措置があり、以下の税率が適用されます。
| 土地 | 家屋(住宅) | 家屋(非住宅) |
|---|---|---|
| 3% | 3% | 4% |
さらに、宅地を取得した場合は、土地の課税標準額が固定資産税評価額の1/2になります。
固定資産税評価額は市町村ごとに設定されるもので、実際の購入価格とは異なる点に注意しましょう。
固定資産税評価額の調べ方は、自治体から送付される固定資産税の納税通知書に記載されています。売主からから引き渡しを受けた資料のなかに、固定資産税の納税通知書が入っていれば、「評価額」の欄を確認しましょう。
市区町村役場で、固定資産課税台帳の閲覧をすることもできます。市区町村役場で固定資産評価証明書を取得するのも手です。ただし、いずれの場合も手数料がかかるのが注意点です。
まだ不動産を取得していない段階で、土地の固定資産税評価額を知りたい場合は、実勢価格からおおよその額を導き出す方法もあります。固定資産税評価額は実勢価格の70%程度といわれているため、販売価格の70%を掛けた金額が、固定資産税評価額の目安となります。一方、新築家屋の固定資産税評価額は、工事金額の50%〜60%程度が目安です。

不動産取得税にはいくつかの軽減措置が用意されており、それにより税負担を大幅に軽減することが可能です。
ここからは、以下のケースについて詳しく見ていきましょう。
住宅を新築または増改築した場合は、家屋の固定資産税評価額から1,200万円差し引いた金額が課税標準となります。
家屋の不動産取得税=(固定資産税評価額ー1,200万円)×3%
適用対象となる住宅の面積要件は、以下のとおりです。
貸家以外の住宅:50㎡以上240㎡以下
貸家の一戸建て住宅:50㎡以上240㎡以下
貸家のマンション・アパート:40㎡以上240㎡以下
上記の面積は、現況の床面積で判定します。登記床面積とは異なる場合があるため、ご注意ください。
さらに認定長期優良住宅を新築・購入した場合は、控除額が1,300万円に拡大します。
家屋(認定長期優良住宅)の不動産取得税=(固定資産税評価額ー1,300万円)×3%
新築住宅の土地は、税額から直接減額されます。
土地の不動産取得税=(固定資産税評価額×1/2)×3%ー控除額
控除額は以下のいずれか高い金額です。
中古住宅を取得した場合も、固定資産税評価額が軽減されます。
不動産取得税=(固定資産税評価額ー控除額)×3%
ただし、控除額がいくらになるかは、自治体によって異なります。
特に中古住宅が新耐震基準に適合しているか否かで、大きく異なります。
たとえば新耐震基準に適合する場合、控除額は100万円〜1,200万円です。
一方で新耐震基準に適合しない場合、3万円〜12万6,000円と大幅に縮小します。
また、中古住宅が立つ土地も合わせて購入した場合、土地の不動産取得税も軽減を受けることが可能です。
土地の購入価格3,000万円、建物の購入価格2,000万円の場合、税額を計算してみましょう。詳細条件は、以下のとおりです。
土地の種類:宅地
建物の種類:新築住宅
土地の固定資産税評価額:2,100万円
建物の固定資産税評価額:1,200万円
土地の不動産取得税:
2,100万円×1/2×3%ー4万5,000円=27万円
建物の不動産取得税:
(1,200万円-1,200万円)×3%=0円
土地のほうの控除額は、土地1㎡あたりの固定資産税評価額×1/2×住宅の課税床面積の2倍(一戸あたり200㎡が上限)×3%<4万5,000円という前提で計算しました。
建物のほうは、固定資産税評価額から1,200万円を差し引くと0円になるため、税額は0円です。

納税のタイミングは、取得直後ではありません。所有権移転登記が完了してから、都道府県が納税通知書を発行し、それが届いてから支払います。納税通知書が届く時期は、だいたい取得後3カ月〜6カ月以内です。
納税通知書には、課税標準額や税率、納付税額、納付期限などが記載されています。あわせて軽減措置の適用状況を確認することも可能です。先ほどご紹介した非課税となるパターンや、税制優遇などで非課税となった場合には、納税通知書は送付されません。
納付期限は通知書到着から30日以内とされているケースが多いです。納付期限を過ぎると延滞金が発生するため注意しましょう。延滞金は納付期限からどれくらい遅れたかによって異なります。期限の翌日から2カ月以内は年2.4%、2カ月を過ぎると年8.7%です。
納付方法は、主に以下のような選択肢があります。
コンビニ納付は、税額30万円以下の場合に限られます。電子納税は事前登録が必要ですが、自宅で納付できるため便利です。

先ほど紹介した軽減措置を受けるには、条件を満たしているだけでは不十分で、納税義務者自らの申請手続きが必須です。申請を忘れると、本来受けられるはずだった税制優遇が受けられず、余分な税負担を強いられることになります。ここからは、申請手続きの流れと注意点について解説します。
申請手続きの流れは、以下のとおりです。
それぞれの流れごとに、どのような手続きをするのか、詳しく解説します。
不動産を取得し、所有権の移転登記をおこないます。取得した不動産の面積などを確認し、軽減措置の要件を満たしているかどうか確認しましょう。
軽減措置の要件を満たしていることが確認できたら、申請に必要な提出書類を準備します。
提出書類は、以下のとおりです。
取得した不動産の種類や、管轄の都道府県によって提出書類は異なります。詳しくは管轄の都道府県のホームページなどで確認しましょう。
提出書類が揃ったら、管轄の都道府県事務所に提出します。提出期限は都道府県によって異なります。たとえば東京都は不動産を取得してから30日以内が提出期限です。
また自治体によっては電子申請を受け付けている都道府県もあります。パソコンやスマートフォンから好きなときに申請できるため、便利です。
申請書類を提出した後は、税務署が審査をおこないます。申請後1〜2カ月の間に審査がおこなわれ、その結果に応じて軽減後の税額が確定します。
審査が通れば、不動産取得税の一部または全額が軽減されます。一部が軽減された場合は、納税通知書が届きます。忘れずに税金を納めましょう。一方で、全額が免除された場合は、納税通知書は送付されません。そのまま手続きは終了となります。
不動産取得税を支払った後に、軽減措置が利用できることに気づいた場合は、払いすぎた税金の還付を受けることも可能です。その場合は、還付請求が必要になります。
還付請求は、還付請求できるようになった日から5年以内です。
不動産取得税は、土地や建物を取得したときに一度だけ課される税金で、購入・建築・贈与などが対象になります。一方で相続や法人の合併など、一定の条件下では課税されません。
税額は固定資産税評価額に税率を掛けて算出されます。住宅や宅地には軽減措置が適用されることがあります。新築住宅では最大1,200万円(認定長期優良住宅は1,300万円)の控除があり、中古住宅の場合は耐震基準の適合状況によって差引される額が変わります。
納税は取得後3〜6カ月以内に納税通知書が届いてからです。納税通知書は、忘れた頃に届くのが特徴です。取得後に納税資金を用意しておき、要件を満たす場合は税制優遇の申請をおこなうなど、準備作業を忘れないようにしましょう。
火災から命を守るために重要な「火災報知器」。消防法の改正に伴い、2006年に新築住宅、2011年には既存住宅を含むすべての住宅で設置が義務付けられました。賃貸物件の場合は部屋ごとに設置されているため「電池切れで警報音が鳴ったらどうやって止めればいいの?」「電池交換は自分でやるの?」など、火災報知器について疑問をお持ちの方も少なくありません。
もし、自分の部屋の火災報知器が電池切れになったら、どうのように対応すればよいのでしょうか。また、その場合にかかった費用はどうなるのでしょうか。今回は、火災報知器が電池切れした場合の対処方法や、交換するタイミング、賃貸物件の火災報知器の重要性などについて解説します。賃貸物件に住む人なら、いつ誰に起きてもおかしくありません。今後の予備知識として身につけておきましょう。

火災報知器の電気切れは突然やってきます。寝ているときに突然大きな警報音が鳴れば、驚いて慌ててしまう方も多いでしょう。どんなときでも落ち着いて対応できるように、ここでは火災報知器が電池切れした場合の対処法を確認しておきましょう。
火災報知器は電池切れする前に、大きな警報音が鳴ったり、「電池切れです」などのアナウンスが鳴ったりします。夜中に突然鳴り出すこともあり、「もしかして火災が発生したのでは?」と感じてしまう方もいるかもしれません。
警報音は家中に鳴り響くため、まずは警報音を止める必要があります。音を止めるときは、火災報知器の本体についている停止ボタンやひもを引っ張ると止めることができます。また、一度止めてもしばらくすると鳴り出す仕様になっているため、早めに対応することが重要です。
火災報知器の警報音が鳴ったら、必ず電池交換を行いましょう。火災報知器の種類にもよりますが、電池交換の大まかな手順は次のとおりです。
以上が大まかな流れですが、火災報知器のメーカーや型番で検索すると、電池交換の方法を調べることができます。あらかじめ調べておくと、いざというときに役立つでしょう。また、火災報知器に使われている電池は、一般的な電池ではなく、多くの場合はリチウム電池が採用されています。リチウム電池はホームセンターや家電量販店、インターネット通販等で購入できるので、突然の電池切れに備えて家に常備しておくことをおすすめします。
警報音が鳴り止まないときは、以下の方法を試してみましょう。
火災報知器のボタンやひもを引っ張っても警報音が止まらない場合は、再度停止スイッチを押してみてください。中には、長押しが必要な火災報知器もあるため、一度押して止まらない場合は長押しで対応しましょう。また、電池交換をしても警報音が鳴り続ける場合は故障している可能性があります。表示灯が点滅していたり、「ピピピ」と聞き慣れない音がしたりしている場合は、取扱説明書で故障に当てはまるか確認してみましょう。電池切れで警報音が鳴り続けていると、周囲の人が火災と勘違いしてしまう可能性があります。周囲の方へ迷惑をかけないためにも、事前に警報音を止める方法やリセット方法を確認しておくことをおすすめします。

警報音が鳴ったらすぐに電池交換を行うべきですが、それ以外でも日頃からボタンやひもを操作して正常に動作するか確認しておきましょう。消防庁では、作動点検のポイントを以下のように解説しています。
火災報知器を点検して反応がない場合は、すでに電池切れか本体が故障している、もしくは寿命を迎えている可能性が高いです。すぐに電池交換か本体の交換を行いましょう。

火災報知器本体の交換時期はおおむね10年です。設置した時期から10年を経過している場合は、本体を交換するタイミングと言えるでしょう。なお、本体の設置年数は設置時に記入しているか、もしくは製造年を確認することでおおよその設置年数がわかります。ただし、賃貸物件の場合、火災報知器の設置と正常な動作を保つことは貸主の責任です。したがって、入居者が勝手に交換することは避け、管理会社や大家さんへ連絡をして対応してもらいましょう。

2011年6月以降、すべての住宅に火災報知器を設置が義務付けられていますが、火災報知器を設置していなかった場合、どのような罰則が課せられるのでしょうか。ここでは、賃貸物件オーナーのリスクや、火災報知器の設置場所や注意点について見ていきます。
火災報知器の設置は義務化されていますが、実は、設置していなくても法律上の罰則はありません。そのため、現在の賃貸物件における火災報知器の設置率は100%ではないのが実情です。しかし、賃貸物件に火災報知器を設置しなかった場合、オーナーには以下のようなリスクがあります。
オーナーが火災報知器を設置していなかったために、火災の被害が拡大した場合には、瑕疵または過失と判断され、オーナーは責任を追求されることになるでしょう。また、火災報知器未設置の場合は、火災保険がおりない可能性もあります。保険が適用されなければ、建物で発生した損害や修繕費用はすべてオーナーの自己負担となるため、火災報知器を設置せずに放置するリスクは非常に高いと考えられます。
火災報知器の「設置場所」は、基本的に寝室と寝室がある階の階段上部(1階の階段は除く)と決められています。しかし、設置が義務付けられている場所は自治体によっても異なります。例えば、東京都の場合は、リビング、子ども部屋、寝室、居室、階段、キッチンなどに設置が必要です。このように、自治体によってルールが異なるため、いちど自治体で定められた設置場所を確認してみましょう。
取り付け位置については「天井」または「壁面」に取り付けることが一般的で、天井の場合は壁や梁から60cm以上離れた天井の中央付近に取り付けます。照明機器は感知の妨げになる可能性があるためできるだけ離す、エアコンの吹き出し口からも1.5m以上離れた場所に取り付けるなど、細かなルールが設けられています。

「火災報知器の設置や交換はオーナーと入居者どちらがやるべき?」と思う方も多いでしょう。そこで、ここでは火災報知器にまつわる以下の質問について解説します。
さっそく回答を見ていきましょう。
東京都の火災予防条例では、「住宅の『関係者』が住宅用火災警報器を設置し、維持しなければならない」と定めています。この住宅の「関係者」が非常に重要で、具体的に以下の三者を指します。
このように、法的には三者すべてに住宅用火災警報器の設置・管理義務があることになります。しかし、実際のところは、入居者が退去したタイミングで管理会社やオーナーが点検を行い、設置や交換をすることが多いです。
火災報知器「本体の交換」は、基本的に管理会社やオーナーが行います。それでは、「電池交換」についてはどうでしょうか。火災報知器の電池が切れてしまったとき、一番初めに気がつくのは入居者です。そのため、入居者が電池交換をする機会のほうが圧倒的に多いでしょう。例えば、エアコンのリモコンの電池が切れたから交換するようなイメージです。
その場合、リモコンの電池代はオーナーに請求するでしょうか?火災報知器の電池切れもこの感覚に近く、基本的には入居者が負担することのほうが多いのが実情です。入居者が火災報知器の電池切れを放置すれば、実際に火災が起きたときのリスクが高くなります。したがって、警報音が鳴ったら放置せず、すぐに対応することが重要です。なお、賃貸契約書に火災報知器についての定めがある場合は、管理会社へ連絡して指示を仰ぎましょう。

火災報知器を入居者が買う機会は少ないかもしれませんが、どこでどのように購入できるのか把握しておくと安心です。ここでは、火災報知器にはどのような種類があるのか、どこで購入できるのか、リースする(借りる)ことはできるのかについて解説します。
火災報知器は、煙や炎を感知する「煙式(光電式)」と周囲の熱が上昇するのを感知する「熱式(定温式)」の2種類があります。東京消防庁のホームページでは、居室や階段などは煙式、台所など火災以外の煙で警報器が誤作動する可能性がある場所は熱式の設置を推奨しています。また、条例によって設置場所が指定されているため、消防庁が推奨する煙式でなく、熱式を採用する場合は設置場所の選定に注意が必要です。
発報方式は、火災を感知した警報器のみが鳴る「単独式」と、1ヶ所で火災保管地するとすべての警報器が連動して鳴る「連動式」の2種類です。また、耳が不自由な方のために光と音の両方で知らせるタイプもあるため、ご自身やご家族のライフスタイルに合わせて選びましょう。
火災報知器を自分で購入する場合は、インターネット通販やホームセンター、家電量販店で購入することができます。本体は2,000円~3,000円前後で購入できますが、電池式のものが多いため、火災報知器の種類に合った電池も購入しておきましょう。なお、取り付けは自分で行うことも可能です。ただし、壁や天井に穴を空ける必要があるため、賃貸物件の場合は事前に管理会社へ確認しておきましょう。
電力会社や電気会社では、火災報知器のリースを行っています。ガスや電気の料金と一緒に支払うことができて、月々数百円から借りることができます。さらに、契約期間中は機器の交換や管理などもおまかせできるため、管理の手間を省くことができます。ただし、ガス会社との契約が前提になるケースが多いため、解約や転居の際には注意が必要です。
今回は、「火災報知器の電池切れや交換は入居者負担するのか?」について解説しました。普段あまり意識にすることのない火災報知器ですが、火災が起きた際、住人の命を守る重要な役割を担っています。そのため、火災報知器の電池が切れたときは、なるべく後回しにせず早急に対応しましょう。
火災報知器の電池が切れたときは、大きな警報音や「電池切れです」といったアナウンスが鳴り響くことがあります。寝ているときや夜中に大きな音がして驚いてしまう方も多いと思いますが、落ち着いて本体についているボタンやひもを引いて警報音を止めましょう。一度警報音止めても、しばらくすると再度警報音が鳴り出すことがあります。いつ鳴っても困らないよう、火災報知器の交換用電池を常備しておくことをおすすめします。
なお、火災報知器の電池交換は基本的には入居者負担ですが、本体の故障や交換は管理会社やオーナーが行うことが一般的です。ただし、賃貸契約書に定めがある場合は、その内容に合わせて対応しましょう。火災報知器の対応で困ったときは、自己判断せず管理会社に相談するのが得策です。
熊本市不動産売却クイック査定です。
「親の所有していた古い家を相続したものの、今は空き家になっていて活用方法がない」とお悩みではありませんか。実は、一定の条件を満たしていれば、補助金を利用して家を解体できる可能性があるんです。
本記事では、古い家(空き家)を解体するときに出る補助金についてご紹介。補助金が出る理由から、申請方法、注意点まで詳しく解説しています。古い家を所有している方は本記事を参考に、解体という選択肢も検討してみてください。

古い家を解体するにあたって補助金を利用できるのは、なぜなのでしょう?その理由は空き家によって引き起こされる以下の問題を、未然に防止するためです。
家が老朽化すると、倒壊のリスクが高まります。特に人が住んでいない家は、定期的な点検や修繕がおこなわれていないことが多いです。そのため、地震や台風などが引き金となり、突然倒壊してしまう可能性もあります。
屋根の瓦が剥がれたり、塀が崩れたりといった部分的な倒壊でも、近隣住民や通行人にケガを負わせてしまう危険性をはらんでいます。
こうした事故を未然に防ぐため、自治体が補助金制度によって空き家の解体を促し、地域の安全を確保しようとしているのです。
誰も住んでいない家は、周囲の目が届きにくいため、不法投棄の標的になりやすいです。ゴミを長期間放置していると、敷地内がゴミで溢れかえっていき、隣家とトラブルに発展することもあります。
所有者には、土地と建物の管理責任があります。そのため、他者が不法投棄をしている場合でも、家の所有者がゴミを撤去しなければならないケースが多いです。
そのまま放置すると、自治体から「所有者が適切な管理を怠った」と判断され、行政指導や罰則の対象になる場合も。こうした事態を防ぐため、自治体は補助金制度を通じて空き家の早期解体を促進し、トラブルが起きないようにしているのです。
空き家を長期間放置すると、外壁の劣化や雑草の繁茂が進み、景観を損ねる原因となります。特に住宅街では、周辺の住環境への影響が大きく、近隣住民からクレームを受けるケースも少なくありません。
景観の悪化を防ぐためにも、空き家の早期撤去はとても重要です。撤去されれば、新しい家に建て替えられたりして、景観の保全につながります。自治体は美しい景観を保つことを目的に、解体費用の一部を補助しているのです。
人の出入りが少ない空き家は、空き巣や不法侵入、放火などの犯罪に利用されるリスクが高まります。隣接する住宅にとっては、身近な場所で犯罪が起きることが、大きな不安要素となるでしょう。
空き家を放置せず、適切に管理・撤去することで、犯罪の発生を未然に防ぐことができます。自治体の補助金制度は、こうした犯罪リスク低減の取り組みとしても位置づけられています。

解体費用の補助金を利用するには、自治体の定めた条件を満たす必要があります。自治体によって条件は異なりますが、以下のような条件が設定されていることが多いです。
補助金の対象は、個人所有の家に限られるケースが多いです。自治体によっては、法人名義の家が受給対象外になるところもあるため、注意しましょう。
築年数が古く耐震性に問題がある建物は、災害時に倒壊などの危険性が高いです。そのため、補助金の条件に旧耐震基準という項目を設けている自治体もあります。
旧耐震基準とは1981年以前の建築確認に適用されていた基準で、震度5強の揺れでも倒壊しないことを前提としています。しかし、震度6以上の大きな地震には耐えられない恐れがあるため、こうした建物は優先的に解体が推奨されているのです。
老朽化している建物は倒壊リスクが高いため、補助金の対象になることが多いです。具体的には「特定空家等」「不良住宅」と判定された場合などが該当します。
| 規定 | 特徴 | |
|---|---|---|
| 特定空家等 | 空家等対策の推進に関する特別措置法 |
倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態 著しく衛生上有害となる恐れのある状態 著しく景観を損なっている状態 |
| 不良住宅 | 住宅地区改良法 | 居住用の建築物またはその一部分で構造・設備が著しく不良であるため、居住するのが著しく不適当な状態 |
特定空家と不良住宅の違いは、現在空き家かどうかという点です。不良住宅は空家に限らず、現在居住している家でも判定を受ける可能性があります。
特定空家等や不良住宅の判定には、自治体による現地調査がおこなわれます。建築士に判定してもらう場合は、1カ月〜2カ月程度かかり、時間を要する点に注意しましょう。
固定資産税などの税金を滞納している人に対しては、補助金の交付を認めない自治体が多いです。
補助金の財源は税金であることから、納税義務を果たしていない人に対して公的支援をおこなうのは適切でないと判断されるためです。
また、きちんと税金を納めている人が不公平感を感じないようにする措置ともいえます。税金の滞納がある場合は、しっかりと納税をしてから補助金を申請しましょう。
空き家の解体に関する補助金制度では、「1年以上使用していないこと」が条件になっていることが多いです。ここでいう「使用していない」とは、電気やガスなどのライフラインが停止している状態を指します。
したがって、居住中の家を建て替える目的で解体する場合は、補助金の対象外となるため注意しましょう。

古い家を壊すときの補助金は、自治体から支給されます。ここからは、代表的な制度を紹介します。
なお、これからご紹介する制度の名称は、自治体ごとに微妙に異なる場合があります。
最初にご紹介するのは、古い家の撤去に対して支給される「老朽危険家屋解体撤去補助金」です。対象となるのは、劣化が激しく倒壊リスクが高い家で、細かい対象要件や助成金額は自治体が個別に定めています。
たとえば、東京都墨田区では、住宅地区改良法の「不良住宅」と認められる場合に、建物所有者に対して解体費の一部を助成しています。金額は解体費用の半額で、50万円が上限です。本制度は不良住宅を減らし、跡地の有効活用を図ることを目的にしています。
「都市景観形成地域老朽空き家解体事業補助金」は、街の景観を守るための制度です。都市景観形成地域に放置されている、古い空き家を壊す際に利用できる可能性があります。
補助率は、解体費用の2割から5割程度で設定されていることが一般的です。
この制度の特徴は、補助を受けるために景観形成基準を満たす土地利用計画の提示が求められる点です。単なる解体ではなく、地域の景観に配慮した再活用が前提となります。
建て替え建設費補助金を設けている自治体もあります。この補助金制度の最大の特徴は、古い家の解体費用に加え、建物の建設費の一部も補助してくれる点です。
地震や台風などで倒壊のリスクが高い家を除却し、新しくて安全な家に建て替えることを狙いとしています。
この制度も対象となるのは劣化が進んでいる古い家で、自治体の審査を受けてから適用可否が判断されます。

古い家の解体に関する補助金の額は、自治体ごとに異なります。中には上限額が100万円という自治体もあり、手厚い支援が受けられるケースも。
ただし上限額100万円とする自治体も、100万円が満額支給されるわけではありません。実際にかかった費用に補助率をかけて計算し、その金額が100万円を下回れば、算出された金額が補助額となります。
一方で、助成金額が少ないところや、そもそも補助金制度がないところもあります。事前に制度内容を確認しておくことが重要です。

古い家の取り壊しを決意し、補助金の申請をする際は、必ずタイミング・流れ・必要書類をおさえましょう。まずタイミングですが、解体工事の前に申請しなければなりません。解体工事に着手してから申請しても、受理されない可能性があるため注意が必要です。
申請の流れは、最初に必要書類を揃えて申請し、適用条件を満たしているかどうか審査を受けます。その後審査に通ってから、解体工事を実施します。解体工事完了後は、自治体に完了報告をおこなう必要があります。自治体は完了報告を確認した後に、補助金を交付する流れです。
必要書類は、自治体によって異なりますが、大まかには以下の書類が必要になると考えておきましょう。
相続した空き家を解体したいときは、所有者がなくなったことを証明する書類や、相続人であることを証明する書類なども必要です。

補助金を利用する際は、以下の点に注意しましょう。
古い家を解体するときは、自治体が建物の状態を調査することが多いです。そのため申請をしてから、審査の結果が届くまでに時間を要します。
申請から審査完了までの期間は、1カ月程度が目安です。審査が終わらない限り、解体工事に着手することはできません。解体工事を先延ばししないよう、できるだけ早めに申請をするようにしましょう。
必ず補助金を受け取れるわけではありません。場合によっては、所定の条件を満たしておらず、審査に通らないこともあり得ます。
審査基準についても自治体ごとに異なります。ある自治体では審査に通っても、他の自治体では対象外になることも少なくありません。
また同じ自治体でも補助金制度の内容を変更したり、廃止したりすることもあります。予算が決まっており、上限に達し次第終了する制度も多いです。
自治体の最新の情報に注意しながら、賢く補助金を活用しましょう。
解体費用の補助金は、工事完了後に支給される後払い方式です。つまり、解体工事の支払いは、まず自己資金で賄う必要があります。補助金があるからといって、工事費用を補助金頼みで予算を組んでしまうと、支払い時に資金が足りなくなる可能性があるためご注意ください。
また、補助金の申請が通ったとしても、工事完了後に補助額が変動することがあります。こうした想定外の事態がおこっても問題なく支払えるよう、満額の工事費を事前に確保しておくことが重要です。
古い家の解体費用に対する補助金は、地域の安全や衛生、景観を守るために、自治体が設けている制度です。
個人所有であることや、税金の未納がないことなど、条件があります。さらに、老朽化して倒壊リスクが高い家であることを、審査してもらう手続きも必要です。補助額についても自治体ごとに違いがあるため、事前によく確認しましょう。
補助金の申請は解体工事前におこない、自治体の審査が完了してから解体工事に着手します。工事完了後の報告も忘れずにおこないましょう。審査には時間を要するため、早めに申請準備に取り掛かることが肝心です。
熊本市不動産売却クイック査定です。
「セカンドハウス」と「別荘」。一見とても似ている言葉ですが、どこが違うかわかりますか?実はセカンドハウスのほうが、税制優遇などのメリットがあり、税金がお得になるのです。
本記事ではセカンドハウスと別荘の違いを解説したうえで、メリット・デメリットを詳しく紹介します。空家を相続して活用法に悩んでいる方や、セカンドハウスの購入を考えている方は必見です。

セカンドハウスと似た言葉に「別荘」があります。どちらも「普段の住まいとは別に所有する家」という点では共通していますが、利用する目的や頻度に明確な違いがあります。
ここからは、まずセカンドハウスの定義を解説し、その後に別荘との違いを詳しく見ていきましょう。
セカンドハウスは、自宅とは別に生活拠点として日常的に使う住まいです。たとえば都市部と地方を行き来する二拠点居住や、週末だけ地方で過ごすような場合が該当します。
セカンドハウスとして利用するためには、自治体に申請し、認定をもらう必要があります。利用頻度が毎月1泊2日以上であれば、セカンドハウスとして認められるのが一般的です。
セカンドハウスと別荘の違いは、利用する目的と頻度です。
| セカンドハウス | 別荘 | |
|---|---|---|
| 利用目的 | 生活拠点 | 保養・リフレッシュ |
| 利用頻度 | 毎月1泊2日以上 | 問わない |
別荘は保養やリフレッシュを目的とした非日常の住まいです。避暑地や自然豊かな場所に建てられることが多く、心身を癒すための空間として利用されます。
一方でセカンドハウスは、生活拠点となる日常的な住まいであり、継続的な利用が前提となります。毎月1泊2日以上の利用があることで、セカンドハウスとしての条件を満たすとされています。

セカンドハウスのメリット・デメリットをまとめました。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 移動の負担が減る 気持ちの切り替えがしやすくなる 税制優遇がある |
維持費の負担が大きい 住宅ローンを使えない可能性 税制優遇には申請が必要 |
それぞれの項目について、詳しく解説します。
セカンドハウスのメリットは、移動の負担が減ることです。
遠方に行く用事が多いと、何回も行き来するのは金銭的にも体力的にも大きな負担になります。しかし、セカンドハウスがあれば、現地に滞在できるため、行き来する頻度を減らすことができます。
たとえば以下のようなケースでは、セカンドハウスがあると非常に便利です。
また、セカンドハウスによって、仕事とプライベートの切り替えがしやすくなるというメリットも。休日はセカンドハウスで過ごすことで、仕事から離れて羽を伸ばすことができます。
さらに税制面での優遇措置もあります。固定資産税、都市計画税、不動産取得税などが対象になりますが、詳しくは『セカンドハウスの「メリット」税制優遇について』で解説します。
生活の拠点が増えるため、不具合や故障が発生すれば修繕費を負担するなど、維持管理費の増加は避けられません。セカンドハウスがマンションの場合は、管理費・修繕積立金を毎月支払います。これらの費用は継続的に発生するため、事前にしっかりと予算を立てておくことが必要です。
また、住宅ローンを利用するのが難しい場合もあります。住宅ローンは普段生活する家のためのローンだからです。その代わりにセカンドハウス向けの専用ローンがありますが、住宅ローンより審査が厳しかったり、金利が高かったりします。また、住宅ローン控除は利用できません。
税制優遇を受ける場合は、申請が必要な点にも注意しなければなりません。毎月1泊2日以上の滞在を証明する書類を添付する必要があります。必要書類は自治体により異なるため、よく確認して適切に手続きを完了させましょう。

セカンドハウスのメリットの一つ、税制優遇について詳しく解説します。セカンドハウスを取得・所有すると、以下の税制優遇を受けられます。
固定資産税は、不動産の所有者に毎年課税される税金です。通常は固定資産税評価額に、標準税率1.4%を掛けて算出されます。
固定資産税=固定資産税評価額(課税標準額)×1.4%(標準税率)
固定資産税には減額措置があります。具体的には、住宅用地の土地にかかる固定資産税が軽減される措置で、減額率は以下のとおりです。
| 区分 | 敷地面積 | 減額率 |
|---|---|---|
| 小規模住宅用地 | 200㎡以下の部分 | 1/6 |
| 一般住宅用地 | 200㎡を超える部分 | 1/3 |
宅地に建てられたセカンドハウスであれば、この減額措置の適用対象です。ただし、建物が立っていない更地は対象外になるため、注意しましょう。
都市計画税も、固定資産税と同じく不動産の所有者に毎年課税されます。ただし、都市計画税が課税されるのは市街化区域内にある不動産に限られます。都市計画税の計算式は、以下のとおりです。
都市計画税=固定資産税評価額(課税標準額)×0.3%(制限税率)
税率は自治体によって異なりますが、0.3%が上限になります。
都市計画税も減額措置があり、減額率は、以下のとおりです。
| 区分 | 敷地面積 | 減額率 |
|---|---|---|
| 小規模住宅用地 | 200㎡以下の部分 | 1/3 |
| 一般住宅用地 | 200㎡を超える部分 | 2/3 |
固定資産税と同じく、宅地に建てられたセカンドハウスは適用を受けることが可能です。
不動産取得税は、不動産を取得した際にかかる税金です。所有権移転登記をしてから、4カ月〜6カ月後くらいに納税通知書が届きます。税額の計算方法は、以下のとおりです。
不動産取得税=固定資産税評価額(課税標準額)×4%(標準税率)
一定の条件を満たすセカンドハウスを取得すると、以下のとおり税制優遇を受けられる可能性があります。
建物の不動産取得税=(固定資産税評価額ー控除額)×3%
土地の不動産取得税=(固定資産税評価額×1/2×3%)-控除額
土地、建物ともに、税率は4%から3%に引き下げられます。また、土地の課税標準額は固定資産税評価額の2分の1に圧縮される制度です。
控除額は建物と土地で計算方法が異なります。建物の控除額は自治体や築年数により変動する仕組みです。土地の控除額は、以下のいずれか多い金額が採用されます。

セカンドハウスを利用する場合、購入する方法と、賃貸で借りる方法があります。ここからはセカンドハウスを購入する場合のメリットとデメリットを解説します。
セカンドハウスを購入するメリットは、以下の2つです。
セカンドハウスを購入することで、資産を保有できる点が大きなメリットです。必要に応じて売却して現金化することもできますし、相続資産として家族に引き継ぐこともできます。
資産の価値を維持するためには、人気エリアや地価上昇が見込まれる地域のセカンドハウスを選びましょう。賃貸とは異なり、家計や景気の状況を見ながら、柔軟な運用ができる点が魅力です。
購入すれば自己所有できるため、リフォームやリノベーションをおこなって、自由にカスタマイズできます。それなりに費用はかかりますが、自分好みの空間に仕上げることで、快適なセカンドライフを満喫できるでしょう。
賃貸だとリフォームやリノベーションは制限されますが、持家なら自由度が高く、長期的な満足度も向上します。
セカンドハウスを使わない期間に、第三者に貸し出して賃貸収入を得ることもできます。セカンドハウスとして使いつつ、民泊として貸し出す方法もあります。需要が高い立地であれば、安定的に収入を得られるでしょう。
ただしセカンドハウスを民泊として活用する場合は、いくつかの条件があります。たとえば、台所、浴室、洗面、トイレが必要なうえ、消防設備への対応が必須条件です。また、民泊の営業日数は年間180日以下でなければなりません。
このように、賃貸運用はさまざまな条件をクリアしなければならず、事前の準備が不可欠です。
セカンドハウスを購入することによるデメリットにも目を向ける必要があります。
セカンドハウスの購入には、初期費用や維持費など多くのコストがかかります。
初期費用については、物件価格だけでなく、登記費用・仲介手数料・税金などの諸費用が発生し、一度に多くの出費が発生します。また、購入後も固定資産税・都市計画税・修繕費・光熱費などを支払い続けなければなりません。
住宅ローンは使えないことが多いため、まとまった自己資金も必要になるでしょう。家計に余裕がある方でないと、生活に負担がかかる恐れがあります。
購入するとなれば、引越しのハードルが高くなることが懸念されます。もし引っ越す場合は、売却や賃貸に出す必要があり、募集には時間と手間がかかります。賃貸住宅に比べると、気軽に住み替えをするのは難しいでしょう。
このように、セカンドハウスの購入は、ライフスタイルや仕事環境の変化に、すぐ対応できない可能性があります。そのため物件選びの際は、長期的な視点で住み続けられそうな物件を選ぶ必要があります。
セカンドハウスを賃貸で借りる場合は、購入に比べて出費が少なく引越ししやすいのがメリットです。しかし自分の資産ではないため、生活するうえで制限がある可能性もあります。ここからは、セカンドハウスを賃貸で借りる場合のメリット・デメリットを解説します。
セカンドハウスを賃貸で借りるメリットは、以下のとおりです。
購入に比べると、賃貸は初期費用や維持管理費など金銭的な負担を抑えられます。賃貸の場合に初期費用として支払うのは敷金・礼金・仲介手数料などで、物件価格のような高額な支払いは不要です。
入居中の物件の維持管理費についても、賃借人側に過失がなければ、基本的にはオーナーが負担してくれます。賃借人として入居中に支払わなければならないのは、家賃・火災保険料・水光熱費・インターネット利用料金などです。固定資産税・都市計画税など税金やローンの返済などの負担もありません。
賃貸の場合は、契約期間が定められているため、その時々の状況に合わせて柔軟に住み替えができます。住み替えの理由は、転勤・転職、子供の進学・独立など多岐にわたります。なかには、ご近所トラブルなど、入居時には予想できなかった事情で住み替えを余儀なくされるケースも少なくありません。
こうした背景から、賃貸のセカンドハウスは「期間限定の住まい」として利用したい人にとって、メリットが大きい選択肢となります。たとえば、一定期間だけ遠方で勤務する予定のある方や二拠点居住を試してみたい方などにとって、賃貸のセカンドハウスはちょうど良い選択肢になるでしょう。
一方で、セカンドハウスを賃貸で借りる場合は、いくつかのデメリットも存在します。
賃貸物件はオーナーの所有物になるため、賃借人が勝手にリフォームやリノベーションができないケースが多いです。そのため、自分好みの空間にカスタマイズするのは難しくなります。
壁紙の変更や設備の入れ替えなども制限されることが多く、居住空間にこだわりたい人には物足りないと感じることがあるでしょう。
賃貸契約にはさまざまな条件があり、生活に制限を受ける可能性があります。たとえばペットの飼育や楽器の使用、長期滞在などに制限がある場合も。
さらに定期借家契約の場合は、契約期間が満了になれば基本的に更新はできず、契約は終了し退去しなければなりません。そのため、賃貸のセカンドハウスを長期的な安定した生活拠点として考えるのは難しいでしょう。

セカンドハウスとして税制優遇を利用するためには、申請をおこない認定を受けることが必要です。申請には以下の注意点があります。
セカンドハウスを取得後60日以内に、都道府県税事務所へ申請する必要があります。購入後は引越し作業などで忙しい時期ですが、くれぐれも期限をすぎないように注意しましょう。
また、自治体によっては、毎年申請が必要なところもあります。たとえば長野県の木曽町では、毎年1月末までに申請をしないと、その年はセカンドハウスの適用を受けられません。自治体によって申請期限が異なる場合もあるため、情報収集をしておきましょう。
申請書に加え、毎月1泊2日以上利用していることを証明できる書類として、以下のような書類を添付しなければなりません。
ただし証明書として利用できる書類は、自治体によって判断が分かれることがあります。自治体のホームページなどでよく確認しましょう。そして証明書類は大切に保管しておくことが必要です。
セカンドハウスは自宅とは別に、仕事や生活の拠点として日常的に利用される住まいです。毎月1泊2日以上利用している場合に、セカンドハウスとして認められます。
セカンドハウスには固定資産税などの税制優遇がある点が大きなメリットです。ただし優遇措置を受けるためには所定の申請が必要で、提出期限や必要書類などに注意しなければなりません。
購入を検討している方は、自治体のホームページなどで制度の詳細をチェックし、確実に税制優遇を受けられるようにしましょう。
熊本市不動産売却クイック査定です。
物件選びをするとき、「軽量鉄骨造」のアパートを見かけたことがある方も多いでしょう。鉄骨という名前から、木造よりも防音性が高く頑丈なイメージを持つ方もいるかもしれません。ところが、木造ともコンクリート造とも異なる軽量鉄骨には注意すべき点やデメリットがあります。そこで今回の記事では、軽量鉄骨アパートはやめとけと言われる理由や軽量鉄骨のメリット、後悔しない軽量鉄骨アパートの選び方などについて解説します。

軽量鉄骨とは、建築における構造様式の一つで、骨組み部分に鉄骨を使用した建物のことを指します。他にも、日本では木造、軽量鉄骨造、重量鉄骨造、鉄筋コンクリート造があります。この中でアパートに用いられるのは、木造や軽量鉄骨です。
また、軽量鉄骨に似た構造で「重量鉄骨」もありますが、これらの違いは使用する鉄骨の厚みです。厚さ6ミリ以下を軽量鉄骨、厚さ6ミリ以上を重量鉄骨と定義しています。鉄骨の厚みが出る分、重量鉄骨の方が強度は高く、高層マンションや高層ビルの建築に使用されます。
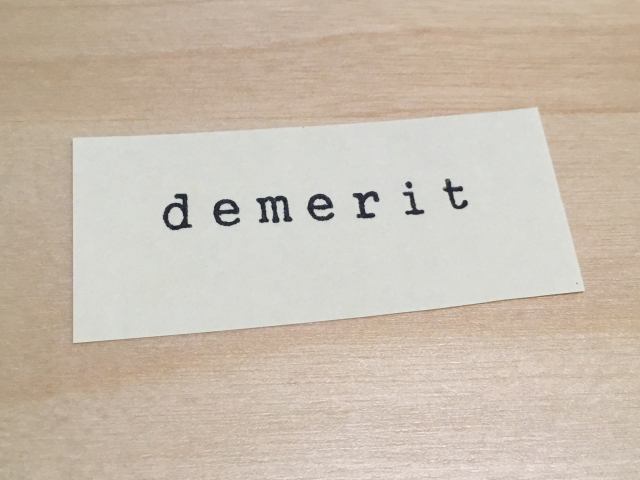
部屋探しをしていると、「軽量鉄骨のアパートはやめておけ!」と言われることがあります。ではなぜ、軽量鉄骨アパートは敬遠されるのでしょうか。ここでは、軽量鉄骨アパートはやめておけと言われる以下の5つの理由について解説します。
それぞれの具体的な内容について解説します。
鉄骨造と聞くと、「防音性が高い」というイメージを持つ人も多いかもしれません。しかし実際は、木造と軽量鉄骨の防音性はほとんど変わらないと言われています。そもそも、軽量鉄骨造のアパートで鉄骨が使用されるのは「柱や梁」の部分です。防音性に関わるのはあくまでも「床と壁」であるため、軽量鉄骨だからといって防音性が高くなることはあまり期待できません。そのため、木造アパートと同様に隣の部屋の話し声が聞こえたり、上の階の足音が響いたりする可能性が高いため注意が必要です。
軽量鉄骨の物件は、調湿・吸湿機能がないため、室内の温度や湿度が外気からの影響を受けやすいというデメリットがあります。そのため「夏は暑く、冬は寒い」という住環境になりがちです。そのため生活する中で、断熱性や通気性を確保する工夫が必要になるでしょう。ただし、夏場にエアコンを使いすぎると結露の原因になったり、電気代が高騰したりする可能性があるため注意が必要です。
軽量鉄骨の建物は、プレハブ工法で施工されることが一般的です。プレハブ工法とは、建物の床や壁、天井などをあらかじめ工場で規格化して現場で組み立てる建築工法のこと。つまり、部材を工場で大量生産すためコストを抑えて、短い期間でアパートを建築することができるのです。その一方で、間取りの自由度が低く、同じような間取りの物件が多くなるケースも少なくありません。
建物を所有していると、毎年固定資産税を支払わなくてはなりません。固定資産税とは、土地や家屋を所有している人が毎年支払う税金で、その年の1月1日時点での建物評価額に基づいて計算されます。一般的に、築年数が経過するにつれて建物評価額が下がるため、固定資産税は安くなっていく傾向です。
しかし、軽量鉄骨は木造住宅に比べて耐久性が高いため、築年数が経過しても価値が大きく低下することはありません。結果として、毎年支払う税金が高額になりやすいというデメリットがあります。ただし、固定資産税についてはオーナーや家主側のデメリットであるため、貸主にはほとんどデメリットにならないでしょう。
鉄骨は塩害や湿気によって錆びやすいため、アパートの立地によっては定期的なメンテナンスが欠かせません。実際に海沿いに住む人からは、鍵穴が錆びついて鍵が抜けなくなった、ベランダの鉄骨が錆びていて危ないなどの声もあります。しかし、鉄骨のサビは目に見える部分だけでなく、目に見えない内部(構造)でも劣化が進行しています。これらの被害を防ぐためには、鉄骨に防錆塗装を施したり、錆びにくい素材で覆ったりする工夫が必要になるでしょう。

ここまで、軽量鉄骨デメリットについて紹介しましたが、軽量鉄骨にも多くのメリットがあります。メリット・デメリットの両方を把握して、住まい選びの参考に役立てましょう。軽量鉄骨のメリットは以下の5つです。
順番に見ていきましょう。
先にお伝えしたように、軽量鉄骨はプレハブ工法で建築されています。プレハブ工法は職人の腕に左右されないため、建物の品質が安定しています。また、建材が気候によって変形したり、変化したりする心配が少ないため欠陥が発生しにくいというメリットがあります。
建物は構造別に耐用年数が定められていますが、軽量鉄骨は木造住宅に比べて耐用年数が長いのもメリットと言えます。軽量鉄骨の場合、鋼材の厚みによって以下のように法定耐用年数が異なります。なお、木造住宅の耐用年数は約22年です。
| 鋼材の厚み | 法定耐用年数 |
|---|---|
| 3ミリ以下 | 19年 | 27年 | 34年 |
現代は建築技術が進化し続けているため、適切にメンテナンスを行うことで実際の建物寿命はより長くすることができます。また、鉄骨造は木造住宅のようにシロアリ被害に悩まされることがないのも大きなメリットと言えるでしょう。
軽量鉄骨は、名前の通り軽量であり、さらに柔軟性があります。地震の揺れに対しても柔軟に対応するため、木造に比べて倒壊しにくいと言われています。地震大国である日本では、耐震性に優れているのは大きなメリットとなるでしょう。また、鉄骨はどの部分も同じ強度を持つため、木材のように場所によって強度が異なるという心配もありません。
軽量鉄骨のアパートは、プレハブ工法によって建築コストが抑えられているため、家賃が安く設定されています。「なるべく家賃を抑えたい」と考えている方は、軽量鉄骨の物件に注目してみるのもおすすめです。木造アパートよりも耐震性に優れ、丈夫な構造であるため日々の安心感にも繋がるでしょう。
軽量鉄骨は木造に比べて火災に強いと言われています。木材は一度火がついてしまうと燃え広がりやすく、全焼してしまう可能性があります。一方、鉄骨造は高温になると強度が低下し変形してしまうものの、鉄骨自体が燃えることはありません。しかし、軽量鉄骨でも倒壊のリスクはあるため注意が必要です。

軽量鉄骨アパートへの引っ越しを検討している方は、事前に下調べしておくことをおすすめします。また、内見時のチェックポイントも紹介しますので、物件選びの参考にしてください。ここでは、後悔しない軽量鉄骨アパートの選び方について解説します。
それぞれの具体的な内容について見ていきましょう。
気になる物件が見つかったら、過去の騒音トラブルや近隣住民のトラブルについて不動産会社に聞いてみましょう。親切な不動産会社は、上下左右にどんな人が住んでいるのか、物件に暮らす人の年齢層などを教えてくれるでしょう。万が一過去に騒音トラブルがあったり、前入居者が短期間で退去したりしている場合には注意が必要です。
お隣の方が不在であれば、内見時に壁を軽く叩いてみると壁の密度が確認できます。密度が高ければ音は響きにくいですが、密度が低いと音や振動が響きやすくなります。また、内見時にお隣の方がいる場合は、壁に耳を当てて隣の音がどのくらい聞こえるのか確認してみましょう。足音や話し声、テレビの音などが聞こえてくる場合は、ちょっとした生活音でも周囲に漏れる可能性があります。
静かな環境で生活したいという方は、部屋の防音性だけでなく、物件の周辺環境にも注意が必要です。特に、駅前や繁華街は人通り、車通りが多くなるため騒がしいでしょう。また、幼稚園や小学校が近い物件は、日中、子どもたちが外で遊ぶ声や、運動会の練習などで騒がしくなる時間帯があります。夜勤の方や、日中は家で静かに生活したい方には不向きな場合がありますので、内見時には物件の周辺環境を必ずチェックしておきましょう。
築年数が浅い物件は、新しい設備や技術が導入されているため、古い物件に比べて快適に生活できる可能性があります。たとえば、モニター付きインターホンが設置されていたり、追い焚き機能付きの給湯器が設置されていたりするケースもあります。
さらに、建物自体の防音性や耐久性が向上しているケースも少なくありません。理想は築10年以内ですが、新しい物件は家賃相場が高めなのでご自身の予算と合わせて検討してみましょう。
内見時には、アパートのエントランスや共用部分がキレイに保たれているか確認してください。共用部分にゴミが落ちていたり、ポストに郵便物が溜まったまま放置されていたりする物件は、住人のモラルやマナーが悪い可能性があります。騒音トラブルや住民同士のトラブルに関わる重要な部分であるため、共用部は必ずチェックしておきましょう。

アパート自体の防音性を高めるのは難しいですが、部屋の防音性は自分で対策することができます。トラブルを未然に防ぎ快適に生活するために、これから紹介する防音対策をぜひ試してみてください。
まずは、ご自身の生活に合ったものを取り入れてみましょう。
遮音カーテンは、特殊な素材や加工を施しているカーテンのことで、音を遮断し室内の音漏れや室外からの騒音を軽減する効果が期待できます。最近はデザインやカラーも豊富なため、お部屋のイメージにあったものを見つけることができるでしょう。ホームセンターやインターネット通販で購入できるため、気軽に取り入れることができます。
音は空気によって伝わりますが、家具は音を吸収してくれるため、配置を工夫することで防音性を高めることができます。たとえば、壁から3cm程度の隙間を空けて家具・家電を設置したり、喋る方向やスピーカーの向きの対角線上に家具を設置したりするだけでも音を和らげることができます。また、家具と壁の間にダンボールを挟むというのもすぐに実践できる効果的な方法です。
家具の配置を工夫しても不安が残る場合は、防音シートや防音パネルなど、防音性を高める専門商品を試してみるのもおすすめです。防音シートは、床、天井、壁、窓などに設置することができます。たとえば、床に設置した場合は、足音や物を落とした際の衝撃音を抑えることができます。
また、窓に貼るタイプの防音シートは、外からの騒音を防ぐことができます。防音シートにはシールタイプ、フェルトタイプ、パネルタイプなどがあるため、用途に応じて選ぶと良いでしょう。ただし、賃貸物件の場合は退去時に原状回復が必要となるため、壁や床を傷つけないよう注意が必要です。
冷蔵庫や洗濯機は稼働中に大きな音がするため、振動マットを敷いておくのがおすすめです。振動による音を防ぐだけでなく、床を傷つけないよう保護する効果もあります。素材や大きさ、色など様々な種類があるため、家電の大きさに合わせて選びましょう。
手軽な防音対策としてスリッパを履くのもおすすめです。スリッパなどの室内履きは衝撃を吸収してくれるため、下の階に伝わる足音を和らげてくれます。ただし、スリッパの種類によっては歩くときにパタパタと音がするため、素足で歩くより足音が大きくなる可能性があります。スリッパを選ぶときは、素材や形状、重量に注意して選びましょう。最近は、防音スリッパと呼ばれる吸音性の高いスリッパもあるため、こういったアイテムをうまく活用してみるのも良いでしょう。
今回は「軽量鉄骨アパートはやめておけ!」と言われる理由について解説しました。軽量鉄骨アパートと聞くと、防音性に優れていると思う方もいるかもしれません。しかし、実際は木造アパートとほぼ変わらないため、防音性に優れているとは言えません。ただし、軽量鉄骨アパートはメリットも多いため、メリット・デメリットの両方を把握してご自身のライフスタイルに合った選択をすることが大切です。
近年は、快適な生活を送るために自分でできる防音対策グッズも増えています。ネガティブな意見にとらわれずに、気になる物件が見つかったらまずは内見してみましょう。本文中で紹介した内見時のポイントを参考にしながら、部屋探しを成功させてください。
熊本市不動産売却クイック査定です。
2017年4月から始まった「都市ガスの自由化」。都市ガスの小売が全面自由化したことで、消費者は自分で好きなガス会社を選べるようになりました。ガスの自由化には、毎月のガス代を抑える、支払い方法に応じてポイントが貯まるなど多くのメリットがあります。しかし、賃貸物件では、管理会社や大家さんがガス会社を指定している場合があります。この場合、入居者は自由にガス会社を選ぶことはできるのでしょうか。そこで今回の記事では、賃貸物件のガス会社を勝手に変更しても良いのか、賃貸でもガス会社が変更できるケース、プロパンガスのデメリットなどについて詳しく解説します。

結論からお伝えすると、賃貸の場合、入居者がガス会社を変更することはできません。ただし、これは「プロパンガス」の場合。都市ガスは、管理会社や大家さんから了承があれば変更できる可能性があります。そこでここでは、プロパンガスと都市ガスの違いやガス会社の変更について解説します。
ガスは大きく分けて「プロパンガス」と「都市ガス」の2種類があります。プロパンガスは、ガスボンベを物件ごとに設置してガスの供給を行います。なお、プロパンガスの場合、物件ごとにガス会社が指定されているため入居者が勝手にガス会社を変更することはできません。また、大家さんに交渉を行ったとしても、既存設備の撤去や新しい会社との契約、設備の再設置などが必要になるため、承認される可能性は非常に低いでしょう。
都市ガスは、地下に通っている配管を使って各家庭にガスを供給しています。都市ガスもガス会社が決まっていることがほとんどですが、管理会社や大家さんの承認があれば自分で契約会社を選ぶことができます。そもそも「都市ガスの自由化」とは、エリアで指定されているガス会社だけでなく、ガス料金やサービス内容を比較して他のガス会社とも契約できるようにしたもの。したがって、一軒家だけでなく賃貸物件でも変更できる場合があります。ただし、賃貸契約で「ガス会社の変更・指定が不可」となっている場合は、都市ガスでも変更できないため注意が必要です。

賃貸物件でも以下に該当する場合は、ガス会社を変更できる場合があります。
詳しく見ていきましょう。
都市ガスが自由化したことで、賃貸物件でも特定のガス会社に固定されずに、入居者が自由にガス会社を選べるようになりました。ただし、全ての賃貸物件が自由に選択できるわけではなく、ガス会社が選べるのは一部の物件です。今後はガス会社が選べる物件が増えていくことが予想されますが、依然として少ないのが実情です。
ガス会社を変更するためには、管理会社や大家さんと交渉するのが有効な手段です。しかし、入居者一人の意見はなかなか反映されにくいため、他の入居者と協力して交渉することが重要です。複数の入居者がガス料金の削減や、サービス向上を理由に交渉すれば説得力が増し、検討してもらえる可能性が高まります。
また、交渉する際は、具体的な料金比較や変更によるメリットをわかりやすくまとめて提案しましょう。さらに、管理側の手間やコストにも配慮して資料をまとめておくことで、よりスムーズに交渉を進めることができます。
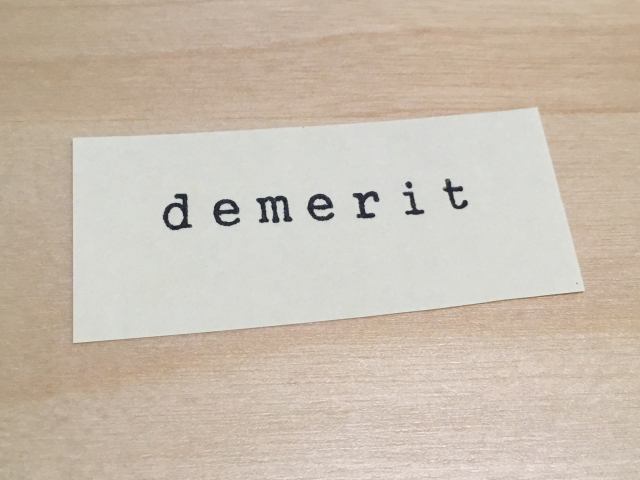
日本の賃貸物件では、プロパンガスが広く使用されています。しかし入居者の中には、「都市ガスの方が安いのに、なぜプロパンなの?」「都市ガスに変更してほしい」と思う方もいるでしょう。ではなぜ、賃貸物件ではプロパンガスの利用率が高いのでしょうか。ここでは、賃貸物件でプロパンガスが多い理由やプロパンガスの料金が高い理由について解説します。
賃貸物件では、管理会社や大家さんがガス会社と長期契約していることが多いです。また、初期設備費用(給湯器や配管設備など)をガス会社が負担する代わりに、ガスの供給契約を独占契約という形で提携している可能性があります。そうなると、プロパンガスから都市ガスへ変更するのは非常に困難であり、入居者はプロパンガスを使用し続けなくてはなりません。
また、独占契約しているため他社と価格競争をする必要がなく、料金は高止まりしやすくなります。都市部では都市ガスが普及しつつありますが、地方のインフラが整っていない地域では、まだまだプロパンガスの普及率が高いのが実情。このような背景から、賃貸物件ではプロパンガスの方が多いと考えられます。
「プロパンガスは高い」という噂を聞いたことがある方も多いのでしょう。事実、プロパンガスと都市ガスを比較すると2倍ほど金額差があるというデータもあるのです。下表では、東京都のプロパンガスと都市ガスの料金を比較しました。
| 基本料金 | 従量料金(10㎥利用時) | 合計金額 | |
|---|---|---|---|
| プロパンガス | 1,730円(1,903円) | 5,850円(6,435円) | 7,580円(8,338円) |
| 都市ガス | 960円(1,056円) | 3,057円(3,363円) | 4,017円(4,419円) |
※()内税込価格
※プロパンガスの価格は「エネ研・石油情報センター」より2025年6月発表データ参照
※プロパンガスの熱量は都市ガス比2.23倍のためプロパン換算しています。
意外と知らない方も多いですが、プロパンガスは公共料金ではありません。都市ガスは2017年に自由化されましたが、プロパンガスは1997年から自由化されています。そのため、プロパンガスはガス会社が自由に価格設定することができます。
また、プロパンガスは各家庭への配送料や設備維持コストがかかるため、その分の料金がガス料金に上乗せされているケースも多いです。このような理由から、都市ガスに比べてプロパンガスの方が高くなるのだと考えられます。

ガス会社を変更する際は、以下の点に注意が必要です。
先にお伝えしたように、プロパンガスの物件はガス会社を変更することができません。プロパンガスか都市ガスかわからない場合は、物件の敷地内にガスボンベが設置されていないか確認してください。また、ガスメーターが敷地内に1箇所しかない場合は、建物一括管理の可能性が高いです。この場合は、都市ガスであってもガス会社の変更ができないため注意が必要です。さらに、物件によっては賃貸借契約書に「ガス会社変更不可」と記載されている場合があるため、こちらも必ず確認しておきましょう。
最後に、住む場所によっては対応しているガス会社が少ない可能性があります。特に地方では、ガス会社が1社しかないケースもあります。そのため、事前に住む地域に対応しているガス会社がいくつあるのか調べておくことをおすすめします。
ガス料金は、毎月の家計管理に関わる部分であるため、「引っ越し先の物件がプロパンガスか都市ガスか気になる」という方も多いでしょう。引っ越し先のガス会社を調べるには、以下の方法が有効です。
引っ越し後はライフラインの開始手続きが必要となるため、不動産会社からガス会社や水道局、電力会社の説明を受けることが一般的。そのため、引っ越し後にガス会社がわからなくなった場合は、不動産会社に確認するのが確実です。また、ガスメーターにガス会社の連絡先が記載されている場合がありますので、そちらを確認するのも良いでしょう。ポータルサイトに記載されている場合もありますが、同じマンションで空き部屋がなければ、インターネット上から物件情報が削除されている可能性があります。
では、実施に「都市ガス」を使っている人と「プロパンガス」を使っている人の口コミを見ていきましょう。
まずは、都市ガスの口コミから紹介します。
前の家はプロパンでガス代高すぎたから、部屋探しは都市ガス一択だった!
都市ガスの口コミは、料金に対してポジティブな意見が多い印象です。一方で、都市ガスの物件が少なく、物件選びの選択肢が少ないといった意見もありました。
次に、プロパンガスの口コミを見ていきましょう。
プロパンガスの口コミは、料金に対するネガティブな意見が多い印象です。プロパンガスの場合、ガス会社を変更することも容易ではないため不満が出やすいのでしょう。引っ越してから後悔しないためには、事前にガスの種類を確認しておくことが大切です。
今回は、「賃貸物件でガス会社を勝手に変更することができるのか」について解説しました。結論からお伝えすると、賃貸物件の約半数はプロパンガスを使用しているため、入居者が勝手にガス会社を変更することはできません。一方、都市ガスの場合は、管理会社や大家さんの承認があれば変更できる可能性があります。
ガス代は毎月支払う出費であるため、できるだけ安く抑えたいと考えるのが一般的。プロパンガスと都市ガスを比較すると、2倍近い価格差が生じる可能性もあるため、物件選びは慎重に行いましょう。これから引っ越しを検討している方は、事前に「プロパンガスか都市ガスか」を調べておくことをおすすめします。
また、現在プロパンガスの物件に住んでいて、「どうしても都市ガスに変更したい」という方は、管理会社または大家さんに交渉してみるのも一つの手段です。ただし、入居者一人の意見は反映されにくいため、入居者同士の協力が必要になります。プロパンガスから都市ガスへの変更はなかなか難しいのが実情ですが、インフラ整備のタイミング等が合えば変更できる可能性もあるでしょう。
熊本市不動産売却クイック査定です。
賃貸物件へ入居する際には、敷金・礼金を払うのが一般的です。しかし、借りる立場からすると「なぜ毎月家賃を払うのに、礼金を払う必要があるの?」「礼金制度が理解出来ない」と思う方もいるかもしれません。では、そもそも礼金とは何のために支払うものなのでしょうか。この記事では、礼金を支払う意味や目的、払いたくない場合の対処法、礼金なし物件の注意点などについて解説します。

礼金は「謝礼金」の一種で、大家さんに対して「貸してくれてありがとう」「お世話になります」といった意味を込めて支払う金銭です。なお、礼金は日本だけの文化と言われており、退去時に返還されることは基本的にありません。礼金の文化には諸説ありますが、昔は部屋を貸してくれる人が少なかったため、このような礼金文化が根付いたのではないかと言われています。そこでここでは、礼金の無い物件はあるのか、礼金の相場、礼金は違法なのか?などについて解説します。
結論からお伝えすると、礼金の無い物件もあります。礼金があると初期費用が高くなるため、空室を防ぐ対策として「礼金なし」にしている物件もあります。しかし、約7割近くの物件は「礼金あり」です。近年は、礼金なし物件も増えつつありますが、まだまだ礼金文化が強く残っているのが実情でしょう。
礼金は、家賃の1カ月~2カ月分が相場です。多くの場合は家賃1ヶ月分ですが、東京や大阪などの都心部や、人気エリアにある物件は礼金が高い傾向にあります。たとえば、家賃15万円の物件で礼金2カ月分であれば、礼金だけで30万円支払わなくてはなりません。初期費用を抑えて引っ越ししたい方は、物件に少し妥協して「礼金なし」物件を選んだ方が安く引っ越しできるでしょう。
仲介手数料は、法律で上限額が1.1カ月分と定められていますが、礼金には法律規制がありません。また、礼金の上限額も定められていないため、2カ月分でも3カ月分でも大家さんが自由に決めることができます。

インターネット上には、「礼金は頭おかしい」などの口コミも見受けられますが、礼金は支払わなくてはいけないのでしょうか。ここでは、礼金を支払う4つの理由について解説します。
項目ごとに見ていきましょう。
礼金が風習化したきっかけは以下の2点です。
1923年の関東大震災では、多くの人が住む場所を失いました。そんな中、家を貸してくれる大家さんに対して「感謝の気持ち」を込めて礼金を渡したのが礼金の始まりではないかと言われています。また、高度経済成長期には、親元を離れて暮らす子どもが多く、大家さんが親代わりになっていました。そのため、親たちが「子どもをよろしくお願いします。」という意味を込めて礼金を渡していたとも言われています。このような風習が現代まで続き、礼金文化として残っているのでしょう。
礼金を多めに取ることで、月々の家賃を下げて安く見せる戦略があります。たとえば、本当は家賃10万円の物件でも、礼金を2カ月分にして家賃を9万円にします。類似物件に比べて家賃が1万円安ければ借りたい人が出てくるでしょう。このように、空室を防ぐために礼金を高めに設定し、家賃を安く見せる方法があります。こういった物件は、長期的に住むなら良いですが、1年未満に退去すると損する可能性があるため注意が必要です。
敷金はクリーニングや退去費用に充てられますが、物件によっては礼金をクリーニング費用に充てることがあります。ただし、礼金の内訳は借主にはわからないため、何に使用されるかは不透明でもあります。
広告料とは、不動産会社に対して支払う報酬のこと。他にも、AD、業務委託料、仲介手数料といった呼び方をすることもあります。広告料の相場は、家賃の50%~100%です。たとえば、家賃10万円の物件を契約したら、不動産会社は広告料として5万円~10万円を受け取るイメージです。条件の悪い物件は、なかなか入居者が決まらないため、入居者からもらう礼金を広告料に充てる大家さんもいます。
SNSでは、「礼金は頭おかしい!」など一部過激な意見もあります。しかし、別観点からの意見もあるため、SNS上の投稿に惑わされすぎないよう注意が必要です。では、実際にどのような口コミがあるのか見ていきましょう。
SNS上では、礼金に対する口コミが多数見受けられます。以下は礼金対する口コミの一例です。
礼金は決して安くないため、「理解できない」という声が多い印象です。特に金銭的に余裕のない若者や年金暮らしの高齢者からは不満の声が上がりやすいでしょう。

高額な礼金を支払いたくない方や、中には金銭的な余裕がなく支払えない方もいるでしょう。ここでは、礼金を支払いたくない場合の対処法を3つ紹介します。
項目ごとに解説します。
近年は、「礼金なし」の物件も増えているため、礼金を支払いたくない、礼金を支払うお金がないという方は、礼金なしの物件に絞って部屋探しを行うのがおすすめです。ただし、礼金なしの物件にはデメリットがあり可能性があります。また、人気エリアや人気物件は、「礼金あり」でも競争率が高く、礼金なしで借りることはなかなか難しいでしょう。
大家さんに直接交渉してみるのも有効な方法です。たとえば、空室期間が長い物件の場合、大家さんはすぐにでも入居してほしいと考えます。そのため、「即入居するから礼金をなしにしてほしい」と交渉してみると良いでしょう。なお、交渉時に上から目線でいくのは要注意。礼金なしの交渉どころか、契約自体を拒否される可能性もあるため注意しましょう。
不動産にも繁忙期と閑散期があります。一般的に1月~3月が繁忙期、6月~8月が閑散期とされています。繁忙期は、進学、就職、転勤などで物件の競争率が高くなるため、希望の物件を見つけたり、礼金なしの交渉をしたりするのが難しくなります。
一方、閑散期であれば、物件の競争率も下がるため、物件も選びやすく、礼金交渉もしやすくなるでしょう。
礼金なし物件には、何らかのデメリットが隠れている場合があります。そのため、これから紹介する注意点に気をつけながら物件探しを行いましょう。
それでは順番に見ていきましょう。
1つ目は、特約付き物件の可能性です。特約付き物件とは、短期解約違約金や契約の縛りがある物件のこと。たとえば、「3カ月以内に退去した場合は、違約金として家賃1カ月分支払う」といった定めや、「2年間は解約できない」などの特約が設けられています。長期的に住む場合はあまり問題ありませんが、短期で部屋を探している方は損をする可能性が高く注意が必要です。
2つ目は、物件自体に欠点がある可能性です。先にお伝えしたように、人気の物件は競争率が高く、礼金1カ月でも借りたい人は多いです。一方、駅から遠く利便性が悪い、築年数が古い、お風呂がないなど、物件自体に欠点があると礼金をゼロにして入居者を募るケースがあります。住んでから後悔しないためにも、あらかじめ物件の詳細を細かくチェックしておくことが大切です。
3つ目は、物件自体に何かしらのトラブルがある、または過去にトラブルがあった可能性です。「事故物件」という言葉を聞いたことがある方も多いかと思いますが、礼金なしの物件は事故物件の可能性もあります。ただし、直近で事故が起こった物件は、物件情報欄に記載されるため事前に確認することができます。
一方、近隣住民でトラブルになりやすい人がいたり、前入居者が何らかの理由ですぐに退去してしまったりした場合は、物件情報に記載されることはありません。したがって、入居前に「なぜ、この物件は礼金なしなのか」不動産会社に理由を聞いてみると良いでしょう。
今回は、「礼金を払うのはおかしい?!」をテーマにお伝えしました。借主側からすると、礼金を支払うメリットは「ほとんどない」と言っても過言ではありません。したがって、礼金は頭おかしいという過激な発言もあながち間違ってはいないでしょう。しかし、礼金の上限額についての法律はなく、礼金1カ月、2ヶ月、もしくはそれ以上でも違法ではありません。また、礼金は敷金のように退去時に返却されるものではないため、礼金が相場より高いときは、しっかり納得した上で支払うようにしましょう。
一方、どうしても礼金を支払いたくない場合は、礼金なし物件に絞って部屋探しをするのも有効な手段です。ただし、礼金なし物件にはデメリットがある可能性が高いため、物件の詳細はしっかり確認しましょう。ネガティブなイメージの強い礼金ですが、礼金文化の背景には「大家さんへの感謝の気持ち」があります。現代は住む場所も多く選択肢は様々ですが、賃貸物件は「借りている」という感謝の気持ちを忘れないことが大切なのではないでしょうか。
熊本市不動産売却クイック査定です。
マンションは規模によって住み心地や費用面に違いがあるため、どのような基準で選べば良いか悩む方も多いのではないでしょうか。
中には「大規模マンションや小規模マンションは買ってはいけない」といった意見を耳にしたことがある方もいるでしょう。しかし、実際にはそれぞれにメリット・デメリットが存在し、ライフスタイルや価値観によって向き・不向きが分かれるものです。
本記事では、大規模マンションと小規模マンションのメリット・デメリットを紹介します。マンション選びで後悔しないための参考情報としてご活用ください。

大規模マンションを購入して後悔する人は、以下のような不満を抱えていることが多いです。
大規模マンションの特徴といえば、良くも悪くも圧倒的な広さです。どこまでも続く共用廊下、高層階までそびえ立つ建物。複数の棟に分かれていたり、広大な駐車場があったりして、移動には一苦労です。
敷地外に出るのに時間がかかるため、ちょっとした外出でもおっくうに感じることがあるでしょう。
大規模マンションは、エレベーターの混雑が予想されます。朝の通勤ラッシュは、多くの人がエレベーターを利用するため、各階に頻繁に停まり、地上に降りるだけでも多大な時間がかかってしまいます。
ようやく来たと思ったら満員で乗れず、さらに待たされることも少なくありません。乗りたいときに乗れないストレスは想像以上で、日常生活の大きな不満につながるでしょう。
特に高層階に住んでいる人にとって、エレベーターは無くてはならない移動手段です。低層階であれば階段の利用も可能ですが、高層階では現実的ではありません。そのためエレベーターへの依存度は非常に高くなります。
大規模マンションは住戸数が多いため、住民同士の繋がりが希薄になりやすいです。隣人の顔すら知らないというケースも珍しくありません。
たとえマンションの共用施設が充実していても、利用者は分散しやすく、自然なコミュニケーションは生まれにくいでしょう。イベントや自治会活動を開いても、誰が参加するかわからないため、参加率が低い傾向があります。
このような状態だと、防犯面のリスクが高くなります。住民同士が多すぎて、部外者が入ってきても気づきにくくなるからです。
高層の大規模マンションは、地震のときに揺れが大きくなりやすい傾向があります。さらにエレベーターが停止すれば、高層階へのアクセスは非常に困難になります。震災後、自宅避難となった場合は、自宅まで物資を運ばなければなりません。そうなればエレベーターを使えないことが、生活に大きな支障をきたします。
停電や断水が発生すると、復旧までに時間がかかることも。避難経路や防災設備の管理も複雑になりがちで、不安を感じる人も多いでしょう。
管理費は、管理員の人件費や設備の点検・清掃など、マンションの日常的な管理業務に充てられる費用です。一方、修繕積立金は一定の周期で行われる外壁補修や防水工事など、大規模修繕に備えた積立金になります。
大規模マンションは共用設備が充実しているため、これらの維持管理にかかるコストが高額になりがちです。フィットネスジムやラウンジ、ゲストルームなど豪華な設備は魅力的ですが、使わない住民にとっては無駄な負担に感じられることもあります。
さらに、建物の規模が大きければ修繕工事の際には高所作業や広範囲な足場の設置が必要となり、その分工事費用も跳ね上がります。建物のデザインが複雑である場合、専門的な工事や部材の調達が必要となり、想定以上の費用が発生するケースも少なくありません。
住民数が多い大規模マンションでは、マンション内の意思決定がまとまりにくいというデメリットがあります。管理組合で何かを決める場合、その決議内容によって必要な賛成票の割合が定められています。
たとえば、管理規約の変更や大幅な共用部の改修を行うには、4分の3以上の賛成が必要です。住民の数が多いほど意見が分かれやすく、賛成票を集めるのが困難になります。その結果、改善や修繕がなかなか進まないケースもあるのです。

大規模マンションは、規模の大きさを活かして以下のようなメリットを享受できます。
大規模マンションは、共用施設が充実していることが多いです。住戸数が多いほど1戸あたりの管理費負担が軽くなり、スケールメリットを発揮できるからです。たとえば300戸規模のマンションで管理費1万円なら、月額合計は300万円となり、維持管理費に十分な予算が確保されます。
共用施設の代表例を挙げると、以下のとおりです。
同じ建物内にこれらの共用施設があれば、生活利便性が大きく向上するでしょう。さらに、複数棟で構成されるマンションでは、敷地内に公園やクリニックなどが併設されることも。子育て世帯から高齢者世帯まで、幅広い層に対応した魅力的な住環境です。
セキュリティ対策が充実しており、安全に暮らせる点も大規模マンションのメリットです。たとえば管理人やコンシェルジュがエントランスに常駐していることで、不審者が入りにくい体制になっています。
24時間有人管理の体制を採用していて、日中は管理人、夜は警備会社が管理しているマンションも多いです。24時間体制で管理する人がいることは、一人暮らしや小さい子どものいる家庭にとってとても心強いです。
また、エントランスのオートロックをはじめ、エレベーターの着床制限や防犯カメラの設置など、複数のセキュリティシステムで守られているマンションも。近年は強盗事件も増加傾向にあるため、セキュリティが充実しているのは重要なポイントです。
大規模マンションは資産価値を保ちやすく、将来的に売却や賃貸をする際も有利に働く可能性があります。先ほど紹介した共用施設やセキュリティの充実が、資産価値として高く評価されるためです。また、タワーマンションは視認性が高いため、地域のランドマークとして認識され、資産価値の向上につながることもあります。
ただし、すべての大規模マンションが資産価値を維持できるわけではありません。立地条件や修繕状況に問題がある場合は、資産価値が低下する恐れも。資産価値を維持しやすいマンションかどうかは、慎重な見極めが必要です。
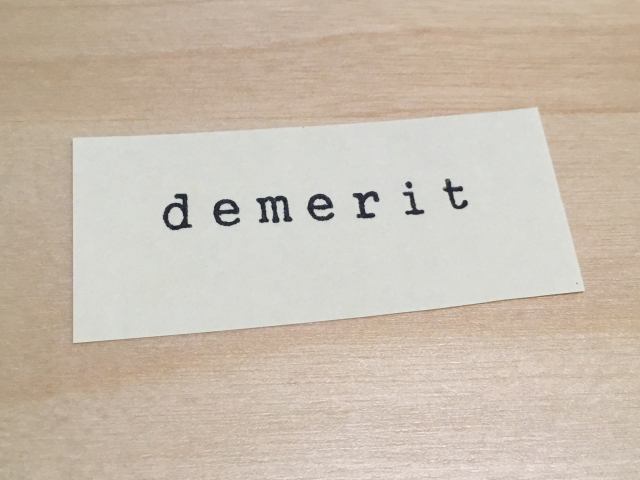
大規模マンションとは正反対の小規模マンションはどうなのでしょうか?小規模マンションにもデメリットはあるため、買って後悔する人もいます。
住戸数が少ない分、1戸あたりの管理費負担が重くのしかかります。費用を分担できる人数が限られるため、管理費や修繕積立金が高くなる傾向です。
国土交通省の令和5年度マンション総合調査によると、マンションの形態ごとの管理費と修繕積立金の平均は以下のとおりです。
| 形態 | 管理費総収入/月/戸あたり | 修繕積立金総収入/月/戸当たり |
|---|---|---|
| 20階建以上 | 24,585円 | 13,834円 |
| 11~19階以上 | 16,597円 | 12,626円 |
| 6~10階以上 | 16,944円 | 13,637円 |
| 4~5階以下 | 17,529円 | 13,864円 |
| 3階以下 | 20,112円 | 14,231円 |
| 平均 | 17,214円 | 13,300円 |
出典:国土交通省「令和5年度マンション総合調査・管理組合向け調査の結果」(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001750163.pdf)
管理費は20階以上が最も高く、次いで3階以下の小規模マンションが高くなっています。修繕積立金については、3階以下が最も高額という結果でした。
以上のデータからも、小規模マンションは大規模マンションと同程度もしくはそれ以上に管理費や修繕積立金が高いことがわかります。
敷地面積が狭かったり階数が低かったりして、共用施設を確保するだけの面積の余裕がありません。また、住戸数が少ないため、豪華な共用施設をつくっても1戸あたりのコスト負担が重くなるのも難点です。
もし共用施設があったとしても、小規模だったり設備が簡素だったりなど、満足度が高いとはいいきれません。共用施設を重視する方にとっては、大規模マンションのほうが魅力的に映る可能性があるでしょう。
小規模マンションの管理組合では、理事役員が少人数で構成されるのが一般的です。国土交通省が作成した「マンション標準管理規約(単棟型)コメント」によれば、理事の員数はおおむね10〜15戸につき1名が目安とされています。たとえば30戸のマンションであれば理事役員は3名程度です。
管理組合業務は修繕積立金の運用や官公署・町内会との渉外など多岐にわたります。人数が少ないと業務の分担が難しく、1人あたりの負担が重くなる傾向があります。
住戸数が少ないため共用の設備にお金をかけられず、セキュリティ対策が手薄になることがあります。たとえばコンシェルジュの常駐や24時間有人管理を採用している例は少なく、大規模マンションと比べると違いが出やすいです。
ただ、オートロックや防犯カメラの設置によって、一定の安全性が確保されている物件が多いです。小規模ならではの制約はあるものの、管理組合や居住者の防犯意識が高ければ、セキュリティ対策を強化することもできます。
ランドマーク性や充実した共用施設がある大規模マンション。それに比べると、資産価値を維持しにくいといわれることもあります。
しかし、小規模マンションのなかには駅近など利便性の高い場所に立地し、資産価値が安定している物件も少なくありません。一概に資産価値を維持しにくいとはいいきれないでしょう。
売却するときのネックがあるとすれば、管理費・修繕積立金が高額であることです。近年は住宅価格が高騰しているため、管理費・修繕積立金の高さを理由に、買い手がつきにくくなる恐れがあります。

小規模マンションには、以下のようなメリットもあります。
住戸数が少ないので、他の居住者と顔を合わせる機会が多いです。その結果、自然と顔見知りになり、繋がりが生まれやすいというメリットがあります。
住民同士の繋がりは、防犯面でも良い効果をもたらします。居住者の顔を把握できるため、居住者以外が出入りしていると「見慣れない顔だな」という違和感を覚えやすくなるのです。
これを「人の目による防犯」といい、心理的な犯罪抑止効果が期待できます。実際、誰かに見られているかもしれないという意識は犯罪を思いとどまらせる効果があります。
「小規模マンションはセキュリティ対策が課題」といわれることがありますが、人の目による防犯が機能していれば、防犯設備に頼らなくても安心して暮らすことができます。住民同士の繋がりがもたらす安心感は、特徴的なメリットともいえるでしょう。
小規模マンションは好立地に建てられることが多いです。都市部では土地の需要が高く、開発用地の確保が難しくなっています。生活利便性の高いエリアでは土地の細分化も進んでおり、結果として狭小地を活用した小規模マンションの建設が増加している状況です。
また、都心部では土地価格の上昇しているため、大規模マンションの事業化ハードルが高くなっています。その点、限られた資金でも事業化しやすい小規模マンションは、現実的な選択肢として不動産デベロッパーに選ばれています。
さらに、「第一種低層住居専用地域」や「第二種低層住居専用地域」といった閑静で良好な住環境が保たれたエリアでも建設可能です。立地の良さに加え、住みやすさも支持されている理由の一つです。
こうした理由から、立地を重視する方にとって魅力的な選択肢といえるでしょう。「不動産は立地がすべて」と言われることもあり、購入時の判断材料として重要視されるポイントです。
居住者が少ないので、混雑に悩まされることは少ないでしょう。階数が低いため、エレベーターの待ち時間も短く、スムーズな移動が可能です。
万が一エレベーターに人が集中しても、気軽に階段移動に切り替えることが可能です。大規模マンションの高層階は階段を使うのは億劫ですが、小規模マンションであればエレベーターと階段どちらも使いやすく、フラットな選択ができます。
こうした混雑の少なさは、日常の利便性や快適性に直結するポイントです。自分のペースを大切にしながら、落ち着いた暮らしを送りたい方にとっては理想的な住まいといえるでしょう。

規模に関わらず、マンションを購入する際は、以下の点を重視して選ぶと後悔しにくいです。
将来的に売却する可能性がある場合は、資産価値を維持しやすい物件を選ぶことが大切です。購入時には売却を想定していなくても、家族構成やライフステージの変化、住宅ローンの返済などが理由で、マンションを手放さざるを得ない状況になることもあります。
マンションの資産価値は、築年数や間取りだけでなく、立地や共用施設などさまざまな要素によって決まります。特に立地は重要で、都心部や駅近の物件は需要が安定しているため、資産価値が下がりにくいでしょう。反対に郊外や駅から遠い物件は需要が落ち込みやすく、資産価値の低下リスクが懸念されます。
また、マンションの場合は共用部が適切管理されているかどうかも、資産価値を保つうえで重要なポイントです。管理組合の運営状況も確認しておくと安心です。管理体制がしっかりしていないと、資産価値が下がる原因になりかねません。
マンションを購入する際は、物件価格だけでなく、管理費や修繕積立金を調べることも大切です。管理費や修繕積立金は、毎月発生するランニングコストなので、家計への影響が大きいです。
国土交通省「令和5年度 マンション総合調査」によると、管理費は1万7,214円、修繕積立金は1万3,300円が平均になるので、一つの目安にすると良いでしょう。ただし、先述のとおり小規模マンションや大規模マンションは管理費・修繕積立金が高額になりやすい点も考慮が必要です。
徴収される金額がマンションの適切な維持管理に足る水準であるかどうかという視点も大切になります。徴収額が不足していると、清掃や設備点検の質が維持できなかったり、将来的な大規模修繕に備える資金が不足したりするリスクもあります。また、居住者の滞納状況も資金運営に影響するため、可能であれば事前に確認しておくと安心です。
こうした情報を把握する際には、管理組合の活動状況を知ることが大切です。不動産会社経由で管理費の議事録や長期修繕計画書を入手することで、資金の使途や適切な管理体制なのか判断する材料になります。
共用設備が充実しているマンションは、誰の目にも魅力的に映るものです。ラウンジやジム、ゲストルームなど、豪華な施設が備わっていると、生活の質が上がりそうな気がしますよね。
しかし、共用設備が充実しているマンションは管理費・修繕積立金も高くなります。使わない設備に対して、長期的にコストを負担し続けるのは非常にもったいないことです。
マンション選びでは、共用設備を本当に使うかどうかを見極めることが大切です。特に大規模マンションは共用設備が豊富な傾向ですが、実際に利用する見込みがあるかどうかを冷静に判断することで、無駄な出費を省くことができます。
大規模マンションはスケールの大きさゆえに、動線の長さやエレベーターの混雑など、生活するうえでストレスを感じることがあります。しかしスケールメリットを活かして、維持管理コストを効率的に集めることが可能なので、共用施設やセキュリティ対策が充実しているのが魅力です。
一方で小規模マンションは住戸数が少ないため、1戸あたりの維持管理コストの負担が重くなりやすいです。しかし、住民同士のつながりや、好立地に建てられる物件が多いことなど、小規模ならではの魅力も存在します。
大規模・小規模それぞれにメリットとデメリットがあるため、一概に「買ってはいけない」とはいいきれません。いずれの場合も、資産価値の維持が可能か、管理費や修繕積立金が適正かどうかを見極めることが、後悔しない物件選びにつながります。
熊本市不動産売却クイック査定です。
これから賃貸住宅を退去する際、「敷金がいくら返ってくるか」は多くの方が気になるポイントではないでしょうか。敷金は大きな額になるため、できるだけ多く返金されることを期待しますよね。しかし蓋を開けてみると敷金がほとんど戻らず、泣き寝入りをしたり、貸主とトラブルになったりするケースも少なくありません。
本記事では敷金の返還割合と返ってこない場合の理由、そしてトラブルを避けるための対処法についてわかりやすく解説します。敷金に関する基本的な知識を身に着けて、納得いかないときは自分で適切な対応をとれるようにしておきましょう。

最初に基本的な考え方を整理すると、敷金とは入居時に貸主に預けるお金のことです。退去する際は貸主が敷金から修繕費用を支払い、残りの金額が借主に返還されます。家賃の1〜2カ月分程度が相場になります。
敷金と似ている用語として、礼金があります。礼金は借主から貸主へのお礼として支払うお金で、返金されることはありません。敷金と礼金は混同しやすいので、注意しましょう。
リクルート住宅総研の調査によると、東京の敷金返還率は以下のとおりです。
| 敷金返還率 | 回答者の割合 |
|---|---|
| 100% | 12.2% |
| 50%~100%未満 | 41.3% |
| 50%未満 | 15.5% |
| なし(0%) | 31.0% |
出典:リクルート住宅総研「NYC,London,Paris&TOKYO賃貸住宅生活実態調査」
最も多いのが50%〜100%未満で返還されたケース、次に多いのが全く返ってこなかったケースです。それらに比べて、全額返金されたケースは12.2%と少数派です。敷金返還率の平均を求めても、42.3%と意外と少ないことがわかります。
退去時に返ってくる敷金は、どれくらいになるのでしょうか?返金額の相場や返金されるタイミングについて解説します。
敷金返還率の平均42.3%を使って、退去時に返ってくる金額をシミュレーションしてみましょう。
| 敷金の金額 | 退去時の返金額 |
|---|---|
| 5万円 | 2万1,150円 |
| 10万円 | 4万2,300円 |
| 15万円 | 6万3,450円 |
| 20万円 | 8万4,600円 |
上記のように家賃の半分近い金額が返ってくると、家計的にも助かりますよね。引っ越し費用や新居の家賃、生活費などに充てることができます。
通常は退去後2カ月以内に敷金が返還されることが多いです。退去から敷金が返還されるまでの流れは以下のとおりです。
退去立会いから敷金精算書が届くまでの期間は、通常1カ月以内です。ただし場合によっては貸主側の処理に時間がかかり、2カ月程度経過してから届くケースも。1カ月経っても届かない場合は、念のため契約書の敷金返還期限を確認します。期限を過ぎそうな場合は、貸主や管理会社に確認したほうが良いでしょう。
そして敷金精算書が届いてから1カ月以内に、敷金が返還されます。敷金精算書は退去時に貸主が作成する書類で、敷金から差し引かれる修繕費の内訳や、敷金の返金額が記載されています。

敷金が返ってこない理由は、簡単にいえば修繕費がかかるからです。具体的には、以下のような理由で返ってこないことが多いです。
それぞれの理由を詳しく見ていきましょう。
よくあるのが、退去時に汚れが見つかり、その修繕費用のせいで敷金が返ってこないケースです。
国土交通省は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」において、借主の故意や過失によって生じた通常の使用範囲を超える損耗については、借主が修繕費を負担するものとしています。一方で、経年変化や日常使用による損耗については、賃料に含まれるべきとしています。
たとえばペットがつけた壁紙の汚れや、喫煙による壁紙の変色は、通常の使用範囲を超える損耗とみなされ、敷金から修繕費が差し引かれることが多いです。反対に、日焼けによる壁紙の変色や家具の設置跡などは、生活していれば自然に起こる現象とされ、修繕費用は請求されないことが多いです。
とはいえ、どこまでを経年変化とするかは、貸主によって判断が分かれるところです。入居時の状態を写真に残しておくと、後で経年変化であることが証明しやすくなることもあります。
賃貸借契約書に記された特記事項の内容によっては、経年変化とみなされる損耗も修繕費用を請求されるケースがあります。特記事項とは、特別に記しておくべき重要事項のことです。もし特記事項の内容が契約書の条項と相反する場合は、基本的に特記事項の内容が優先されます。
たとえば、壁紙の張替え費用を借主に負担させる特記事項です。他にも、極端なケースでは「借主が修繕費を負担する」「貸主は修繕義務を負わない」といった一方的な条項が盛り込まれている場合もあります。
特記事項をよく確認しないまま契約を結んでしまうと、その内容に同意したとみなされてしまいます。入居時には全く気付かず、退去時に初めて気づいて後悔するケースも。借主に不利になるような特記事項がないか、締結前に必ず確認しましょう。
契約書に「ハウスクリーニングの費用を借主が負担する」と書かれているケースもあります。ハウスクリーニングとは、退去時に専門業者が室内を清掃するサービスで、キッチンや浴室、床などの全体的なクリーニングが含まれます。
費用相場は、一人暮らし用の物件でおよそ2万円〜4万円程度。部屋が広くなるほど金額も上がり、3LDK以上のファミリー向け物件では7.5万円〜10万円程度かかることも。敷金から差し引かれる修繕費のなかでも、ハウスクリーニングは大きな割合を占めます。
繰り返しになりますが、既に締結済みの契約書に対して、後から異議を唱えるのは難しい場合もあります。締結する前に内容を確認し、納得いかない点があれば事前に交渉しておくことが大切です。

納得いかない修繕費を請求され、敷金が戻らなかった場合は、適切な対処が求められます。
ここからは代表的な対処法として、以下の2つをご紹介します。
それぞれの対処法について、具体的な手順や注意点を詳しく解説します。
敷金の返還を求める対処法の一つとして、内容証明郵便を送る方法があります。内容証明郵便は、いつ・だれが・どのような内容の文書を送ったか、郵便局が証明してくれるサービスです。借主と貸主の間で「言った言わない」のトラブルを防ぐ効果があります。
この文書は法的な証拠として残ることから、裁判に発展した場合にも活用することが可能です。弁護士など専門家を代理人として立て、その人の名義で送ることで、相手にプレッシャーを与えることもできるでしょう。
内容証明郵便はただ書けば良いというものではなく、細かなルールが存在します。たとえば1枚あたりの文字数制限があるほか、割り印の押印や文書の3通作成(相手用・自分用・郵便局保管用)が必要です。
法的な効力を発揮させるために、ルールをしっかり確認しましょう。場合によっては、弁護士など専門家の力を借りることもおすすめします。
内容証明郵便を送っても効果がなかった場合、敷金返還を求める次の対処法として少額訴訟があります。少額訴訟は60万円以下の金銭の支払いを求めるケースに限り利用できる、特別な訴訟手続きです。
原則として1回の審理で判決が下され、訴訟の途中で話し合いによる和解に至るケースもあります。弁護士を立てる必要がなく、訴訟費用も数万円と低コストです。
ただし少額訴訟にあたっては、証拠や証人を揃えておく必要があります。また、訴訟である以上、必ず勝てるとは限りません。
とはいえ、話し合いで解決が難しい場合において、少額訴訟は敷金を取り戻すための現実的な手段のひとつです。

入居時からの心がけによって、敷金が返ってくる確率を上げることができます。具体的な方法は、以下のとおりです。
それぞれの方法について、詳しく解説します。
敷金から差し引かれるのは、お部屋の修繕費です。ということは、キレイに使っていれば、修繕費を軽減でき、結果として敷金が多く返ってくることになります。
普段から家中を丁寧に掃除をすることは、お部屋をキレイに使ううえで重要です。特にキッチンは油汚れがたまりやすく、水回りはカビや水垢が大敵になります。長い間これらの掃除を怠ると、自分の力では落ちなくなってしまうおそれがあるため注意しましょう。
また、退去前に掃除することは、退去の立ち会いでキレイな印象を与えられます。面倒臭がらずしっかりと手間をかけると、効果的なアピールポイントになるでしょう。
入居期間が長いほど、経年変化による損耗が認められやすくなる可能性があります。実際のところ、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、建物や設備の経過年数が多いほど借主の負担割合を減少させる考え方を採用しています。
これにより、修繕費として敷金から差し引かれる額が少なくなる可能性があります。契約書の特記事項には注意しつつ、長期的な入居を前提として物件を選ぶことが、敷金を多く返してもらうポイントになります。
ただ、長く住む場合も、キレイに使うことは大前提です。故意や過失による損耗や通常の使用範囲を超える損耗は、修繕の負担を求められるため、丁寧な暮らしを心がけましょう。
敷金をめぐるトラブルを回避するために、退去時は必ず立ち会いましょう。退去時の立会いでは、貸主や管理会社が来て部屋の状況を確認します。
この場に立ち会うことで、双方の認識をすり合わせることができます。たとえば壁の汚れを指摘された際、入居時に撮っておいた写真を見せて「もともとあった汚れです」と主張することも可能です。直接話し合いをすることで、不当な修繕費を請求されるリスクは減るでしょう。
引越し前後は慌ただしく、立ち合いに時間を取るのが難しい方も少なくありません。しかし後々のトラブルを防ぐために必要なプロセスと認識して、時間を惜しまず参加することが重要です。
ここからは敷金が返ってきた人と返ってこなかった人の口コミを紹介します。
敷金が返還されるかどうかは、やはり綺麗に使っているかどうかが重要なポイントです。日頃からの清掃に加え、退去時の清掃に力を入れたほうが良いでしょう。
敷金が返還されず、泣き寝入りをしている人は少なくないようです。ハウスクリーニング料金が敷金から支払われているケースが多く、さらに追加で費用を請求されるケースも見受けられました。
敷金の返還される割合は、50%〜100%未満というケースが多いです。部屋が汚れていたり、退去時の修繕費負担に関する特記事項が盛り込まれていたりする場合は、注意が必要になります。
もし敷金の返金額に納得いかない場合は、内容証明郵便や少額訴訟といった対処法が有効です。しかし最も有効なのは、入居時から綺麗に住むことです。日頃のちょっとした心がけで、返ってくる敷金が大きく変わる可能性があります。
熊本市不動産売却クイック査定です。
0円物件とは、無償譲渡を前提として売り出されている物件です。日本では空家の増加が社会問題になっていますが、0円物件はその解決策としても注目されています。
しかし「安物買いの銭失い」ということわざにもあるように「一見お得に見える話には罠がありそう」と不安に感じる方も多いでしょう。
本記事では0円物件のデメリット・メリット、購入するときのポイントを解説します。「0円物件に興味があるけど踏み出せない」という方は必見です。

0円物件は無料で不動産を取得できることから、魅力的に見えます。一方で、以下のようなデメリットがあります。
それぞれのデメリットを見ていきましょう。
0円物件では、仲介会社が入らないことが多いです。そのため、売買契約や登記などの手続きを自分自身でおこなわないといけません。
仲介会社が入っていれば一連の手続きを専門的な立場からサポートしてくれるのですが、0円物件の場合はそうはいきません。そのため、初めて不動産取引をする方が0円物件を購入すると、いろいろと戸惑う場面が多いでしょう。
売買契約書に不備があり、後々トラブルにつながることも。登記手続きなどはミスがあると大変なので、司法書士など専門家に依頼したほうが安心です。
不動産を購入すると、以下の税金がかかります。
| 印紙税 | 売買契約書を交わすときにかかる |
|---|---|
| 登録免許税 | 不動産を登記するときにかかる |
| 不動産取得税 | 不動産の買主に課税される 課税時期は登記後4カ月~6カ月後 |
| 固定資産税・都市計画税 | 不動産の所有者に課税される 毎年4月~5月頃に納税通知書が届く |
これらの税金は、たとえ0円物件でも免除されません。他にも司法書士に登記手続きなどを依頼する場合は、司法書士報酬も発生します。
また0円物件は無償譲渡なので、贈与とみなされ贈与税が課される可能性もあります。贈与税は不動産の評価額によって決まるため、たとえ0円でも税金で赤字になることも。
0円物件は長年放置された空家であることが多く、築年数の経過によって老朽化が進んでいることも少なくありません。具体的には、雨漏りやシロアリ被害、配管の老朽化、断熱性能の欠如などが懸念されます。見た目はきれいでも、床下や屋根裏など目に見えない部分に深刻な劣化が潜んでいることもあるでしょう。
そのため、0円物件で快適に暮らすためには、大規模な修繕が必要になるケースが多いです。たとえば雨漏りやシロアリ被害が長年放置され被害が進行すると、修繕も広範囲に及びます。
リフォーム費用は数十万円から数百万円にのぼることもあり、結果的に「無料で手に入れたはずの家」が高額な出費を伴うことになります。DIYで対応しようとしても、専門的な知識や技術が必要な部分は業者に依頼せざるを得ません。
購入前に建物の状態をしっかり確認し、必要な修繕費用まで見積もっておくことが重要です。
0円物件のなかには、一般的な市場ではなかなか売れない「訳アリ物件」が含まれていることがあります。訳アリ物件とは何かしらの欠点や不具合を抱えている物件のことで、事故物件と呼ばれることも。
大きく分けると、心理的瑕疵物件・物理的瑕疵物件・法律的瑕疵物件・その他の瑕疵物件の4種類に分類されます。それぞれの具体例を挙げると以下のとおりです。
| 心理的瑕疵物件 | 他殺・自殺があった物件 |
|---|---|
| 孤独死が長く放置され特殊清掃をおこなった物件 | |
| 物理的瑕疵物件 | 床の傾き・雨漏り・シロアリ被害などがある物件 |
| 耐震性が低い物件 | |
| 法律的瑕疵物件 | 再建築不可物件 |
| 権利関係が複雑な物件 | |
| 環境的瑕疵物件 | 近隣トラブルを抱えた物件 |
| 騒音・臭気がひどい物件 |
訳アリ物件の多くは流動性が低く、価格を極端に下げないと買い手がつきません。売主が早く物件を手放したいために価格を下げ続けた結果、0円物件として売り出されることもあるのです。
表面上は魅力的な物件に見えても、実際に住んでみると精神的な負担や生活上の不便さを感じることもあります。また、訳アリ物件は売却したくてもなかなか売れないことが多いです。
また、売却しようとしても買い手が見つからず、資産価値がほとんどないというケースも。購入前には、物件の履歴や周辺環境、法的制限などをしっかり調査することが不可欠です。
0円物件を一度取得すると、たとえ住まなくなったとしても、簡単に手放すことはできません。そもそも0円物件は、買い手がつきにくいから0円で売られているケースがほとんどです。その物件を手放す際、買い手がなかなか見つからず、売却できない可能性は高いでしょう。
次の買い手が現れない限り、所有権の移転はできません。所有権が自分にある限り、固定資産税や都市計画税といった税金が毎年発生し、草刈りや建物の管理などの維持責任も伴います。たとえば、老朽化した建物が倒壊して通行人や近隣住民に被害を与えた場合、所有者が損害賠償責任を問われることも。
取得した建物は解体すれば所有権を放棄できますが、土地については所有権放棄が認められていないのが実情です。誰かに譲渡するか、自治体に寄付するなどの方法を取る必要があります。これには費用や手間がかかるため、結果的に「手放したくても手放せない負の資産」となってしまうリスクがあるのです。

0円物件はデメリットだけではありません。以下のような魅力的なメリットもあります。
それぞれのメリットについて解説します。
0円物件の最大の魅力は、なんといっても「購入費用がかからない」という点です。通常の不動産価格は数百万円から数千万円ですが、0円物件は無料で手に入るため、初期投資を抑えたい人にとっては大変魅力的です。
金融機関から住宅ローンを借りて、毎月返済する必要もありません。金利や返済のプレッシャーから解放されるのは大きなメリットです。特に、地方移住やセカンドハウスを検討している人にとっては、試験的に住んでみる拠点として活用しやすいでしょう。
また、事業用やアトリエ、倉庫など、住居以外の用途で活用することも可能です。もちろん、維持費や修繕費は別途かかりますが、「土地と建物を無料で手に入れられる」という事実は、他にはない大きな魅力といえるでしょう。
こちらは売主のメリットです。0円物件を売り出す側は諸費用がほとんどかからず、無料で物件を譲渡できます。
通常、不動産を売却する場合は、買主を探してもらうために仲介会社を媒介契約を結び、成約時には仲介手数料がかかることが多いです。仲介手数料の金額は売却価格によって変動するものの、数十万円〜数百万円程度のまとまった出費が発生します。
また、建物付きでは売れない場合、売主側で解体の費用を負担することも少なくありません。なかなか買主が見つからず値下げを続けた結果、かなり安くでしか売れず売却価格よりも仲介手数料や解体費用のほうが多くなり、最終的に赤字に陥るケースも。
一方で0円物件は自治体やマッチングサイトを活用し、仲介会社を通さずに仲介手数料を軽減する仕組みがあります。基本的に建物も残した状態で譲渡できるため、解体費用もかかりません。
なかなか買い手がつかない不動産を所有している方にとっては、金銭的な負担がなく譲渡できる点が大きなメリットです。
0円物件を購入・活用することで、空き家問題の解決に貢献することが可能です。日本では空き家の増加が深刻な社会問題となっています。総務省「令和5年住宅・土地統計調査」によると、空家数は900万戸と過去最多を記録し、2018年からわずか5年で51万戸も増加している状況です。特に地方では人口減少により放置された住宅が目立ちます。
放置された空き家は、防犯上のリスクや景観の悪化、倒壊の危険など、地域にとってさまざまなマイナスの影響を及ぼします。新たな所有者が現れ、修繕や活用を進めることで、地域の安全性や美観が向上し、ひいては地域活性化にもつながります。
また、移住者や若者が空き家を活用して新たな生活を始めることで、地域コミュニティに新しい風を吹き込むことも期待されます。単なる「無料の家」ではなく、社会的な意義を持つ選択肢として、0円物件は注目されています。
0円物件を取得し、リフォームや移住を検討する際には、自治体が提供する補助金制度を活用できる可能性があります。こうした補助金を活用することで、修繕やリフォームの費用に充てることもできるでしょう。
多くの自治体では、空き家の利活用を促進するために、改修費用の一部を補助する制度や、移住者向けの支援金、子育て世帯への住宅取得支援など、さまざまな支援策を用意しています。
補助金を活用することで、0円物件の「安かろう悪かろう」というイメージを払拭し、安心して住める住環境を整えることが可能になります。取得前に自治体の制度をしっかり調べ、条件を満たすように計画を立てることが、賢い活用の第一歩です。

0円物件でも、不動産を購入するからには絶対に後悔はしたくないですよね。納得のいく物件を購入するためのポイントは、以下のとおりです。
それぞれのポイントを詳しく解説します。
専門家に相談することで、リスクや手続きの不安を軽減できます。0円物件を購入する際は税金や修繕費など隠れたコストが発生する可能性があり、素人判断ではリスクを見落としがちです。
不安がある場合は、宅地建物取引士や司法書士など不動産のプロに相談したほうが良いでしょう。契約書の不備や登記手続きの漏れなど、トラブルの原因を未然に排除できます。とくに0円物件は通常の売買とは違い、贈与とみなされる場合もあるため、税務面の確認は欠かせません。
専門家に手続きを委任すると司法書士報酬などの費用がかかりますが、早めに連携しておいたほうが後々のトラブルを減らせます。プロの力を借りて、起こりうるリスクを冷静に見極めましょう。
0円物件は無償で取得できるものの、リフォームや耐震補強など想像以上に出費がかさむケースがあります。そこで活用したいのが、自治体の補助金制度です。
補助金をもらうことで、取得後のリフォームなど、費用負担を軽減できる可能性があります。
利用できる補助金制度は自治体によって異なります。自治体のホームページや、補助金ポータルサイトを見れば、事前にどのような制度があるか調べられます。利用できそうなものがあれば、担当窓口に細かい利用条件を聞いておきましょう。
0円物件にこだわらず、他の選択肢も比較検討することが大切です。0円物件は立地が不便だったり高額な修繕費がかかったりして、自分に最適な物件が見つからない場合もあります。
そのため同じエリアの中古住宅など、0円物件以外の安価な物件も視野に入れて検討することが大切です。他の物件と比較検討することで、自分が家選びで大切にしたいことが見えてきます。
また、物件価格だけでなく修繕費などトータルで考えると、他の物件のほうがお得な場合もあるでしょう。たとえば数十万円で購入できる物件でも、管理状態が良好で修繕費を抑えられる場合は、結果的にコストパフォーマンスが高くなることも。
維持管理のしやすさや、将来の活用可能性など他の視点も含めて総合的に判断するのがおすすめです。
ホームインスペクションは専門家が建物の構造や設備などの劣化状況を確認し、修繕が必要な箇所や費用の目安を提示してくれるサービスです。0円物件は築年数が古く長期間放置されていた家が多いため、ホームインスペクションが重要な役割を果たします。
特にシロアリ被害や雨漏りなどは素人では見抜きにくいため、専門家の目でチェックしてもらうことが安心につながるでしょう。購入後に「こんなに修繕費がかかるとは思わなかった」と後悔するリスクを大幅に減らすことができます。
ホームインスペクションの料金は、数万円程度の費用が発生します。しかし長期的な視点で見れば、価値のある投資といえるでしょう。

実際に0円物件を購入した人の体験談や口コミを参考にすることで、リアルなメリット・デメリットがわかります。ここからは0円物件を検討している人や買った人の口コミを紹介します。
これから人口が減って、空き家がどんどん増えるのは間違いなさそうですよね。だから、若いうちは賃貸で自由に暮らして、年齢を重ねてから0円物件とか、安めの中古住宅を買うっていうスタイルが、コスパ的には一番いい気がします。
奥多摩エリアでは、0円物件の提供に加えてリフォーム補助金が出る制度もあるみたいです。もともとは町に寄付された空家で、人を呼び込みたい思いからこうした制度を作ったようです。
“0円物件”という言葉だけを見ると、誰でもただ同然で家が手に入ると思ってしまいがちですが、正直に言うと、初心者の方にはおすすめできません。実際、私自身も3万円ほどで戸建てを購入したことがありますが、想像以上に大変でした。DIY必須・強メンタル必須・リフォーム箇所の判断必須。5万〜10万円程度で購入できる物件は、初心者の99%が扱いきれないと感じています。
昨日、0円物件の情報サイトを見てみたのですが、全体的に築年数の古い物件が多く、フルリフォームが前提になっているような印象を受けました。DIYにかなり慣れている方でないと、なかなか手が出せないレベルかもしれません。価格が安い物件にはそれなりの理由があるので気を付けなければ。
0円物件は築古でフルリフォーム必須のケースが多く、DIYや判断力が求められるため、初心者にはハードルが高めです。一方で地域によっては補助金制度もあるため、賢く活用できれば0円物件も検討の価値があります。
0円物件は無料で購入できる物件ですが、税金やリフォーム費用が別途かかる点に注意しなければなりません。一方で不動産価格が高騰するなか、物件価格がかからない点は大きなメリットです。購入する際は、安いからといって1人で判断せず、不動産のプロに相談してみましょう。補助金やホームインスペクションについても検討することで、後悔のない選択ができます。
熊本市不動産売却クイック査定です。
これまで家賃の支払いと言えば、振込や口座引落しが一般的でした。しかし、キャッシュレス決済の普及に伴い、現金や財布を持たない人が増え、家賃もクレジットカードで支払いたいと考える人が増えています。そのため、クレジットカード対応物件が首都圏を中心に増加しています。
クレジットカード払いには、さまざまなメリットがあります。一方でデメリットもあるため、メリット・デメリットの両方を理解しておくことが大切です。そこで今回は、家賃はクレジットカードで支払うことができるのか、クレジットカード支払いのメリット・デメリットなどについて詳しく解説します。

毎月口座から引き落としされる家賃。「ポイントがつくし、クレジットカード払いにしたい」と考えた方も多いのではないでしょうか。家賃をクレジットカードに変更する場合、まずは大家さんや管理会社に交渉する必要があります。では、実際に家賃をクレジットカードで払う交渉は可能なのでしょうか。
結論からお伝えすると、クレジットカード払いの交渉は断られる可能性のほうが高いです。というのも、クレジットカード対応にするためには、決済代行会社の選定、システム設計、個人情報の管理などやるべきことが多く、さらにコストがかかります。
入居者一人のために、クレジットカード対応にするには、業務負担やコストなどのリスクが大きいため、一般的には断られる可能性のほうが高いでしょう。
クレジットカード払いは断られる可能性が高いとお伝えしましたが、具体的な理由は以下の通りです。
家賃をクレジットカード払いにすると、大家さんはクレジットカード会社に手数料を支払わなくてはなりません。一般的には、カードの使用ごとに2%~5%の手数料が取られるため、取引が増えるほどコストも増えます。大手の管理会社であれば、手数料や業務の手間はさほど問題ないかもしれません。しかし、小さな管理会社や大家さんが直接管理する物件はコストがかかるため対応できないというのが実情です。
クレジットカードの支払いは、口座引落に比べて入金確認が遅くなります。これは、入居者から引き落としをして、管理会社に着金するまでに時間がかかるためです。大家さんの中には、投資用ローンやアパートローンを組んで賃貸経営している方も多く、大家さん側にもローンの返済期日があります。そのため、入金が遅くなることを懸念する大家さんも少なくありません。
家賃をクレジットカード払いにすると、入居者と不動産会社の間にクレジットカード会社が入るため、家賃収入に関する会計処理が複雑になります。さらに、クレジットカードは翌月払いが多いため、口座引落のようにシンプルな会計処理がしにくくなります。小さなお店や商店街でクレジットカードを使用できない店がありますが、これは会計処理の問題やコストがかかるためです。

ここまで、クレジットカード払いできない理由についてお伝えしましたが、家賃をクレジットカードで支払うこともできます。ここでは、クレジットカード払いにする2つの方法を紹介します。
順番に見ていきましょう。
クレジットカード払いにこだわるのであれば、あらかじめクレジットカード対応物件に絞って物件探しをしましょう。大手のポータルサイトであれば、物件検索画面で「クレジットカード対応可」の検索が可能です。また、クレジットカード払いに対応する物件の特集などが設けられているケースもあります。
ただし、通常の物件と比較すると、物件数が少ないため選択肢が狭まるというデメリットがあります。希望条件の物件が見つかれば毎月クレジットカードで家賃を支払うことができるため、根気強く探してみましょう。
クレジットカードで支払うためには、家賃決済サービスを使うのも有効な手段です。家賃決済サービスは、入居者と不動産会社の間に入って決済をしてくれる仕組みのこと。つまり、不動産会社がクレジットカード未対応でも、家賃をクレジットカード払いにすることができます。
ただし、家賃決済サービスを利用すると入居者が手数料を負担しなくてはなりません。とはいえ、クレジットカードで支払うことでポイントやマイルが貯まるため、利用するメリットも大きいでしょう。

家賃の支払い方法は、物件や管理会社によって異なります。ここでは、「クレジットカード以外」の支払い方法を確認していきましょう。
支払い方法と共に、それぞれのメリット・デメリットを解説します。
自動引落しは、支払いを忘れたり、金額を間違えたりするトラブルを防ぐことができます。ただし、口座残高が不足していると引き落としができなくなり、口座振込となる場合があります。口座振替になると手数料は入居者負担となるため注意が必要です。
口座振込は、不動産会社が指定する期日までに振込する方法です。ネットバンキングを利用すれば手数料を抑えながら、24時間いつでも手軽に振込できます。ただし、振込の度に手数料がかかるため、この点はデメリットとなるでしょう。
コンビニ支払いは、払込票明が自宅に届きます。それを持ってコンビニのレジで掲示すれば家賃を支払うことができます。ただし、多くの場合支払い方法は現金のみであるため、手元に現金を用意しておく必要があります。また、振込期日が過ぎた場合や払込票を紛失すると支払いできないケースがあるため、払込票の管理には注意が必要です。
大家さんが同じ建物内に住んでいる場合や、管理会社が近い場合は、家賃を現金手渡しで対応できる物件もあります。毎月大家さんとコミュニケーションが図れるため、設備の故障を相談したり、家賃交渉したりしやすくなるでしょう。ただし、同じ建物内に住んでいても自動引落しや口座振込を希望する大家さんも多く、現金で持参するのは歓迎されない物件も多いです。また、人付き合いが苦手な方や忙しい方にとっては、ストレスの原因になるかもしれません。

クレジットカード払いにはどのようなメリットがあるのか確認していきましょう。
項目ごとに詳しく解説します。
1つ目のメリットは、ポイントがたまることです。クレジットカードのポイントは、利用金額に応じてポイントが還元されます。家賃は支出の大部分を占めるため、より多くのポイントを貯めることができるでしょう。ただし、物件の中には「ポイント加算対象外」となっている物件があるため注意が必要です。こうした情報は物件サイトには掲載されていないため、不動産会社や管理会社に事前確認が必要です。
2つ目のメリットは、振込の手間が省けることです。家賃を毎月銀行振込で支払っていた方は、クレジットカード払いにすることで振込の手間を省くことができます。また、振込の場合は手間だけでなく手数料もかかります。振込手数料は金融機関によって異なりますが、10万円以上の振込は手数料が高額になる傾向です。一回の金額は小さくても、何年も支払い続ければ、数千円~数万円になることもあります。クレジットカード払いにすることで手数料が節約できる点は大きなメリットとなるでしょう。
3つ目のメリットは、毎月の支出が管理しやすいことです。水道や光熱費など、公共料金をクレジットカード払いにしている方も多いでしょう。これらに加えて、家賃もクレジットカード払いにすれば支出が可視化でき、家計管理がしやすくなります。おすすめはクレジットカードを家計簿アプリと連携させること。簡単に家計簿が作成できるため、余計な出費を抑え、日々の節約に役立つでしょう。
4つ目のメリットは、支払いのタイミングが明確であることです。クレジットカード払いは、基本的にカード会社が一時的に立て替える後払いシステムです。したがって、支払日に残高が不足していても支払いが行われます。また、クレジットカード払い対応の物件は、初期費用もクレジットカードで支払いできることがあります。初期費用は、敷金・礼金、仲介手数料、前家賃など、まとまった資金が必要です。
しかし、入居までにこれらの資金を現金で準備できない方もいるでしょう。そういった場合でも、クレジットカード払いなら後払いが可能となるため、余裕を持って資金を準備することができます。

次は、クレジットカード払いのデメリットについて解説します。
メリットとデメリットを把握して、ご自身に合った選択をしましょう。
1つ目のデメリットは、家賃が高くなる可能性があることです。前述した通り、クレジットカードは手数料がかかります。そのため、不動産会社も手数料を考慮した上で家賃設定をします。そのため、同じエリアにある類似物件と比較して、家賃は高めに設定されているケースが多いです。
2つ目のデメリットは、クレジットカードによって対応できない場合があることです。クレジットカード対応可能物件でも、使用できるクレジットカードに制限があるケースもあります。たとえば、VISA、JCBは使用可でも、AMEXは使用不可など、物件によってさまざまです。したがって、入居前には必ず不動産会社に確認しておくことをおすすめします。
3つ目のデメリットは、限度額を高めに設定する必要があることです。限度額を上げると紛失した際に限度額まで使用される恐れがあり、限度額を上げたくないと思う方もいるかもしれません。しかし、光熱費や通信費、食費などの支払いに家賃が加わると、カードの限度額に達してしまいカードが使用できなくなる可能性があります。したがって、クレジットカード対応物件に入居したら、なるべく早めに限度額を変更しましょう。
4つ目のデメリットは、支払いが遅れると信用情報に傷がつくということです。クレジットカードの信用情報は、個人の信用力を評価する重要なデータです。信用情報機関に登録されたデータは、今後新たにクレジットカードを作成する時や、ローン会社の審査の際に参照されます。たとえば、クレジットカードの支払いを何度か滞納したとしましょう。数年後、結婚のタイミングで住宅購入を決めました。
ところが、独身時代にクレジットカードの支払いを滞納してしまったため、住宅ローンが借りられなかったというケースがあります。なお、自動引落しや口座振込の場合は、基本的に信用情報に傷がつくことはありません。したがって、ご自身の状況をよく理解した上で、支払い方法を選択しましょう。
家賃をクレジットカードで支払うことは可能です。ただし、既に入居している物件で、支払い方法を変更することは断られる可能性が高いでしょう。なぜなら、クレジットカード払いにすると、管理者側のコストや業務負担が増えるためです。クレジットカード払いにこだわる方は、入居前にクレジットカード払いに対応している物件を選ぶことをおすすめします。なお、クレジットカード払いには、ポイントがたまる、振込の手間が省ける、支出が管理しやすいなどのメリットがあります。
一方、家賃が高くなる可能性がある、クレジットカードによっては対応不可、限度額を高めに設定する必要がある、支払いが遅れると信用情報に傷がつくなどのデメリットがあるため注意が必要です。メリット・デメリットの重要性は人によって異なります。そのため、ご自身のライフスタイルや優先順位に合わせて物件選びをすることが大切です。
熊本市不動産売却クイック査定です。
多くの人が憧れるタワーマンションですが、必ずしも理想の住まいとは限りません。実際に「新築タワーマンション」と検索すると、「人生最悪の買い物です」といったネガティブなキーワードが候補に出てくることもあります。
本記事では新築タワーマンションのメリット・デメリットと後悔しないための購入ポイントを解説します。タワーマンションに興味がある方は、購入前にぜひチェックしてください。

なぜ「新築タワーマンションは人生最悪の買い物」と言われているのでしょうか?その理由と考えられるのは、以下のデメリットです。
それぞれのデメリットについて詳しく見ていきましょう。
タワーマンションは住戸数に対して駐車場の数が不足しているケースが多く見られます。特に都市部では土地の制約もあり、全住戸分の駐車スペースを確保するのが難しいのが現状です。
既に満車の場合は、近隣の月極駐車場を探す必要があります。しかしタワーマンションの立地は人気エリアであることが多く、周辺の駐車場も高額かつ空きが少ない傾向です。
結果として車を所有していても駐車できず、泣く泣く手放すことになるケースも。車を日常的に使う方にとっては見逃せないデメリットです。
ネットショッピングが普及した今、宅配サービスの利用頻度は年々増加しています。インターネットで購入した商品を届けてもらうため、頻繁に宅配サービスを利用している方は多いでしょう。しかし、タワーマンションに住んでいると、配達に時間がかかるのが難点です。
タワーマンションは面積が広く、階数も高いです。宅配業者がインターホンを押してからお部屋に届けるまでに、長い廊下やエレベーターを通らなければなりません。
また、同じマンションに住んでいる人の荷物が複数ある場合は、1軒ずつ順番に配達されます。そうなれば余計に配達時間がかかるでしょう。
最近では宅配ボックスを備えたマンションも増えてきていますが、大型荷物や冷蔵品は対応できないことも。また、宅配ボックスを利用しても自分で運ぶ手間がかかるため、重い荷物やまとめ買いをされる方は不便に感じる場面が多いでしょう。
小さな子供がいるご家庭にとって、近くに遊び場があるかどうかは重要なポイントですよね。しかし、タワーマンションは敷地の多くを建物や駐車場、共用施設に充てているため、子供用の遊具や広場が設けられていないことがあります。
近くに遊び場がないと、子供は外で遊ぶ機会が減り、ストレスがたまってしまうことも。家の中で遊んだり、遠くの公園まで付き添ったり、いろいろ工夫が必要になります。
「タワーマンションは日当たりが良さそうだから、洗濯物がよく乾きそう」と感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし実際は、外干しが禁止されているマンションも多く存在します。こういったルールは、強風による落下物の危険性や景観維持の観点から定められているものです。
特に布団やシーツなどの大きな洗濯物は干せないケースが多く、部屋干しや乾燥機の使用が前提となります。湿気の多い季節には生乾き臭の悩みも増え、洗濯環境に不満を感じる方も少なくありません。
住戸数に応じてエレベーターが設置されていますが、通勤時間帯は混雑が予想されます。タワーマンションは階数が多いので、どうしても輸送に時間がかかります。
ようやく来たと思ったら、満員で乗れないことも。一度見送ると、次のエレベーターが来るまでしばらく待たなければなりません。朝は一刻一秒を争うので、ストレスを感じる方も多いでしょう。
最近では待ち時間を短縮できるよう制御されたエレベーターも増えていますが、混雑を完全に解消するのは難しいのが現実です。低層階であれば階段を使う選択肢もありますが、高層階ではそうはいきません。
高層階は眺望が良い反面、風の影響を強く受けやすいというデメリットもあります。特に冬場は地上よりも体感温度が低く、ベランダに出るのも億劫になるほどの強風が吹くことも。
洗濯物や植物をベランダに置く場合も、風で飛ばされないよう注意が必要です。また、窓を開けたときに強風が吹き抜けてドアがバタンと閉まることもあります。このように日常生活にも影響をおよぼすため、風対策をしっかり考えなければなりません。
タワーマンションはその高さゆえに、地震の際に揺れを大きく感じやすい構造です。
建物自体は耐震・制震・免震といった技術で安全性が確保されています。しかし高層階では長周期地震動による「ゆっくり大きく揺れる」現象が発生しやすく、恐怖を感じる人も少なくありません。
家具の転倒防止対策や避難経路の確認など、日頃からの備えが重要です。安心して暮らすためには、建物の構造だけでなく、自分自身の防災意識も問われます。
災害時にエレベーターが停止すると、タワーマンションでは階段での移動が唯一の手段になります。
たとえば避難するとき、階段に住民が押し寄せてくる可能性があります。パニック状態に陥っていると、将棋倒しになったり避難が遅れたりして危険です。
また、災害発生後は水や食料など物資の支給があります。それらを運ぶのに階段を何段も上り下りしなければなりません。
飲用・食事用として1日1人当たり3Lが必要になるため、家族でお住まいの方は相当な重量を運ぶ必要があります。私の知り合いは東日本大震災のときにタワーマンションに住んでいて、水や食料の運搬に大変苦労していました。
タワーマンションへの引っ越しは、通常の集合住宅に比べて手間もコストもかかります。エレベーターの使用時間を事前に予約する必要があったり、荷物の搬入経路が長くなったりと、作業員の負担が大きくなるためです。
特に高層階への引っ越しは、荷物の運搬に時間がかかるため、作業時間も長引きます。
近年ではドライバー不足が深刻化しており、タワマンに関わらず引越し費用全体が高騰しています。引越し費用を抑えたい場合は、荷物の削減や繁忙期を避けるなどの対策が欠かせません。
タワーマンションは共用施設や設備が充実している分、管理費や修繕積立金といった維持費も高額になりやすいです。
管理費は、管理員の人件費や清掃費、設備の保守点検費用などが含まれています。修繕積立金は10〜15年に1度くらいの頻度で実施される大規模修繕に向けて貯めている資金です。これらの費用は毎月発生するため、家計への影響も大きくなります。
国土交通省は令和5年度マンション総合調査の結果として、管理費と修繕積立金の平均を以下のとおり公表しています。
| 形態 | 管理費総収入/月/戸あたり | 修繕積立金総収入/月/戸当たり |
|---|---|---|
| 20階建以上 | 24,585円 | 13,834円 |
| 11~19階以上 | 16,597円 | 12,626円 |
| 6~10階以上 | 16,944円 | 13,637円 |
| 4~5階以下 | 17,529円 | 13,864円 |
| 3階以下 | 20,112円 | 14,231円 |
| 平均 | 17,214円 | 13,300円 |
出典:国土交通省「令和5年度マンション総合調査・管理組合向け調査の結果」(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001750163.pdf)
このデータを見ると、20階建て以上のタワーマンションの管理費は最も高く、平均を大幅に上回っていることがわかります。修繕積立金については3〜5階の低層マンションと比べれば安いものの、平均よりは高い水準です。
新築時は修繕積立金を安く設定して売り出されることも少なくありません。将来的に修繕積立金が足りなくなったり、滞納者が増えて適切な修繕ができなくなったりする恐れもあります。

新築タワーマンションはデメリットばかりではありません。以下のようなメリットもあります。
それぞれのメリットについて詳しく解説します。
タワーマンションに住むことは、ひとつの「ステータス」として捉えられることがあります。ホテルのようなエントランスや高層階からの眺望など、豪華な見た目が住む人の印象を引き上げてくれるでしょう。
日頃の満足度が高いことはもちろん、来客時には「ここに住んでいるんだ」と誇れる空間です。特に都市部では、タワーマンションに住んでいること自体が一種のブランドとして認識されることもあります。
駅近や都心部など利便性の高いエリアに建てられることが多いため、通勤・通学・買い物などであらゆるシーンで便利さを感じやすいです。再開発で商業施設と一体開発された物件では、生活に必要なものが徒歩圏内で揃います。
交通アクセスの良さは、将来的な売却や賃貸を考えたときも有利に働くでしょう。共働き世帯が増え仕事や家事に追われるなか、時間を節約できる好立地の物件は安定した需要があります。
タワーマンションの高層階は、眺望の良さが魅力です。視界を遮るものがなく、遠くの山々や街並み、美しい夜景を臨めます。立地によっては、花火大会を特等席で楽しめる物件もあるでしょう。
わざわざ外に出かけなくても、自宅で十分贅沢な時間が手に入ります。開放感を求める方や景色を重視する方にとって、タワーマンションの高層階は理想的な住まいです。
高層階は地上から距離が離れているため、騒音が届きにくい環境です。車の走行音や人の話し声を気にせず、静かな環境で暮らすことができます。
幹線道路沿いや繁華街は騒音が懸念されることが多いですが、タワーマンションの高層階であれば影響を最小限に抑えられるでしょう。
静かな空間は、在宅ワークやリラックスタイムにも最適です。都心部の利便性を享受しながら、落ち着いた暮らしを実現できます。
蚊やゴキブリなどの虫が侵入しにくい点も、高層階のメリットです。虫は地面に近い場所に多く生息しています。一般的に10階以上になると、虫の数は減少するといわれています。
夏場は網戸を開ける機会も増えますが、虫の侵入を心配せずに済みます。虫が苦手な方や小さなお子さんがいるご家庭も、安心して暮らせるでしょう。
タワーマンションの多くは、最新の設備や豪華な共用施設を備えています。たとえばフィットネスジムやラウンジ、ゲストルーム、キッズルームなどを備えたタワーマンションがあります。
住戸内には床暖房や浴室乾燥機、ディスポーザーなど高性能な設備が勢ぞろい。日々の暮らしを快適にしてくれるでしょう。利便性と快適性を両立した住まいを求める方にとって、タワーマンションは最適な選択肢です。
立地や設備が充実している物件は、資産価値が高く評価される傾向です。特に駅近や人気エリアにある物件は、将来にわたり長く安定した需要が見込まれます。
耐久性に優れている物件も多く、築年数が経過しても適切にメンテナンスしていれば資産価値が落ちにくいでしょう。もし将来自分が住まなくなったときも、売却や賃貸に出して住み替えられます。
厳重なセキュリティ設備が整っており、不審者の侵入を防いでくれます。近年は強盗事件も相次いでいるため、安全に暮らせるのは大きなメリットです。
セキュリティ設備は、多重のオートロックや防犯カメラなどがあります。管理員が24時間体制で見守る、有人セキュリティを採用しているタワーマンションも多いです。
エレベーターにセキュリティキーが必要なタイプもあり、居住者以外が自由に出入りできない仕組みになっています。特に女性の一人暮らしや小さなお子さんがいる家庭にとっては、大きな安心材料です。
タワーマンションの中には、ホテルのようなコンシェルジュサービスを提供している物件もあります。クリーニングの取次ぎや宅配便の受け取り、タクシーの手配など、日常のちょっとした手間を代行してくれる存在です。
高級感のあるサービスは、生活の質をワンランク上げてくれるでしょう。忙しい方にとっては非常に便利なサービスです。

新築タワーマンションを購入する方は、後悔しないよう以下のポイントを意識して物件を選びましょう。
それぞれのポイントについて、詳しく解説します。
将来的な資産価値を見据えて、価値が落ちにくい立地を選ぶことが重要です。タワーマンションに限らず、不動産の価値は立地でほぼ決まるといっても過言ではありません。
立地が良ければ生活の利便性が向上するだけなく、底堅い需要によって資産価値の大幅低下も防げます。人気のエリアに属していて、駅から近い物件を選びましょう。
万が一住み替えが必要になった場合でも、売却や賃貸に出しやすく、資産としての柔軟性が保たれます。購入時には住みたい場所だけでなく、売りやすい場所かどうか意識して選びましょう。
物件の住み心地はパンフレットやモデルルームだけでは判断できません。自分の目でリアルな住み心地を確認するために、内見には必ず行きましょう。内見では不動産会社の担当者に同行してもらい、実際の空間を見せてもらえます。
内見では住戸内に目がいきがちですが、共用部や周辺環境もチェックすることがポイントです。内見では見るべきポイントを挙げると、以下のとおりです。
| 住戸内 | 日当たり・眺望を遮るものはないか 騒音を感じないか(外や近隣住戸からの音の聞こえ方) 収納スペースは足りるか |
|---|---|
| 住戸内 | 共用部 共用部は清潔に保たれているか エレベーターの待ち時間はどれくらいか ゴミ出しルールはどうなっているか 住民間のトラブルは発生していないか |
| 住戸内 | 周辺環境 駅からの道のりを歩いて確認する(距離や治安) 近くに買い物施設はあるか 子供がいる場合は通学路の距離や治安 |
内見は入居後の暮らしを想像する貴重な機会です。後悔しないように丁寧におこないましょう。
タワーマンションの共用施設にどんなものがあるか確認することも重要です。フィットネスジム、ラウンジ、ゲストルーム、キッズルーム、パーティールームなど、まるでホテルのような設備が整っている物件もあります。
共用施設が多い物件は一見魅力的に見えますが、維持費がかさむ点に注意しなければなりません。自分や家族が実際に使うかどうかを冷静に見極める必要があります。
たとえばフィットネスジムやプールは使わないという方もいるでしょう。「使わない施設が多い=無駄な出費」とならないよう注意しなければなりません。
また、施設の利用ルールや予約方法、利用時間なども事前に確認しておくと、入居後のトラブルを防げます。見た目の豪華さに惑わされず、実用性とコストのバランスを意識して選びましょう。
理想の住まいを見つけるためには、複数の物件を比較することが肝心です。1件だけを見て即決してしまうと、他の選択肢と比較できず、後悔する可能性があります。
最低でも3件以上のタワーマンションを内見し、それぞれの立地、間取り、設備、管理体制、価格帯などを比較検討しましょう。比較することで、相場感や自分の優先順位が明確になり、「本当に自分に合った物件」が見えてきます。
時間と労力はかかりますが、納得のいく選択をするためには欠かせないプロセスです。
不動産のプロである営業担当者に、いろいろ相談してみるのもおすすめです。インターネットや資料だけではわからない情報を得ることができます。
たとえば、過去の販売状況や住民の傾向、管理組合の運営状況、将来的な修繕計画など、購入後の生活に関わる重要な情報を教えてもらえることがあります。
複数の物件を扱っている不動産会社であれば、特定の物件に偏らない中立的なアドバイスを受けやすくなります。信頼できるプロの意見を参考にしながら、自分の判断軸を持って選ぶことが大切です。
新築タワーマンションが「人生最悪の買い物です」と言われる背景には、そのスケールの大きさゆえに生じる災害時の不便さや、引越し・宅配にかかる手間とコストの高さなどが挙げられます。
一方で、充実した共用施設や最新の設備など、タワーマンションならではの魅力も確かに存在します。 メリットを最大限に活かすためには、立地条件の見極めや、内見を通じた実際の住み心地の確認が欠かせません。
「憧れ」だけで選ばず、冷静な視点で判断することが、後悔しない住まい選びへの第一歩です。
熊本市不動産売却クイック査定です。
これから賃貸契約をする予定の方は、入居審査に通るかどうかが気になるポイントではないでしょうか。
本記事では賃貸契約の入居審査に落ちる確率やその原因、通過するための方法を解説します。これから賃貸契約の入居審査を受ける予定の方は、ぜひ本記事の内容を参考にしてください。

入居審査に落ちる方は、1割〜2割程度と言われています。数字だけ見ると、通る方のほうが圧倒的多数派で、落ちる方は少数派です。
とはいえ、落ちてしまう方が一定数いることは事実です。しかも落ちた理由が開示されることはほとんどありません。同じ状態のまま次の物件に申し込んでも、審査落ちを繰り返す可能性が高くなります。
たとえ理由を開示されなくても、自分でなぜダメだったのか分析し、次に向けた対策をすることが重要です。次の項目からは、入居審査で落ちてしまう主な原因について詳しく解説します。

入居審査で落ちてしまった場合、何らかの原因があるはずです。考えられる主な原因としては、以下のとおりです。
それぞれの原因について詳しく見ていきましょう。
入居審査において、特に重視されるポイントが年収です。年収が少なく毎月の家賃を支払うのが難しそうな方は、審査に通らない可能性があります。
審査に通過しやすくするには、自分の収入に見合った家賃の物件に申し込むことがポイントです。目安としては、月収の3分の1以内に収まる家賃の物件を選ぶと良いでしょう。
また、定職に就いていない方は、安定した収入が見込めないと判断され、審査のハードルが上がる傾向があります。
信用情報に問題があると「家賃の滞納リスクがある」と判断され、入居審査で不利になることがあります。
「ブラックリスト」という言葉を聞いたことがありませんか。信用情報機関に返済遅延や自己破産などネガティブな情報が登録されている状態をブラックリストといいます。契約者本人がブラックリストに載っている場合は、信用が疑われ入居審査に影響する可能性が高いです。
過去にクレジットカードやローンなどを滞納した経験がある方は要注意です。登録された情報は5〜10年程度で削除されますが、それまでは影響が残る可能性があります。
一部の物件では賃貸契約を結ぶにあたり、連帯保証人が必要とされます。連帯保証人は、もし契約者が家賃を支払えなくなったとき、支払いを肩代わりする人です。
そのため連帯保証人を用意できない、あるいは支払い能力に問題ありと判断されると、審査に通るのが難しくなります。連帯保証人は信用力のある方に依頼するのが望ましいでしょう。
もし連帯保証人を頼めそうな人がいない場合は、保証人不要の物件を選ぶことで審査落ちを回避できる可能性があります。保証人不要の物件は意外と多く、代わりに保証会社と契約することで、家賃滞納のリスクヘッジをしています。
書類の不備が、入居審査に悪影響をおよぼすこともあります。
必要書類が不足していたり、記入内容に誤りがあったりすると、正確な審査ができません。また、収入や勤務先などに関して虚偽の申告をしてしまうと、信頼そのものを失います。
意図せぬ記入ミスが、虚偽の申告とみなされることも。必要書類を提出する前に、抜け漏れや誤りがないか慎重に確認しましょう。
家賃滞納や契約違反など過去のトラブルが発覚し、入居させてもらえないこともあります。「また同じトラブルを繰り返すのではないか」と懸念されるためです。
トラブル履歴を調べるために、オーナーや管理会社が、現在住んでいる物件の管理会社にヒアリングをおこなうケースもあります。
また、職業や外国籍であることを理由に入居を断られてしまう場合もあります。たとえば夜職の方は収入が安定しづらく、家賃滞納リスクが高いとみなされることが多いです。外国籍の方も、文化の違いや言葉の壁によるトラブルが懸念され、入居できないことがあります。

審査の通過率を上げるための対処法として、以下のような方法が挙げられます。
賃貸の入居審査で重要な判断材料になる信用情報は、本人が事前に確認・把握できるものです。CICやJICC、KSCなどの信用情報機関を通じて、インターネットや郵送で自分の信用情報を取得できます。
万が一、誤った情報が登録されていた場合は、訂正依頼をすることも可能です。ブラックリストに登録されている情報が事実の場合は、保証会社の利用や物件選びでリスク軽減対策をとることをおすすめします。
入居審査では「月収が家賃に見合っているか」が審査されます。目安としては、家賃が月収の3分の1以下であることが望ましいとされています。たとえば手取り月収が18万円であれば、家賃は6万円以下の物件を選ぶのが無難です。
月収の3分の1を超える水準になると、家賃負担が生活費に食い込むリスクが高まり、審査でマイナス評価を受ける可能性があります。
収入を証明する書類として、住民税課税証明書や源泉徴収票などを準備しておくと良いでしょう。特にフリーランスや非正規雇用の方の場合、収入が変動しやすいため、長期間の収入がわかる書類をそろえておくことが重要です。
また、預貯金額や副収入がある場合は、それもアピール材料になります。審査前には自分の収入と支出のバランスを見直し、「この家賃なら無理なく払える」という根拠を用意しておくことが、審査通過につながります。
最近では保証会社の利用が必須となっている物件が増えています。保証会社とは、入居者が万一家賃を滞納した場合に、代わりに家賃を立て替えてくれる機関です。
オーナーや管理会社にとっては、家賃滞納リスクを軽減できる仕組みです。保証会社を利用することで、入居審査のハードルが下がることもあります。
特に、親族に連帯保証人を頼みにくい方や、信用情報に不安のある方にとっては、保証会社は有効な選択肢になります。ただし、利用にあたっては初回保証料(家賃の30〜100%程度)がかかるほか、月額保証料や更新保証料も発生するため、費用面の確認は欠かせません。
入居審査に通るかどうか不安な要素がある場合は、物件を探す前に不動産会社に相談するのがおすすめです。たとえば、年収が少なかったり非正規雇用だったり、審査に影響しそうな情報は伝えておきましょう。
不動産会社は多くの顧客に物件を紹介してきた経験があります。プロの視点でアドバイスをもらうことで、通過しやすい物件や保証会社の紹介など、具体的な対策を教えてもらえるでしょう。
また、不動産会社はオーナーや管理会社と直接やりとりする立場にあるため、入居希望者の人柄や事情をうまく伝えてくれる「橋渡し役」にもなってくれます。
ネガティブな要素があっても、不動産会社の伝え方次第では審査に通してくれることも。条件に合う物件を選ぶだけでなく、頼れる営業担当に出会うことが、審査通過の鍵です。

最後に賃貸住宅に入居するまでの流れをおさらいしましょう。お部屋探しから入居までは以下の流れで進みます。
お部屋探しから入居までの期間は、早い方は1〜2週間、遅い方は3カ月程度と個人差があります。たとえば4月からの入居を目指す場合は、2月くらいからお部屋探しを始めたほうが良いでしょう。
それぞれのプロセスでやるべきことについて詳しく解説します。
不動産ポータルサイトなどを活用して、希望条件を満たす物件を探します。エリア・予算・面積・設備仕様などの希望条件を洗い出し、優先順位を付けておくのがおすすめです。
特に意識して決めておきたいのが、予算です。入居審査で収入と家賃のバランスを審査されることを見据え、月収の3分の1に収まるように設定しましょう。
お部屋探しにかかる期間は、だいたい1〜2週間ほどです。良い出会いがあれば、1日でお部屋探しが終わる場合もあります。
気になるお部屋が見つかったら、次は不動産会社への問い合わせです。メールや電話で、物件の取扱い店舗に連絡をします。
残念ながら、人気物件は問い合わせをした時点で既に埋まっている場合もあります。しかし希望条件を伝えれば、別の物件を紹介してもらうことが可能です。
また、入居審査に通るかどうか不安材料がある場合は、最初の問い合わせで担当者に伝えます。事情を考慮したうえで、審査に通りやすい物件を紹介してもらえるでしょう。
後日問い合わせをした不動産会社へ出向き、担当者と一緒にお部屋の内見をします。内見は自分の目で直接物件を確認できるチャンスです。
日当たりや眺めを確認したり、手持ちの家具が収まるかどうかメジャーで測ったりすることもできます。室内だけでなく、共用部の管理状況や周辺の治安・利便性などのチェックも忘れないようにしましょう。
内見をして気に入れば、敷金・礼金や仲介手数料など初期費用について確認しましょう。また入居審査に必要書類や連帯保証人の要否を聞いておくと、その後の手続きもスムーズに進められます。
住みたい物件が決まったら、不動産会社を通してオーナーに入居を申し込みましょう。その際、入居申込書とあわせて、入居審査の必要書類も提出します。主な必要書類は、以下のとおりです。
入居申込書は収入や連帯保証人などの欄があるため、抜け漏れやミスがないよう慎重な記入が必要です。記入する際は、必ず連帯保証人へ連絡して許可を得ておきましょう。
上記書類のほかに、入居申込書に押す印鑑も必要になる場合があります。
いよいよオーナーによる入居審査がおこなわれます。審査期間は3日〜1週間程度です。それまで結果の連絡が来るのを待ちましょう。
審査に落ちてしまった場合は、お部屋探しからやり直しになります。落ちた理由は開示してもらえないことがほとんどです。
なぜ落ちたのか自分で考えてみて、次は審査に通過できそうな物件を探してみましょう。収入面に問題がありそうな場合は、予算を下げてみると効果的です。
入居審査を通過したら、賃貸借契約を結びます。賃貸借契約で必要となる書類は以下のとおりです。
必要書類は物件によって異なるため、事前に確認しておきましょう。特に連帯保証人の確認書類は、相手方に取得を依頼しなければなりません。取得に時間がかかるものもあるため、依頼してから提出までの時間的余裕を持たせることが望ましいです。
契約を結んだら、入居日に合わせて鍵の引き渡しを受けます。入居に向けて、引越しの準備や住所変更などの手続きを進めましょう。
賃貸住宅の入居審査は、およそ1〜2割の人が落ちるといわれています。通らない理由は、年収や信用力、連帯保証人などが関係していることが多いです。
もし気になる点があれば、信用情報や月収を事前に確認しておくと安心です。どう対策すべきか迷うときは、不動産会社に相談しましょう。
信頼できる担当者であれば、オーナーに上手く伝えてくれたり審査に通りやすい物件を紹介してくれたりして、あなたの味方になってくれるはずです。
万が一審査に落ちてしまっても、次に向けた対策を打てば大丈夫です。自分の状況を客観的に見つめ直し、ぴったりなお部屋を見つけてください。
熊本市不動産売却クイック査定です。
昨今では都心部を中心に不動産価格が高騰しています。家を買うのに自己資金をほとんど使ってしまい、貯金が底をついたという方も。
本記事では家を購入後に貯金がなくなった場合のデメリットや、貯金を残す方法を解説します。貯金がなくなりそうな方は、資金計画を練る際の参考にしてください。

住宅は大きな買い物ですが、購入後もさまざまな費用がかかります。安定した生活を送るためには、ある程度貯金を確保しておかなければなりません。
ここからは貯金残高の目安と、住宅購入後にかかる費用を解説します。
住宅購入後の貯金残高は、手取り月収の3〜4カ月分が最低ラインです。たとえば手取り月収30万円とすると、90万円〜120万円の貯金を確保しておいたほうが良いでしょう。もし何らかの理由で収入が途絶えても、3〜4カ月の間は生活をカバーできます。
さらに余裕を持たせたい場合は、手取り月収の6カ月分あると安心です。ただ、これは会社員を想定した目安になります。フリーランスの場合は収入が不安定なので、1年分の収入と同等の貯金が望ましいでしょう。
住宅を購入してもお金はかかり続けます。住宅購入後にかかる主な費用は、以下のとおりです。
| 固定資産税 | 土地・建物に毎年課される税金 |
| 都市計画税 | 都市計画区域内の土地・建物に毎年課される税金 |
| 不動産取得税 | 土地・建物を取得したときに課される税金 |
| 火災保険料 | 火災や自然災害による損害を補償する保険料 |
| 地震保険料 | 地震による損害を補償する保険料 |
| 管理費※マンションの場合 | マンション共用部の維持管理費用 |
| 修繕積立金※マンションの場合 | マンションの大規模修繕のための積立金 |
固定資産税・都市計画税は毎年課税される税金です。不動産取得税が課税されるのは一度だけですが、購入から半年〜1年経った頃に納税書が届きます。いずれの税金も不動産の固定資産税評価額をもとに算出されるため、物件ごとの差が大きいです。
火災保険料や地震保険料は、自然災害などで家が損害を受けたときに保険金を受け取るための料金です。地震保険付き火災保険料(5年一括払い)の相場は、戸建て住宅で32万円〜40万円、マンションで9.1万円〜10.5万円程度になります。加入は任意ですが、住宅が損傷した場合に自己資金で賄うのは大きな負担がかかるため、必要不可欠な出費です。
マンションの場合は管理費と修繕積立金がかかります。管理費は共用部の清掃・水光熱費、設備点検費用、管理人の人件費などに使われます。修繕積立金は10〜15年のサイクルで実施される大規模修繕に向けて積み立てておくお金です。管理費は約1.5万円、修繕積立金は約1.2万円が相場で、あわせて3万円弱の費用を毎月支払い続けます。

「家は人生で最も大きな買い物」とよく言われますよね。でも、どれくらいのお金がかかるのか具体的なイメージが沸かない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ここからは家を購入するときにかかるお金について解説します。
公益財団法人東日本不動産流通機構の「首都圏不動産流通市場の動向(2024年)」によると、物件種別ごとの成約価格は以下のとおりです。
| 新築戸建住宅 | 4,354万円(前年比7.0%上昇) |
| 中古戸建住宅 | 3,948万円(前年比2.6%上昇) |
| 中古マンション | 4,890万円(前年比2.6%上昇) |
すべての物件種別で価格が前年を上回っており、住宅価格が上昇していることがわかります。価格高騰の主な要因としては、建築資材や住宅設備の価格上昇や人件費の増加が挙げられます。また、土地を購入して家を建てる場合は、地価の上昇も価格を押し上げる一因です。
家を購入する際は、諸費用もかかります。諸費用は購入価格の10%くらいが相場です。たとえば4,000万円の家を購入した場合、400万円程度の諸費用がかかります。
主な諸費用をまとめました。
| 仲介手数料 |
不動産会社に支払う報酬 (家の購入価格×3%+6万円)+消費税 |
| 印紙税 |
不動産売買契約書に課税される税金 1万円~3万円程度 |
| 登録免許税 | 所有権移転登記の際に課税される税金 |
| 司法書士報酬 |
登記手続きを司法書士に依頼した場合に支払う報酬 5万円~10万円程度 |
このほか、新築マンションを購入する場合は修繕積立基金がかかります。初回の大規模修繕に充てるお金で、20万円〜80万円とまとまった金額が必要です。
さらに住宅ローンを利用する場合は、融資事務手数料やローン保証料、物件調査手数料なども発生します。また、印紙税や登録免許税も別途必要です。

家を購入した後に貯金がなくなると、家計は大きなダメージを負います。具体的なデメリットを挙げると、以下のとおりです。
一つ目のデメリットは、住宅購入後に緊急事態が発生し、大きな出費を伴うケースです。たとえば予期せぬ病気やケガをしてしまった場合、高額な医療費がかかる可能性があります。特に収入を支える人が働けなくなると、生活への影響は深刻です。
入院が1週間におよべば、自己負担総額は数十万円に達することも珍しくありません。病気やケガがきっかけで介護が必要になれば、医療費だけでなく、介護サービスやバリアフリー改修費なども追加されます。
さらに、住宅の不具合による突発的な修繕も考えられます。たとえば屋根の雨漏りや給排水管の破損などが見つかった場合、修繕費用がかさむ可能性が高いです。特に中古住宅では思ったより劣化が進んでいて、予想以上の修繕費用がかかることもあります。
このような緊急事態はあらかじめ予測することが困難です。万が一の事態が起こっても対応できるよう、住宅購入後も貯金を残しておくことが大切です。
家を所有していると、特別な事情がなくても税金や保険料などの諸経費が発生します。これらの諸経費は、一定期間ごとに継続して支払う必要があります。加えて、引越し費用や家具購入費用などスポット的に発生する諸経費も考慮しなければなりません。
住宅購入後に貯金がないと、これらの費用を支払うのが難しくなります。特に税金を滞納すると、最終的には財産の差し押さえにつながる恐れがあるため注意が必要です。
貯金がない状態が続くと、精神的なストレスを感じる人もいます。「予期せぬ出費があったらどうしよう」「生活費を切り詰めないと」という焦りが募り、将来への不安を抱え続けることになるからです。
さらに、趣味やレジャーなど、やりたいことも我慢しなければなりません。外食など人と交流する機会も減り、疎遠になってしまうことも。お金がないことを理由に家にこもっていると、ストレスはたまる一方です。
このような状態が続くと、精神的な負担が体調にも影響を及ぼすことがあります。ストレスを軽減し前向きに生活するためにも、貯金を確保しておいたほうが良いでしょう。

家を購入した後に貯金を残すためには、家の購入に充てる自己資金を減らす工夫が必要になります。具体的な方法は、以下の3つです。
それぞれの方法を詳しく見ていきましょう。
一つ目の方法は、住宅ローンを利用する方法です。住宅ローンは金融機関からお金を借りて、購入後に分割して返済します。借入金を利用した分だけ、家の購入に充てる自己資金を減らせるため、余った分を貯金に回すことが可能です。
家の購入に自己資金を一切使いたくない場合は、フルローン、オーバーローンという方法があります。フルローンとは、頭金ゼロで物件価格の全額を借り入れる方法です。オーバーローンは、物件価格を超えた金額を借りられ、購入時の諸費用も賄えます。
ただ住宅ローンを返済する際は、金利が上乗せされる点に注意が必要です。返済金額が膨らみ、借入金額を大幅に上回る可能性があります。近年は日銀の政策金利引き上げに伴い、住宅ローン金利の上昇も懸念されます。長期にわたって毎月返済し続けることになるため、無理のない金額を借り入れることが肝心です。
二つ目の方法は、親族に資金援助をお願いする方法です。返済の必要がなければ、住宅ローンよりも負担を減らせるでしょう。
また、親族からの資金援助は「住宅取得等資金の贈与の非課税」という制度を利用できます。通常、資金提供を受けると贈与税の対象になりますが、この制度を利用すれば一定額まで非課税で贈与を受けられます。非課税となる贈与額は、省エネ等住宅は最大1,000万円、それ以外の住宅は最大500万円です。
ただ援助の意向がない親族に、無理に頼むのはトラブルのもとになります。親族とよく話し合い、負担のない範囲で協力をお願いしましょう。
新築物件や都心物件は人気が高く、物件価格の高騰が続いています。一方で中古物件や地方物件を選ぶことで出費を抑え、浮いた資金を貯金に回すことが可能です。
ただ中古物件や地方物件にはデメリットもあるため、理解したうえで選ぶ必要があります。たとえば中古物件は老朽化が進み、突発的な修繕費が発生することも。地方物件は交通アクセスが悪く、通勤や通学が不便になることもあるでしょう。
こうしたリスクを避けるためにも、必ず現地に行って、自身の許容できる範囲か確かめることが大切です。築年数やエリアのこだわりを少し緩めることで、思わぬ掘り出し物に出会える可能性もあります。

ここからは、リアルな口コミを紹介します。
家購入時、手元に残す貯金はどれくらいが良いのでしょう。引っ越し費用や家具家電購入費を除いて、手元に残るのは100〜80万くらいですが、少し心もとない気がしています。
我が家の家計は月々の給料よりボーナスで相当助けられているので…
フィナンシャルプランナーとの相談が2回終わりました。車買ってから全然貯金ができていません。老後と教育費は何とかなりそうですが、マイホームは「予算下げるか買う時期をずらさないと厳しいかもしれません」と言われてしまいました。
マツエクやネイルにも通いたい気持ちはあるのですが、今は収入がほとんどなく、貯金も心もとない状況です。この先さらに生活が厳しくなりそうだと考えると、定期的にそういった美容サービスに通うことは難しく、今は控えようと思っています。
夫と結婚してから、まもなく三年が経ちます。その間に結婚式を挙げ、住宅ローンを組んでマイホームを購入し、第一子を出産。今は第二子を迎える準備を進めているところです。こうして振り返ると、金銭的に余裕がないのも当然だと感じています。
マイホームを購入できたのは良かったですが、やはり費用の大きさに圧倒されます。結婚式を挙げていないこともあり、これほど大きな金額が一度に動くのは今回が初めてで、正直なところ少し戸惑っています。
いずれ働き始めたら少しずつ貯金を増やしていけばいいとは思うのですが、それでも一気に手元のお金が減っていくのはやはり不安ですね。 実際に住み始めるのはまだ先ですが、来月から住宅ローンの返済もスタートするのかと思うと…心の準備が追いつきません。
マイホームを買って、貯金がなくなることについて不安の声がありました。貯金をためるために趣味を我慢している方も見受けられました。
ローンを借りていても、返済に追われ貯金が貯まらないケースもあります。返済しながら将来に必要な資金を貯金できるような計画が必要です。
家を購入する際は、貯金を使い果たさないよう慎重に計画することが重要です。貯金が底をつくと、病気やケガ、突発的な家の修繕に対応できません。さらに税金や保険料などが家計を圧迫して、生活が苦しくなる恐れがあります。
貯金残高は、最低でも手取り月収の3〜4カ月残しておくべきです。もし収入が途絶えても、3〜4カ月は生活を立て直すための時間を確保できます。購入後も貯金を残すためには、以下の方法が有効です。
貯金は将来の生活を支える大切なお金です。しっかりと資金計画を立てて、無理のない範囲で理想の家を見つけてください。
熊本市不動産売却クイック査定です。
賃貸住宅を選ぶとき「忙しくて内見する時間がない」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。しかし内見なしで賃貸契約するのはリスクがあり、注意点を覚えておかないと後悔してしまうことも。
本記事では内見しないで賃貸契約する割合や、注意点を解説します。これから賃貸住宅への引越しを検討している方は、本記事を参考にして後悔のない物件選びをしてください。

内見なしで契約する人はどのくらいいるのでしょうか。その割合を見てみましょう。
イエプラコラムによると、以下のような結果が公表されていました。
“賃貸物件を内見しないで契約する人の割合は約27.7%です。3〜4人に1人は内見しないで契約しています。”
“繁忙期の2〜3月は、内見しないで契約する人が増えます。家AGENT 池袋店で申し込んだお客様300名のうち、内見しないで契約した人の割合は約41.3%でした。”
引用元:イエプラコラム・家AGENT 池袋店 独自調査(2024年6月受付 300名分のデータ)
このように内見なしで契約する人の割合は、時期によって変動します。しかし、いずれにしろ内見して契約する人のほうが多いです。

内見する人としない人は分かれますが、それぞれどのような理由があるのでしょうか。内見しないで契約した理由と、内見した後で契約する理由を解説します。
何かしらの特別な事情を抱えている場合が多いです。具体的には以下のような理由が挙げられます。
賃貸住宅の契約は、基本的に早い者勝ちです。「現地を見て決めよう」と思っていると、他の人に取られてしまう可能性があります。
人気物件であるほど、競争率は上がります。特に立地が良い、家賃が安い、設備が充実している物件は、競争率が高いです。
内見を省略することで、契約までの時間を短縮できます。「希望した物件に必ず住みたい」という心理が働いているのです。
新築物件は完成前から募集が始まることが多いのですが、まだ工事中のため内見できない場合があります。
新築物件は人気が高いので、完成まで待っていると埋まってしまうことも。その場合は実物見るのをあきらめて、図面やパースを参考にして契約する人が多いです。
転勤や進学などで遠方から引っ越してくる場合に、やむを得ず内見なしで契約するケースもあります。距離が遠いゆえに、現地に行くのに多大な時間と費用がかかるためです。
特に海外からの移住だと、ハードルは非常に高いです。その場合は、不動産会社とオンラインで相談しながら契約を進めることもあります。VRでお部屋の様子を確認できる物件も増えてきているので、そういった情報を頼りに契約します。
内見した後で契約する人は、「自分の目で確認できるから」という理由が大きいです。具体的な理由をまとめました。
間取り図や写真だけで、実際の広さや使い勝手を判断するのは難しいです。
しかし現地に行けば、実際にお部屋の中に入って体感できます。「思っていたより狭い」「収納が少ない」といったミスマッチもすぐに見抜けます。
治安や騒音など周辺環境も、足を運ばないとわからない情報です。
駅から物件まで歩いてみれば、通勤・通学路の安全性を確認できます。物件に着いたら、外や隣室からの音の聞こえ方を確認することもできるでしょう。
写真や地図だけでは判断できないリアルな住み心地を体験できるチャンスです。
写真では綺麗に見えても、実際は壁紙が剥がれていたり水回り設備が老朽化していたりする場合があります。
実際に訪問して、お部屋の傷や汚れ、設備の動作確認をすることで、入居後のトラブルを未然に防ぐことができます。

内見なしで契約を結ぶのは、リスクが伴います。後悔しない物件選びのために、覚えておきたい注意点を紹介します。
写真だけで契約を結んだら「思ったより部屋が狭かった」というパターンです。
ポータルサイトに載っている物件写真は、実際よりも広く見えます。その理由は写真1枚で広い範囲を捉えられるよう、広告レンズで撮られていることが多いからです。
写真だけを当てにすると、後悔することになりかねません。本当の広さを知るためには、その空間に身を置いてみることが一番です。
間取り図と実物が違うこともあります。
他の人が居住中の物件は、他の部屋の図面を掲載していることがあるためです。その他、人為的なミスで、間取り図の表記が間違っていたということも。
間取り図と違っても、基本的には現状が優先されます。イメージしていた間取りと違い、使い勝手が悪く後悔する人も少なくありません。
「写真では綺麗な部屋だったはずなのに、実物は汚い」というパターンです。
ポータルサイトには、新築時に撮影された写真が掲載されている場合があります。何人もの人が住んでいれば、当然汚れてしまうこともあるでしょう。
築年数が古いのに写真が綺麗な場合は、特に注意が必要です。不動産会社の担当者に「この写真はいつ撮ったものですか」と確認することをおすすめします。
住んでみたら、隣人の生活音や電車の音がうるさいこともあります。騒音は住み心地に直結する要素なので、大きな後悔の原因になります。
「建物の構造を見れば、防音性が高いかどうかわかるのでは」と思った方、油断は禁物です。鉄筋コンクリート造など堅牢な構造でも、部屋を仕切る壁は薄いケースもあります。また、騒音のボリュームが非常に大きい場合、構造だけではカバーできないことも多いです。
実際の音の聞こえ方は、現地に行かないとわかりません。同じ音でも人によって受け取り方は異なるので、直接その場で確かめることがとても重要です。
周辺の治安も、実際に現地に行ってみないとわからないことです。駅から物件までの道のりが暗かったり、柄の悪い人が歩いていたりすると不安ですよね。
物件選びでは部屋の条件に気を取られがちです。周辺の治安は見落としやすいポイントなので、注意しましょう。
どうしても見に行けない場合は、以下のような調査方法もあります。

ここからは、リアルな口コミを紹介します。
「数年おきに引越ししていますが、いまだに物件を選ぶときに内見をしたことがないんです。次はしてみたいなと思いつつ面倒で。」
「前職が転勤族だったこともあって、すでに人生で15回くらい引っ越ししていますが、1回も内見したことがありません。1回も後悔したことないんですが、そんなに内見って大事ですか・・・?」
「不動産の繁忙期になると物件が決まるのが早いと聞いてましたが、内見もなしに1日で申し込みが2件も入るなんて。ここからは吟味する時間がないから、即断力が必要です。」
「おうちを決めました!内見できていませんが、条件が良すぎるので先行契約しました!」
「物件契約完了!新築物件は初めて…内見できないから不安はありますが、信じるしかないです。」
内見をせずに契約することについて、さまざまな声がありました。
頻繁に引越しをしている方のなかには、これまで一度も内見せずに決めてきたが後悔したことがないという意見もあります。また、不動産の繁忙期や新築物件といった理由で、不安を感じながらも内見を省略しているケースも見受けられました。
内見の重要性は認識しつつも、状況に応じて柔軟に判断している人が多い印象です。

できるだけ内見したほうが良いとはいえ、どうしてもできない場合もありますよね。ここからは、以下のシチュエーションに合わせた対処法を紹介します。
新築工事中の物件に対して、内見しないで契約することを先行契約といいます。どうしても他の人に取られたくない場合は、先行契約をするのもありです。
一方で、先行申し込みという方法もあります。最初に申し込みをして審査を済ませておき、建物の完成後に優先的に内見させてもらい、契約するかどうか判断する方法です。
リスクがなく、他の人に取られる心配をできるだけ減らせるのがメリットです。
ただし、先行申し込みは先行契約に比べると効力が弱いです。先行契約で埋まってしまえば、入居することはできません。
遠方に住んでいる場合は、他の人を頼ることでリスクを減らせます。
たとえば自分が行けない代わりに、親族や友人に行ってもらう方法です。引越し先エリアに知り合いがいる場合は、ぜひ検討してみると良いでしょう。事前に見てほしいポイントを伝えておくと、見に行く側も効率的にチェックできます。
あとは不動産会社の担当者に内見代行を頼む方法です。気になる箇所の写真を撮影してもらったり、寸法を測ってもらったりすると不安を払拭できる可能性があります。
入居者がいる物件で、絶対に取られたくない場合は、先行契約します。
もし先行契約にリスクを感じるのであれば、先行申し込みで手を打ちます。確実な予約ではありませんが、少しでも優先度を高めたい場合にはおすすめの方法です。
あとは「入居者に立会ってもらえないか」ダメもとで聞いてみるのも手です。入居者がOKしてくれれば、居住中でも部屋を見せてもらえる可能性があります。

賃貸住宅の契約は生活の拠点を決める重要な決断なので、後悔はしたくないものです。後悔しないためにやるべきことを紹介します。
一つ目は、不動産会社に相談する方法です。内見できない分、不動産会社とたくさんコミュニケーションをとって、情報を集めます。
まずは、物件の写真や動画、図面などできるだけ多くの資料を不動産会社に用意してもらいましょう。特に重要事項説明書には、契約前に知っておくべき情報が記載されているので、要チェックです。
もらった資料から読み取れない部分は、不動産会社に内見代行を依頼してみてください。気になる部分のチェックや採寸などに対応してもらえることが多いです。
以下の項目は、最低限チェックしてもらいたいポイントです。
不動産会社の協力を得て、しっかり情報を集められれば、入居後のギャップを減らすことができます。
Googleマップを活用すれば、パソコン上で周辺環境の調査をすることも可能です。たとえば駅から物件までのルートをストリートビューで見ると、街灯や人通りの多さなどをイメージできるでしょう。
Googleマップを3D表示に変更すると、周辺に日当たりを遮る高い建物はないかということも確認できます。実際に見に行くのと比べて精度は劣りますが、何も調べないよりはリスクを減らせるはずです。
現地に行かない限り、土地の高低差や、河川の有無など重要な情報が抜け落ちる可能性があります。そのため、ハザードマップを活用し、災害リスクを事前に調べることが不可欠です。
国土交通省の運営するハザードマップポータルサイトでは、全国の災害リスクを調べられます。「重ねるハザードマップ」機能を使えば、住所を入力するだけでその地点の洪水や土砂災害のリスクが色分け表示されます。
安心して住み続けるために、災害リスクを十分に考慮したうえで物件を選びましょう。
内見しないで賃貸契約する割合は半数以下で、大半の人は内見してから契約します。自分の目で確認することでリスクを最小限に抑えられるので、納得感を持って契約するための重要なプロセスといえます。
しかし、やむを得ないケースもあります。その場合は不動産会社や親族に見に行ってもらうなど、積極的に情報収集をすることが肝心です。
熊本市不動産売却クイック査定です。
賃貸物件には「女性専用物件」があります。これは文字通り、女性のみ居住が許されたアパートやマンションのことです。女性が安心して生活できることを目的に設計されていて、首都圏を中心に近年増加傾向にあります。一見メリットの多い女性専用物件ですが、実はデメリットも存在します。
住んでから後悔しないためにも、あらかじめ女性専用物件の落とし穴について理解しておくことが大切です。この記事では、女性専用物件のメリット・デメリットや実際の口コミや評判などについて解説します。

まずは、女性専用アパート・マンションのメリットを確認していきましょう。女性専用物件には、以下のようなメリットがあります。
「引っ越しで街選びをする際、何を重要視するか」というアンケートを行ったところ、1位「治安の良さ」、2位「大きなスーパーがある」、3位「アクセスの良さ」という結果でした。この結果から、多くの女性が「安心安全に生活できること」を求めて物件探しをしていることが伺えます。
具体的には、オートロックや防犯カメラ、モニター付きインターホンの設備が備わっている物件が人気です。女性専用物件は、これらの設備が全て備わっているケースが多く、なかには管理人が24時間駐在している物件もあります。物件によっては、関係者以外の立ち入りが厳しく制限されるため、より高い防犯効果が期待できるでしょう。
隣人が「女性」というだけで安心感があると感じる方も多いのではないでしょうか。女性専用物件は、当然のことながら住人は全員女性です。そのため、自然と安心感が得られる点は大きなメリットと言えます。また、その物件に集まる住人は、あなたと同じように安心感を求めてその物件を選んでいます。
したがって防犯意識が高く、トラブルや揉め事に発展するリスクは低くなるでしょう。初めての一人暮らしや慣れない土地へ引っ越しする方は不安感が強くなるため、女性専用物件がおすすめです。
女性のために作られた物件であるため、内装や外装が女性好みにデザインされているケースが多いです。ただし、外観から女性専用とわかるとトラブルに巻き込まれる可能性があるため、外観はシンプルなケースもあります。内装は清潔感があり、温かみを感じる色合いが採用されたり、収納が大きめに作られていたりすることが一般的です。
設備が充実しているのも女性専用物件の特徴です。たとえば、バス・トイレ別、独立洗面台、室内に洗濯機置き場がある、収納が多い、キッチンが広いなどがあります。一般的な物件では部屋を広くとるために、洗濯機を室外に設置するケースがよくあります。
しかし、洗濯物の盗難被害に遭う可能性があるため、女性専用物件では室内に設置されていることが多いです。他にも、広い洗面台や広めのキッチンも女性専用物件ならではの特徴と言えるでしょう。

次に、女性専用アパート・マンションのデメリットについて紹介します。
入居してから後悔しないために、あらかじめデメリットを把握しておきましょう。
内装や外装、設備にこだわっている女性専用物件は、建築費や維持費がかかるため相場よりも家賃が高めに設定されているケースが多いです。女性専用物件は年々増加しているものの、まだまだ希少価値が高い物件です。そのため、もともと家賃を高めに設定している大家さんも少なくありません。人気エリアにある物件や利便性の良い物件は、さらに家賃が高くなることもあるでしょう。
女性専用アパート・マンションは、物件の広告で「女性専用」と謳われているため、不審者や犯罪者に逆に目をつけられる可能性があります。また、入居者から女性専用という情報が外部に漏れることもあるでしょう。これにより、外部からの不正行為やストーカー被害、窃盗などの標的にされる可能性も否定できません。
したがって、女性専用であっても日頃から防犯対策を意識しておくことが大切です。また、入居前に物件周辺の治安や犯罪発生件数などを調べておくことをおすすめします。
先述したように、女性専用アパート・マンションはまだまだ物件数が少ないため、エリアの選択肢が少ないというデメリットがあります。また、人気が高く空室が出にくいため、「借りたくても借りられない」という方が多いのも実情です。したがって、エリアや家賃、間取りなど、何かしらの条件を妥協する必要が出てくるでしょう。
女性専用アパート・マンションでは、女性専用物件ならではの厳しい規則が設けられていることがあります。たとえば、男性の立ち入り制限がされている場合、彼氏や男友だち、父・兄弟が急に来ても入ることができません。また、引越し業者が立ち入りする際も事前申請が必要です。入居者の安全性を守るための規則ですが、一方で生活の利便性や交友関係に影響が出る場合もあるため、あらかじめ入居規則をしっかり確認しておきましょう。

では、実際に女性専用アパート・マンションで暮らす利用者の口コミや評判はどうなのでしょうか。まずは、良い口コミから見ていきましょう。
夜中に大きな物音がしたり、近隣住民が大声で叫んでいたりすると、家の中にいても不安になるものです。その点、女性専用物件は、入居者全員が女性であるため静かで暮らしやすいという意見がありました。また、管理人や大家さんも女性であることが多く、より安心して毎日を過ごすことができるようです。

次に、女性専用アパート・マンションの悪い口コミを見ていきましょう。
女性専用物件のなかには、立地が悪い物件もあります。たとえ家の中が安全でも、駅から徒歩30分、バス停まで遠いというような物件では、「夜道が怖い」と感じる方もいるでしょう。また、他の住人が規則を守らず、男性を連れ込んでいるというのは女性専用物件でよくあるトラブルです。
このような場合は、管理会社へ連絡して入居者への注意喚起を促しましょう。管理会社の対応が悪いという口コミも見られましたが、管理会社の対応に不満がある場合は、担当者の変更を依頼しましょう。それでも改善が見られない場合は、お住まいの地域の消費者センターや弁護士に相談するのも一つの手段です。
女性専用物件は、女性の安心安全な暮らしを実現するために、防犯対策や住宅設備が充実しています。他にも女性に嬉しいメリットがたくさんあるため、一人暮らしが初めての方にもおすすめです。その一方で、エリアが限られる、家賃が高い、規則が厳しいなどのデメリットもあります。また、女性専用物件は非常に人気が高く、空室が出たタイミングですぐに次の入居者が決まってしまうため、焦って物件を決めてしまう方もいるでしょう。
しかし、家族であっても男性の立ち入りが禁止されていたり、業者の立ち入りは事前申請が必要であったり、入居者の自由が制限されることがあります。したがって、入居前にはしっかりルールを確認した上で慎重に判断することが大切です。
熊本市不動産売却クイック査定です。
「隣人がうるさい!黙らせる方法はない?」とお困りではありませんか。騒音は日常生活に大きな影響を与え、ストレスや睡眠不足を招くことも多いです。特に住宅が密集する都市部では騒音問題が多く、適切な対策が必要になります。
本記事ではうるさい隣人を黙らせる方法を解説します。マンション・アパートと一軒家それぞれの環境に適した対策を紹介するので、ぜひ参考にしてください。

マンションやアパートでうるさい隣人を黙らせる方法は、以下の3つです。
それぞれの方法について詳しく説明します。
一番簡単な方法は、管理会社や大家に相談してみることです。直接話し合うとトラブルになりやすいですが、第三者を通すことでスムーズに解決できる可能性があります。
管理会社や大家に相談すれば、掲示板に注意喚起の紙を貼るなど対応してもらえます。ただ客観的な情報がないと、動いてもらえないことも多いです。
そのため相談する際は「何時ごろ・どのような音が聞こえるのか」を伝えましょう。音を録音しておくと、より説得力が増します。
もう一つの方法は、手紙を書いて相手のポストに投函することです。顔を合わせずに、こちらの意思を伝えることができます。
相手に受け入れてもらえれば、騒音の改善が期待できます。ただ、手紙を書く際は感情的にならないように注意しましょう。
以下に、手紙の例文を記載します。
〇〇号室〇〇様
拝啓
突然のご連絡をお許しください。私は△△号室に住んでおります、□□と申します。いつもお世話になっております。
この度、恐縮ながらひとつお願いがあり、ご連絡を差し上げました。最近、夜間にお部屋からの音が聞こえることがあり、私の生活に少なからぬ影響が出ております。もし可能でしたら音量を少し抑えていただけますと、たいへんありがたく存じます。
お互いが快適に過ごせるよう、ご協力いただけますと幸いです。何かご不明点やご相談がございましたら、お気軽にお知らせください。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
敬具
△△号室 □□
このように、できるだけ丁寧な文章を心がけましょう。
何度も手紙を送ると圧力を感じさせる可能性もあるため、一度送ってから様子を見たほうが良いです。改善が見られない場合は、また次の対策を検討しましょう。
騒音問題に詳しい弁護士に相談してみるのも一つの方法です。ただ弁護士への相談は有料になるため、事前に話したいことを整理しておく必要があります。
国が設立した法律相談所「法テラス」では、弁護士の無料法律相談を受けられます。1回30分の相談で、3回まで無料です。ただ利用できるのは収入と資産が一定基準以下の人に限定されます。詳しくは日本司法支援センターのホームページでご確認ください。
また、法テラス以外にも、市区町村窓口で定期的に無料相談会が開かれていることもあります。
法律のプロである弁護士に相談することで、どうすれば良いか適切な対応策がわかります。騒音測定データなど有効な証拠の集め方もアドバイスしてもらうことが可能です。また、弁護士に代理人として交渉してもらえば、隣人との直接対立を避けつつスムーズに解決を図れるでしょう。

次に一軒家における騒音問題の対策を解説します。主な対策は以下のとおりです。
それぞれの対策について詳しく見てみましょう。
一軒家の場合は、所属する自治会や町内会に相談するのも一つの方法です。まずは、役員や班長など身近な担当者に相談してみましょう。
騒音問題を個人間のトラブルとしてではなく、地域の問題として扱ってもらうことができます。具体的には、回覧板や掲示板で騒音の被害状況を地域住民に周知してくれる場合があります。
ただ、自治会によっては「個人間の揉め事には介入できない」と対応を断られてしまうケースも。それでも何らかの助言や情報提供を受けられる可能性があるので、一度相談してみる価値はあるでしょう。
民生委員も、騒音被害の身近な相談相手になってくれるでしょう。
民生委員は国から委託されたボランティア職員で、地域のさまざまな相談に応じています。必要に応じて関係機関につないでくれるため、解決の糸口が見つかる可能性があります。
同じ地域に住んでいるため、気軽に相談しやすい点もメリットです。さらに守秘義務があるので、安心して悩みを打ち明けることができます。
民生委員に相談したいときは、市区町村に連絡すると、担当窓口を案内してもらえます。
騒音被害が改善されない場合は、警察の力を借りるのも手です。相談する場合は、警視庁総合相談センター「♯9110」に電話をかけましょう。「騒音被害を受けている」と伝えると、適切な相談窓口へ案内してもらえます。
緊急性がある場合は、110番通報をおこないます。たとえば騒音を出している住民に苦情を申し入れた際に脅迫を受けた場合は、迷わず110番通報をしましょう。
ただ、警察には民事不介入という原則があるため、騒音問題は当事者間での解決を求められることも。しかし、騒音があまりにもひどい場合や事件性がある場合は、ためらわず警察に相談したほうが良いです。

隣人がうるさいからといって、不適切な対応をとると事態がさらに悪化することがあります。特に以下の対応は、絶対に避けるべきです。
それぞれの注意点を解説します。
隣人宅に訪問してクレームを入れるのはおすすめしません。一見手っ取り早い解決策のように見えますが、面と向かうとお互い感情的になりやすく、冷静な対応が難しくなります。
相手が騒音を認めなかったり、改善の意思が見られなかったりすると、こちら側もイライラしてしまいます。感情にまかせて、攻撃的な発言をしてしまう可能性も否めません。
隣人が逆上して、騒音がさらにひどくなる可能性もあります。直接苦情を入れたことがきっかけで、脅迫や嫌がらせを受けるケースも多いです。
相手に直接伝えたい場合は、手紙のほうがおすすめです。手紙なら冷静に言葉を選び、穏やかな伝え方ができます。また相手側に考える時間を与えられるので、騒音を見直すきっかけになるでしょう。
仕返しとして、壁を強く叩いたり大音量で音楽を流したりする行為は、絶対に避けるべきです。
仕返しをしたところで、騒音の根本的な解決にはなりません。それどころか、相手が対抗して騒音問題がさらにエスカレートする可能性があります。過去には騒音の仕返しから重大な犯罪に発展した例もあり、大変危険な行為です。
騒音問題は感情的にならず冷静に対処することが肝心です。管理会社など第三者に介入してもらい、トラブルを避けながら解決を目指しましょう。
隣人の騒音が改善されないとき、自分でできる騒音対策もあります。主な対策を挙げると、以下のとおりです。
それぞれの対策について、詳しく見ていきましょう。
レイアウト変更は、簡単にできる騒音対策です。専門的な工事は必要ないので、賃貸住宅に住んでいる方も実践しやすいです。
一番簡単な方法は、騒音源となる隣人宅から離れた部屋に、寝室やリビングを配置することです。あとは大型の家具を隣人宅に接する壁・窓の近くに置くことで、音をある程度抑えられます。厚手のカーテンやパーテーションを併用することで、さらなる効果が期待できるでしょう。
市販の防音グッズを活用するのも一つの方法です。たとえば吸音パネル、遮音シート、防音カーテンなどは、部屋の隙間から伝わる音をシャットアウトしてくれます。
防音グッズは比較的低コストで、設置方法も簡単なものが多いです。初めての方も手軽に防音効果を実感できるでしょう。
あとは最もコスパの良い防音グッズとして、耳栓があります。耳栓は数百円で買えて、お部屋のインテリアにも影響を与えません。最近は遮音性抜群の耳栓も増えているので、ぜひ最初に試してみるのがおすすめです。
リフォームするのは手間がかかりますが、騒音の低減に大きな効果が見込めます。
具体的には壁や天井など構造部分に防音材を追加したり、遮音ドアを採用したりする方法があります。初期費用はかかりますが、長期的に見れば快適性を向上させるための有効な投資になるでしょう。
賃貸住宅の場合は、どうしても建物の防音性能に限界があります。自分でできる防音対策も限られるため、騒音に耐えられない場合は引越しするのも現実的な対策です。
新しい住まいを探す際は、建物の防音性能や住民間のトラブル事例、周辺環境の騒音レベルなどを確認しましょう。
持ち家で騒音問題が深刻な場合、最終的には売却を視野に入れることになります。新しい住まいに住み替えることは、生活の安定や健康維持の観点からもメリットが大きいです。
ただ売却には手間や費用がかかります。騒音問題が解消されないまま生活を続けるリスクとのバランスを見て慎重に検討しましょう。
騒音のある家を売却する際は、以下の注意点があります。
それぞれの注意点について、詳しく説明します。
売主は、売却物件の瑕疵について買主にきちんと告知しなければなりません。瑕疵とは欠点や不具合のことで、騒音問題も瑕疵とみなされる可能性があります。
告知を怠った場合は契約不適合責任を問われ、買主から損害賠償を請求される可能性も。騒音がある旨は口頭説明に加え、重要事項説明書への記載も忘れないようにしましょう。
うるさい隣人がいる物件は、値引きを求められる可能性があります。騒音は住み心地に悪影響を与えるからです。
そのため値引きする可能性を見越して、少し高めの価格設定にしておきましょう。もし値引きを求められたら、想定していた範囲内で価格を調整します。
値引き交渉に応じると、買主はお得に感じてくれる可能性があります。結果として契約成立につながりやすくなるでしょう。
深刻な騒音問題を抱えている物件は、なかなか売却先が見つからない可能性があります。騒音を告知しなければならず、買い手が少なくなるためです。
早く売却したい場合は、専門の買取業者に買い取ってもらう方法もあります。専門業者ならではのノウハウがあるので、騒音問題がある物件も積極的に買い取ってもらえる可能性が高いです。
うるさい隣人を黙らせるためには、まず第三者に相談することが1番です。マンションの場合は、管理会社や大家、一軒家の場合は自治会や民生委員に相談すると良いでしょう。
隣人と直接やりとりすることは、できるだけ避けたほうが良いです。どうしても自分で伝えたい場合は、丁寧な言葉で手紙を書くのも有効な方法といえます。
隣人宅に直接訪問してクレームを入れたり、騒音の仕返しをする行為は絶対に避けるべきです。根本的な解決にはならず、大きなトラブルにつながりかねません。
なかなか改善しない場合は、引越しや売却を検討するのも一つの解決策です。売却する場合は、騒音があることをしっかり説明しましょう。専門の買取業者に買い取ってもらう方法もあるので、お困りの場合はぜひ検討してみてください。
熊本市不動産売却クイック査定です。
屋上は景色が良くて開放的な空間であり、ドラマや映画の一場面にもよく登場しますよね。「うちのマンションも、身近に利用できるのでは」と考える方も多いのではないでしょうか。しかし実際のところ、マンションの屋上は立ち入りが制限され、住民が勝手に入れないことが多いです。
本記事では、なぜ屋上に勝手に入れないのかという理由について解説します。屋上の代替案として、ルーフバルコニー付き物件の魅力も紹介するため、これからマンションへの引越しを検討している方は必見です。

マンションの屋上は、立ち入り禁止になっていることがほとんどです。もし勝手に入ると、たとえ住民であっても、不法侵入とみなされる恐れがあります。

住民の立ち入りを制限するのには、訳があります。主な理由を挙げると、以下の4つです。
それぞれの理由について、詳しく見ていきましょう。
屋上は高所にあるため、転落事故のリスクがあります。手すりの高さが十分確保されていないマンションもあり、特に小さい子どもにとっては非常に危ないです。雨天や強風時には足元が滑りやすくなり、事故の危険性がさらに高まります。
また、屋上にいる人が物を落とすのも危険です。高所から落ちると、スマホのような小さな物でも、加速度が増して強い衝撃が生じます。通行人に直撃すると、深刻なケガにつながりかねません。
このような重大事故のリスクを排除するために、屋上を立ち入り禁止にしているマンションは多いです。
屋上は、不審者の侵入経路となる可能性があります。そのため、住民や外部の人が自由に出入りできる屋上は、防犯対策が不十分といえます。
不審者が屋上を経由して住戸内に入り、空き巣などのリスクが高まるでしょう。具体的には、ロープで最上階のバルコニーに降りるなどの手口が考えられます。
このような犯罪から住民を守るために、屋上を開放していないマンションは多いです。屋上の立ち入りを制限することで侵入経路を塞ぎ、建物のセキュリティを確保できます。
住民が屋上に頻繁に立ち入ると、屋上の防水層が劣化する恐れがあります。
防水層でよく使われる露出アスファルトや塩ビ系シートは、不特定多数の人が歩くことを想定していません。屋上を開放すれば、すぐに表面が傷んでしまうでしょう。
屋上は建物全体の防水機能を維持する重要な部分です。そのため防水層が傷むと、マンションの耐久性が低下し、深刻な問題につながる可能性があります。
また、屋上には給排水設備や空調設備、エレベーター機械室などが設置されています。住民がむやみに触ると、故障や事故につながることもあり危険です。
屋上の利用がきっかけで、住民や近隣からのクレームになることもあります。屋上は広くて開放的な空間だからこそ、トラブルにつながりやすい面があるのです。
たとえば友達を呼んで大騒ぎすると、近隣の迷惑になります。屋上で子どもが走り回って、階下にドタドタと振動が響くと、不快に感じる人もいるでしょう。
屋上を利用する際のマナーも、問題になります。ゴミを放置したりタバコをポイ捨てしたりすると、美観を損ねるだけでなく、火災の危険性も高まります。
一度は屋上を開放していたものの、クレームが増えたことで屋上の利用を禁止したマンションも少なくありません。

「せっかく広いスペースがあるのに、立ち入り禁止にするなんてもったいない」と考える方も多いでしょう。なかには、屋上スペースを賢く活用しているマンションもあります。一部の例を見てみましょう。
一部のマンションでは、屋上に菜園を整備し、住民に貸し出しています。新鮮な野菜やハーブを育てることができ、住民同士の交流の場にもなるでしょう。
遮る物がなく太陽の光がたっぷり入るため、さまざまな作物を栽培しやすい環境です。
また、土や植物で屋上を覆うことで、建物の断熱効果が高まります。夏は涼しく、冬は温かく過ごせる点がメリットです。
次にご紹介するのは、屋上をドッグランとして開放している事例です。ペット飼育可の物件に多く見られます。
ペットの運動不足解消や、住民同士の交流の場として役立ちます。適切なフェンスを設置していれば、ペットを安全に遊ばせることが可能です。
ただ、ペットの鳴き声や排泄物の処理などで住民同士のトラブルになることも多いです。しっかりとルールを定めたうえで運用することが求められます。
屋上庭園を設けているマンションもあります。緑豊かな空間は、住民がリフレッシュできる憩いの場です。
庭園の種類は、簡易的な緑化だけの物件もあれば、水辺のある本格的な庭園まで、さまざまです。魚や昆虫が生息するビオトープを取り入れ、自然に近い環境を楽しめるところもあります。
庭園の土や植物は、建物の断熱効果を高める役割もあります。室内の温度が調整されやすくなり、季節を問わず快適に過ごすことが可能です。
一部のマンションでは、屋上を物干しスペースとして使うことができます。比較的築年数の経過したレトロな物件に多い傾向です。
とにかく日当たり抜群なので、洗濯物を短時間で乾かすことができます。布団やラグなど大きな物をスペースを気にせずに干せるのも嬉しいポイントです。
屋上に太陽光パネルを設置するマンションも増えてきています。共用部で発電した電気はさまざまな活用方法があります。
まずは共用部や各住戸で使い、管理費や電気代の削減につなげることが可能です。それでも余った電力は売電すれば、収益源になります。蓄電池を設置し、非常用電源として利用する方法も、災害時の備えとしておすすめです。
ただ太陽光パネルを設置すると、初期費用やメンテナンス費用が必要になります。自治体によっては補助金を用意しているところもあるので、気になる方は調べてみてください。
屋上に基地局アンテナを設置して、毎月収入を得ているマンションもあります。通常、初期費用やメンテナンス費用は不要で、携帯電話会社が管理を行います。
ただ設置できるかどうかは、携帯電話会社の需要によります。需要のない地域では、そもそも契約が成立しません。
負担ゼロで収益を得る魅力的な方法ですが、一部のマンションだけに限られた活用方法といえます。
屋上に看板広告を設置して、収入を得る方法です。大通り沿いや駅から近い立地のマンションは看板広告のニーズが高いため、安定した収入が期待できるでしょう。
しかし設置には初期費用がかかるほか、強風や災害時の安全対策を徹底しなければなりません。広告看板のデザインやサイズの規制も遵守する必要があります。

屋上を住民が使えるようにする場合は、以下の注意点があります。
安全確保やトラブル防止のために、利用ルールを定めることが重要です。利用ルールの一例を挙げてみました。
この他にも利用時間を決めたり、花火大会の時だけ限定開放したりするマンションがあります。
屋上を開放する前に、そもそも不特定多数の利用に耐えうる防水層なのか確認しましょう。屋上の利用が増えることで、防水層への負担が大きくなります。
水漏れの原因にならないように事前に耐久性を確認し、必要に応じて補修を行うことが大切です。
屋上を使用していないときは施錠を徹底します。むやみに開放しないことで、事故や犯罪のリスクを防ぐことができます。
一般的には、各住戸の鍵を使って住民それぞれが屋上の扉を開け閉めしているところが多いです。さらに厳格に管理するのであれば、鍵を管理人室で保管し、使うときだけ貸し出す方法もあります。

「屋上を活用したいのに開放されていない」という場合は、ルーフバルコニー付きマンションに引っ越す選択肢もあります。
ルーフバルコニーとは、階下の屋根の上にあるバルコニーです。通常のベランダやバルコニーより広々とした面積を確保できます。屋根がないので、屋上のような雰囲気を味わえます。
ルーフバルコニー付きマンションには、メリット・デメリットがあるので、両方を理解したうえで選びましょう。
メリットは、以下のとおりです。
明るい屋外空間で開放感を味わえるのが、ルーフバルコニー付きマンションの醍醐味です。ガーデニングやアウトドアリビングなど、ライフスタイルに合わせた活用ができるでしょう。外からの視線を気にせず、安心して過ごせる環境も魅力です。
一方でデメリットは、以下のとおりです。
ルーフバルコニーは共用部であり、ほとんどの物件で使用料がかかります。スペースが広いほど掃除に手間がかかる点にも注意しなければなりません。また、希少性が高いため選択肢が狭まる可能性もあります。
マンションの屋上は、安全や防犯上の理由で閉鎖されていることが多いです。一部のマンションでは屋上を開放しているところもありますが、利用ルールを定めるなど慎重な運用が求められます。
開放的な空間を求めるなら、ルーフバルコニー付きマンションという選択肢もあります。広々とした空間で、さまざまな使い方ができるでしょう。