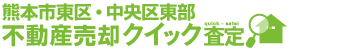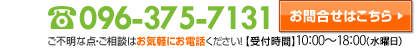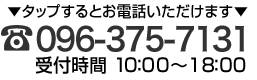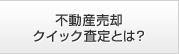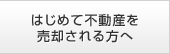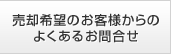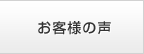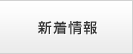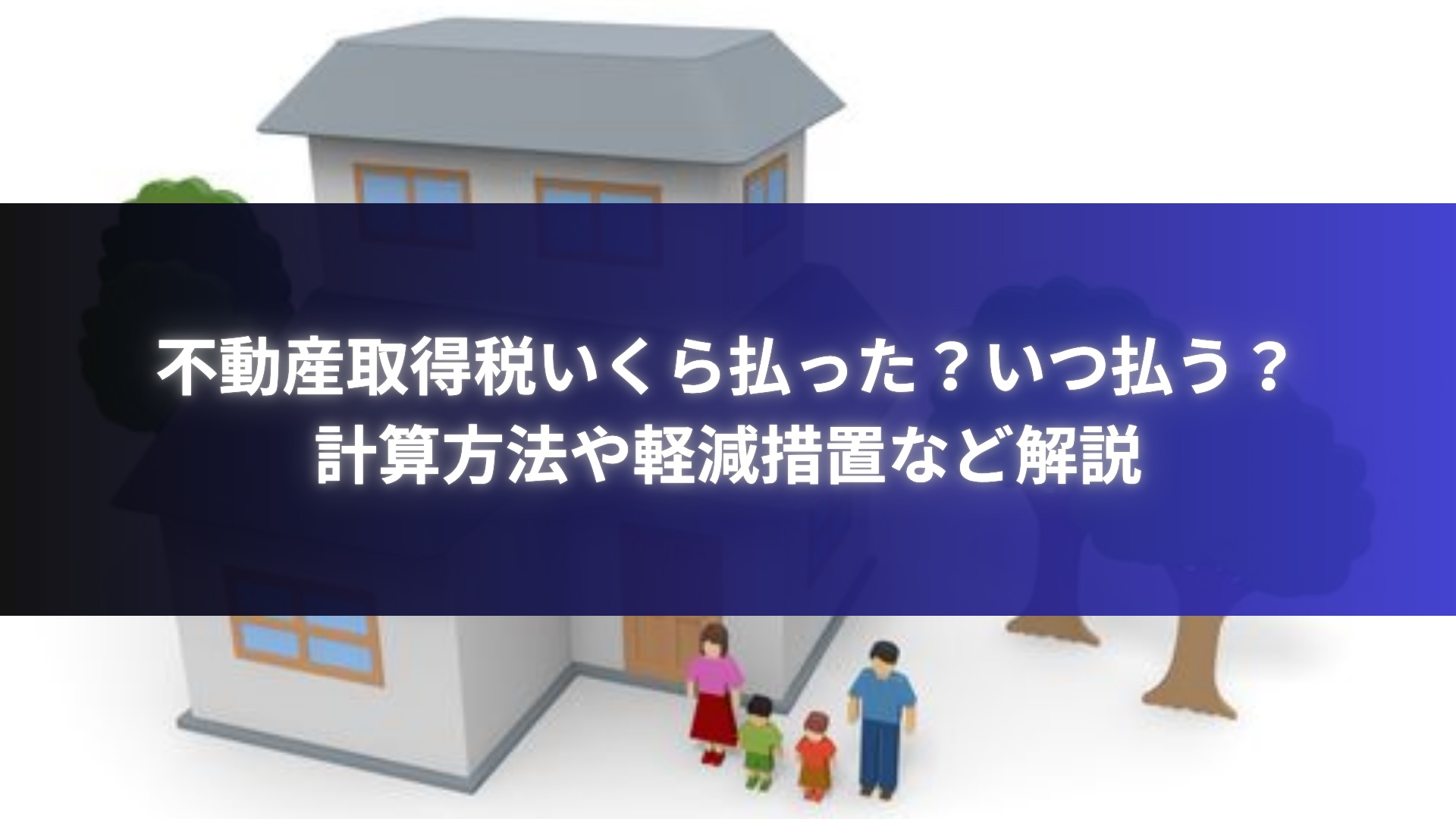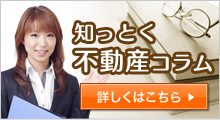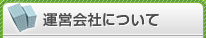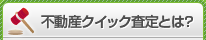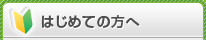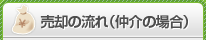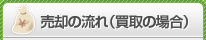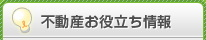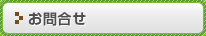不動産取得税は、土地や建物を購入したときにかかる税金の一つです。新しく不動産を取得すると、他の人は税金をいくら払ったのか気になる方も多いのではないでしょうか。実はこの税金には軽減措置があるため、条件を満たせば税負担を大幅に軽減することもできるんです。
本記事では不動産取得税の基本的な知識と、計算方法や軽減措置などを解説します。
目次
そもそも不動産取得税とは?

土地や建物を取得して、その不動産の所有権を得たときに一度だけ課される地方税です。地方税とは行政サービスにかかる費用を負担するもので、都道府県に納めます。
取得方法は、購入・建築・贈与などが該当します。贈与のように無償で不動産を取得した場合でも、課税される点に注意しましょう。
一方で、相続による取得は原則として不動産取得税がかかりません。相続は無償かつ法定の権利移転であるため、課税の趣旨にそぐわないとされているためです。
納税義務者
納税義務者は、さまざまな取得方法によって、不動産の所有権を得た人です。具体的には、購入の場合は買主、建築の場合は施主、贈与の場合は受贈者が納税義務者となります。
納税義務は、登記の有無にかかわらず発生します。登記をしていなくても実質的に不動産を取得したと認められる場合は、納税しなければなりません。
また、共有名義で不動産を取得した場合は、共有者全員が連帯して納税義務を負います。これは、それぞれの持分割合だけ納めれば良いということではなく、共有者一人ひとりに全額の納付義務が課されているという意味です。たとえば二人で一つの不動産を共有している場合、共有者の一方が税金を納めなかったとき、もう一方の共有者に全額の請求がいきます。
納税義務者には都道府県から納税通知書が送付されます。取得の事実があれば、納税通知書が届いた時点ですでに不動産を売却していたとしても、納税義務が発生する点に注意が必要です。
このように納税義務者は、登記の有無や所有の継続に関係なく、取得の事実に基づいて課税される仕組みになっています。
課税されるのは土地と建物
課税対象となるのは、土地と建物です。それぞれの種類について詳しく解説します。
土地の種類には、以下のようなものが含まれます。
- 住宅地(宅地)
- 田・畑などの農地
- 山林・原野
- 塩田・鉱泉地
- 池沼・牧場など
建物の種類は、以下のとおりです。
- 一戸建て住宅、マンションなどの居住用建物
- 店舗、事務所、工場、倉庫などの事業用建物
- 賃貸住宅や共同住宅など
このように、さまざまな種類の土地や建物について、所有権の移転が確認された場合は課税されます。
不動産取得税が非課税になることもある

一定の条件をみたす場合は、非課税になることもあります。これは、取得方法や取得者の属性によって、税負担が免除されることがあるためです。非課税となる代表的なケースは、以下の5つです。
- 相続による不動産取得
- 法人の合併や分割による不動産取得
- 土地区画整理事業による換地の取得
- 特定の法人による事業不動産の取得
- 不動産価格が免税点を下回る場合
相続による不動産取得
先述のとおり、相続による取得は非課税です。相続は、被相続人の死亡によって法的相続人に財産が移転するものであり、取得の意志があるかどうかは関係ありません。そのため、形式的な所有権の移動と位置づけられ、課税の対象外となるのです。
ただし、例外もあります。「特定遺贈」のなかでも、遺言書によって法定相続人以外が不動産を取得する場合は、税金が課される点に注意しましょう。
法人の合併や分割による不動産取得
合併や分割など企業再編にともなう所有権の移転は、事業継続のための形式的な変更に過ぎません。そのため実質的な取得とはみなされず、非課税となります。
しかし、非課税になるためには、一定の条件を満たす必要があります。たとえば金銭等不交付要件があり、組織再編の対価として支払えるのは株式のみで、現金などによる支払いは許可されないという要件です。株式は、承継会社または承継会社の親会社の株式に限られます。
土地区画整理法による換地の取得
土地区画整理事業は、土地の区画を整えて、公共施設の整備や宅地の利用増進を図る事業です。土地を再整備する際に、従前の土地の代わりに新しく割り当てられる土地のことを換地といいます。
換地は従前の土地の所有者がその権利を維持したまま、新しい土地に移る仕組みです。そのため売買や贈与のような新たな取得とはみなされず、税金はかかりません。このことは地方税法でも明記されています。
特定の法人による事業不動産の取得
学校法人や宗教法人、社会福祉法人など特定の法人が事業に使う不動産を取得した場合、非課税です。ただし本来の事業とは関係のない用途で取得した不動産は、課税対象になります。
不動産価格が免税点を下回る場合
不動産価格が以下の免税点を下回る場合は、免税対象となります。
土地:10万円
新築・増築・改築した家屋:23万円
家屋:12万円
ただし、免税された土地・家屋に隣接する土地・家屋を1年以内に取得した場合は、免税された土地・建物と合わせて1つの土地・家屋とみなされます。その際、不動産価格が免税点を超えた場合は課税対象となるため注意しましょう。
不動産取得税の計算方法について

税額がいくらかかるのか知りたい方は、固定資産税評価額がわかれば、自分で計算することができます。事前にいくらかかるのか知っておくと、時間に余裕を持って納税資金を準備することができます。納税通知書が来ても焦らずに対応できますよね。
ここからは税額の計算方法と計算例をご紹介します。
計算方法
固定資産税評価額に税率を掛けて算出します。基本的な計算式は、以下のとおりです。
不動産取得税=固定資産税評価額(課税標準額)×税率4%
ただし土地と住宅家屋には税率の軽減措置があり、以下の税率が適用されます。
| 土地 | 家屋(住宅) | 家屋(非住宅) |
|---|---|---|
| 3% | 3% | 4% |
さらに、宅地を取得した場合は、土地の課税標準額が固定資産税評価額の1/2になります。
固定資産税評価額は市町村ごとに設定されるもので、実際の購入価格とは異なる点に注意しましょう。
固定資産税評価額の調べ方は、自治体から送付される固定資産税の納税通知書に記載されています。売主からから引き渡しを受けた資料のなかに、固定資産税の納税通知書が入っていれば、「評価額」の欄を確認しましょう。
市区町村役場で、固定資産課税台帳の閲覧をすることもできます。市区町村役場で固定資産評価証明書を取得するのも手です。ただし、いずれの場合も手数料がかかるのが注意点です。
まだ不動産を取得していない段階で、土地の固定資産税評価額を知りたい場合は、実勢価格からおおよその額を導き出す方法もあります。固定資産税評価額は実勢価格の70%程度といわれているため、販売価格の70%を掛けた金額が、固定資産税評価額の目安となります。一方、新築家屋の固定資産税評価額は、工事金額の50%〜60%程度が目安です。
不動産取得税には軽減措置もある

不動産取得税にはいくつかの軽減措置が用意されており、それにより税負担を大幅に軽減することが可能です。
ここからは、以下のケースについて詳しく見ていきましょう。
- 新築住宅を取得したとき
- 中古住宅を取得したとき
新築住宅を取得したとき
住宅を新築または増改築した場合は、家屋の固定資産税評価額から1,200万円差し引いた金額が課税標準となります。
家屋の不動産取得税=(固定資産税評価額ー1,200万円)×3%
適用対象となる住宅の面積要件は、以下のとおりです。
貸家以外の住宅:50㎡以上240㎡以下
貸家の一戸建て住宅:50㎡以上240㎡以下
貸家のマンション・アパート:40㎡以上240㎡以下
上記の面積は、現況の床面積で判定します。登記床面積とは異なる場合があるため、ご注意ください。
さらに認定長期優良住宅を新築・購入した場合は、控除額が1,300万円に拡大します。
家屋(認定長期優良住宅)の不動産取得税=(固定資産税評価額ー1,300万円)×3%
新築住宅の土地は、税額から直接減額されます。
土地の不動産取得税=(固定資産税評価額×1/2)×3%ー控除額
控除額は以下のいずれか高い金額です。
- 4万5,000円
- 土地1㎡あたりの固定資産税評価額×1/2×住宅の課税床面積の2倍(一戸あたり200㎡が上限)×3%
中古住宅を取得したとき
中古住宅を取得した場合も、固定資産税評価額が軽減されます。
不動産取得税=(固定資産税評価額ー控除額)×3%
ただし、控除額がいくらになるかは、自治体によって異なります。
特に中古住宅が新耐震基準に適合しているか否かで、大きく異なります。
たとえば新耐震基準に適合する場合、控除額は100万円〜1,200万円です。
一方で新耐震基準に適合しない場合、3万円〜12万6,000円と大幅に縮小します。
また、中古住宅が立つ土地も合わせて購入した場合、土地の不動産取得税も軽減を受けることが可能です。
計算例
土地の購入価格3,000万円、建物の購入価格2,000万円の場合、税額を計算してみましょう。詳細条件は、以下のとおりです。
土地の種類:宅地
建物の種類:新築住宅
土地の固定資産税評価額:2,100万円
建物の固定資産税評価額:1,200万円
土地の不動産取得税:
2,100万円×1/2×3%ー4万5,000円=27万円
建物の不動産取得税:
(1,200万円-1,200万円)×3%=0円
土地のほうの控除額は、土地1㎡あたりの固定資産税評価額×1/2×住宅の課税床面積の2倍(一戸あたり200㎡が上限)×3%<4万5,000円という前提で計算しました。
建物のほうは、固定資産税評価額から1,200万円を差し引くと0円になるため、税額は0円です。
不動産取得税はいつ払う?不納税する方法

納税のタイミングは、取得直後ではありません。所有権移転登記が完了してから、都道府県が納税通知書を発行し、それが届いてから支払います。納税通知書が届く時期は、だいたい取得後3カ月〜6カ月以内です。
納税通知書には、課税標準額や税率、納付税額、納付期限などが記載されています。あわせて軽減措置の適用状況を確認することも可能です。先ほどご紹介した非課税となるパターンや、税制優遇などで非課税となった場合には、納税通知書は送付されません。
納付期限は通知書到着から30日以内とされているケースが多いです。納付期限を過ぎると延滞金が発生するため注意しましょう。延滞金は納付期限からどれくらい遅れたかによって異なります。期限の翌日から2カ月以内は年2.4%、2カ月を過ぎると年8.7%です。
納付方法は、主に以下のような選択肢があります。
- 金融機関窓口
- 都道府県税事務所
- コンビニ納付
- クレジットカード決済
- 電子納税
コンビニ納付は、税額30万円以下の場合に限られます。電子納税は事前登録が必要ですが、自宅で納付できるため便利です。
軽減措置の申請方法

先ほど紹介した軽減措置を受けるには、条件を満たしているだけでは不十分で、納税義務者自らの申請手続きが必須です。申請を忘れると、本来受けられるはずだった税制優遇が受けられず、余分な税負担を強いられることになります。ここからは、申請手続きの流れと注意点について解説します。
申請手続きの流れ
申請手続きの流れは、以下のとおりです。
- 不動産の取得
- 提出書類の準備
- 申請書類の提出
- 審査と結果通知
- 納付手続き
それぞれの流れごとに、どのような手続きをするのか、詳しく解説します。
不動産の取得
不動産を取得し、所有権の移転登記をおこないます。取得した不動産の面積などを確認し、軽減措置の要件を満たしているかどうか確認しましょう。
提出書類の準備
軽減措置の要件を満たしていることが確認できたら、申請に必要な提出書類を準備します。
提出書類は、以下のとおりです。
- 不動産取得税申告書
- 建築確認済証と確認申請書第三面
- 建築工事請負契約書
- 平面図(共同住宅、二世帯住宅、併用住宅の場合)
- 長期優良住宅認定通知書(認定長期優良住宅として軽減を受ける場合)
- 分筆・合筆の経過が確認できる書類(土地を分筆・合筆する場合)
- 賃貸借契約書(一戸建て以外の住宅で貸家の場合)
- 検査済証
- 登記事項証明書
- 建物引渡証明書
- 請負業者の印鑑証明書
取得した不動産の種類や、管轄の都道府県によって提出書類は異なります。詳しくは管轄の都道府県のホームページなどで確認しましょう。
申請書類の提出
提出書類が揃ったら、管轄の都道府県事務所に提出します。提出期限は都道府県によって異なります。たとえば東京都は不動産を取得してから30日以内が提出期限です。
また自治体によっては電子申請を受け付けている都道府県もあります。パソコンやスマートフォンから好きなときに申請できるため、便利です。
審査の結果通知
申請書類を提出した後は、税務署が審査をおこないます。申請後1〜2カ月の間に審査がおこなわれ、その結果に応じて軽減後の税額が確定します。
納付手続き
審査が通れば、不動産取得税の一部または全額が軽減されます。一部が軽減された場合は、納税通知書が届きます。忘れずに税金を納めましょう。一方で、全額が免除された場合は、納税通知書は送付されません。そのまま手続きは終了となります。
納税後に還付を受けることも可能
不動産取得税を支払った後に、軽減措置が利用できることに気づいた場合は、払いすぎた税金の還付を受けることも可能です。その場合は、還付請求が必要になります。
還付請求は、還付請求できるようになった日から5年以内です。
まとめ
不動産取得税は、土地や建物を取得したときに一度だけ課される税金で、購入・建築・贈与などが対象になります。一方で相続や法人の合併など、一定の条件下では課税されません。
税額は固定資産税評価額に税率を掛けて算出されます。住宅や宅地には軽減措置が適用されることがあります。新築住宅では最大1,200万円(認定長期優良住宅は1,300万円)の控除があり、中古住宅の場合は耐震基準の適合状況によって差引される額が変わります。
納税は取得後3〜6カ月以内に納税通知書が届いてからです。納税通知書は、忘れた頃に届くのが特徴です。取得後に納税資金を用意しておき、要件を満たす場合は税制優遇の申請をおこなうなど、準備作業を忘れないようにしましょう。