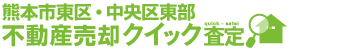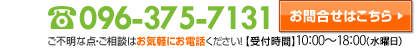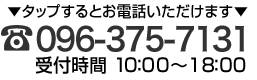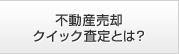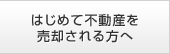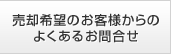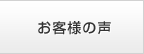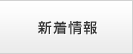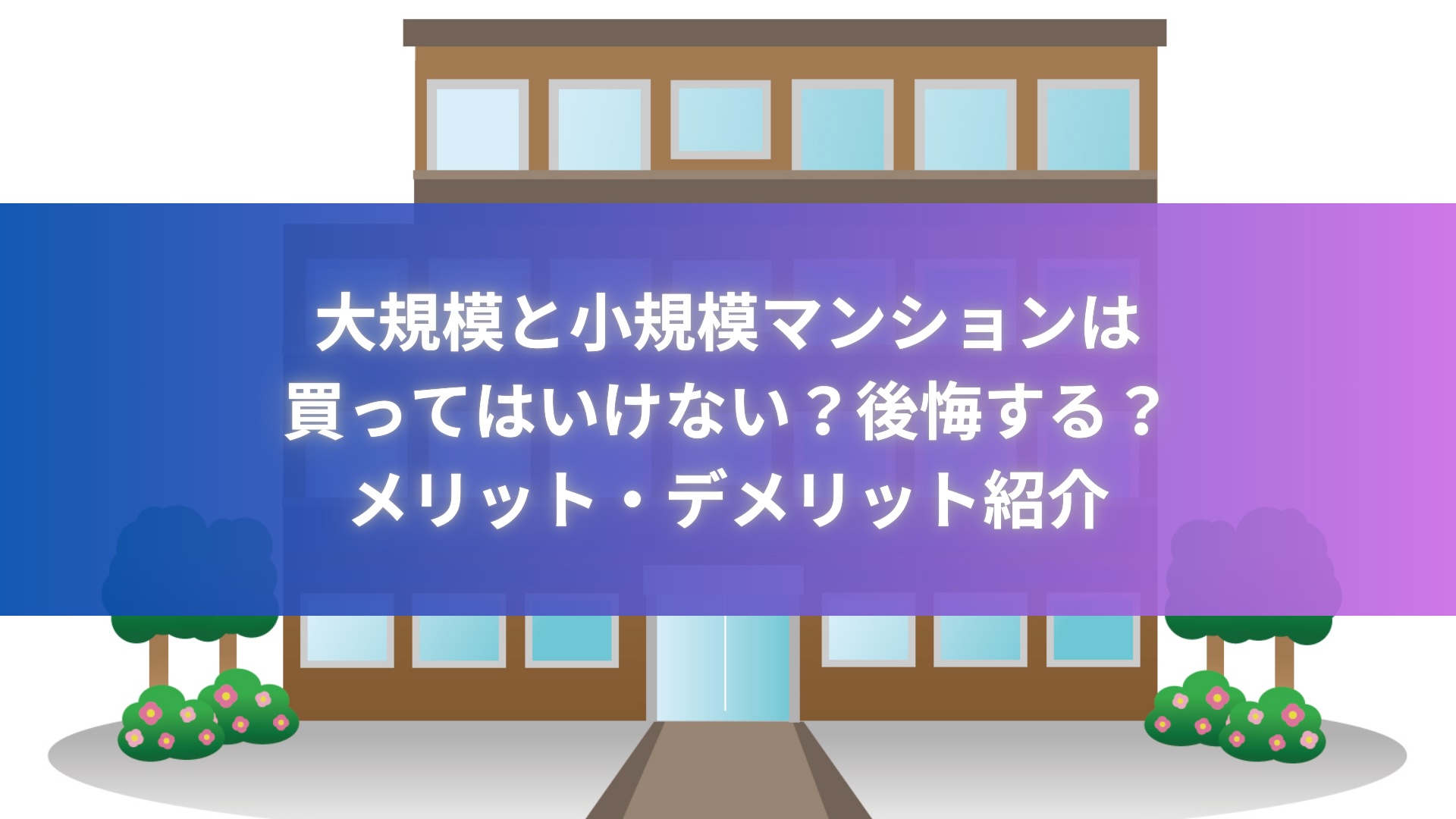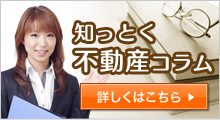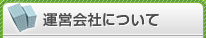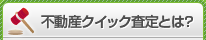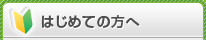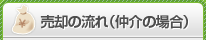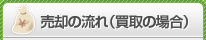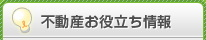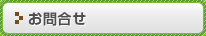熊本市不動産売却クイック査定です。
マンションは規模によって住み心地や費用面に違いがあるため、どのような基準で選べば良いか悩む方も多いのではないでしょうか。
中には「大規模マンションや小規模マンションは買ってはいけない」といった意見を耳にしたことがある方もいるでしょう。しかし、実際にはそれぞれにメリット・デメリットが存在し、ライフスタイルや価値観によって向き・不向きが分かれるものです。
本記事では、大規模マンションと小規模マンションのメリット・デメリットを紹介します。マンション選びで後悔しないための参考情報としてご活用ください。
目次
大規模マンションは買ってはいけない?後悔する理由とは?デメリット

大規模マンションを購入して後悔する人は、以下のような不満を抱えていることが多いです。
- 広すぎる
- 混雑する時間がある
- 住民同士の繋がりがあまりない
- 震災や災害等に弱い
- 管理費や修繕積立金が高い
- マンション内で話しがまとまりにくい
広すぎる
大規模マンションの特徴といえば、良くも悪くも圧倒的な広さです。どこまでも続く共用廊下、高層階までそびえ立つ建物。複数の棟に分かれていたり、広大な駐車場があったりして、移動には一苦労です。
敷地外に出るのに時間がかかるため、ちょっとした外出でもおっくうに感じることがあるでしょう。
混雑する時間がある
大規模マンションは、エレベーターの混雑が予想されます。朝の通勤ラッシュは、多くの人がエレベーターを利用するため、各階に頻繁に停まり、地上に降りるだけでも多大な時間がかかってしまいます。
ようやく来たと思ったら満員で乗れず、さらに待たされることも少なくありません。乗りたいときに乗れないストレスは想像以上で、日常生活の大きな不満につながるでしょう。
特に高層階に住んでいる人にとって、エレベーターは無くてはならない移動手段です。低層階であれば階段の利用も可能ですが、高層階では現実的ではありません。そのためエレベーターへの依存度は非常に高くなります。
住民同士の繋がりがあまりない
大規模マンションは住戸数が多いため、住民同士の繋がりが希薄になりやすいです。隣人の顔すら知らないというケースも珍しくありません。
たとえマンションの共用施設が充実していても、利用者は分散しやすく、自然なコミュニケーションは生まれにくいでしょう。イベントや自治会活動を開いても、誰が参加するかわからないため、参加率が低い傾向があります。
このような状態だと、防犯面のリスクが高くなります。住民同士が多すぎて、部外者が入ってきても気づきにくくなるからです。
震災や災害等に弱い
高層の大規模マンションは、地震のときに揺れが大きくなりやすい傾向があります。さらにエレベーターが停止すれば、高層階へのアクセスは非常に困難になります。震災後、自宅避難となった場合は、自宅まで物資を運ばなければなりません。そうなればエレベーターを使えないことが、生活に大きな支障をきたします。
停電や断水が発生すると、復旧までに時間がかかることも。避難経路や防災設備の管理も複雑になりがちで、不安を感じる人も多いでしょう。
管理費や修繕積立金が高い
管理費は、管理員の人件費や設備の点検・清掃など、マンションの日常的な管理業務に充てられる費用です。一方、修繕積立金は一定の周期で行われる外壁補修や防水工事など、大規模修繕に備えた積立金になります。
大規模マンションは共用設備が充実しているため、これらの維持管理にかかるコストが高額になりがちです。フィットネスジムやラウンジ、ゲストルームなど豪華な設備は魅力的ですが、使わない住民にとっては無駄な負担に感じられることもあります。
さらに、建物の規模が大きければ修繕工事の際には高所作業や広範囲な足場の設置が必要となり、その分工事費用も跳ね上がります。建物のデザインが複雑である場合、専門的な工事や部材の調達が必要となり、想定以上の費用が発生するケースも少なくありません。
マンション内で話がまとまりにくい
住民数が多い大規模マンションでは、マンション内の意思決定がまとまりにくいというデメリットがあります。管理組合で何かを決める場合、その決議内容によって必要な賛成票の割合が定められています。
たとえば、管理規約の変更や大幅な共用部の改修を行うには、4分の3以上の賛成が必要です。住民の数が多いほど意見が分かれやすく、賛成票を集めるのが困難になります。その結果、改善や修繕がなかなか進まないケースもあるのです。
大規模マンションを購入するメリット

大規模マンションは、規模の大きさを活かして以下のようなメリットを享受できます。
- 共用施設や管理体制が充実している
- セキュリティ対策が充実
- 資産価値を維持しやすい
共用施設や管理体制が充実している
大規模マンションは、共用施設が充実していることが多いです。住戸数が多いほど1戸あたりの管理費負担が軽くなり、スケールメリットを発揮できるからです。たとえば300戸規模のマンションで管理費1万円なら、月額合計は300万円となり、維持管理費に十分な予算が確保されます。
共用施設の代表例を挙げると、以下のとおりです。
- ラウンジ
- フィットネスジム
- ゲストルーム
- キッズルーム
- 図書館
- 保育施設
- 屋内駐輪場
同じ建物内にこれらの共用施設があれば、生活利便性が大きく向上するでしょう。さらに、複数棟で構成されるマンションでは、敷地内に公園やクリニックなどが併設されることも。子育て世帯から高齢者世帯まで、幅広い層に対応した魅力的な住環境です。
セキュリティ対策が充実
セキュリティ対策が充実しており、安全に暮らせる点も大規模マンションのメリットです。たとえば管理人やコンシェルジュがエントランスに常駐していることで、不審者が入りにくい体制になっています。
24時間有人管理の体制を採用していて、日中は管理人、夜は警備会社が管理しているマンションも多いです。24時間体制で管理する人がいることは、一人暮らしや小さい子どものいる家庭にとってとても心強いです。
また、エントランスのオートロックをはじめ、エレベーターの着床制限や防犯カメラの設置など、複数のセキュリティシステムで守られているマンションも。近年は強盗事件も増加傾向にあるため、セキュリティが充実しているのは重要なポイントです。
資産価値を維持しやすい
大規模マンションは資産価値を保ちやすく、将来的に売却や賃貸をする際も有利に働く可能性があります。先ほど紹介した共用施設やセキュリティの充実が、資産価値として高く評価されるためです。また、タワーマンションは視認性が高いため、地域のランドマークとして認識され、資産価値の向上につながることもあります。
ただし、すべての大規模マンションが資産価値を維持できるわけではありません。立地条件や修繕状況に問題がある場合は、資産価値が低下する恐れも。資産価値を維持しやすいマンションかどうかは、慎重な見極めが必要です。
小規模マンションは買ってはいけない?後悔する理由とは?デメリット
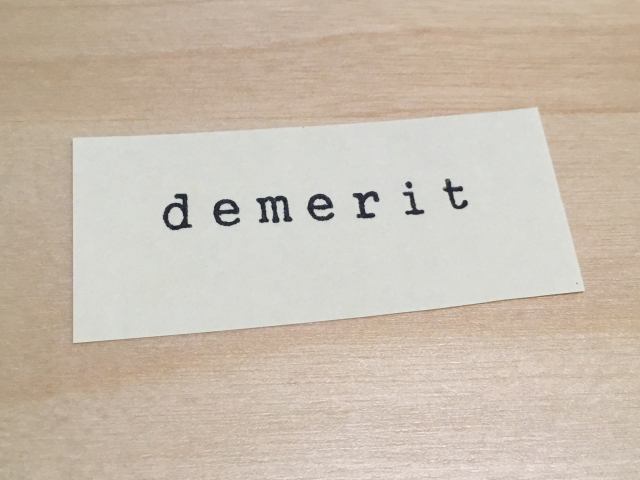
大規模マンションとは正反対の小規模マンションはどうなのでしょうか?小規模マンションにもデメリットはあるため、買って後悔する人もいます。
- 管理費・修繕積立金が高い
- 共用施設が充実していない
- 管理組合など負担がある
- セキュリティ対策が乏しい
- 資産価値を維持しにくい
管理費・修繕積立金が高い
住戸数が少ない分、1戸あたりの管理費負担が重くのしかかります。費用を分担できる人数が限られるため、管理費や修繕積立金が高くなる傾向です。
国土交通省の令和5年度マンション総合調査によると、マンションの形態ごとの管理費と修繕積立金の平均は以下のとおりです。
| 形態 | 管理費総収入/月/戸あたり | 修繕積立金総収入/月/戸当たり |
|---|---|---|
| 20階建以上 | 24,585円 | 13,834円 |
| 11~19階以上 | 16,597円 | 12,626円 |
| 6~10階以上 | 16,944円 | 13,637円 |
| 4~5階以下 | 17,529円 | 13,864円 |
| 3階以下 | 20,112円 | 14,231円 |
| 平均 | 17,214円 | 13,300円 |
出典:国土交通省「令和5年度マンション総合調査・管理組合向け調査の結果」(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001750163.pdf)
管理費は20階以上が最も高く、次いで3階以下の小規模マンションが高くなっています。修繕積立金については、3階以下が最も高額という結果でした。
以上のデータからも、小規模マンションは大規模マンションと同程度もしくはそれ以上に管理費や修繕積立金が高いことがわかります。
共用施設が充実していない
敷地面積が狭かったり階数が低かったりして、共用施設を確保するだけの面積の余裕がありません。また、住戸数が少ないため、豪華な共用施設をつくっても1戸あたりのコスト負担が重くなるのも難点です。
もし共用施設があったとしても、小規模だったり設備が簡素だったりなど、満足度が高いとはいいきれません。共用施設を重視する方にとっては、大規模マンションのほうが魅力的に映る可能性があるでしょう。
管理組合など負担がある
小規模マンションの管理組合では、理事役員が少人数で構成されるのが一般的です。国土交通省が作成した「マンション標準管理規約(単棟型)コメント」によれば、理事の員数はおおむね10〜15戸につき1名が目安とされています。たとえば30戸のマンションであれば理事役員は3名程度です。
管理組合業務は修繕積立金の運用や官公署・町内会との渉外など多岐にわたります。人数が少ないと業務の分担が難しく、1人あたりの負担が重くなる傾向があります。
セキュリティ対策が乏しい
住戸数が少ないため共用の設備にお金をかけられず、セキュリティ対策が手薄になることがあります。たとえばコンシェルジュの常駐や24時間有人管理を採用している例は少なく、大規模マンションと比べると違いが出やすいです。
ただ、オートロックや防犯カメラの設置によって、一定の安全性が確保されている物件が多いです。小規模ならではの制約はあるものの、管理組合や居住者の防犯意識が高ければ、セキュリティ対策を強化することもできます。
資産価値を維持しにくい
ランドマーク性や充実した共用施設がある大規模マンション。それに比べると、資産価値を維持しにくいといわれることもあります。
しかし、小規模マンションのなかには駅近など利便性の高い場所に立地し、資産価値が安定している物件も少なくありません。一概に資産価値を維持しにくいとはいいきれないでしょう。
売却するときのネックがあるとすれば、管理費・修繕積立金が高額であることです。近年は住宅価格が高騰しているため、管理費・修繕積立金の高さを理由に、買い手がつきにくくなる恐れがあります。
小規模マンションを購入するメリット

小規模マンションには、以下のようなメリットもあります。
- 住民同士の繋がりがある
- 立地条件の良い場所が多い
- 混雑しない
住民同士の繋がりがある
住戸数が少ないので、他の居住者と顔を合わせる機会が多いです。その結果、自然と顔見知りになり、繋がりが生まれやすいというメリットがあります。
住民同士の繋がりは、防犯面でも良い効果をもたらします。居住者の顔を把握できるため、居住者以外が出入りしていると「見慣れない顔だな」という違和感を覚えやすくなるのです。
これを「人の目による防犯」といい、心理的な犯罪抑止効果が期待できます。実際、誰かに見られているかもしれないという意識は犯罪を思いとどまらせる効果があります。
「小規模マンションはセキュリティ対策が課題」といわれることがありますが、人の目による防犯が機能していれば、防犯設備に頼らなくても安心して暮らすことができます。住民同士の繋がりがもたらす安心感は、特徴的なメリットともいえるでしょう。
立地条件の良い場所が多い
小規模マンションは好立地に建てられることが多いです。都市部では土地の需要が高く、開発用地の確保が難しくなっています。生活利便性の高いエリアでは土地の細分化も進んでおり、結果として狭小地を活用した小規模マンションの建設が増加している状況です。
また、都心部では土地価格の上昇しているため、大規模マンションの事業化ハードルが高くなっています。その点、限られた資金でも事業化しやすい小規模マンションは、現実的な選択肢として不動産デベロッパーに選ばれています。
さらに、「第一種低層住居専用地域」や「第二種低層住居専用地域」といった閑静で良好な住環境が保たれたエリアでも建設可能です。立地の良さに加え、住みやすさも支持されている理由の一つです。
こうした理由から、立地を重視する方にとって魅力的な選択肢といえるでしょう。「不動産は立地がすべて」と言われることもあり、購入時の判断材料として重要視されるポイントです。
混雑しない
居住者が少ないので、混雑に悩まされることは少ないでしょう。階数が低いため、エレベーターの待ち時間も短く、スムーズな移動が可能です。
万が一エレベーターに人が集中しても、気軽に階段移動に切り替えることが可能です。大規模マンションの高層階は階段を使うのは億劫ですが、小規模マンションであればエレベーターと階段どちらも使いやすく、フラットな選択ができます。
こうした混雑の少なさは、日常の利便性や快適性に直結するポイントです。自分のペースを大切にしながら、落ち着いた暮らしを送りたい方にとっては理想的な住まいといえるでしょう。
大規模マンションや小規模マンション購入するなら!後悔しないポイント

規模に関わらず、マンションを購入する際は、以下の点を重視して選ぶと後悔しにくいです。
- 資産価値が維持できるか調べる
- 管理費や修繕積立金を調べる
- 共用設備を使うか見極める
資産価値を維持できるか調べる
将来的に売却する可能性がある場合は、資産価値を維持しやすい物件を選ぶことが大切です。購入時には売却を想定していなくても、家族構成やライフステージの変化、住宅ローンの返済などが理由で、マンションを手放さざるを得ない状況になることもあります。
マンションの資産価値は、築年数や間取りだけでなく、立地や共用施設などさまざまな要素によって決まります。特に立地は重要で、都心部や駅近の物件は需要が安定しているため、資産価値が下がりにくいでしょう。反対に郊外や駅から遠い物件は需要が落ち込みやすく、資産価値の低下リスクが懸念されます。
また、マンションの場合は共用部が適切管理されているかどうかも、資産価値を保つうえで重要なポイントです。管理組合の運営状況も確認しておくと安心です。管理体制がしっかりしていないと、資産価値が下がる原因になりかねません。
管理費や修繕積立金を調べる
マンションを購入する際は、物件価格だけでなく、管理費や修繕積立金を調べることも大切です。管理費や修繕積立金は、毎月発生するランニングコストなので、家計への影響が大きいです。
国土交通省「令和5年度 マンション総合調査」によると、管理費は1万7,214円、修繕積立金は1万3,300円が平均になるので、一つの目安にすると良いでしょう。ただし、先述のとおり小規模マンションや大規模マンションは管理費・修繕積立金が高額になりやすい点も考慮が必要です。
徴収される金額がマンションの適切な維持管理に足る水準であるかどうかという視点も大切になります。徴収額が不足していると、清掃や設備点検の質が維持できなかったり、将来的な大規模修繕に備える資金が不足したりするリスクもあります。また、居住者の滞納状況も資金運営に影響するため、可能であれば事前に確認しておくと安心です。
こうした情報を把握する際には、管理組合の活動状況を知ることが大切です。不動産会社経由で管理費の議事録や長期修繕計画書を入手することで、資金の使途や適切な管理体制なのか判断する材料になります。
共用設備を使うか見極める
共用設備が充実しているマンションは、誰の目にも魅力的に映るものです。ラウンジやジム、ゲストルームなど、豪華な施設が備わっていると、生活の質が上がりそうな気がしますよね。
しかし、共用設備が充実しているマンションは管理費・修繕積立金も高くなります。使わない設備に対して、長期的にコストを負担し続けるのは非常にもったいないことです。
マンション選びでは、共用設備を本当に使うかどうかを見極めることが大切です。特に大規模マンションは共用設備が豊富な傾向ですが、実際に利用する見込みがあるかどうかを冷静に判断することで、無駄な出費を省くことができます。
まとめ
大規模マンションはスケールの大きさゆえに、動線の長さやエレベーターの混雑など、生活するうえでストレスを感じることがあります。しかしスケールメリットを活かして、維持管理コストを効率的に集めることが可能なので、共用施設やセキュリティ対策が充実しているのが魅力です。
一方で小規模マンションは住戸数が少ないため、1戸あたりの維持管理コストの負担が重くなりやすいです。しかし、住民同士のつながりや、好立地に建てられる物件が多いことなど、小規模ならではの魅力も存在します。
大規模・小規模それぞれにメリットとデメリットがあるため、一概に「買ってはいけない」とはいいきれません。いずれの場合も、資産価値の維持が可能か、管理費や修繕積立金が適正かどうかを見極めることが、後悔しない物件選びにつながります。