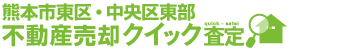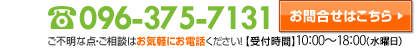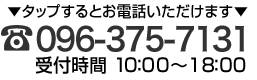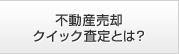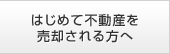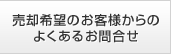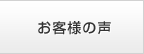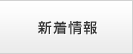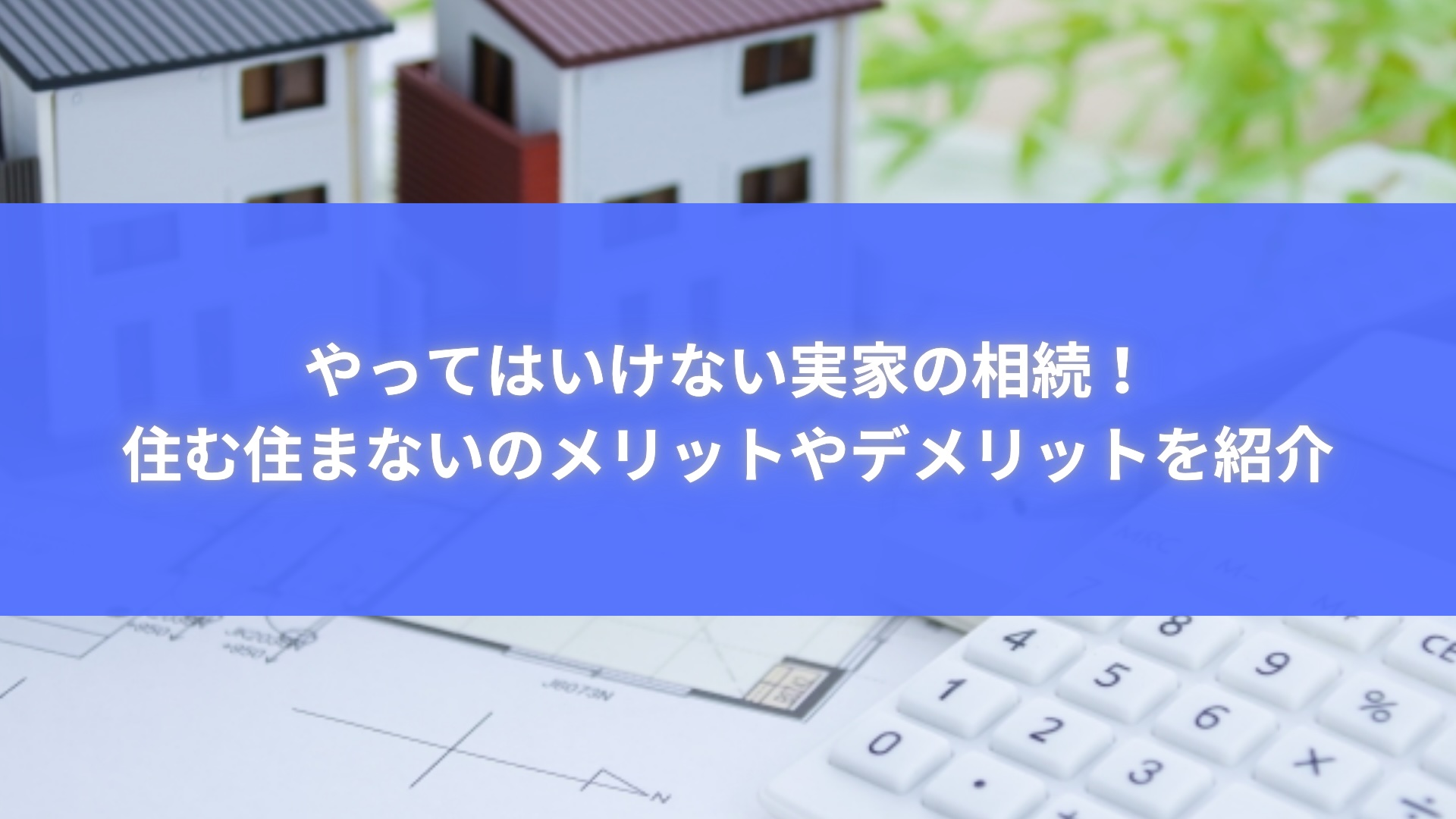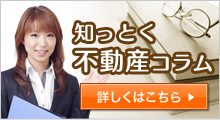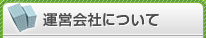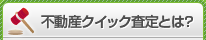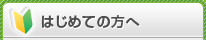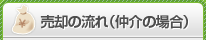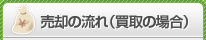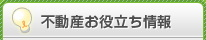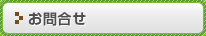熊本市不動産売却クイック査定です。
実家を相続したものの、「やってはいけないことってあるの?」「何から始めれば良いのかわからない」と悩む人も少なくありません。相続は人生で何度も経験するものではないため、無理もないでしょう。しかし、間違った相続を行うとトラブルに発展するリスク高くなるため注意が必要です。
この記事では、実家の相続でやってはいけないことや実家の活用方法、相続した実家に住むときの注意点など、相続に関することを詳しく解説します。実家の相続を巡る問題は、早めに解決することが重要です。やってはいけないことは何なのか、問題点がどこにあるのか、ひとつずつ確認して今後の対処法を考えておきましょう。
目次
やってはいけない!実家の相続での注意点を紹介

実家の相続でやってはいけないことは、以下の5つです。
- 共有名義にする
- 相続登記をしない
- 活用方法を決めない「とりあえず相続」
- 無計画に解体する
- 相続した後すぐに実家を売却する
では、なぜ「やってはいけない」のか、それぞれ項目ごとに解説していきます。
共有名義にする
共有名義とは、1つの不動産を複数人が共同で所有することをいいます。例えば、兄弟で土地を2分割して、共有名義にした場合を例として考えてみましょう。相続するときは、兄が管理することで意見はまとまっていました。
しかし、家の老朽化によって管理に手間がかかるようになります。さらに、固定資産税などの維持費もかかるため、兄は「売却したい」と考えはじめます。しかし、弟が「思い出の詰まった家を売却したくない」と言って、兄弟の意見が分かれれば家を売却することはできません。
このように、共有名義は「共有者全員の同意」がないと売却したり、貸し出ししたりすることはできません。相続した実家の活用方法について、共有者同士の意見が合わず揉め事に発展するのはよくある相続トラブルです。したがって、安易な判断は避け単独名義にするのか、共有名義にするのかよく話し合うことが重要です。
相続登記をしない
令和6年4月より、相続登記が義務化されました。これは、所有者が亡くなったあとに相続登記されない「所有者不明土地」が全国で増加していることが一つの要因です。相続によって不動産を取得した相続人は、相続を知った日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。
もし、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となります。したがって、不動産を相続したら早めに登記申請を行いましょう。詳しくは、東京法務局の下記Webサイトをご確認ください。
東京法務局 相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始)~なくそう所有者不明土地!~
活用方法を決めない「とりあえず相続」
相続は、予期せぬタイミングで問題に直面することもあります。また、相続に備えて実家の活用方法を話し合っている人が少ないというのも実情です。しかし、活用方法を考えておかなければ、「とりあえず相続」してそのまま空き家になってしまうケースも少なくありません。
空き家を所有すると、メンテナンスが必要なだけでなく、固定資産税などの税金がかかります。さらに、空き家を放置すれば、倒壊、外壁落下、害虫被害、悪臭など様々なリスクが考えられます。そのため、実家を相続する場合は、活用方法を具体的に決めておくことが非常に重要です。
無計画に解体する
前述したように、老朽化した空き家を放置すると様々なリスクがあります。それらのリスクを懸念して、「解体して更地にしよう」と考える方もいるかもしれません。しかし、無計画に空き家を解体するのは要注意。なぜなら、住宅用地には固定資産税の軽減措置が適用されているからです。
固定資産税の軽減措置では、住宅用地であれば課税標準を3分の1に減額する他、200㎡以下の部分に対する課税標準は6分の1に減額することとされています。すなわち、実家を壊して更地にしてしまうと毎年支払う固定資産税が6倍に上がってしまう可能性があるのです。また、解体するには高額な費用がかかります。下表では、30坪の家を解体するには、どれくらいの費用がかかるのか構造別にまとめました。
| 構造 | 坪単価 | 30坪の家 |
|---|---|---|
| 木造 | 3~5万円/坪 | 90~150万円 |
| 鉄筋造 | 5~7万円/坪 | 150~210万円 |
| 鉄筋コンクリート造 | 6~8万円/坪 | 180~240万円 |
空き家を放置するのも危険ですが、無計画に解体するのもリスクが伴います。したがって解体する前に、不動産会社や専門家に相談することをおすすめします。
相続した後すぐに実家を売却する
「相続税」という言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。被相続人(亡くなった人)から不動産や現金などの財産を相続する場合、相続税という税金を納めなくてはいけません。しかし、相続税が高額だと相続した不動産を売却しなければ相続税が支払えないというケースもあるでしょう。
そのため、一定の要件を満たす宅地はついては、相続する土地の評価額を最大8割減額することができます。これを、「小規模宅地等の特例」といいます。この小規模宅地等の特例を受けるために、「相続税の申告期限(被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から数えて10ヶ月以内)まで、その家に住み保有し続けること」という要件があります。
したがって、10ヶ月未満で実家を売却してしまうと、小規模宅地等の特例が適用できなくなる可能性があります。相続税の減税割合によっては、10ヶ月を経過してから売却した方が良いケースもあるため注意しましょう。
相続した実家の活用方法

相続した実家には、以下のような活用方法があります。
- 自分で実家に住む
- 賃貸住宅として貸す
- 土地として貸す
順番に見ていきましょう。
自分で実家に住む
実家に住むのは、最も手間がかからない活用方法です。これまで賃貸で生活していた人は、実家に住むことで家賃を払う必要がなくなります。また、自分で住めば、固定資産税の軽減措置を引き続き受けられることもメリットと言えるでしょう。
ただし、実家以外に財産がなく相続人が複数いるときは、公平な遺産分割が難しくなります。相続人同士で折り合いがつかなければ、他の相続人に代償金を支払う必要もあるでしょう。
賃貸として貸す
実家を貸家にするのもおすすめです。老朽化や汚れが目立つ場所は、リフォームや修繕しておくと借主が見つかりやすくなります。また、実家を事業用として貸し出すのも良いでしょう。近年は、古民家を利用したカフェや宿泊施設、福祉施設などが増えています。
事業用として貸し出しすれば、建物の修繕や改修工事は事業者が行ってくれるケースが多いです。空き家のまま放置しておくよりも、賃貸収入が得られる、家の劣化が進みにくいなど、メリットも多いでしょう。
ただし、事業者が撤去したあとは、次の借手が見つかりにくくなるというデメリットがあります。遠方に住んでいて自分で住めない、空き家の活用方法がわからないという方は、貸し出すことも検討してみましょう。
土地として貸す
広い土地や利便性の良い場所にある実家は、解体して土地として貸す方法もあります。特に、商業施設や学校、会社、アパートやマンションが建ち並ぶ地域では、駐車場としての需要が高いです。そのため、有効活用できそうな地域であれば、更地にして貸し出すことを検討してみましょう。
ただし、需要の低い地域では、無計画に解体すると税金が高くなる、借手が見つからないなどの可能性があります。解体する際は、専門家の意見を参考にして需要がある地域なのか見極めることが重要です。
相続した実家に住むときの注意点

相続した実家に住むのはメリットが多い一方で、以下の点には注意が必要です。
- 維持費がかかる
- 誰が住むかでトラブルになる
具体的な内容について解説します。
維持費がかかる
相続した実家が老朽化していたり、築年数が経過していたりする場合はリフォームや修繕が必要になる場合があります。家の状態によっては、すぐに住むことができないこともあるでしょう。
また、住宅を所有するには維持費がかかります。固定資産税、都市計画税に加えて、設備のメンテナンス費用なども考えておかなければなりません。
誰が住むかでトラブルになる
共有名義の場合、誰が実家に住むかで揉める可能性があります。特に、利便性の良い家は、住みたいと考える人も多いため、あらかじめ誰が住むのかを決めておくことをおすすめします。
実家を相続するなら!対策方法を紹介

相続者同士で折り合いがつかなければ、思い出の詰まった実家を空き家のまま放置したり、持て余してしまったりする可能性が考えられます。実家を持て余さないためには、以下の対策を意識してみてください。
- 親の生前に間に話し合っておく
- 相続放棄も検討する
それぞれの具体的な内容について確認していきましょう。
親の生前に間に話し合っておく
親の生前に相続について話し合うことは「縁起が悪い」と感じる方もいるかもしれません。しかし、多くの親は、自分たちの残した財産で兄弟や家族の仲が悪くなることを望んでいないでしょう。
親の死後、実家を管理・使用するのは残された家族です。そのため、生前に「親の意向」と「子どもの意向」をしっかり反映させながら、お互いが納得できる答えを検討しておくことが大切です。
相続放棄も検討する
親の残した財産は、必ずしも相続しないといけないわけではありません。管理できない、維持費が払えないなど、引き継ぐことにデメリットが多いと感じれば、相続放棄するのも一つの選択肢です。
しかし、相続放棄すれば、実家だけでなく全ての財産を放棄することになります。プラスになる財産が多ければ相続する価値は十分にあるため、相続放棄するかどうかは慎重に判断しましょう。
実家を相続した後に手放したいと思ったら

実家を相続したものの、「手放したい」と思うこともあるでしょう。そんなときは、以下の方法を検討してください。
- 売却する
- 空き家バンクを活用する
- 寄付する
項目ごとに解説します。
売却する
活用しない空き家は、古家付きのまま売却することができます。古家付きのまま売却できれば解体費用もかからないため、立地条件やエリアによっては高値で売却できる可能性もあります。
ただし、すぐに売却できるとは限りません。一般的に不動産の売却期間は、3~6ヶ月が一つの目安です。中には、1年以上売れないというケースもあるため、すぐに現金化したい人やスケジュールに余裕のない人は注意が必要です。
空き家バンクを活用
空き家バンクは、空き家を貸したい人と売りたい人が登録し、空き家に住みたい人を探すためのマッチングサービスです。近年日本で問題になっている空き家の増加を少しでも減らすための取り組みであり、各地で多くの空き家が登録されています。
各自治体の空き家担当部署が窓口で、空き家を貸したい・売りたい人、空き家を借りたい・買いたい人をつなぎます。なお、空き家バンクへの登録は無料で行えますが、不動産取引となると不動産会社の仲介が必要になります。不動産会社へ仲介を依頼すれば仲介手数料が発生しますので、この点には注意が必要です。
寄付する
実家を手放す方法には、国や自治体に寄付するという選択肢もあります。ただし、無条件で寄付を受付しているわけではありません。国や自治体が求める条件と合致すれば、無料で引き取ってもらえる可能性があります。まずは、実家を管轄している自治体窓口で相談してみましょう。
まとめ
今回は、実家を相続するときにやってはいけないことを中心にお伝えしました。相続は人生で何度も経験することではないため、実家の活用方法に悩む人は多いものです。しかし、相続するか相続放棄をするか考えられる猶予期間は3ヶ月しかありません。この3ヶ月を短いと感じるか、長いと感じるかは、事前に対処方や活用方法を考えているかで大きく異なるでしょう。後悔の少ない選択をするためにも、日頃から実家の活用方法を家族や相続人同士で話し合っておくことが重要です。
また、相続するか悩んだときは、「今後住む予定があるか」「実家の活用方法が決まっているか」を考えてみてください。今、賃貸物件に住んでいて将来的に実家に住みたいと考えていれば、相続する必要があると言えるでしょう。一方、遠方に住んでいて既に自分の家を持っている、今後誰も住む予定がない、などであれば相続放棄するのも一つの手段です。この記事を一つのきっかけとして、相続について考えてみましょう。