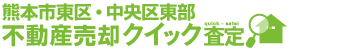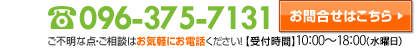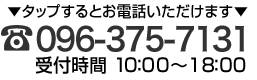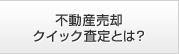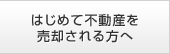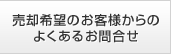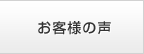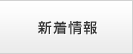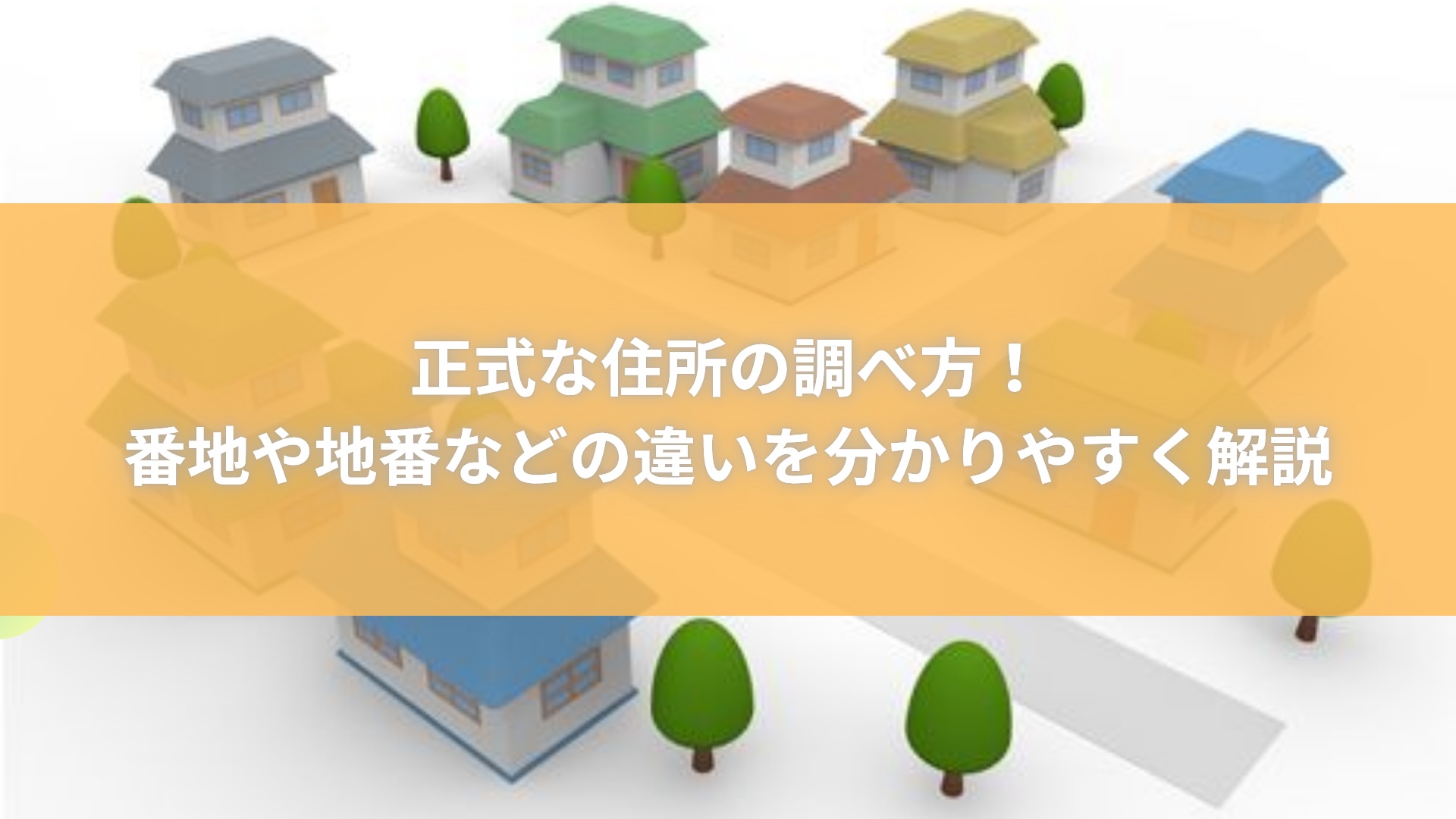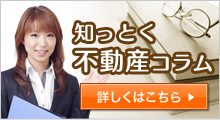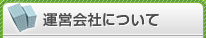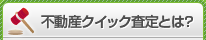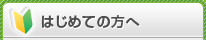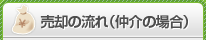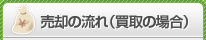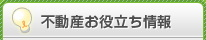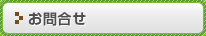熊本市不動産売却クイック査定です。
正式な住所は、登記手続きや契約書類などさまざまな場面で必要になります。「相続した土地の住所がわからない」という困りごともあるのではないでしょうか。
本記事では正式な住所の調べ方について解説します。用語の違いも分かりやすく解説しているので、ぜひ参考にしてください。
目次
正式な住所表記とは?「地番」と「住所」がある

正式な住所には、2つの書き方があります。一見似ているようですが、それぞれの書き方は基本的な概念が異なるため、TPOによって区別しなければなりません。
ざっくり説明すると、不動産取引では「地番」、郵便送付や住民登録などは「住所」が用いられます。ただ、2つの書き方のどちらを採用すべきか、判断が難しいことも少なくありません。
ここからは2つの書き方それぞれの概念をわかりやすく解説します。基本的な概念を理解することで、それぞれの書き方をどのような場面で使うのが適切か臨機応変に判断できるようになるでしょう。
「地番」とは?
地番は法務局が登記制度の運用をするために作った番号です。そのため、不動産を登記するときなどに、聞かれることが多いです。
登記簿上では土地を一筆という単位で数えるのですが、地番は一筆ごとにナンバリングされます。一筆の土地を二つに分筆した場合は、それぞれの土地に付されます。たとえば一丁目5番地の土地を分筆した場合、一丁目5-1番地と一丁目5-2番地という二つに区分されるイメージです。
あくまで登記制度の運用に基づき作られたもので、地理的な位置情報を示すものではありません。そのため、1-3番地の横が1-20番地など数字に連続性がない場合もあります。
地番がナンバリングされるのは、土地が登記され、法務局で登記情報が登録されるタイミングです。したがって全ての土地に付されているわけではありません。未登記の土地や国有地のなかには、無番地と呼ばれる土地もあります。
歴史を紐解くと、1871年の明治時代まで遡ります。米で納めていた年貢からお金で納める税金に変更する税制改正「地租改正」によって、地番が誕生しました。当時全国で一斉に土地の測量が実施され、政府が土地ごとに番号を振ったのが運用のはじまりです。
「住所」とは?
自治体が定める家屋の所在地です。家屋が建つ土地だけが持っているもので、何もない更地には住所はありません。
郵便や宅配の配送、行政手続きなど多岐にわたる用途で利用され、家屋の場所を特定する役割があります。地番よりも一般の人に馴染み深い書き方で、私たちの日常生活には欠かせません。
家屋の位置関係に沿って番号が規則正しくナンバリングされています。書き順は、最初に町名、次に街区符号、最後に住居番号です。町名は〇〇一丁目、街区符号は番、住居番号は号という用語で記載します。
|
〇〇一丁目 + 〇番 + 〇号 町名 街区符号 住居番号 |
町名は皇居に近い順や、街の中心部に近い順で決まる方法などがあります。街区符号の付け方は河川や鉄道などで街区の境界を設けたうえで、隣接する街区が一続きになるように順序よく数字が付けられます。この割り振り方は、道に沿って蛇行しながら番号が付けられる方式が一般的です。さらに一つの街区の周りの道路を、決められた距離(5〜10メートル程度)で分割し、時計回りに数字を振ります。家屋の入口に対応する数字が、その家屋の住居番号になる仕組みです。このような仕組みによって規則的な体系が作られています。
決定するタイミングは、その土地に家屋が建つときになります。土地を購入して家屋を新築する場合は、竣工の1カ月ほど前には決定するようなスケジュールです。自治体に新築届を出し、2〜3週間くらいで自治体から決定通知が来ます。
そもそも住所は、いつ頃から使われるようになったのでしょうか。スタートしたのは1962年(昭和37年)で、地番よりも後の登場になります。その当時、明治時代から用いられていた地番は、土地の分筆などで複雑化していました。こうした複雑さから、郵便物の配送で混乱が生じることも。そこで住居表示制度を取り入れ、家屋の所在をわかりやすくしたのです。
この制度は、住宅が密集する都市部を中心に普及していきました。一方で地方ではそこまで地番が複雑化しておらず、そのまま採用し続けるところもありました。このような経緯があり、現在も混在しているのが実情です。
正式な住所表記!「地番」「番地」「番」の違いとは?

公式な場面で住所を記入する際は、その書き方のルールを守ることも重要になります。普段住所を書く際は数字をハイフンで区切る人が大半だと思いますが、ハイフンは省略記号であるため、公式な場面で使うのはあまり好ましくないです。公式な場面では、数字の間にハイフンではなく決められた用語を入れます。ただ、用語の使い方を知らないと、どれを使うべきか迷ってしまいますよね。
それぞれ以下の用語を使います。
| 使う用語 | |
|---|---|
| 地番 |
〇〇一丁目 + 〇番地 町名 地番 |
| 住所 |
〇〇一丁目 + 〇番 + 〇号 町名 街区符号 住居番号 |
似たような響きの用語が出てきて、非常に紛らわしいですね。整理すると、番地は地番に、番は住所を書くときに用いられるものです。ここからは用語の見分け方と、それぞれの関係性について詳しく解説します。
「地番」と「住所」の違いとは?
区別するポイントをまとめると、以下のとおりです。
| 地番 | 住所 | |
|---|---|---|
| 1.誰が決めるのか | 法務局 | 自治体 |
| 2.何のために作られたか | 登記を管理するため | 家屋の位置を特定するため |
| 3.何を示しているか | 土地の所在 | 家屋の所在 |
| 3.いつ使うか |
不動産売買、相続 登記手続き 建築・開発計画 税務申告 境界確認など |
郵便配送 宅配サービス 行政サービス 身分証明など |
一番対照的な特徴は、地番を割り振るのは法務局、住所を割り振るのは自治体という点です。
何のために作られたかという目的も相違します。地番は土地の登記を管理する目的、住所は家屋の位置を特定する目的で作られた番号です。
示す対象も異なり、地番は土地、住所は家屋の所在を示してます。ちなみに登記上で家屋を管理する番号は家屋番号といい、地番とは別物です。住所については、家屋がない限りナンバリングされず、地番が採用されます。
使う場面も対照的で、地番は不動産取引や登記、住所は郵便配送や宅配サービスで使われます。たとえば不動産の所有権を確認したり、土地の境界を特定したりするときは地番が役立ちます。一方で郵便物の配送など、日常生活でよく使われるのは住所です。
「地番」と「番地」の違いとは?
番地は、地番を書くときに使う用語です。具体的には、〇〇一丁目1番地のように、町名の後ろに配置されます。
「地番」と「番」の違いとは?
とても似た響きですが、別物です。区別するポイントは、どちらの表示に使われる用語かという点です。先ほど説明したとおり、住所を書く際に町名の次に続くのが番です。
正式な住所「地番」の調べ方

正式な住所として地番を知りたい場合の調べ方は、以下のとおりです。
- 法務局へ問い合わせる
- 「地番検索サービス」を使って調べる
- 固定資産税の納税通知書を確認する
- 「登記済証」か「登記識別情報通知書」を確認する
- ブルーマップを使って調べる
- 「公図」を閲覧して調べる
法務局へ問い合わせる
アナログではありますが確実な調べ方は、法務局に問い合わせることです。法務局は土地の登記情報を管理しているため、聞けば教えてもらえる可能性があります。
管轄の法務局に電話して、問い合わせてみましょう。聞き方としては「地番の照会をお願いできますか?」と言えば良いです。ただ一部の法務局では照会に応じてくれないところもあります。
「地番検索サービス」を使って調べる
法務局が提供する「地番検索サービス」を使えば、インターネットで手軽に調べられます。こちらのサービスは、登記情報などを調べられる「登記情報提供サービス」の機能の一つです。
オンラインで手間をかけずに調べられるのがメリットです。ただ最初に「登記情報提供サービス」の利用申し込みが必要になります。検索だけであれば無料ですが、登記簿の閲覧は有料になる点にも注意しなければなりません。
また、サービス提供エリアは順次拡大中であるものの、対象外のエリアも存在します。調べたいエリアが対象内かどうかを確認してから利用しましょう。
固定資産税の課税明細書を確認する
自分が所有している土地であれば、固定資産税の課税明細書と照らし合わせて確認することも可能です。固定資産税の課税明細書とは、不動産所有者に対して毎年送られている書類で、固定資産税の納税通知書に添付されています。
課税明細書の左上に「土地の所在」「家屋の所在」という欄に記載されているのが、所有している土地の地番です。
課税明細書を紛失してしまった場合は、自治体で発行してもらえる固定資産税台帳(名寄帳)で確認する方法もあります。固定資産税台帳(名寄帳)は個人が所有している土地・家屋をまとめた一覧表です。土地・家屋の所在地の欄に地番が記載されています。
ただし固定資産税台帳(名寄帳)の取得は有料です。自治体によって取得費用は異なりますが、だいたい1通300円程度かかります。
「登記済証」か「登記識別情報通知書」を確認する
同じく土地の所有者に限定されますが、登記済証または登記識別情報通知書を参照することで確認することもできます。いずれも登記が完了した証明書の役割を果たし、不動産の所有者だけが持っている書類です。
2004年の不動産登記法改正に伴い、2005年3月以降は登記済証から登記識別情報通知に変わりました。したがって不動産の取得時期が2005年3月より前であれば登記済証、2005年3月以降であれば登記識別情報通知が手元にあるはずです。
登記済証の場合は、「不動産の表示」という欄に地番が記載されています。登記識別情報通知書の場合は冒頭に記載のある「不動産」という欄を確認してください。
ただし登記済証または登記識別情報通知書に記載されている情報が正しいとは限りません。発行後に自治体の合併や土地区画整理事業によって情報が変化している場合もあるからです。
ブルーマップを使って調べる
ブルーマップを閲覧して、調査することもできます。住宅地図の上に青字で印刷されていることが「ブルーマップ」という名前の由来になっています。
ブルーマップは一冊3万円前後と高額なため、閲覧できる場所に出向いて調べるのが現実的です。ブルーマップを閲覧できる場所は、以下のとおりです。
- 国立国会図書館東京本館
- 法務局
- 公立図書館
- 市区町村役場
国立国会図書館東京本館では全国のブルーマップを閲覧可能です。国立国会図書館のサイトではブルーマップ目録を掲載しているため、該当地域があるか事前に確認してから調べに行きましょう。
法務局には、管轄地域のブルーマップが設置されています。一方で公立図書館や市区町村役場は、置いてあるところと置いていないところがあり、施設ごとに差がある状態です。
また、ブルーマップを使う方法には注意点があります。それは、記載されていない地域やブルーマップ自体が発行されていない地域が存在することです。ブルーマップで確認できない場合は、他の方法を使って調べなければなりません。
「公図」を閲覧して調べる
最後に紹介するのは、公図(公図)を閲覧する方法です。作成された明治時代の呼び名を継承して、「字図(あざず)」と呼ばれることも多いです。公図は地図のような図面で、土地の位置や形状が示されており、各土地にナンバリングがされています。
取得方法は、法務局から取り寄せる方法とインターネットの登記情報提供サービスからダウンロードする方法などがあります。法務局の窓口で申請すれば、全国の公図を取得することが可能です。登記情報提供サービスは手軽な方法ですが、先述のとおり利用申し込みが必要になります。
正式な「住所(住居表記)」の調べ方

普段住んでいる場所の住所は覚えていても、相続した土地は正式な住所がわからない場合もありますよね。そのような場合に正式な住所を調べる方法は、以下のとおりです。
- マイナンバーカードを使って調べる
- 家に届く郵便物で調べる
- 市区町村役場で住民票の写しを取得する
- 法務局へ問い合わせる
- 地番から住所を調べる
それぞれの方法を詳しく解説します。
マイナンバーカードを使って調べる
一番手っ取り早い方法は、マイナンバーカードを確認する方法です。
マイナンバーカードに記載されている住所は、住民票に登録されている住所と一致するため正式な住所といえます。マイナンバーカードの表面に記載されている住所欄を確認しましょう。〇〇一丁目〇番〇号というように記載されており、略式のハイフンではない正式な表記までわかります。
途中で住所変更している場合は、マイナンバーカードの裏面に記載された住所が最新の住所です。スマホやパソコンでマイナポータルにログインし、「わたしの情報」で最新の登録状況を確認することも可能です。
また、マイナンバーカードをまだ発行していない方は、個人番号通知書でも住所を調べられます。しかし住所変更手続きをしていない場合、記載されている住所は古い情報になるためご注意ください。
家に届く郵便物で調べる
家に届く郵便物を確認する方法もあります。とくに自治体からの郵便物は、住民票の住所宛てに発送されているため、正式な住所を確認するのに最適です。
たとえば税金に関する郵便物は、毎年送られてきます。住民税や年金、国民健康保険に関するお知らせなどが手元にないか確認してみましょう。
ただ税金などの支払い義務がない方は、自治体からの郵便物がない可能性もあります。その場合は他の方法で確認するしかありません。
市区町村役場で住民票の写しを取得する
住民票の写しにも正式な住所が載っています。市区町村役場の窓口で申請することで取得可能です。
マイナンバーカード所持者はコンビニエンスストアでも取得可能ですが、住所だけ調べたいのであればマイナンバーカードの住所欄を確認したほうが早いです。
住所の欄に記載されているのが、住民票に登録されている住所になります。〇〇一丁目〇番〇号というように、正式な表記で記載されています。
住民票の写しを取得する際は、手数料が必要です。手数料の金額は自治体によって異なりますが、だいたい300円前後で設定されています。
法務局へ問い合わせる
マイナンバーカードや市区町村役場からの郵便物が手元にない場合は、法務局に問い合わせてみるのも手です。
法務局では不動産の登記情報を管理するにあたり、所有者の住所も管理しているためです。ただ法務局でわかるのはあくまで登記上の住所であり、住民票の住所とは異なる場合もある点にご注意ください。
調べ方としては、管轄の法務局に電話をかけて地番照会を依頼します。自分が認識している住所を伝えれば、正式な住所を教えてもらえます。
地番から住所を調べる
地番だけがわかっている場合は、そこから住所を調べることもできます。
具体的に住所を確認する手段は、以下の2通りです。
- ゼンリンのブルーマップから調べる
- 地番参考図から調べる
ブルーマップは住宅地図と公図を重ね合わせているため、地番が記載されている場所から住所を調べることも可能です。管轄の法務局や図書館にあるブルーマップで確認してみましょう。
もう一つの方法は、地番参考図から調べる方法です。この図面は固定資産税を課税する目的で、自治体が作成している資料になります。インターネットで地番参考図を公開している自治体もあるので、手軽に調べられるのが魅力です。地図で位置関係を調べて、そこから住所を導き出します。
正式な住所「地番」が分かるメリット

正式な地番が分かると、以下のようなメリットがあります。
- 土地の価格が分かる
- 登記情報が分かる
- 建築条件が分かる
それぞれのメリットについて詳しく解説します。
土地の価格が分かる
地番が分かっていれば、土地の価格相場を調査する際にその精度が高まります。土地を売却したい場合や購入したい場合に、いくらで売れそうか、買えそうか考えるのに役立つでしょう。
たとえば、国土交通省の検索サイト「不動産情報ライブラリ」では、地価公示を調べることが可能です。地価公示には「所在および地番」という欄があり、そこに記載されている内容から近隣の土地の価格相場を調べられます。
実勢価格は地価公示の1.1〜1.2倍程度なので、どのくらいで取引がされているかも推察できるでしょう。
登記情報が分かる
地番を使って、登記情報を取得できます。登記情報に記載されているのは、以下のような情報です。
- 土地の面積
- 現在の所有者
- 過去の所有者
- 所有権以外の権利(抵当権など)
登記情報は土地を購入・売却・相続するときに役立ちます。たとえば購入したい土地がある場合に、現在の所有者が誰なのか調べることが可能です。登記情報はすべての人に開示されているので、所有者でなくても取得・閲覧できます。
不動産を売却する場合には、すぐに売れるか確認する材料にもなります。基本的にローンが残っている不動産は、そのままでは売れません。登記情報で抵当権の有無を確認すれば、ローンが残っていないかチェックできます。
登記情報は、隣地との境界を確定する際の参考資料になることも。登記情報と一緒に地積測量図が備え付けられていれば、土地面積の算定根拠なども明らかになります。
建築条件が分かる
土地を活用する際は、都市計画法や建築基準法のルールに従わなければなりません。なかには土地を取得しても、法規制によって家を建てられない場合もあります。建物を建てられたとしても、工事規制を受けたり、用途が限定されたりすることも少なくありません。
そのようなリスクを回避するために、事前にその土地がどんな法規制を受けるのか調べておくと安心です。地番は法規制を調べる際にも役立ちます。
家を建てる際の法規制の一例を挙げると、以下のとおりです。
- 容積率
- 建ぺい率
- 用地地域
- 斜線制限
- 高度地区
法規制の詳細は、市区町村役場の窓口で調べることが可能です。その際にどの土地か特定するために地番を伝えます。
事前に法規制を把握していれば、設計段階での調整が円滑に進み、余計な手間を省けます。また、必要な許認可の手続きも確認できるため、工事の進行もスムーズです。
まとめ
日本には2種類の正式な住所がありますが、それぞれ用途などが異なります。地番は土地の登記を管理するための番号で、法務局が定めます。一方で、家屋の場所を特定する役割があり、定めているのは自治体です。
地番の調べ方は法務局に問い合わせる方法が確実ですが、所有している土地であれば登記済証など手元にある書類で調べることもできます。住所はマイナンバーカードや自治体からの郵便物で調べる方法が一番早いです。
正式な地番がわかると、土地の価格や登記情報、建築条件を調査できるため、不動産取引に役立ちます。土地を購入・売却予定の方や、親族から土地を相続した方は、2種類の正式な住所の違いをしっかり理解し、臨機応変に情報を取得してください。