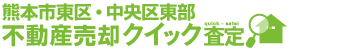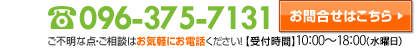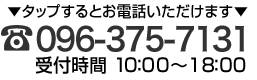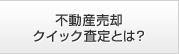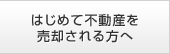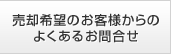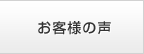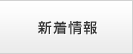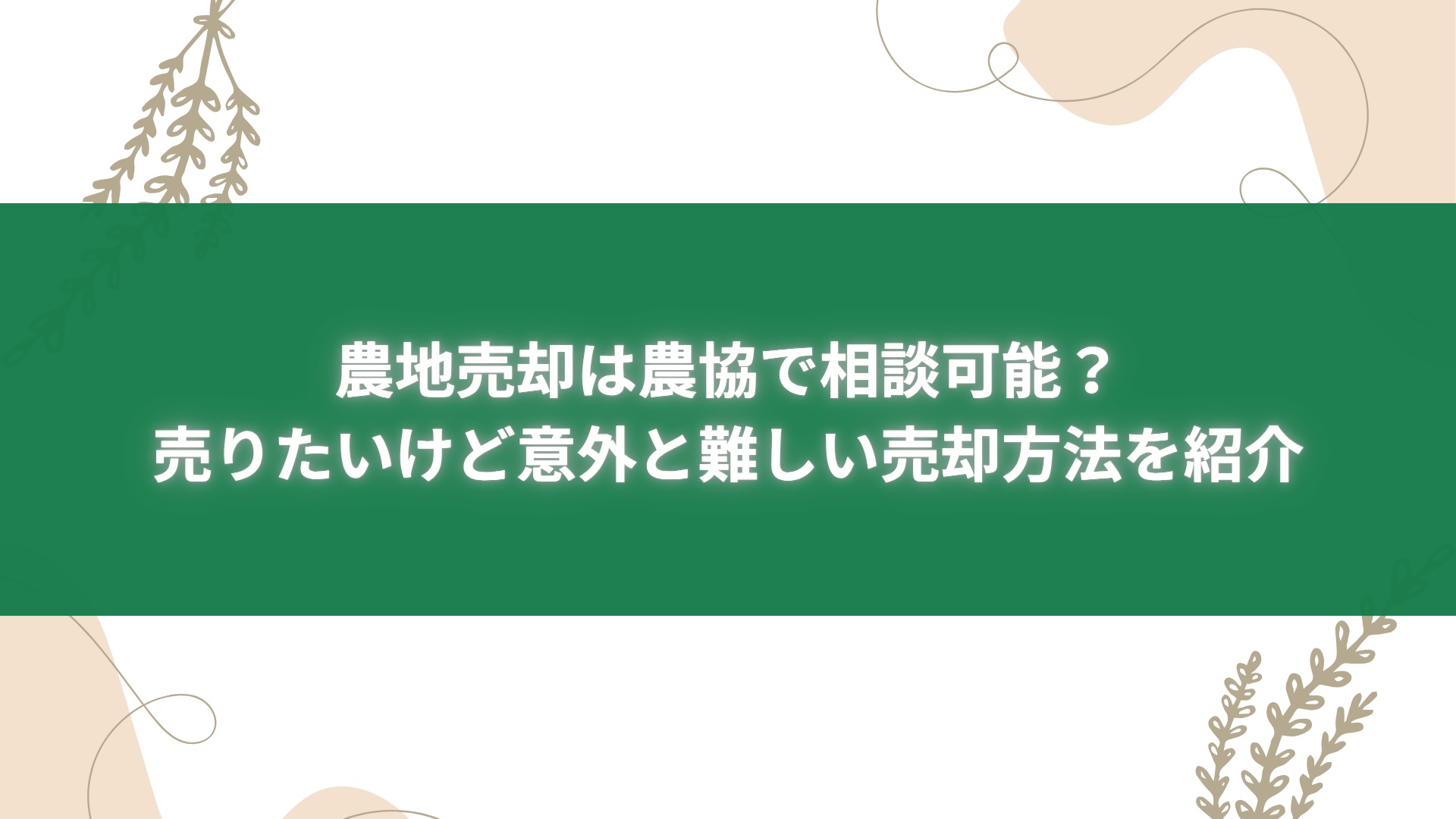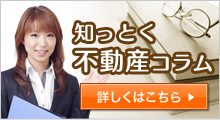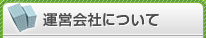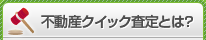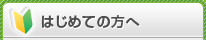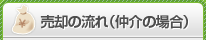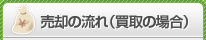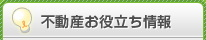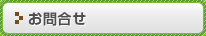熊本市不動産売却クイック査定です。
農地売却を検討している場合は、農協に相談することが可能です。農地のまま売却する場合は買主候補が農業従事者に限定されるため、農協のアドバイスが大いに役立つでしょう。
本記事では農協に相談するメリット・デメリットと具体的な手順、売れない場合の対策について解説します。
目次
農地売却について農協で相談するメリットについて

農協とは農業協同組合の略で、JA(ジェイエー)というニックネームでも知られています。農業の発展を目的として、農業資材の農産物の販売支援や金融・保険サービスなど多岐にわたる事業を展開している組織です。
農協は農地に関するさまざまな情報を持っているため、売却について相談すると以下のようなメリットが期待できます。
- 農地を購入したい人を探してくれる
- 売却価格を査定してくれる
- トラブルなど色々サポートしてくれる
農地を購入したい人を探してくれる
農協は買主を探すサポートをしてくれます。地域の農家や関連事業者など農協独自の情報ネットワークを活用できるため、幅広いターゲットの中から効率よく購入希望者を探せるでしょう。
また農協は農地の活用状況や土地の需要を把握しており、売却に適したタイミングや戦略についてのアドバイスをもらえることも多いです。
売却価格を査定してくれる
農協は農地の売却価格を査定してくれます。過去の実績が豊富であるため、適正な価格で査定してくれる可能性が高いです。
農地に詳しくない不動産仲介業者に依頼すると、立地条件や周辺環境など通常の住宅地と同じような基準で査定され、売却価格が低くなる恐れがあります。
農地の場合は、その地域の農産物の種類や土壌の質なども価格を決める重要な要素であるため、特有の事情を理解している農協に相談するほうが安心です。
売却価格の相場を知ることで、不利な条件提示を避けて交渉を有利に進めることも可能です。
トラブルなど色々サポートしてくれる
農地売却では、農業委員会への許可取得の手続きが発生し、通常よりも多くの手続きが必要です。農協に相談することで手続きをスムーズに進め、トラブルを未然に防ぐことができます。
たとえば買主が農業を継続できるかどうかの審査など、売却後の活用方法も見据えたきめ細かいサポートをしてくれます。税金対策や土地活用方法についてもアドバイスを受けられるため、初めて農地売却をする方は心強いでしょう。
農地売却について農協で相談するデメリットについて

農協に相談すると、買主探しや価格査定など売却に関するさまざまなサポートを受けられます。ただし相談は有料になる点に注意しましょう。
相談は有料
農協に売却をサポートをしてもらった場合、不動産会社に仲介を依頼するときと同様に、仲介手数料がかかります。
仲介手数料の金額は、宅地建物取引業法で定められた上限額を参考に設定されることが多いです。宅地建物取引業法では、仲介手数料の上限額が以下のとおり規定されています。
| 不動産売買価格 | 仲介手数料の上限額 |
|---|---|
| 200万円以下 | 売買価格×5%+消費税 |
| 200万円超400万円以下 | (売買価格×4%+2万円)+消費税 |
| 400万円超 | (売買価格×3%+6万円)+消費税 |
ただし、上記の上限額によらず農協が自由に設定することもできます。ややこしいのですが、宅地建物取引業法は宅地に適用される法律であり、農地は規定の対象外となるためです。
思わぬ負担を避けるためには、農協に相談するときに仲介手数料の金額を聞いておきましょう。その際、仲介手数料の支払い時期についても確認しておくと良いです。通常は売買契約締結後と引き渡し時の2回に分割して支払います。
農地売却は農協で相談する方法や手順

農協に売却をサポートしてもらう方法は、以下の2種類です。
- 農地のまま売却する
- 農地を宅地に転用して売却する
農地のまま売却する場合と宅地に転用して売却する場合では、手続きの流れが異なります。
農地のまま売却する場合の流れ
相談から引き渡しまで以下の流れで進めます。
- 農協に相談する
- 買主を探してもらう
- 買主と売買契約を結ぶ
- 農業委員会に農地法第3条許可を申請する
- 所有権移転請求権の仮登記をする
- 農業委員会から農地法第3条許可が下りる
- 農地引渡し・代金決済・所有権移転の本登記をおこなう
まずは農協に相談し、買主を探してもらうことから始めましょう。買主候補となるのは農業を営む個人や法人です。買主が見つかって条件がまとまり次第、売買契約を結びます。
売買契約締結後は、農業委員会に農地法第3条許可を申請します。農地法第3条許可がなければ売却後の所有権移転登記ができません。
たとえば以下のような場合は、許可を得られない可能性があるため注意が必要です。
- 買主が耕作に供すべき農地の全てを効率的に耕作すると認められない場合
- 農業生産法人以外の法人が権利取得する場合
つまり農業委員会は「買主が購入した後も、農業が引き継がれるかどうか」という視点で、許可を下ろすかどうかを判断しているのです。
許可を申請してから許可が下りるまでの期間は、だいたい1カ月かかります。その間に第三者に所有権移転登記をされないよう、所有権移転請求権の仮登記をおこなっておくと安心です。
許可が下りれば買主に引き渡し、売買代金の精算と所有権移転の本登記をおこない、取引完了となります。
農地を宅地に転用して売却する場合の流れ
相談から引き渡しまで以下の流れで進めます。
- 農業委員会に宅地への転用可否を確認する
- 農協に相談する
- 買主を探してもらう
- 買主と売買契約を結ぶ
- 農業委員会に農地転用の申請をする
- 所有権移転請求権の仮登記をする
- 農業員会から農地転用の許可が下りる
- 地目変更登記をおこなう
- 農地引渡し・代金決済・所有権移転の本登記をおこなう
宅地に転用すると農業従事者以外にも売却できるため、買主候補の幅が広がります。ただし宅地へ転用する場合は、農業委員会や都道府県知事から許可が下りることが必須条件です。
最初から宅地への転用が認められてない場合もあるため、早めの段階で農業委員会に宅地転用の可否を確認しておきましょう。
買主が見つかり売買契約を結んだら、次は転用の申請をします。転用の手続きは届出と許可の2種類があり、市街化区域では「転用の届出」、市街化調整区域では「転用の許可」が必要です。
届出の場合は農業委員会が審査し、2週間程度で受理通知書が発行されます。一方で許可の場合は都道府県知事によって慎重に審査されるため、2ヶ月程度と長期にわたることが多いです。
許可が下りたら、地目変更登記を忘れずにおこないましょう。不動産登記法により、変更があった日から1カ月以内に地目変更登記を申請することが定められています。
最後に引き渡しと代金決済、所有権移転の本登記をおこなう点は、農地のまま売却する場合と同じです。
農地売買は住宅売却よりも難しい

農協に相談することは可能ですが、必ず買主が見つかるとは限りません。実際は住宅の売却よりもハードルが高いのが事実です。
農地売却が住宅売却より難しいといわれるのは、以下の理由があります。
- 農地を購入するのは農家
- 農家の高齢化
- 農地売却は農業委員会の許可が必要
- 農地以外に転用できないことがある
農地を購入するのは農家
農地をそのまま売却する場合、買主候補は農業従事者のみに限定されます。日本の農業を維持するために、農業に従事していない人や農業を続ける意思がない人に売ることはできないのです。
また農業従事者は減少傾向が続いており、買主候補の人数が非常に少なくなっている現状があります。2023年の基幹的農業従事者の人数は約116万人と、2000年の240万人と比較して半分以下にまで落ち込んでいる状況です。
上記のように買主候補が限られ、さらにその人数が減り続けているという点が、農地売却を難しくしている理由の一つです。
農家の高齢化
近年では農家の高齢化が進み、農業の後継者不足や若年層の農地離れが深刻です。
農林水産省の「農林業センサス」によれば、2020年の基幹的農業従事者のうち、65歳以上の階層は全体の71%を占めています。一方で49歳以下の若年層の割合はわずか11%と非常に少ない割合です。
このまま農家の高齢化が続けば、農業の担い手は減っていきます。農地を買いたいというニーズが縮小すると、農地売却はますます難しくなるでしょう。
農地売却は農業委員会の許可が必要
農地売却は手続き面でもハードルがあります。農地の売却をおこなう場合は農業委員会に申請して許可を得なければならず、通常の売却よりも時間と手間が増えるからです。
さらに正式な手続きを経て申請しても、買主に農業継続の意思がないと判断されれば許可が下りないこともあります。農業委員会の審査は売買契約後になるため、契約時点で不確実性が残る点に不安を感じる買主もいるでしょう。
申請してから許可が下りるまでに1カ月程度時間がかかることもネックです。引き渡しまでにタイムロスが発生するため、「すぐに購入したい」という買主のニーズを逃してしまう可能性があります。
農地以外に転用できないことがある
農地を宅地に転用すれば活用方法が広がるため、買主候補を増やすことが可能です。しかし転用許可は農業委員会や都道府県知事による審査に委ねられており、農地売却同様に不確実性をはらんでいます。
審査結果によっては宅地への転用が認められず、売却活動が停滞するリスクもあります。特に市街化調整区域にある農地は、審査が厳しくなるため簡単には許可が下りません。
審査期間も市街化調整区域の場合は2ヶ月と長い時間がかかります。短期間で取引を完了させたい買主のニーズを満たすことは難しく、どうしても流動性は低くなるでしょう。
農地が売れない場合の対策

農地が売れない場合は、以下の対策によって売りやすくなる可能性があります。
- 農地を転用をする
- 貸し出す
- 不動産会社に依頼
- 市民貸農園
- 太陽光発電を設置
農地を転用をする
農地以外の用途に転用すれば、より多くの買主候補が見つかる可能性があります。たとえば宅地に転用することで、農業以外のニーズを持つ層にもアプローチすることが可能です。
特に市街化区域は都市化が進んでいる地域と位置づけられているため、住宅用地としての需要が期待できるでしょう。
農地転用には申請が必要になりますが、市街化区域であれば農業委員会の届出だけで済み、手続きが比較的簡単です。
貸し出す
農地が売れない場合は、貸し出すのも手です。農地を有効活用して、安定した収入を得ることができます。
農協では農地の借り手を探したい方向けに、農地利用集積円滑化事業を展開しています。農地利用集積円滑化事業とは、農協が農地所有者を代理して農地の貸付をおこなう仕組みです。
このほかにも行政やNPOなどが提供しているマッチングサービスを利用してみるのもおすすめです。農地を貸し出す場合は、借り手との間で賃貸契約を結びます。賃貸契約には貸し出す条件や契約期間、管理体制などを明記することが重要です。
ただし農地を貸し出す場合も、農業委員会に申請して許可を受ける必要があります。許可を受けないでおこなった賃貸は無効となるため、注意しましょう。
不動産会社に依頼
3つ目の対策は、不動産会社に売却を依頼することです。
農協に相談しても買主が見つからないのであれば、不動産会社にあたってみるのも手です。
不動産会社を選ぶ際は、周辺地域や都市計画法・農地法に詳しいかどうかで選びましょう。農地売却に精通した不動産会社に依頼することで、取引成功の可能性が高まります。
不動産会社独自のネットワークを持っており、農業以外の利用目的を持つ開発業者にもアプローチが可能です。農業だけにとらわれない営業活動ができるでしょう。
売買契約や引き渡しの手続きなどもサポートしてくれるため、安心感もあります。ただし不動産会社に売却を依頼すると、仲介手数料が発生する点に留意しなければなりません。
市民貸農園
市民貸農園とは市民が気軽に農業体験できる仕組みで、農地の新たな利用方法として注目されています。
農業従事者は高齢化や人口減少が進んでいますが、利用対象を農業未経験の市民に広げることで活用幅が広がります。地域コミュニティの活性化に加え、農業の魅力を若年層に伝える場にもなるでしょう。
農地所有者は土地を有効活用しながら、定期的な収入を得られる点もメリットです。また農地にほとんど手を加えずに始められるため、将来的に売却や転用がしやすいメリットもあります。
一方で市民貸農園を成功させるためには、運営体制の整備やイベントの開催など、きめこまやかな維持管理が求められます。また市民貸農園を開業する際は、農業員会などへの届け出が必要となる点に注意が必要です。
太陽光発電を設置
太陽光発電を設置して、再生可能エネルギーの生産拠点として活用する方法もあります。
農業を継続しながら太陽光発電をしたい場合は、営農型太陽光発電がおすすめです。営農型太陽光発電とは、農地に簡易的な支柱を立てて、その上部にパネルを設置し太陽光を電気に変換する事業です。
営農型太陽光発電を設置する場合は、農地転用許可は必要ありません。代わりに一時的な転用許可を得ることが条件になっています。
営農型太陽光発電設備を設置するための農地の一時転用許可件数は年々増加しており、2022年度までの累計件数は5,351件です。
農地売却の税金について

農地を売却して利益が出た場合は、譲渡所得に対して所得税と住民税がかかります。
譲渡所得の計算式は、以下のとおりです。
譲渡所得=(売却価格ー取得費ー売却にかかる費用)
所得税と住民税の税率は所有期間が5年以下か5年超かどうかで異なります。それぞれの税率は以下のとおりです。
| 所得税税率 | 住民税税率 | |
|---|---|---|
| 保有期間5年以下 | 30% | 9% |
| 保有期間5年超 | 15% | 5% |
なお、2037年までは復興特別所得税として、毎年の基準所得税額の2.1%が上乗せされます。
譲渡所得には、いくつかの控除特例があります。一定の条件を満たす場合は税金の負担を減らせるため、該当する特例がないか確認しましょう。
まとめ
農協に農地売却を相談すると、買主探しや売却価格の査定などさまざまなサポートをしてくれます。ただし農協を介して売却する場合は、仲介手数料がかかる点に注意しましょう。
農地は購入希望者が少なく、一般的に売却が難しいです。まずは農協に相談してみて、売却活動が上手くいかない場合は、本記事で紹介した対策を参考にしてみてください。